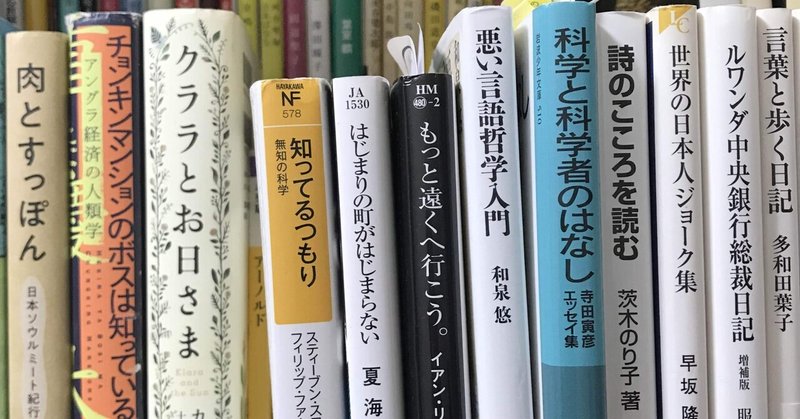
令和4年読書の記録 わたしの10冊
令和4年読書の記録 わたしの10冊
去年も12月20日に同じことをやっていたので今年もやってみようと思う。今年も読書に助けられてギリギリ直立できていたような一年でした。以下はたぶんこの1年のうちに同じような内容を一度書いておりますが、改めてまとめることをご容赦ください。

◯石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣病』
これはほんとに読むのが苦しくて苦しくて、
なんか胃袋の奥の辺から突き上げてくる
シクシクとした痛みのような感情のせいで
ぼろぼろ涙が溢れてくるから、
ページを捲るのが途中ほんまにしんどかった。人は死人が出てなお、
それでも責任逃れをしたくなるものなのか。
「めちゃくちゃおもろかったから
読んでみて!」と
他人に薦めるような本でもないと思うけど、
これは是非読んでほしいし、
僕はこれから何回も読みたい。
二年前に読んだ緒方正人さんの
『チッソは私であった』もあわせて読みたい。

◯夢野久作『ドグラ・マグラ』
スカラカ、チャカポコ。
チャカポコ、チャカポコ。あーア。
夢野久作先生は。私と誕生日が同じ。
ただそれだけのことなのに。
それがやたら嬉しくて。
おかしな世界が描いていて。
それがやたら嬉しくて。
若い頃に読んでから。
打ちっぱなしのコンクリの。
前を伏し目がちにして。
歩く男の情景が。
ずっと脳裏にあったのに。
いま改めて読んでみて。
そんな場面は全くなく。
どういうことかと思ったが。
これも胎児の夢の如く。
心理遺伝というやつか。
いかれた世界と思いきや。
真理に迫る言葉あり。
真と読めば虚のようで。
虚として読めば真がある。
実におもろい世界やで。
スカラカ、チャカポコ。
チャカポコ、チャカポコ。
濃厚接触者になり外出できなかった時に
読んだんですよね。
ああいう、
なんにもできないタイミングがなかったら、
いまも読んでないかもしれないから、
あれはあれでよかったんだな。

◯和泉悠『悪い言語哲学入門』
「あんたバカぁ?」「このタコが!」
「だって女/男の子だもん」
普段耳にする言葉のなかにも
「悪い言葉」はたくさん潜んでいますが、
果たしてその言葉は何が悪いのでしょう?
悪口は何が悪いのでしょう?
ときどき悪くないのはなぜなのでしょう?Japaneseを縮めただけなのに
どうしてJapには
差別的意味が含まれるのでしょう?
言葉の善悪の問題を
哲学や言語哲学の観点から考える本。
一つ一つの事例について
丁寧すぎるほど丁寧に考察していて
詰将棋みたいです。
普段からこのくらい
言葉と丁寧に付き合いたい。
「蒸気船やタンカーは、個人が所有しているわけではなく、社会の中で巨大な位置を占め、便利で有益かもしれませんが、慎重に適用しなくては、運河に挟まったり、大事故を引き起こしたりするでしょう」

◯太宰治『きりぎりす』
魔女のブロンディーさんが紹介していた
短編『きりぎりす』が気になったから
読んでみた太宰治中期の短編集。
『きりぎりす』に代表される
女性一人称語り小説が
僕はめちゃくちゃ好きです。
『きりぎりす』で語り手の女性に
別れを告げられる芸術家の男は、
かつて純粋であったのに、
有名になり金が入ったことで
「金目当て」の俗物になってしまうんですが、
そういう芸術家を非難させているところに
太宰治のかっこよさがあるんだと思う。
いくつかの作品のなかに
「僕は自分の見知ったことしか書けない」
というようなことが書いてあり、
自分もそういうことしか書けないから、
同じやん!と危うく恥ずかしい勘違いを
しそうになったけど嬉しいのは嬉しい。

◯カズオ・イシグロ『クララとお日さま』
2017年、ノーベル文学賞を受賞した後、
はじめて出版された
カズオ・イシグロの8作目の長編小説。
英語で読んでいないから、
通訳の土屋政雄さんの
翻訳の話になると思うんですが、
文体が私はすごく好きです。
主人公のクララの繊細さ、優しさが
とても上手く描写されています。
クララはどんな時も
友人のジョジーのことを思っていて、
激しい感情を面に出すことがありません。
いつも冷静に物事を、
事実を観察している様は、
現実の子どもたちも、
意外とこうやって
大人を観察しているんじゃないのかな?
なんて思ったりします。
それは、私が偉い人の傲慢や思い込み、
似非正義感などを見通せてしまうのとも
似ているかもしれず、
その点、私はクララに共感も覚えました。
しかし、中盤、私はクララと
「お日様」の関係性に
疑いを持ってしまいました。
こんな私がクララに共感を覚えたなどと、
本当は言ってはならないのです。
クララの「お日様」に対する思い、
信じる力を
少しでも虚構だと思ってしまった自分は、
実に汚い世界を生きているのだと思う。
自分の汚さを恥じると共に、読み終えた今、
その汚さが少なからず
浄化されたような気分でおります。

◯ スティーブンスローマン/
フィリップファーンバック
『知ってるつもり無知の科学』
自転車がどんな構造をしているか、
絵に描いてみることはできますか?
自転車通勤の人なんかは
「バカにするなよ」と思うかもしれませんが、
私は多くの人が正確には
書けないのではないかと思います。
自転車でなくてもいいです。
例えば、炊飯器はどういう構造をしていて、
どういう理屈によって
ご飯を炊けるのでしょう。
扇風機がスイッチ一つで回転するのはなぜ?
ファスナーはどういう仕組みになっているの?
その全てについて、
私はしっかりとした説明ができませんが、
そのすべてを問題なく使いこなせてもいます。
「知ってるつもり」・・「無知の錯覚」。
何も知らないくせに知った風に
過ごしていることは、
何も悪いことではありません。
だいたいみんな、そうなんです。
個人の持ってる知識なんて五十歩百歩。
というか、「個人の知識」って何でしょう。
本書の解説で山本貴光さんが書いています。「ものを考えたり書いたりするのに使われる言語やそれを使って表された知識からして過去の人びとの共同創作物だし、創作に使われる各種の道具も誰かがつくったものだ。それに誰かとのおしゃべりや読書から思いついたアイディアは、果たして自分だけで考えたと言い切れるかといえばそんなことはない。私たちは、さまざまな形で他の人の知識を借りている。知識はコミュニティのなかにある。」

◯夏海公司『はじまりの町がはじまらない」
大垣書店の棚に並んでて
むしょーに気になって気になって
仕方なくて買いました。
いわゆる「ジャケ買い」。
こういう勘を大事にして生きたい。
ロールプレイングゲームと思われる
ゲームの中の世界が舞台。
ゲームの「はじまりの町」は
冒険者がやってくることで
潤うはずなんですが、
その冒険者が最近全然やってこない。
よくよく調べてみたら町を出て
最初に遭遇するモンスターが強すぎてすぐ全滅してしまう、とか、
設定されているミッションが
難しすぎたり魅力的じゃなかったりして
冒険者が集まってこないらしい。
それなら町の在り方を「改善」して
冒険者にとって魅力的な「はじまりの町」に
作り直そうじゃないか、と
真面目だけど頭の回転は十人並みの町長と
毒舌の秘書官が奮闘する物語。
ゲームの中の話かと思いきや、
物語が進むにつれて、
やがてゲームの外の世界、つまり、
現実世界を巻き込んだ事件に
発展していきます。
っていう話を僕は幸い、
子供の頃からドラクエや
ファイファンをやっていたから
すんなり理解できたんですが、
ゲームに親しんでいなかったら
全く理解できなかったかもしれない。
オール巨人が、
「最近の漫才がわからなくなってきた」とか、
そんな理由で今年から
M1の審査員を辞めましたが、
小説の世界についても、
前提となる知識が無いと
その世界観が全くわからないですよね。
これから未来、
どんどんと創り上げられていく
新しい価値観を含むフィクションの世界を
「理解」し続けるためには、
現実世界で僕たちは、
あらゆる方面にベクトルを向けて
学びを怠ってはいけないのです。

◯イアン・リード『もっと遠くへ行こう』
近未来の都会から離れた
田舎に住む夫婦のお話。
夫のジュニアと妻のヘンは
幸せに暮らしていますが、ある日、
テレンスという謎の組織の人間があらわれて、
ジュニアが宇宙への
一時移住計画の候補になったと告げます。
ヘンと離れて宇宙旅行するなんてことは
考えられないと突っ撥ねるのかと思いきや、
なんやかんや、テレンスの言いなりになって
動くジュニア、ヘンの様子も何かおかしい。
何か夫婦の間に流れる空気に
違和感があるのですが、
それが何かはわかりません。
平凡な、それでも幸せな
結婚生活を送っていた夫婦に
特殊な事情が舞い込んできたことにより、
当たり前としてあった前提が覆されていく。「実はおかしかったんじゃないのか」
「夫婦って何?」
「本当は私たちの関係って
ものすごくおかしかったんじゃないのか」
「おれは凡庸な人間と思っていたけど
そんなことはないのか」・・
読めば、こっちがもっと
遠くへ行ける気がする。

◯湊かなえ『告白』
私が小説を書いてみようなどと
考えるきっかけをくださったのが
湊かなえさんです。
お会いしたことはありませんが、
勝手に先生とお慕い申し上げております。
先生とは、いずれ、どこかで
作家としてお会いする。ということを
私は勝手に先生と約束しています。
その約束がぼやけてしまわないように、
定期的に先生の本は読まないといけません。
しかし、後味の悪い小説でした。
イヤミスの女王と
呼ばれるだけのことはあります。
これがデビュー作なんですね。
先生とお慕い申し上げているにもかかわらず、
私は先生のことを実はあまり知らないのです。
後書きで映画監督の中島哲也さんが
書いていますが、
登場人物それぞれの「告白」には
「嘘が混ざっているはずだ」と。
私もそのように思いました。
全員が全員、おそらく、
自分に都合のいいように
事実を改竄していると思います。
現実でもそうじゃありませんか。
自分が悪くないこと、
悪いのは◯◯であることを立証するために、
自分が悪いかもしれない証拠となるものは
上手に隠蔽します。
責任は押し付けられるところ押し付けます。
自分にも、そういうところがあり、
それが果てしない恥辱であるからこそ、
それを平気でやってのける
立場のある輩のことが
許せなかったりするものです。
『告白』の登場人物たちも、
きっと嘘をついていると思いますが、
それを追求したところで何も変わりませんし、
そういう読み方はしません。
ただ、読んでいる私に
都合のいいように解釈するならば、
いちばん最後、物語の最後の最後の
森口先生の最後の告白は、
私は嘘だと思います。私はそう読みました。
読み手に判断を委ねるところも、
湊かなえさんの作品
の魅力なのかもしれません。
『少女』も面白かった。

◯ガイ・ドイッチャー
『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』
ホメロスの叙事詩『イリアス』
『オデュッセイア』では、
海と牛が両方とも「葡萄酒色」と
表現されていて「青」はまったく
出てこないそうです。
だからといって、
果たしてその頃の人たちは、
「青」を認識していなかったことに
なるのかしら。
グーグ・イミディル語という言語には
前後左右にあたる語がなく、
すべて「東西南北」で
位置を伝えるらしいんですが、
じゃあ、例えばその言語話者は
過去にあった恐怖体験についても
「3年前に東から来たサメに襲われて〜」
などという言い方をするのか?とか、
男性名詞女性名詞のある言語では、
例えばドイツ人にとって
男性名詞である「りんご」は
男らしかったりするのかしら?とか。
解説の今井むつみさんが末尾で、
「ともあれ、本書は最初から最後まで、たいへんわくわくする、知的好奇心を掻き立てられる一冊だ。人はなぜ言語を持つのか、言語をもって人は何をするのか。この巨大な問いを、ぜひ日本の読者のみなさんも著者といっしょに考えて頂けたら幸いである。」
と書いているのがよくわかる一冊です。
このほかに今年になってから購読するようになった『文藝』や『SFマガジン』、毎月読んでる『文學界』にも面白い作品がたくさんありました。
◯宇佐見りん『くるまの娘』
◯山下紘加『あくてえ』
◯年森瑛『N/A』
◯安堂ホセ『ジャクソンひとり』
◯日比野コレコ『ビューティフルからビューティフルへ』・・・
あと、SFマガジンを読んでいて知った斜線堂有紀さんのことは大好きになりました。来年は本なんか読まなくてもいい人生がいいようなそんな人生はイヤなような。読書ってほんっとにいいもんですね!
#読書 #読書の記録
#令和4年読書の記録
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
