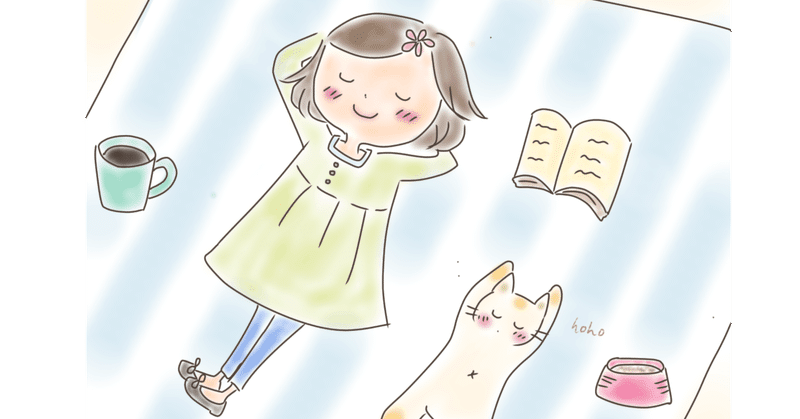
『みぃちゃん』
私は今日も一人で、バケツとシャベルを持って公園の砂場に立った。
シャベルで掘った砂を山のように積み上げて、バケツに汲んだ水をかける。山を固定するために湿った砂を両手でペタペタと軽くたたいていく。
そうして黙々と動かし続けていた私の手に、そっと触れる小さな手があった。
私は動きを止めて、その手を伸ばした相手を見た。
白いシャツに薄茶色のオーバーオールのスカートを着て白いソックスを履いた、私よりも少し小さい女の子だった。丸い目をして三角の口をして、その手は触れたまま私をじっと見つめている。見たことのない顔だった。
「…一緒に遊ぶ?」
ためらいがちに声をかけると、女の子は私の目をじっとそらさずに見つめたまま、こくんと頷いた。
二人で、湿らせた砂場の山を固めていく。まるで元々知っていたかのように私と同じ手順で、その子も手を動かしていく。
お互いの姿が隠れるほどの大きな砂山を作ったら、こんどは両方から横穴を掘る。自然と息の合う女の子をすっかり気に入った私は「名前はなんていうの?」と聞いた。おともだちを作るときのあいさつだ。
「みぃちゃん」
その返事を聞いたとたん、動揺した私は自分が開けた穴を崩してしまった。
「あー」
少しがっかりした顔をしたあと、すぐに2人でその穴を補修して新しいトンネルを作った。
トンネルが貫通して両側から伸ばしたお互いの指先が触れたとき、やった、って2人で顔を見合わせて笑った。
「みぃちゃんは、どこから来たの?」
別れ際に聞いた私の質問に、みぃちゃんはちょっと眉をひそめて考える仕草をし、口をキュッと両方に結んで「うーん」と首をかしげた。答えのないまま、「またね」と別れた。
家に帰ったとき、まだ外は明るかったけど時間はいつもより遅かった。
「どこに行っていたの?」と聞くお母さんに、「ともだちと砂場で遊んでた」と答えた。
お母さんは夕食の支度をしながら背中越しに「へぇ、誰と?」と聞いてきて、私はちょっと戸惑った。
みぃちゃん、と、答えられない。
口をキュッと結んで「うーん」とごまかして、部屋の一角を見る。花の絶えないその場所には、私の姉妹である”みぃちゃん”が私と同じ顔で微笑んでいた。
双子で生まれた私たちに、両親はありがちな共通の名前をつけなかった。代わりに、共通の意味をもつ名前をつけた。
"みなみ"と"のどか"。
暖かい陽だまりを共に穏やかに過ごしていけますように。
まだ幼い私たちは周囲から"みぃちゃん"と"のんちゃん"と呼ばれて、お互いもそう呼びあって育った。
みぃちゃんが突然の事故でこんなに早くいなくなってしまうなんて、誰も想像していなかった。
翌日も、その次の日も、私が公園に行くと薄茶色のオーバーオールのスカートを着たみぃちゃんが来た。顔は私と似ていなかった。
2人で砂山を作って、かけっこをして、遊具にぶら下がって遊んだ。他のどんな友だちよりも相性が良くて面白いと思うことも同じだった。
そんな毎日を過ごすうち、初めて会ったときは私より小さかったみぃちゃんの身長がいつの間にか私を超えていた。見た目はまるで年上のお姉さんに遊んでもらっているようだった。どこに住んでいるんだろう。何歳だろう。何年生だろう。時々それを不思議に思ったけれど、この楽しい毎日が途切れるような気がして聞くことはできなかった。
ある日、みぃちゃんは来なかった。
一人で砂山を作って、トンネルを掘って、それを崩しても、姿を見せない。少し気になって、公園を出て近くの道路を歩いてみた。
塀のある曲り角を過ぎるとそこで、ひどい傷を負って横たわる猫を見つけた。
白と薄茶色の胴体に、白い足。
あのオーバーオールを着て白いソックスを履いた公園のみぃちゃんの姿が思い浮かんだ。
もちろんみぃちゃんが猫なわけないけど、私はまだ息のあるその猫を放っておくことができなくて、抱きかかえて家に連れて帰ることにした。怪我をしているから手当を急がなければいけない。まだ子猫のような見た目に反して、持ち上げたら想像より重かった。
私はなんとか両腕で猫を抱えて自宅にたどり着き、玄関のドアにドン、ドン、と体当たりして帰宅を知らせた。
音を聞きつけたお母さんが玄関を開けて、まずは汚れた私の姿を見て驚いた表情をした。そして、抱きかかえている猫を見てまた目を見開いて、こぼれるように「みぃちゃん」と言った。
この日のことは何度聞いても、なんで「みぃちゃん」と言葉にしたのかお母さんにも分からないのだという。
私にとっては公園で遊んでいたみぃちゃんが浮かんでいたけど、その名前を知らないはずのお母さんが言うみぃちゃんは、私の双子のみぃちゃん、つまりみなみちゃんになる。
その場はとにかく怪我を負った猫をなんとかするのが先決で、ちょうど家にいたお父さんがすぐに近くの動物病院へ電話をかけて私たちを車で連れて行ってくれた。おそらく事故にあったであろう怪我を負った薄茶色の猫は幸いにも命に別状はなく、数日の治療入院のあと我が家で引き取ることになった。
猫の名前を決めるとき、私にとってはこれしかないという名前をおそるおそる聞いてみた。
「"みぃちゃん"は?」
お父さんもお母さんも「いいんじゃない」と受け入れてくれた。私の中ではなぜか双子のみなみちゃんではなく、公園で一緒に遊んだみぃちゃんが浮かんでいた。猫だけど、あの時の子だと思えて仕方がなかった。
こうして、猫のみぃちゃんが家族の一員になった。
公園のみぃちゃんにその後会うことはなかった。
------
日当たりの良い南向きのテラスで、私はうーんと全身で伸びをした。身体の隅々まで毛づくろいをして、大きなあくびをして、ゴロンと横たわる。太陽に暖められた床から伝わる温もりを受けて幸せを感じる。
この体に合った習性をちゃんと身に付けているのだから、よく出来ているものだわ、と思う。
人間だった頃の、"みなみ"という名前で家族から「みぃちゃん」と呼ばれて育った幼い頃の記憶が残ったまま、ある日私は猫の姿で目を覚ました。暗闇に飲まれるような人間最後の瞬間はかすかなもので、離乳を済ませてからは記憶を頼りに草むらや路地をさまよい歩き、見覚えのある公園までたどり着いた。
公園の砂場で、一人で遊んでいたのはのんちゃんだった。懐かしさと、また一緒に遊びたいという強い強い願望のせいか身体の奥が熱くなり、気が付いたら2本足で立っていた。カーブミラーに映る姿は人間の女の子だった。
姿や顔立ちは、“みなみ”とも、のんちゃんとも違っていた。魂が同じでも、肉体は生まれ変わった新しいものになったのだと思った。
その日から、私はのんちゃんと砂場で遊ぶようになった。角を曲がれば公園が見える草むらで寝起きし、のんちゃんの姿が見えたら人間の姿になって一緒に遊んだ。
最初は私より大きかったのんちゃんの手が日に日に小さく感じるようになって、猫の成長は人間よりも早いんだと知った。
不自然さを悟られるのではないかと心配になりながらも毎日を過ごすうちに、だんだんのんちゃんの面倒を見るお姉さんのような気持ちが芽生えてきた。時計を見て、夕飯に間に合うように帰るように促した。歩道を歩くのんちゃんの後ろ姿を見えなくなるまで見送った。
そうして、のんちゃんの心配ばかりしていたら、つい自分の身がおろそかになってしまった。
ブロック塀で見通しの悪い曲がり角を出た瞬間、飛び出してきた車と接触した。運転手は人間の子どもとぶつかったと思ったのだろう、あわてて車から降りて横たわる私に駆け寄ってきたけれど、猫の姿に戻ってしまった私を見ると、そのまま黙って立ち去ってしまった。
かろうじて呼吸はできるけれど、全身の痛みで起き上がることも目を開くこともできない。眠いという感覚ではなく、意識が遠のいた。
次に目を覚ましたとき、目に映ったのは眩しい光に包まれて私を覗き込むのんちゃんの顔だった。
「みぃちゃん!」
横にお母さんの顔もあった。
「みぃちゃん!」
その隣にはお父さんの顔も。
みんなが私を「みぃちゃん」と呼んでいる。
家族に囲まれているという現実に感情の大波があふれ出て、怪我の治療のせいで手も足も動かせない私はかろうじて小さな声で「みぃ」と鳴いた。
---
暖かい日差しを受けながら、私はゴロンと姿勢を変えた。
テラスに面した部屋にある木製の小さな棚には、人間だった頃の私の写真が飾ってある。その棚に新しい花束を添えて、のんちゃんが私の横に腰をおろした。私は姿勢を変えて彼女の膝にぴったりと寄り添う。のんちゃんの細長い指が私の首元を優しく撫でる。
猫として再びこの家の一員になってから10年以上の時が経ち、のんちゃんは綺麗なお姉さんに成長した。
人よりはやい体の成長とともに私の精神も成熟し、いまでは娘や孫を見るような愛おしい感情を持ってのんちゃんのそばにいる。
窓の外にはお父さんが手入れをしている植木の葉が風に揺れている。テラスにはお母さんが揃えた個性的な陶器の鉢植えが並ぶ。
みぃちゃんとのんちゃん。
"みなみ"と"のどか"。
陽だまりの暖かさを共有した二人の名前が、今も並んでここにいる。
終(3689文字)
「第19回坊っちゃん文学賞」応募作品です。
スキやシェア、コメントはとても励みになります。ありがとうございます。いただいたサポートは取材や書籍等に使用します。これからも様々な体験を通して知見を広めます。
