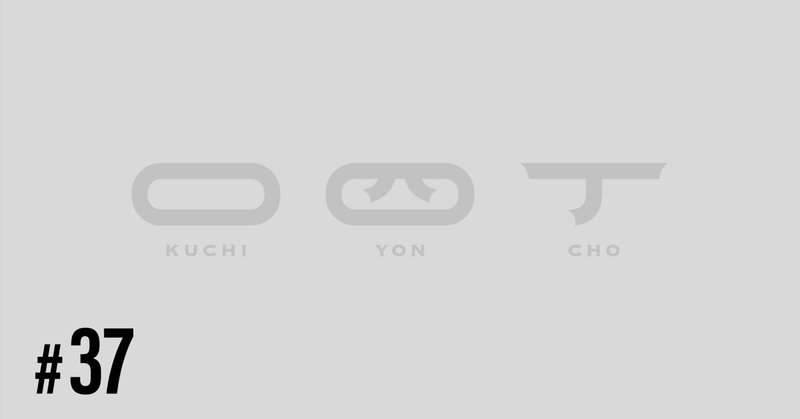
いくつかのメリークリスマス
僕がまだ両親と同じ部屋で寝ていた、幼いころ。
サンタクロースへと手紙を書いてリビングに飾られたツリーの下に置いておく。気づくとその手紙は無くなっていて、クリスマス当日の朝には手紙があった場所にプレゼントが置いてある。サンタはやってくる時間を間違えないよう大変だっただろう。だってその日だけ僕はえらく早起きをするのだ。
まだ空は薄暗くて、リビングには電気がついていた。朝なのに夜みたいで、なんだか不思議だった。
そういえば、僕がさすがに早起きをしすぎた年がある。薄暗いどころではなく真っ暗な、2時とか3時くらいだったと思う。そのとき寝室の外、廊下のほうから物音が聞こえた。両親も寝ている時間だ。これはサンタが来た瞬間に違いない。僕はドキドキした。サンタに気づいてしまったらプレゼントをもらえないような気がして、そして二度と来てくれないような気がして、必死に目を瞑った。
いつの間にか朝になっていた。
あのとき同じ部屋で寝ている両親を確認しなくてよかったと思う。そこには両親が寝ていなかったかもしれないし、寝ていたかもしれないのだ。
高校生になった、16歳のころ。
クラスの男女数人でクリスマスに遊ぶことになった。お菓子と飲み物を買ってカラオケ。大きなスクリーンのあるパーティールームだった。
僕は良くも悪くも、何かが変わっていくのを感じていた。公園で遊んでいた小学生とも、友達の家でゲームばかりしていた中学生とも、もう明確に違う。純粋にプレゼントを待っていたクリスマスとももちろん違う。高校生になった僕らの遊びにはほのかに、しかし確実に「男女」の空気が漂っていた。
カラオケのあと大通のクリスマス市にいって、特に何を買うでもなく人混みをただ歩いた。アイツは前を歩いているあの子のことが好きで、コイツは今日ここにいない子のことが好きで、もしかしたら僕のことを好きな子もいたりして、なんて。
幸せを運ぶサンタはもう来なくなって、じゃあ僕は僕自身で幸せになるしかないのだろうか。なれるだろうか。そんなことを思ったかどうかは覚えていないけれど。
5年前。
またしても人混みを歩いていた。またしてもクリスマス市だ。人混みの内訳はカップルか家族ばかりだったが、僕は1人ぼっちだ。
一人暮らしの家にはツリーがないし、わざわざ飾るほどでもない。それでもクリスマスらしいものが何一つないと寂しいもので、ちょっとした置き物くらい買えるだろうかと思ってやって来たのだ。
ある出店で、クリスマス仕様のマトリョーシカを見つけた。ツリーの形の人形を開けるとサンタが。その中からは雪だるまが出てくる。これに決めた。
お店の女性はロシア人だろうか、会計をしながら、カタコトの日本語で僕に話しかけてきた。「カノジョハイルノ?」まさかクリスマス市に1人でやってきてマトリョーシカを買う男が実在するとは思わなかったのだろう。僕が「いないんです」と答えると、彼女は切なそうな、申し訳なさそうな顔をしてしまった。申し訳ないのは僕のほうだ。クリスマス市に1人でやってきてマトリョーシカを買う男を実在させてしまったのだから。「デモ、コレカッテクレテシアワセヨ」マトリョーシカを手渡しながら彼女はそう言った。
形はどうあれ人を幸せにできたならいいことじゃないか。サンタと呼ぶにはいささか哀れな背中だけれど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
