
『優しい地獄』を何度も歩いてみる
『優しい地獄』イリナ・グリゴレ 亜紀書房 2022
イリナさんはルーマニアから日本へ来た。1989年まではルーマニア社会主義共和国だったから、社会主義も社会主義から切り替わりも、資本主義への移行も経験している。多くの社会主義国家は失敗したとされている。いまでは赤狩りとまでは行かないけれど、当然の帰結とばかり過去のものとしたり、社会主義と聞いただけで拒否反応を示す人もいる。その一方で、改めてコミュニズムに可能性を見出そうとする人も出てきた。今年の正月のNHK『欲望の資本主義』で、旧社会主義陣営だったチェコの経済学者トーマス・セドラチェクさんとマルクス研究者の斎藤幸平さんの対談をみた。社会主義だった国の人の方が資本主義の良さを知っていると思った。資本主義の方が、制度上は国家は中央集権的に管理になりにくく、腐敗もしにくい。だから野放図な資本主義さえ止めることができれば、可能性はあるのだと思った。コミュニズムという考え方にも可能性はあると思う。ただ、国家レベルの規模では成立し得ないのだと思う。社会でモノを共有しながら互助的に維持していくのは、顔の見えない相手では難しい。
過去も現在も日本政府は粛々と暴力を遂行していると思う。社会主義国家に比べれば露骨さはない。イリナさんがルーマニアで経験してきたような、国民の心身に苦役を強いるようなことはあまりない。じゃあ日本人が幸せかといえば、そうでもない。少なくとも幸福度ランキングはルーマニアより低い(2022年度はルーマニア28位、日本は54位)。格差や貧困もじわじわと広がっている。だから社会からの落伍者にならぬようにという緊張感から逃れられない。そのために押し殺しながら、同じ道を朝と夜に行き来して、誰のためかわからないものを作ったり売ったりしている。そう思いながら、生活の糧を得ために働く。土日に自分を取り戻し、またロボットの自分を起動させる。
工場は、子供の目線から見ると、人間と機械が混ざった、豚の内臓のような無茶苦茶な空間に映った。解体した豚を一度見ると良い。内臓と血の塊の中からまた温かい、死んだばかりの生き物の湯気が立ち上る。
私にとって、工場の機械も生物の器官として理解できたが、やはり豚が生き物なのに対して、あの中の鉄塊が恐ろしいものの内臓としか見えなかった。
工場は豊かさの象徴でもある。テクノロジーやモノで所狭しと埋め尽くされている。以前、大きな工場にいくと、「場内はトラックが最優先」と掲げてあって、人として少しショックだった。効率とはそういうものかと思いつつ、奇妙に思え、抵抗を感じた。大量生産を可能にしたのは機械だ、でも維持管理しているのは人間だしに、動作音や排熱のなかで働く人々がいる。そこで働く人たちは微々たる存在で顔がない。工場に最適化される食肉工場もAmazonの物流倉庫もその中で何が起きているのかわからない。社会を維持するために不可欠で、都市からは存在の見えないブラックボックスだ。
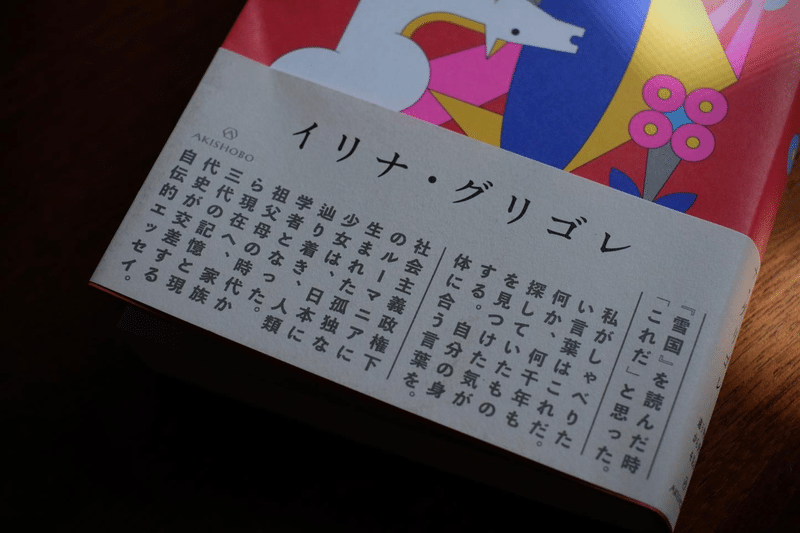
イリナさんの父はそれでもその工場で真面目に働いたが、帰宅後は酒に溺れ、人や物に当たった。それはPTSDのなのだろう。『私たちはなぜ犬を愛し、豚を食べ、牛を身にまとうのか』で書かれたことと同じだ。望まない行為を強いられ続け、心身は壊れた。「死んだばかりの生き物の湯気」は心身を収奪された者たちのため息や魂のようにも思える。
社会主義とは、宗教とアートと尊厳を社会から抜き取ったとき、人間の身体がどうやって生きていくのか、という実験だったとしか思えない。・・・言葉と身体の感覚を失う毎日だった。高校生になったある日、急に話せなくなったことがあった。一生をかけてその言葉と身体を取り戻すことがこれからの私の目標だ。
イリナさんも工場で働かされ、こう綴っていた。工場や組織の中で働くことは本質的に人に何かを強いる。暴力的な側面が含まれ、それが多いか少ないかだけのことだ。身体だけでなく組織に属すると使える言葉は限られる。反対の意思表示は難しい。仕事のための言葉を使い、情報に向き合い、アウトプットすることで、自分の感覚が鈍っていく。そういったコミュニケーションは、国家に不都合な言葉を消した『1984』の世界とどのくらい違うのだろう。そうしている頭の中に傷ができていく。ぼくは本を読めなくなるときがある。身体は疲れていないのに、文字が入ってこない。ロボットとしての言葉がリピートされてしまい、切り替えられなくなる。
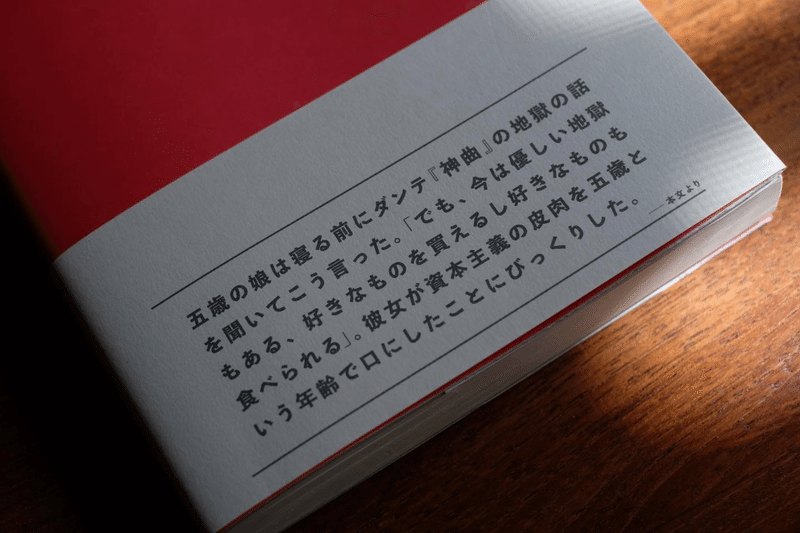
社会主義は生きていることだけを許し、人を道具として使ったんだと思う。でもその点については資本主義も変わらない。「資本主義では完璧な身体でいることを求められる」、イリナさん怪我しながら旅行した香港でそう感じた。道具としての人間を求めるのは、イデオロギーの問題ではない。デヴィッド・グレーバーが『官僚制のユートピア』という本を書いている。彼のいう官僚制とは官僚的な組織全般を指している。国や行政に限らず、民間企業の階層組織も含まれる。組織の問題として捉えると、社会主義も資本主義も根本的にはあまり変わらない。社会主義国家は中央集権化された官僚組織だけれど、企業も生産性を重視した官僚組織であるのは同じ。むしろ厳しい競争によって、企業の従業員は目的のための服従をもっと強いられる。資本主義は、無数の社会主義的な組織によって構成されている。
でも、今は優しい地獄もある、好きな物を変えるし好きなものも食べられる。
イリナさんがダンテ『神曲』の話を聞かせたときに、5歳の娘が資本主義社会をそう表現した。そんな地獄の中でイリナさんが生きていて、ぼくも生きている。死ぬわけではない、けど優しい地獄は終わらない。彼女の「一生をかけてその言葉と身体を取り戻す」とはどんなものだったのだろう。そう思いながらこの本を読んでいた。ひとつは、本や映画をだった。ドゥルーズ、ベンヤミン、タルコフスキー、ガルシア・マルケスが彼女の思考を照合し拡張してくれるのかもしれない。哲学やフィクションは、鈍った感覚や言葉を甦らしてくれて、下支えをしてくれてどこかに居場所をつくってくれるのだと思う。もうひとつは、家族や彼女とともに過ごした人との想い出だと思う。記憶としてだけでなく、祖母から学んだ料理を作るたびに祖母を思い出したり、父が送ってくれたワインととともに蘇る葡萄を素足で潰した感触であり、身体に染みついたものだった。日本に来てから田中泯さんの踊りに辿り着いた。
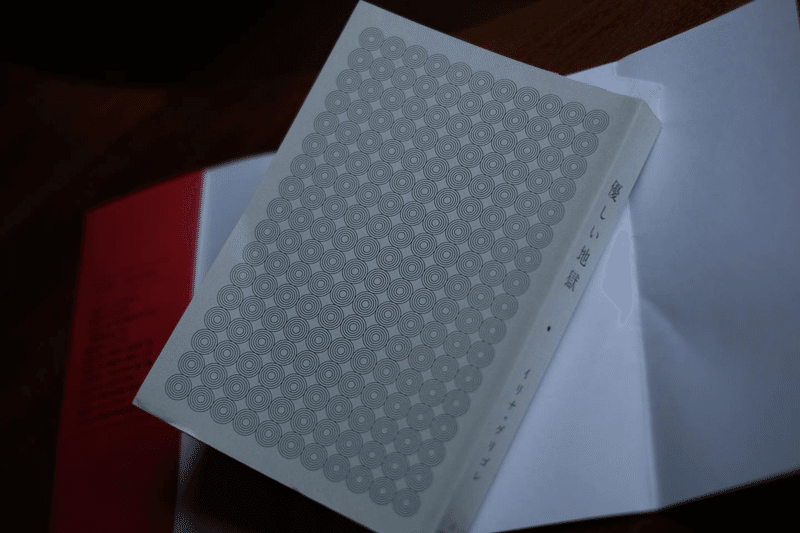
イリナさんは社会主義の国に生まれ、川端康成の『雪国』で日本語に憧れ、家族に学者がいない中で人類学者、青森に住みながらとしてフィールドワーク続けている。人生設計とかキャリアプランとか、目標をもって生きなさいと言われ続ける。目標や計画はある程度は必要だし、そうしないとかえって疲弊することもある。けれど長いスパンでのそれは優しい地獄により深く沈んでいくということになる。彼女は自身の中に場所が反復されているといい、ドゥルーズの『差異と反復』から引用する。
「反復すること、それは行動することである。ただし、類似物も等価物でもない何かユニークで特異なものに対して行動することである」。また「そして、そのような外的行動としての反復は、それはそれでまた、秘めやかなバイブレーション、すなわち、その反復を活気続けている特異なものにおける内的でより、深い反復に反響するだろう」
この現在地に対して自分の言葉と身体を反復させることで、次の何かが生成する。優しい地獄を耐え忍ぶだけにせず、その状況を有り難いものとして受け取って行動する、そういうことなのだと思う。ぼくは目標や計画に拐われてしまってないだろうか。この場所と対峙できているだろうか。地獄に陥らないためにも。
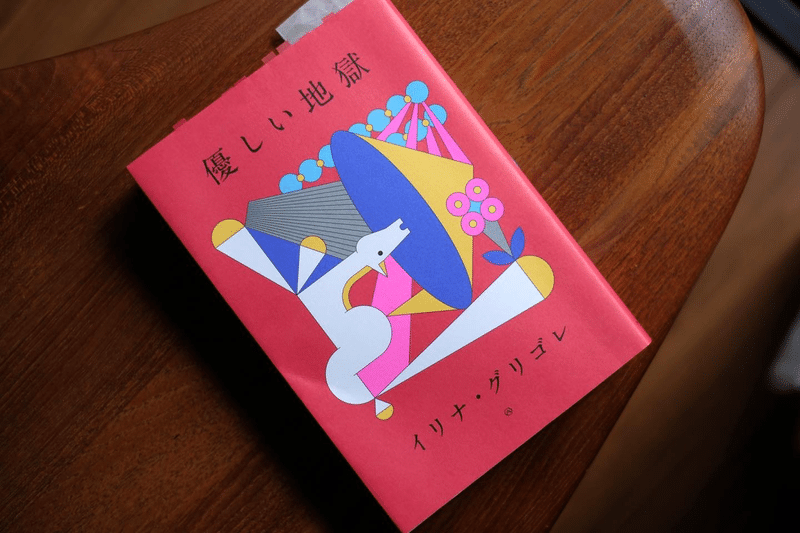
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
