
本当に『さよなら、男社会』したい。。。
先日こんな場面に出くわした。ある男性上司が女性の部下に指摘をした。社内Slackの発信がちょっとしたトラブルになったからだった。男性のちゃんとやっとけとよ、といった言い草に女性はカチンときた。彼女は確認をとってから投稿したにも関わらず、トラブルの落ち度はあなたにあるかのように指摘されたことが我慢ならなかった。
この女性はかなり弁が立つ。自分の伝え方にも非はあるものの、あなたにも非はあるということを明確に問い詰めた。はぐらかしと問い詰めの応酬が続いた。上司は言い淀みはじめ、語気は徐々に弱まっていった。上司はどうやら涙ぐんでいる様子だった。彼にも言い逃れのできない非があることを認めたようだった。
いい加減さもあるものの根のやさしい彼は、己の内の許し難いのものに気づいたのだろうか、閾値を超えて涙が込み上げてきたとうだった。すると女性も涙声になった。もらい泣きしたらしい。そんな場に居合わせたぼくはとても気まずかった。
側から見ていると、男性上司が序盤に謝ればいい話だった。謝れず、引き下がれなくなって、涙の騒動になった。10歳くらい違う男女が一緒に涙ぐんでいる。当人たちの気持ち穏やかではないと思う。でもぼくはなんだかいい場面を見せてもらったと思っていた。
その涙は子供が喧嘩をしてお互い泣き出すような、そんな場面だったと思う。それが会社という場で起きたのがよかった。つくづくそう思ってしまうのは、社会人あるべき姿といった堅苦しい構造を逸脱しているからだと思う。
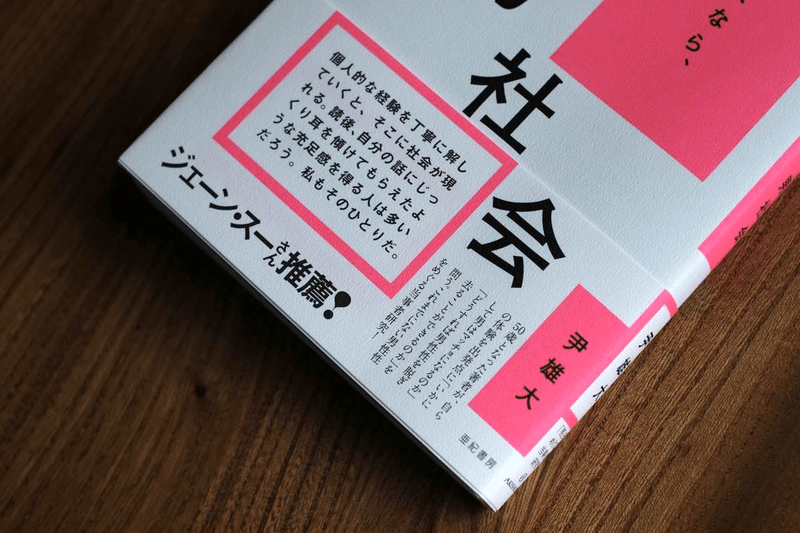
その構造とは男社会とも言い換えられます。ジェンダーやポジションや年功序列が強固に絡み合った構造に抗うことはなかなか難しい。ぼくは会社という場所はとても居づらい。部活動や体育会系のようなノリには馴染めない。でも多くの会社にはそういったノリが充満している。利益の追求というときに無理難題な目標のために、そのノリに乗ることが求められる。
克己心という意気込みを強調すればするほど、実際の自分とそうなりたい自分との間にズレが生じるはずなのだが、大人たちはそうした感覚のもたらす違和をどうやら問題にしてはいなかった。おそらく現実と理想のズレがあったとしても、それは一致できない「心の弱さ」で片付けてしまうのだろう。
こういった引用をしながらも、この文に同意してしまうのは自分が弱いからではないか?と思ってしまう。組織に属していると、組織に問題があったとしても、そういった指摘はできない。面倒な奴とタグ付けされて、居づらくなりたくないと思ってしまう。だから自分の責任として、改善の余地があってそこに取り組むと誓わなければならない。ビョンチョル・ハンの『疲労社会』にあった「肯定性の過剰」というものにも通づる。あなたはできるはずだという肯定だけはしてくれるものの、成果を出せないのはあなたの努力が足りないとだけ宣告される。
生き延びるための戦略が習慣となるに従い、元々の気質を上書きするように慎ましくあろうとする態度が自分を覆うようになり、次第に自身に対する共感は後退し、疑念が湧くようになる。うまく立ち回るという性格は何も積極的な行動でのみ発揮されるわけではない。遠慮がちな態度によっても可能なのだ。それが表面的にうまくいくほどに、深いところでは「自分は何かを演じていない限り、周囲から認められない」という疑いが増す。
ニュースや人から聞いた話だと明らかにおかしいと感じることでも、自分のことになる目を瞑る。大勢の側に居場所があったり、上司やリーダーから認められるために、自分の考えには蓋をしてしまう。組織に感じる違和と排斥されたくない気持ちの板挟みに陥りながら、口角を上げて過ごさねばならない。自分を通すことと組織に居場所があること、その両方があって自尊心は築かれるはずだ。でも現実には、どちらの方が自尊心を維持できるか天秤にかけなくてはならない。
多くの人は居場所を選ぶ。その傷を自分で治ことをす方向には向かわず、通過儀礼かのように人にもその傷を負わせる。もはや護っているのか自傷しているのかもわからない。どちらを選んでも辛いことだから、最後はそこから去ることでしか苦悩からは逃れられない。
こういったことに自覚的でありながら発言や行動をすることもあるものの、多くの部分で無自覚に自動的に行なっていることもあると思う。男社会のルールに息苦しさを感じながらも、ぼくだって誰かにストレスをかけたり傷つけているのだろう。間接的な影響まで含めたらさらに多いのかもしれない。

男社会の根深さを目の当たりすることがある。表向きは既得権益に批判的な人であっても、その人のつくった組織も男社会が色濃い、そんなことはよくある。そんな場面を繰り返し出くわすと、この男社会というよりも組織をつくること自体に、男社会的な性質が不可分なのがわかる。
リン・スタルスベルグの『私はいま自由なの? ー男女平等世界一の国ノルウェーが直面した現実』では、女性には働くための支援が用意され、男性の育児休暇が取りやすくなったノルウェーの社会が描かれている。それでも女性は出産という生まれながらに備わった役割のために、いつまで経っても子育ての役割を期待されている。
男社会が仕方ないと言いたいのではない。男も辛かったんだと言いたいわけでもない。ひとつ言えるのは、この資本主義社会の中で男は働かせやすかった、それによって社会的な立場を得やすかった、その代わり女性に家事や子育てを任せる理由にもなったということだ。ジェンダーによる差別を無くし、能力主義になったとしても、別のヒエラルキーが生じるでしょう。経済格差や貧困の問題もあります。経済合理性を掲げて無理をさせて無駄をさせない。そんな社会であるかかぎり、男社会が解消できたとしても生産性の良い人たちとそうでない人たちという差別によって、新たな〇〇社会が生まれてきてしまうだけだと思うのです。
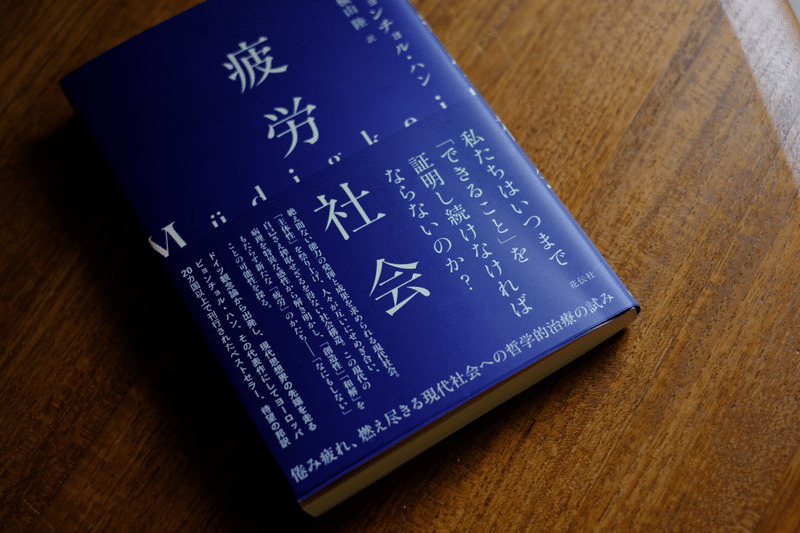
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
