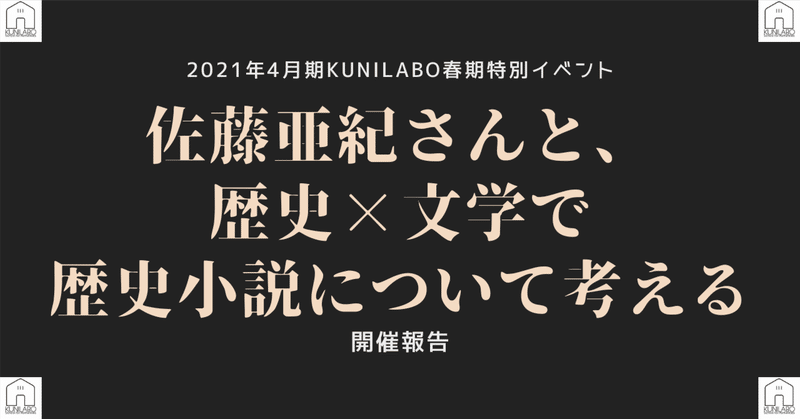
「佐藤亜紀さんと、歴史×文学で歴史小説について考える」開催報告その③
KUNILABO×東北大学日本学研究会 イベント
「佐藤亜紀さんと 歴史×文学で歴史小説について考える」
2021年3月9日に開催され、90名定員いっぱいの参加者を集め、好評を博したイベントの開催報告その③です。今回は参加者の感想です。
【開催概要】
https://kunilabo202103onlinehistoryliterature.peatix.com/?lang=ja
【感想①】
泉谷瞬(近畿大学 文芸学部 文学科 講師)
「佐藤亜紀さんと、歴史×文学で歴史小説について考える」で交わされた議論は多岐にわたるが、中心となるキーワードを私なりに挙げるならば、それは「想像力」である。
佐藤亜紀氏の講演「歴史小説の技法」では、日本の近代文学における「歴史小説」の条件(と一般に考えられているもの)を検討するところから始まり、西欧文学との比較や海音寺潮五郎の発言などを参照することで、歴史学研究と「歴史小説」の間に生じてしまっている越えがたい壁が指摘された。講演内容からまず窺えるのは、歴史学研究が積み重ねてきた理論と手法に対する佐藤氏の敬意である。それは、集合的な営みとしての学問が持つ力への信頼と言い換えてもよいだろう。しかし同時に、日本の「歴史小説」が提示する「想像力」は、研究が持つ力に果たしてどこまで並ぶことができているか、という疑念も感じられた。
これは、歴史学研究の成果によって個別の文学作品を「検証」するといった単純な話ではもちろんないだろう。佐藤氏いわく、歴史学研究の態度とは「すべてが(仮)=かっこかり」であり、当座の間、“それ”を事実として扱うというのが基本である。だからといって、どんなものでも「(仮)」に放り込めるわけではない。十分な調査と史料批判の蓄積によってその蓋然性は保証されており(これこそがまさに「集合的な営み」だ)、そこから導き出された他者性にこそ「歴史小説」の「想像力」は対峙しなければならないのではないか――そのような関係として、両者が対比された意味を私は受け取った。
以下、個人的な話題となることをご容赦願いたい。本イベントに参加していて頭に浮かんだのは、自分が以前に分析対象として調査したことのある日本文学作品である。この作品に対する分析をどのようにまとめるか、いまだに保留しているので具体的なタイトルは伏せたいが、「私小説」に近いスタイルで1940年代後半に執筆された小説とだけ述べておく。
この小説には、作者が体験した戦時中のある出来事が描かれている。登場人物の名前以外、地名や施設などの固有名詞はほぼそのまま採用されているため、舞台を具体的に追跡することが十分可能となっている。物語の中心となるのは、1925年のジュネーヴ議定書において使用が禁じられたある化学兵器の製造である。結末では、この製造にまつわる悲惨な事故が提示されるのだが、モデルとなった施設に関する記録・証言集と比較する限り、当時に起こったはずの事実を正確に近い形で記述していることが明らかとなった(作者はその関連施設に勤務していたことも判明しているため、同じ事故を見たと考えられる)。
しかし、一点だけ小説と記録の指し示す内容が食い違う箇所が存在するのである。小説の場面には、記録に残っていないある人物が「追加」されており、しかもその人物に課せられた境遇こそが、作品全体の主題を代弁するものとして解釈できるように構成されている。
この追加された存在こそを、本作の「想像力」と呼ぶべきなのか。仮にそうであるならば、それによってどのような他者性を本作は出現させているのか。こうした分析を適切に言語化できるだけの力が今の私にはない。すなわち、こちら側の「想像力」がまだ追いついていないのである。ならば追いつけるように努める必要がある。
劣情の混じった、非常に狭い決まりきったサーキットをくるくる回ることを「想像力」と呼んでいないか。――佐藤氏が述べたこの言葉を、読者の立場である私も常に肝に銘じておきたい。「想像力」とは我々の願望に奉仕するものではなく、むしろまったく逆の道を進むことで我々を常に当惑させるような力なのだろう。
【感想②】歴史と歴史小説について何も知らなかったと知った日
ひつじ(KUNILABOスタッフ)
歴史小説とは? とそもそも真面目に考えた事がなく、今回の主題「歴史✕文学で歴史小説について考える」を目の当たりにして初めて「そう言えば、自分は歴史と歴史小説をそれぞれどう捉えていたろう……」と改めて考える事になりました。講座概要にあるように、「歴史小説=大河ドラマの原作、司馬遼太郎のいくつかの小説」がまず代表的なものとして頭に浮かびます。では、池波正太郎の『仕掛人・藤枝梅安』は? それは確か時代小説と呼びます。何故そう区別するのか。それは架空の人物が主人公であり、話もあまり史実にもとづいていないから。何故架空の人物が主人公ではだめなの? では『平家物語』は? 出来事のほとんどは史実に基づいているし、主人公は架空の人物ではないとされている。でも、那須与一の扇の的や、源義経の八艘飛びは、超人的な英雄の活躍であって、作り話としか思えない。そういう点を見ると、あまり歴史小説っぽくない。でも、そもそも『平家物語』を歴史小説とは呼ばない。どうして?
考えるほどに、私は何故この疑問を曖昧なまま考えずにいたのかと情けなくなります。
佐藤亜紀さんが解説された通り、現代日本の歴史小説とはまず「主人公は実在した歴史上の人物。また、武将であり、維新の志士であり、武士階級。筋書きはその業績を追っていく事にあり、政治史の展開を物語化している。また、史実に忠実であることが、たいへん重要とされる」です。この条件を備えているのがまさに司馬遼太郎の小説であり、典型と言えそうです。そして、もうひとつ、「日本人の大半が歴史に興味を持つと手に取る本は、アカデミックな入門書やガイドではなく歴史小説である」という傾向も、顕著でしょう。ああ、耳が痛い……。黒岩重吾を読んで聖徳太子の生涯と業績を知ろうとしていた暗い過去がよみがえって参ります。
これらのお話をうかがい、歴史教育の面からもこの傾向は見られる事が連想されました。現代日本で「歴史」というと「何があったか」の「出来事性」よりも、「英雄譚」「メッセージ」等を伝える「物語性」をイメージする人が多いと聞きます。「歴史が好き」というとき、「過去に何があったか」という事実やその検証や真理を求める行為等の事を指さないそうです。何故なのか。それは、「歴史」自体が国民国家の持続性と深く結びつき、国をまとめあげる力として活用されています。「歴史」は日本人の物語を共有させる道具と政治的に意識されている例は昨今身近に感じる事も多いと思います。
私のようにこんなにうかつになんとなく「歴史」や「歴史小説」について捉えていると、プロパガンダ的な物語性にからめとられる危険もまた常にあります。
そんな不安を懐き始めたときに、佐藤亜紀さんがおっしゃったのは「他者と向かい合う」というお話でした。自分とはまったく違い、分かり合うこともないけれど、そこには確かに人間がいる。歴史研究のように史料を丹念に追って行くと、小説家を想像の外の世界に引きずり出してくれる何かがある、と。
これは読者としては、いわゆる「作家の想像力で生み出す物語」に飲まれないための方法にも思えました。事例のひとつに、『黄金列車』に関連する名簿のお話が出ました。ハンガリーを出る時に黄金列車に乗るはずだった人員の名簿には、乗車予定者の生年月日と出生地が書かれていたそうです。佐藤さんは出生地を見ていくだけでも推測が進むことがあったといいます。それは名前に加えられる学歴から読み取れる上級職員の出身地が、誰もブダペシュトではないということ。また、子供の数と生年月日から、いつ頃家庭を持ったかも推測する事が出来ます。このような情報は、佐藤さんに「地方に任官してから子供を作るのがひとつのコースだったのでは?」という発見を与えました。それでもなお佐藤さんは「行政史を調べてみないとわからないこともある」と、徹底して調べる姿勢を示し「進行中の歴史研究については、謙虚な姿勢を持って臨むもの。歴史についての小説を書こうと思ったときはそれが重要だと考える」と話されたのでした。
それでは、歴史研究を読めるように努力すれば、小説はなくてもいいのでしょうか。そこで秋山晋吾先生から、「そこにあるはずだけれども見えてこない。それをどう史料から読むか、が、歴史研究では重要。『黄金列車』は時代背景だけでなく、ディティールの信頼性が際立ち、確か。都合よくするために書いていると思わせる部分がない。そして、確かにそこにあるのに、歴史研究では論文や著書になりにくい部分を、歴史小説がすくい上げてくれるという役割分担がある」とコメントがされました。
お互いの専門をリスペクトし合う歴史家と歴史小説家の対話。このような両分野の関係が広がっていけば、これからの歴史や歴史小説の読まれ方も新しくなって行くのでは、かつての役割から解き放ち、見つめられる事のなかった魅力が再発見されるのでは、と、希望が募ります。
お手本のような西原志保先生の端正な文学批評、秋山先生の歴史家の視点で読む歴史小説、また、歴史研究の実例と歴史小説の比較。このイベントの開催拠点となった国立人文研究所。これからも、人文学の分野横断的な対話や、対話が一般に開かれる事で、より人文学が多くの人に良いものを与え、発展しますように。
KUNILABOの活動、人文学の面白さに興味や共感いただけましたら、サポートくださいますと幸いです。
