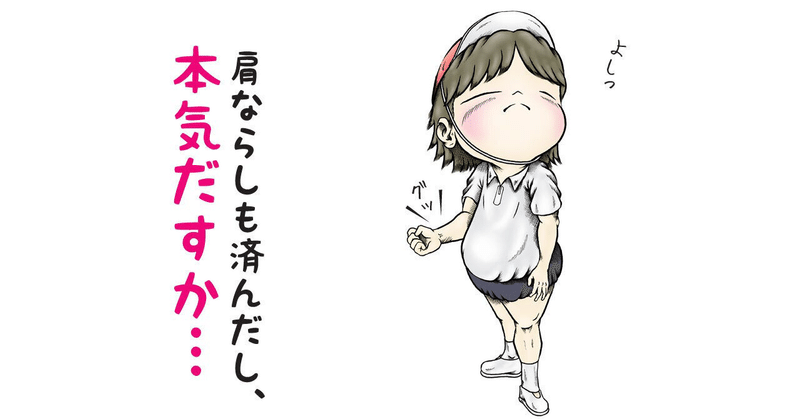
体育の授業(器械運動)について
今回は体育の授業について書いていきます。
体育は子どものころから、個人的に一番好きな授業でした。が、その分苦手な子たちの気もちを考えて授業づくりをするように心がけています。
行う種目によって、かなり流れがちがうのですが、今日は跳び箱やマット運動などの器械運動系の授業で流れを書いていきます。
基本的な流れは
①ミニレッスン
②今日の目標確認
③個人練習
④振り返り
というシンプルな流れです。
一つずつ解説していきます。がその前に、大前提として、器械運動系の授業では必ずといっていいほど、学習カードを配ります。
学習カードは、自分で作る場合もありますが、多くの場合、インターネット等で探して活用させてもらっています。
以下、一例として、このようなサイトのものを使うことが多いです。
学習カードを配り、この単元のゴールを確認します。
例えば、
「4つの技をマスターして、タブレットに録画しよう」
などです。
ゴールをはっきりとさせてから、授業に入ります。
ではここからは授業の流れです。
①ミニレッスン
毎回の授業のはじめには、ミニレッスンとして指導を入れています。
例えば、マット運動であれば、後転のコツなど、子どもたちがつまづきやすいポイントを実演(子どもにやってもらうこと多し)を交えて行います。
②今日の目標確認
それぞれ、学習カードをもとに自分の目標を立てます。この時、目標の高い、低いは特に言及しません。
ゴールは最初に確認しているので、そのゴールに向かい、この時間どのような目標を立てるかは子どもたちに任せます。
③個人練習
目標を決めたら、それぞれ練習に入ります。この時、クラスの実情にもよりますが、特にグループ等は決めません。
一人で集中してやるもよし、仲間とアドバイスしながらやるもよしとします。ただし、意図的に一人にされている場合は別です。(仲間外し等)こちらで場所やグループを指定して行います。
④振り返り
授業が残り7~8分になったら振り返りを行います。この時間の目標に対して達成度はどうであったか振り返ります。
この振り返りをもとに、次回のミニレッスンの内容を考えます。
上記のような流れですが、状況に応じて途中で指導を入れたり、個別にアドバイスをしたりするなど担任は動きながら見取ります。
初めに書いたように、体育は種目によってかなり進め方がちがうので、おいおい種目ごとに書いていこうと思います。
本日もお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
