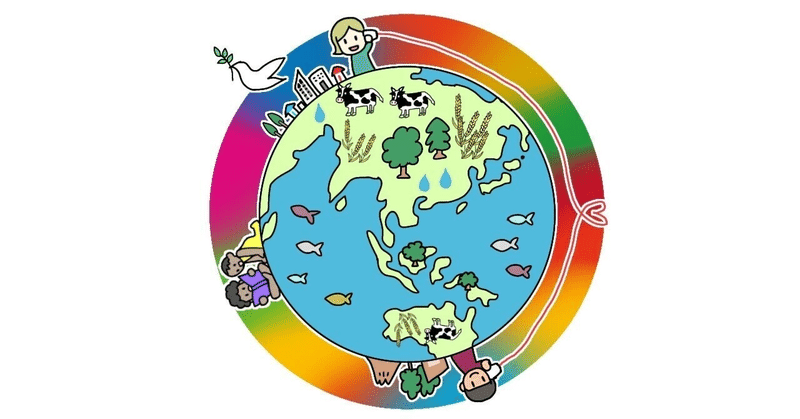
ナージャと共に、一緒に6か国で学んだ気になってしまった私がいろいろ考えたこと
読み出したら、あまりに面白くてツボにはまり、肉じゃがを作る鍋の前でも手放せず。新鮮な驚きと、ユーモアさと、なるほどなあ・・・との思いが絶妙にミックスした本。
『6か国転校生ナージャの発見』 キリーロバ・ナージャ
筆者のナージャさんは、ソ連・レニングラード(現ロシア・サンクトぺテルブルグ)生まれ。タイトルにもあるように、6つの国・4つの言語で教育を受けた彼女。なんと、小中学校は毎年違う国に現地校に通い、小学校は3回卒業!
ロシア→日本(京都)→イギリス→フランス→日本(東京)→アメリカ→日本(東京)→カナダ→日本(札幌)と、聞くだけで頭の中がくらくらする。
私自身、中学生の時に転校したことがあるけど、同じ市の中学校だった。それでも、友達もいないし学校のルールやら、持ち物やらが全部違い、慣れるまでちょっと心細かった。
そんな比ではない、ナージャさんの小中学生時代。両親の転勤と共にそれぞれの国で受けた教育は、驚きの連続だったようだ。
例えば、水泳。彼女は、5歳から中2まで水泳を習っていたから得意だ。しかし、小4で日本のスイミングスクールに通っていた時のこと。初日、ちょっと泳いでみてと言われ、バッチリ泳いだ彼女に降りかかってきたものは、先生の怒鳴り声。「フォームがなっていない!」
そう、日本はフォーム重視なのだそうだ。カタチが大事。だから泳ぎがうまくても、ビート板を使った基礎練習をおろそかにしない。
ロシアはスピード、日本はカタチ、アメリカは持久性、カナダは総合力が重視されるとのこと。そんな中で、彼女は水泳を通して、何を学んでほしいのか。何のために習い、何のために習わせるのか。考えることで自分にとってベストなやり方が見え、これは、スポーツや勉強に共通していることかも・・・と述べている。
なるほど・・・
環境が変わると変わるものが「ふつう」なのだ。だから、まわりと違う自分の「ふつう」こそが、「個性」の原料だとも。
もう一つ。「苦手なことは克服しなくてもいい!」とのこと。苦手をしっかり実行したら、ルールの抜け道を探し、自分がこれならできるやり方に変えてみて実行してみる・・・のがいいそうだ。
これは、苦手が多い私にとって、希望の光が差し込むようだ。嬉しい!
いろいろ考えさせられるこの本は、やっぱり、私にすごい宝物を授けてくれたようだ。
・上記、本書 P75~78、P116、P122より、抜粋、引用
#教育 #ハマった沼を語らせて #読書感想文 #6か国転校生ナージャの発見 #キリーロバ・ナージャ #日本語教師 #言語
もしサポートいただけたら、とてもありがたいです。自分をより向上させるための書籍購入や研究会、勉強会の参加費用にします。また、日本在住で中国語圏生徒達の日本語学習のフォローにあてたいです。
