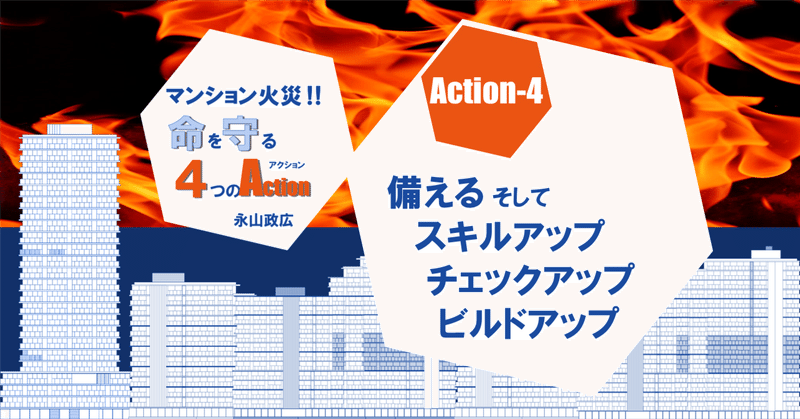
【マンション火災‼ 命を守る4つのAction】Action-4 備える そして スキルアップ・チェックアップ・ビルドアップ
はじめに
1995年 阪神・淡路大震災
2011年 東日本大震災
2016年 熊本地震
そして2024年 能登半島地震――。
何年かおきに繰り返される自然災害は、幸福な日常を、非日常の深い闇へと突き落としてしまいます。
一方で、火災は、毎日のように日本のどこかで繰り返されている、ありふれた出来事かもしれません。
しかし、その日常の災害により、毎年1500人前後の人命が失われ、1千億円以上の損害を被っているという事実に目を背けるわけにはいきません。
そしてマンション――
災害に強いと言われていますが、実のところどうなのでしょう。
本当に強いのだとしても、
どうして強いのか、どこが強いのかを理解しないままでいたら、
その効果を十分享受できないのではないでしょうか。
マンションの一室に目を向けてみると、
そこには、戸建て住宅とそれほど違いのない光景があるはずです。
もし火災が起きたとしたら、と想像したことがありますか?
そして、災害に強いというマンションが、どのようにして守ってくれるのか、考えたことがありますか?
本書は、そうした思考の道案内をするべく書かれたものです。
これまでの固定概念を一旦クリアし、
ご一緒に考えていきましょう。
マンションの火災から、
どのようにして自分自身を、大切な家族を、そして財産を守っていくのか。
順序だてて考えを進めていくために、やるべき事柄を段階別に分類しました。これが4つのAction(アクション)です。
それぞれを単独で読まれても、理解できる構成にはなっていますが、
やはり、Action-1からAction-2へというように、順番に従って読み進める方が最も効果的でしょう。
また、【参考】と掲示した部分は、より深く情報を得たい方のために加えたものですから、飛ばしていただいても文脈から外れることはありません。
Action-3からの続き
火災で起きることを想像し、
火災から守るための設備を確かめ、
そして、火災時の行動を考えてみました。
その成果を活かすためには、
もう一つのActionが必要です。
一人ひとり、各住戸、そしてマンション全体の備えが欠かせません。
そして、その備えを実効性があるものへと
高めていくことが重要なのです。
4.1 最も重要な備えは出火の防止
どんなに迅速に消火したとしても、ひとたび出火してしまうと、様々な被害が生じてしまいます。
何よりも優先して取り組むべき備えとは、出火を防ぐことではないでしょうか。
そのためには、どのようにして火災が起こるのか、その原因を理解しなければなりません。
まず、住宅火災の出火原因を調べてみましょう。
■火災統計を見てみると
2022年中に日本国内で起きた11,411件の住宅火災を、出火原因ごとに分類してみると、次のグラフになります。

(消防庁「令和4年における火災の状況」に基づき作成)
コンロ、タバコ、ストーブ、配線器具……。
身の回りにあるものばかりですね。
出火原因となるこれらのものを、単に「危ないもの」と遠ざけるのではなく、どうして出火につながるのかを理解すれば、安全に使うことができるはずです。
順に見ていきましょう。
■コンロからの出火は不注意から
コンロは、以前から住宅火災出火原因の上位にランクされています。
様々な出火パターンがありますが、代表的なものは、天ぷらなどの揚げ物中に、油が発火してしまうことでしょう。大半は、調理中にその場を離れてしまうという不注意によるものです。
そのため、メーカーでも様々な工夫がなされてきました。その一つが、調理油過熱防止装置です。
揚げ物用の油は、340~380℃くらいになると発火してしまいます。それを防止するための装置なのです。現在市販されているガスコンロは、すべてのバーナーに、この装置が取り付けられているわけですが、どういうわけか調理油から発火する火災がなくなりません。
どうしてでしょうか?
詳しく話を進める前に、調理油過熱防止装置について説明しましょう。バーナーの中央部に写真のような突起物があるはずです。これが、この装置の温度センサー部になります。

上から押すと下がり、離すとバネの力で戻るようになっており、センサー表面が鍋の底に密着し、鍋の温度を適正に測定することができます。
250℃くらいになるとセンサーが働き、ガスを遮断するようになっているので、とても340℃には達しないはずですが……。
その理由は、鍋に原因があるのです。

図のように鍋底の変形や傷、焦げ付きなどによってセンサーに正しい温度が伝わらず、鍋の温度は340℃に達しているのに250℃以下と判断してしまうのです。
調理油過熱防止装置は、調理を自動化するためのものではありません。本来人間がしっかりと油温を管理すべきものであり、そのときに生じるヒューマンエラーの一部をカバーしてくれるだけです。
鍋の不具合まで検知することは難しく、カバー範囲には限界があります。
ですから、「調理中は、火元を離れない」という大原則を守るべきでしょう。
「わずかな時間だから」と、その場を離れてしまうことが多いのではないでしょうか。しかし、点火してから10分以内に発火した事例もあるくらいですから、油断できません。
このようにガスコンロは、ちょっとした不注意から出火してしまう危険があります。その点、電磁調理器(IH)なら大丈夫だと安心する人も多いのではないでしょうか。
しかし、そうとも言えません。IHでも不注意により出火してしまうことがあるのです。
IHでもガスコンロと同じように温度センサーを配置し、過熱されないようにヒーターの出力を制御していますが、次のようなケースでは、正確な温度測定ができなくなってしまいます。

いずれのケースでも厄介なことに、鍋が僅かに浮いた状態でも加熱ができてしまうということです。
したがって、ガスコンロと同様に、安全装置に過信はせず、調理場を離れないということが重要です。
■タバコは息を潜めながら出火する
ご存じのとおり、タバコの火力は微々たるものです。少し押し付けただけでも消えてしまいます。
そのようなものが火災を引き起こすなんて想像しにくいかもしれませんね。
タバコをはじめ、線香や火花などは微小火源と呼ばれ、共通した出火メカニズムを有しています。
それは、まるで息を潜めているかのように、じわりじわりと燃え広がっていくのです。
次の図は、タバコ火災の再現実験を行ったときのものです。

吸い殻が挟まっているのに気づかず、押し入れに布団を入れてしまった状態を想定しました。内部が見やすいように扉の代わりにビニルシートで仕切られています。
30分経過したくらいでは、それほど大きな変化がなく、1時間経過したあたりで、ビニルシートの隙間から煙が漏れるようになってきました。
これくらいの状態では、煙感知器が作動しないかもしれません。
それから16分後に奥の方から炎が立ち上がります。
このように微小火源は、火種が残っていても気づきにくく、かなり時間が経過してから出火するのが特徴です。
この実験では1時間程度で出火しましたが、条件次第ではさらに遅くなることもあり、丸1日経過してから出火した事例もあるくらいです。
次のような出火パターンがありますので、大丈夫だと思わず、細心の注意を払いましょう。

いずれもすぐには発火せず、周囲の可燃物とともにくすぶり続けます。この状態は、炎が見られないので、無炎燃焼と呼んでいますが、ある程度の熱エネルギーが溜まると炎を上げて燃え出すのです。(有炎燃焼)
無炎燃焼中は、かなりの一酸化炭素が発生します。
直接死に至るほどの濃度はありませんが、長時間吸引すると身体の感覚が麻痺し始めるので、侮れません。出火に気づいたとしても身体の自由が利かず、逃げることができなくなるかもしれないのです。
寝タバコでの火災は、こうしたパターンに至ってしまうことが多く、息を潜めて襲ってくる悪魔のような存在だと言えるでしょう。
■ストーブ火災は油断から
ストーブからの出火と聞くと、次のような場面を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
石油ストーブの上で洗濯物を干しておいたところ、何かの拍子に落下して燃えだしてしまった――そのような設定を再現した実験です。

この映像を見れば、誰もが納得するような顛末ですが、こうした事故はなかなか減りません。これまで大丈夫だったからと、油断してしまうのでしょう。
このようにストーブ火災の多くは、「慣れ」という油断から発生しているのですが、別の意味の油断でも発生しています。
それは、電気ストーブに対する「思い違い」です。
石油ストーブの場合、目の前で実際に灯油が燃えているわけですから、近くに可燃物があれば危険だと、多くの人は理解しているはずです。ただ、その安全距離に対する認識が、普段の慣れで麻痺してしまうのでしょう。
一方、電気ストーブは、燃焼しているわけではないので、石油ストーブに比べ安全だという思い込みが起きやすいのではないでしょうか。

電気ストーブでも、石油ストーブに劣らないくらいの発熱性能を有しているものもあるので、決して油断してはいけないのですが、「火を使わない=安全」というイメージが定着してしまったのでしょうか。
東京消防庁の調べによれば、2016年中に発生したストーブ火災112件のうち、約76%が電気ストーブによるものでした。

(東京消防庁「平成29年版火災の実態」に基づき作成)
石油ストーブの場合は警戒し、可燃物の距離を保つように注意するものの、電気ストーブでは安心しているため、距離が短くなってしまうのではないでしょうか。

前図のように布団の近くで電気ストーブを付けたまま就寝してしまい、知らぬ間に布団がずれ落ちて、ストーブに接触してしまうというパターンが多いのではないかと思います。
何かの加減で可燃物が動いてしまうことを予想して、安全な距離を設定しなければなりません。水平方向だけでなく、上方からの落下は、思わぬところまで移動してしまうので、特に注意が必要です。
よろしければサポートお願いいたします!いただいたサポートは災害研究の活動費として使わせていただきます。

