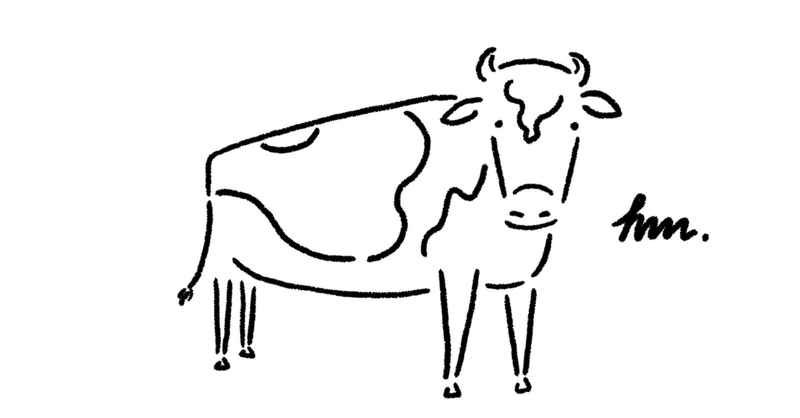
場違いなほど美味しすぎた「熟成肉店」のお話。
8年ほど前の話だろうか。
最寄りの駅近くに「場違い」なほど美味しい「熟成肉店」があった。
大通りに面しながらもまるで人気(ひとけ)がなさそうなその店に、私はたびたび目を奪われていた。4階建ての食彩館という施設に様々なジャンルの飲食店が箱詰めされていて、ちょうど一階の部分、ちょっと奥まったところにその店は看板を出していた。少し足を踏み入ってみなければそこにスペースがあったことなどふと忘れてしまう、極力存在感を消したみたいな佇まいだった。
だが、それが特に私の目をひいたのだ。知る人ぞ知るを体現するかのような隠れ家的な店に、まだ学生だった自分は密かに憧れていた。
社会に出て間もなくの頃だ。ボーナスの使い道に苦心していると、友人から声がかかった。
「あの熟成肉店に行ってみない?」
その提案には驚いた。あの店が気になっていたのは、私だけかと思っていたからだ。まさか友人たちも注目していたとは。案外ああいった佇まいのほうが人の目をひくのだろうか?と疑問を口にすると
「いや、いつも話してたじゃん。いつか、あの店行きたいって」
と笑って返された。
実は私には「話したいコトを言ったそばから忘れてしまう」という悪癖がある。だから過去の私と現在の私が一致しないことがしばしばあるのだが、どうも過去の私は口酸っぱく「この熟成肉店に興味がある」と触れて回っていたらしい。(この激しい物忘れが後々ある障害だったと分かるのだが、今回の話には関係がないので割愛する)
他人事のように「過去の私、ナイス」とかおちゃらけながら、持て余した給料の使い道が決まった。時期は3月だったか。積雪もすっかり溶けきった頃合いだった。
入店のエピソードに移る前に、今回同伴した3人の友人たちについて話をしたい。
中学時代の同級生なのだが、実は当初は仲が良いわけではなかった。中学を卒業すると、見事に別々の高校に進んでまったくの疎遠になった。それこそラインに登録すらされていない人もいた。学校の連絡網を食い入るように見てなんとか連絡がつく、といった具合だ。内一人とは個人的に繋がっていたが、頻繁に連絡を取るような間柄ではなかった。
高校を卒業した頃、彼らとは同窓会で再開を果たした。そして奇妙なことに、なぜかその場で意気投合したのだ。中学の時に仲が良かったかと聞かれれば、まったくもってそうではない。その4人で遊ぶ機会などは一切なかった。個人的に繋がっていた一人とはたまに遊びに出歩く程度の仲であったが、他二人とプライベートで遊ぶ機会など皆無だった。
だが、高校生活まるまる3年間を経て、たまたま同じような性質のベクトルに人間性が変化していったのか、4人で一緒に居ることがたまらなく心地よい時間になっていた。
公民館ホールでの成人式の日なんて、当時高校の生徒会長だった男性の登壇をぼんやり眺めながら、一連のプログラムが終わるやいなや、さっさと4人揃って引き上げた。クラス毎や部活毎で集まった華やかな人だかりを尻目に、適当なお酒を近所のコンビニで買って私の家に駆け込む。そうして始めるのは決まって麻雀だ。
私達は麻雀が好きだった。点レートを賭けたりするようなホンキのものではないが、カジュアルに、それでいて三味線をひきながら(※)互いにしのぎを削る場がなんとも愉快で楽しかった。笑いが耐えなかったが、一時的に帰省していた叔父さんから「うるせぇぞ!」と包丁片手に怒鳴り立てられるぐらい盛り上がってしまうのが偶に瑕だった。
(※)三味線を弾く
本来の意味は「口で三味線の伴奏を真似ること」だが、いつしか「口先で相手を巧みに騙すこと」という意味でも使われるようになった言葉だ。 これが麻雀にも持ち込まれ、「嘘を言って相手を惑わせ、自分を有利にする」といった意味合いで使われるようになった。 対局中に使用される場合には「それって三味線じゃない?」
私自身、普段はそうやって人から叱りつけられる程、盛り上がることは少ない部類の人間だったはずだが、この4人で遊んでいるときは例外だった。夜中の公園でとうに見飽きたはずの線香花火をちらしながら、箸でもおちたように馬鹿騒ぎできるほど、童心に戻れた。
もちろんながら、今回熟成肉店に行くメンバーはこの4人だ。
それはもう、お互い感想を語り合って「うまいうまい!」といいながら、けたたましく笑い合う。そんな光景が予想された。
結果はどうだったかというと
『静寂』だった。
いや、店内は適度に騒がしい。別にトラブルに巻き込まれたわけでも、入店前日に誰かの身内に訃報が飛んだわけでもない。春の兆しが見え始めた何の変哲もない土曜日の夜だ。リザーブも滞りなく進んだ。メニュー出しが遅れたわけでも、お冷の継ぎが遅かったわけでもない。
美味しすぎたのだ。その熟成肉が。
あまりに美味しすぎて、全員が感嘆符をあげることしかできず、結果私達のテーブルに広がったのは『静寂』だったのだ。
その店の外見はこじんまりとしているが、内装はガチャガチャとしていてどこかアメリカン風。壁には所狭しと、まるで映画スターのタペストリーみたいな写真がペタペタと張り巡らされていて、窓際のくぼみのへりにはカウボーイチックなマトリョーシカや、シャーマンが彫ったような木彫りの人形が無造作に置かれていた。天井にはくるくるとシーリングファンが回っていて、肉とワインの芳醇な香りを店内中にばらまいている。全体的に木造調で作られた店の雰囲気は、まるでクリント・イーストウッド主演の西部劇に出てくるような酒場だ。柱には「wanted!」とか書かれてそうな勢いで、牛の部位毎の特徴を事細かく紹介したチップスが貼られていた。
テーブルにつくと、よくあるメニュー立てに、冊子状のグランドメニューと、赤身肉によくあうオススメ赤ワイン一覧のラミネートが挟まれている。
まったく手慣れない様子で赤ワインを見つめながら、グランドメニューを開く。前菜、副菜、単品、こじんまりした店の規模に比例して、メニューの数は抑えめだった。
だが肝心の肉がない。戸惑っていると、店員から声がかかる。その手には肩幅くらいのコルクボードが握られていた。そこに「内もも200g」とか「外もも245g」とか「しんたま180g」と書かれたポストイットが列を成して貼られていた。
店員が説明を始める。ここから色々な種類を組み合わせて注文するらしい。それらを同じ皿に乗っけて提供してくれるのだという。とりあえず一人200g食べれるように勘定して、800g注文を取ることにした。指し示したポストイットが剥がされて、一箇所にまとめられる。そうして店員が厨房に引っ込んだ。と思いきや、すぐに戻ってきた。
焼き上げ前の「肉の固まり」が木製のお盆に乗せられて届けられたのだ。隅には臭み消しのハーブが添えられている。赤が際立ったそのビジュアルの強烈さに、思わずアイドルのチェキ会みたいに写真撮影をしてしまった。これを、いまから時間をかけてじっくり焼いていくのだという。大体が30分以上かかってしまうので、お客さんには事前にこうして魅せるのが決まりらしい。なるほど、憎い演出である。まんまと釘付けだ。その肉のブロックは当時の私にとっては「最強で無敵のアイドル」に見えた。
そうして焼き上がる間、適当にサラダを取り分けながら余所余所しい様子で待っていると、いよいよ「肉」がやってきた。先程まで肉が乗せられていた木製の盆に、今度は銀のフタが被せられていた。だが、それはあまり意味がない。なんとフタの端っこから肉の切れ端が既にチラチラと見えているからだ。中身の正体は一瞬の内に看破できてしまったが、逆にそれが私達の期待を高ぶらせた。隠しきれない小さなフタをチョイスしたのは、あえてかもしれない。
そうして、目の前で、まるで年末ジャンボの抽選結果を発表するみたいにジャーンとフタが開けられた。
肉の花が咲いた。
中央にお手製のポテトサラダが添えられており、そこにお子様ランチの旗みたいにポストイット付きの爪楊枝が突き刺さっていた。ポストイットは、先程コルクボードから剥がされたもので、確かに注文した肉の名称とグラム数が書かれている。中央から裾の尾が広がるように、肉という肉がくるりと配置されていた。イメージするなら、ふぐ刺しの肉バージョンみたいな感じ。円を描くように、だが適度に不揃いな形をした肉のふぐ刺しは、まるでローストビーフみたいな艶と色合いだった。ちょっと周りが茶色くなっているだけで、断面はほぼほぼ赤い。これは「生焼け」で食べれないだろう、と私達の本能が感覚に訴えていた。だが、これは食べてよいのだという。味はついているからそのままでもいいし、卓上の岩塩、黒コショウ、オリーブオイルをお好みでかけてもよいという。とりあえずと、4人で示し合わせたように、何もつけずに食べることにした。
一斉に口にほうばる。
訪れたのは、冒頭で言った通りの『静寂』だった。
正確には咀嚼音と感嘆符。私はおもわず手を押さえた。ただただ味覚という一点だけに他すべての感覚器が集約されたような、そんな生き物になった気分だった。しばらくしてから、ハッとしたように友人たちに目をやった。するとどうだろうか、私とまったく同じようなリアクションをしていた。突然盲目になったかのように視線が虚空に向いていて、驚いて顔から全ての表情が抜け落ちてしまっていた。ちょうど口のなかで肉がホロホロと溶けた頃に、やっと私達は目を合わせた。だが言葉はなく、続いたのはそれぞれがニ枚目の肉に箸を運ぶ様子だった。
一枚目の肉では、何が起こったか全くもって謎だったのだ。気を取り直してニ枚目で状況を整理することにした。
まず、一口目はしっかりと「肉」の厚みを感じられた。そうして旨味という旨味が溢れ出すのだが、気がつくと口のなかで雲散してしまう。無くなってしまうのだ。旨味を残したまま、ある程度咀嚼されたそれは、まるでお味噌汁に入った絹ごし豆腐くらいの強度に落ちてしまう。美味しすぎる。だが同時に名残惜しすぎる。待ってくれと言わんばかりに口に運んだニ枚目こそ、先程起こった無言の正体だった。感想を述べるには、あまりにも足りない須臾の出来事。そうしてニ枚目が口の中からどこかに消え去った後で、やっと感嘆符以外の感想を口にできた。
「ヤバい」
もう、全員それだった。哀れにも、その時の私達はこの感動を表現できるほどのボキャブラリーを持ち合わせていなかった。だがこの場合、言葉は無粋だっただろう。この後もしばらく続く感嘆符だけの時間が、その感動を十分に物語っていた。
それから、この肉を食べに来ることが給料日直後の習慣になった。月イチだ。憧れの目で見つめることしかできなかった店舗の、立派な常連となった。
私の住んでいる土地は、田舎といえば田舎だ。とても都心とは呼べないような場所だが、明らかにこの熟成肉店は”場違い”な立地にあった。こんなのは都心の一等地で経営するべきなのだ。なぜこんな辺鄙な場所に来てしまったのか。次元があまりにも違う。だが決して手が届かない値段ではない。せいぜい奮発した飲み会1回分くらいで食べに行けてしまう。いや、行けてしまってはならない。もっと万単位払ってやっと食べれるくらいでなければ納得できない。新卒の私達ですら気軽に来店できてしまうほどリーズナブルだったのだ。
なぜか分からないが、私達はその店に対して意味の分からない文句をつけていた。こんなところに居ていいタマじゃないぞ!と。謎すぎる過大評価であるが、そうでもしないとこの幸運を受け止めきれなかったのだ。
物事には飽きというものがある。
諸行無常。反復する内に新鮮さは失われていき、色褪せていくのが世の常だ。
しかし、この肉の前では、私たちはいつも予防注射前の犬みたいに大人しくなった。はじめて店に入ったあの時のような気持ちが幾度もリフレインする。そうして期待が最高潮に高まっているのに、この熟成肉とかいうやつは常に最高点を叩き出してくる。思い出させてくれる。そのたびに私たちは言葉を失っていた。
当然だが、速攻で口コミをした。といってもネットにかき込むとかそういう活動ではない。別々のコミュニティの友人たちを連れて行ったのだ。私はイイと思ったものに、すぐに他の人を巻き込もうとするキライがある。そして、当たり前のようにファンを増やしていった。
だが、この習慣は途切れることになる。
今から6年前。私が始めて来店した日からだと約2年。その店が閉店したのだ。
私達は、まるで熟成肉をはじめて口にした時のように言葉を失った。
それから嘆いた。一週間くらいホンキで落ち込んだ。友人たちも同じ様子だった。なぜ潰れてしまったのか。まったく理由がわからなかった。だが、同時に、この辺鄙な街で収まるような器ではなかったと、どこか納得していた。
近場の熟成肉店は潰れてしまったけれど、しばらくしてお気に入りの店舗を見つけた。こちらも熟成肉店だ。何かの祝い事だったり、身内で執り行う新年会忘年会は決まってこの店にしている。
食の感動というのは人生を豊かにする。
8年前、あの店に出逢えていなかったら、私の人生はもっと空虚なものになっていたかもしれない。
今日も今日とて、あの赤さにと想いを馳せるのである。

熟成肉とは、一定期間低温で保存した肉。低温保存によって肉の質感、味が変化することでおいしくなる。食肉は、死後硬直後、酵素の働きで保水性が高まり、アミノ酸やペプチドが増加して味、香りがよくなると言われている。
🐈気に入りましたら、ぜひサイトマップも覗いていってくださいな🐈
🍛ついでにインドカレーのお話もいかが?🍛
ネコぐらしは『文字生生物』を目指して、毎日noteで発信しています。📒
※文字の中を生きる生物(水生生物の文字版)🐈
あなたのスキとフォローが、この生物を成長させる糧🍚
ここまで読んで頂き、ありがとうございます✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
