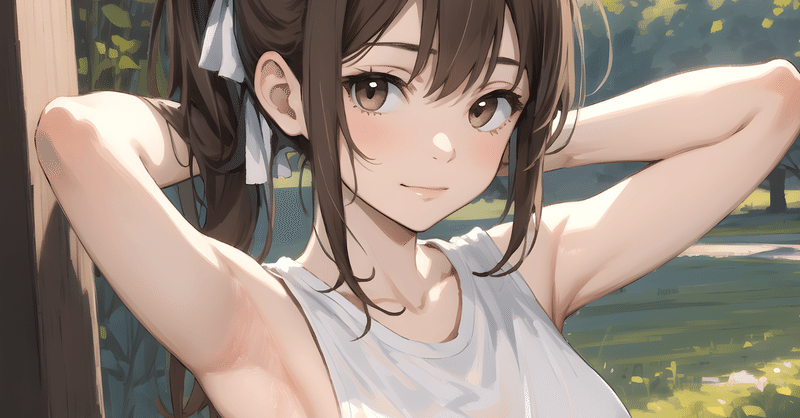
②くすぐりフェチの僕が彼女の死ぬほど弱い腋をローションで徹底的にくすぐって笑い狂わせた話
「ねえ叶実、そろそろ休憩しない?」
夏休みの宿題に絶賛取組中。
テーブルの正面に女の子座りしている唯夏が、数学の問題集から目を離してそう切り出した。
僕――夢咲叶実は、参考書に隣接されたデジタル時計を一瞥する。
「そうだね。もう10時だし、一旦休憩を挟もっか」
朝の8時から始めて、約2時間。
そろそろお互いの集中力が切れる頃合いだ。
まあここまで喋りながらやってる時点で、集中力なんて最初からあるのか怪しいけれど。
「はぁ~~~疲れた!!」
両腕をテーブルに伸ばし、ばたんと前屈みに突っ伏す唯夏。ネイビーのノースリーブが、白くて滑らかな肌を強調している。見慣れたルームウェアだけれど、それが途轍もなく可愛い。下は同色のショートパンツで、足は黒のショートソックスで隠されている。
髪型は今日も変わらずサイドテール。今年のゴールデンウィークに、地毛の黒髪を茶色に染めた。校則では禁止されてないから、他のクラスメイトにも染めている人をちらほら見かける。純白のシュシュは、僕が15歳の誕生日に渡したもの。もう1年くらい経つのに、未だに使ってくれるのは素直に嬉しい。
僕はカーペットに置かれた500mLのペットボトルを手に取り、キャップを開けて中の天然水を一口飲む。冷房が効いてるとはいえ、熱中症対策は怠らない。こまめな水分補給は大切だ。
「お疲れ様。このペースだと、あと1週間で終わりそうだね」
「1週間!? まだそんなにかかるの!?」
唯夏はテーブルからバッと顔を上げて、驚愕したように目を丸くする。その体勢だと、僅かに汗ばんだ谷間がちらりと見えてしまう。彼女の性格的に、それは過失ではなく故意だろう。しかし胸にはあまり興奮しないので、余裕で平常心を保っていられる。
ちなみに唯夏のバストは、身長と同じく標準サイズ。体重については非公開らしい。生まれつき痩せ型なので、別に恥ずかしがる必要はないと思うけれど。
「多分ね。でも終わったらいっぱい遊べるよ?」
「え~~~やだ!! 私は今すぐ叶実と遊びたい! どエロいことを沢山したい!」
「唯夏の頭の中ってそれしかないの?」
「ふふっ、今さら何言ってんの? 私は授業中に官能小説を読むくらいだよ? 四六時中エロいことしか考えてないよ♪」
ジト目で悪戯っぽく微笑む唯夏。
彼女の性への興味関心は、昔から尋常じゃない。
そのエピソードをまとめたら、きっと1冊の本が出来上がってしまうだろう。
もっと他に熱量を注ぐことはあると思うけれど。
「そうだったね。唯夏はかなりの性欲魔人だったね」
「おっ、そんな格好いい異名を与えてくれるの? 照れるじゃん♪」
「格好いいかどうかはともかく、僕は唯夏の前世がサキュバスだったのではないかと疑っているよ」
「そしたら私、沢山の男と寝てたことになるけどいいの?」
「…………」
僕は今、男としての器を試されているのだろうか。
本心としては別に構わないのだけれど、しかしだからと言って、愚直にそう答えたらそれはそれで唯夏の機嫌を損ねてしまいそうなので、無難にノーを選択する。
「いや、そんなの僕には耐えられない」
「そうだよね!! 叶実は私のこと大好きだもんね! たとえ前世の話でも嫉妬しちゃうよね!」
「面倒くさいなこの幼馴染……」
「あはははは!」
お腹を抱えて楽しそうに笑う唯夏。
彼女は昔から笑い上戸なのだ。
よく会話中にツボにはまって、涙が出るくらい爆笑することもある。
「でもありがと♪ 私も叶実のこと大好きだよ♡」
「はいはい。僕も唯夏のことが大好きだよ」
「おっ? 顔赤くなってるけどもしかして照れてるの? かーくん可愛い♡」
「その呼び方は小学生までにしてよ」
「えへへ♡」
最上唯夏。
改めて、僕の彼女兼くすぐりパートナーである。
さらに幼稚園からの幼馴染にして、小中高と同じクラスメイトだ。
唯夏と付き合い始めたのは、中学2年生の頃。夏祭りで告白した時の緊張感は、未だに忘れられない。しかしそれからは2人で大人の階段を一段ずつ登っていき、今ではあの時の初々しさがすっかり蒸発している。
そんな僕たちは、中学3年生の冬に実家から遠く離れた同じ志望校に合格した。そのため新学期が始まる春からは、通学時間と交通費と家賃の削減という名目で、2LDKのマンションに一緒に住むことを決めた。まあ元々実家は隣同士にあったし、僕たちにとってはその延長線上みたいなものだった。
お互いの両親は、昔から家族ぐるみの付き合いだったこともあり、反対どころか応援する姿勢で、僕たちの交際と同棲を認めてくれた。ただし学業に支障をきたさない節度のある生活をするようにと、それぞれ真面目な両親から釘を刺されている。
そんな訳で、夏休みの宿題が疎かになるなどあってはならないのだ。言語道断と言ってもいい。2学期の最初にはテストも待っているし、そこで赤点なんて取ろうものなら、お互い両親に何て咎められるか分からない。下手したら同棲解消が命じられる可能性だってある。この充実した生活を続けるためにも、それだけは絶対に避けたい。
そう――だから今日はこうして、僕と唯夏は朝から一緒に夏休みの宿題を進めている訳だ。場所は白とピンクを基調とした彼女の可愛らしい部屋。香水の甘くていい匂いが、部屋全体を優しく包み込んでいる。
唯夏はテーブルの上に頬杖をついて、何やら蠱惑的な笑みを浮かべる。
「ねえ……休憩がてら、シちゃう?」
「……そういうのは、宿題が終わってからの約束だから」
「ふうん? ほんとはめちゃくちゃシたいくせに♡」
こういう扇情的な言動に、今までどれだけ心を乱されてきたことか。唯夏は人の性欲を掻き立てるのが天才的に上手いと思う。言わば誘い受けの達人である。正直その見透かした表情を見せられるだけで、パブロフの犬のようにムラッとしてしまう。
しかし。
今は夏休みの宿題という最優先事項がある。
お互いの未来のためにも、性的なことに時間を費やしてる暇はないのだ。
僕は唯夏から目を逸らし、澄ました顔で返答する。
「別にそんなことないよ。唯夏には悪いけれど、僕はそう簡単には流されない」
「へえ……♡ それじゃあ私がどんな挑発をしても、叶実は欲情しないってことね?」
「もちろん。唯夏の挑発なんてもう慣れてるしね」
「これまで全敗なのに?」
そう言って。
唯夏はにやりと笑うと――突如カーペットにゆっくりと横たわり、両手をまっすぐに伸ばした。
「はぁ~~~。もう疲れて動けないや」
クラリと。
理性が揺れる音がした。
なぜなら唯夏がノースリーブで万歳したことで、白くて綺麗な『腋』がばっちり見えてしまってるからだ。ぐり100かつ腋フェチの僕からしたら、そんなの興奮せずにはいられない。序盤から何て強力なカードを切ってくるのだろう。
とはいえ。
いま本能に従ったら、僕の負けだ。
それに毎回唯夏の思い通りになっていたら、流石に彼氏の沽券に関わる。
だから僕は何とか煩悩を断ち切り、炭酸飲料よりも爽やかな笑顔を浮かべて言う。
「疲れたよね。もう少ししたらお昼にしよっか」
「叶実の方こそ無理してない? これ、出さなくていいの?」
両足の親指で、正座で無防備になってるエクスカリバーをちょんちょん触られる。ルームパンツとボクサーパンツで守護されてるとはいえ、その焦れったい刺激は確かに伝わってくる。しかし絶対に負ける訳にはいかないので、僕は極めて紳士的に微笑む。
「今は……別にいいよ。それよりも他にやるべきことがあるからね」
「そうなの? 私のこと、こちょこちょしなくていいの?」
ブチリと。
脳味噌の血管が切れる音がした。
こちょこちょ。
くすぐりフェチにとって、興奮の引き金となるオノマトペ。
その6文字を耳にするだけで、僕の中に眠ってる怪物が目覚めてしまう。
まして発言者は、ぐら100の可愛い彼女。
くすぐりフェチの性なのか――悲しいかな、既に僕のエクスカリバーは大きく反応していた。
もちろんそれを見逃す唯夏ではない。
「ふふ、叶実の変態♡ 私はただ『こちょこちょ』って言っただけなのに、こんなに硬くなっちゃうんだ♡」
「……気のせいじゃない?」
「へえ~~♡ そうやって見栄張るんだ~~♡ ところでさ……さっきから私の『腋』、ずっと見てない?」
ドロリと。
全身にマグマのような熱い感情が流れていく。
僕の中の怪物が動き出し、まともな理性を溶かし始めていく。
腋。
もうその単語を異性の口から聞くだけで、とても興奮してしまう。
なぜなら僕は、極度の腋フェチだから。
むろんくすぐりと腋を天秤にかけたら、前者の方が下に傾く。しかし腋だけで賢者になれるのも紛うことなき事実だ。そして唯夏もまたそれを熟知している。だからこそここで腋という単語を口にしてきたのだろう。
しかし――まだ。
まだ最後のストッパーは、外されていない。
今ならまだ、正常な人間に戻れる。
僕は精いっぱい怪物を抑圧し、落ち着いた口調で答える。
「それは……唯夏がそんなポーズをしてくるのが悪い」
「ふうん♡ そんなにえっちかな? 私の――」
そこで言葉を区切って。
唯夏は意地悪く微笑み、破壊力抜群のワードを放つ。
「わ・き・の・し・た♪」
グサリと。
僕の性癖に、その五文字がぶっ刺さる。
なんて。
なんてエロいんだろう――この幼馴染は。
こんなの、反則すぎる。
全ての言動が、僕の理性を狂わしていく。
けれど――
「……唯夏。もうこんなことはやめよう。僕はこれ以上、自分を抑えられる自信がない」
「抑えなくていいんだよ? 叶実の欲望、私に全部ぶつけてよ」
「…………」
「ま、仮に腋をくすぐられたとしても、私は絶対に笑わないけどね♡ こちょこちょなんて所詮は子供の遊びでしょ? 私には全く効かないし、あんなの余裕で耐えられるから♪」
カチリと。
そのあまりに生意気すぎる台詞が、ついに僕の最後のストッパーを外してしまった。
これはもう。
これはもう――分からせるしかないだろう。
誰がどう見ても分からせ案件。
分からせルート一直線である。
逆に分からせなければ、この激しく燃えるような感情を鎮めることができない。
今はただ、天災の如く荒ぶるぐり欲に支配されている。
僕はその場からゆっくりと立ち上がると――I字で寝転がる唯夏に近付き、目を爛々と輝かせて彼女を見下ろした。
「覚悟はいい? 唯夏」
「あは。もしかして私……今日笑い死ぬ?」
「言い残すことはそれだけね。じゃあ早速始めるよ――」
「ひっ……待って!! まだ心の準備が――ひゃはあっ!?」
その直後。
耳を劈くような笑い声が部屋に響いたのは、言うまでもない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
