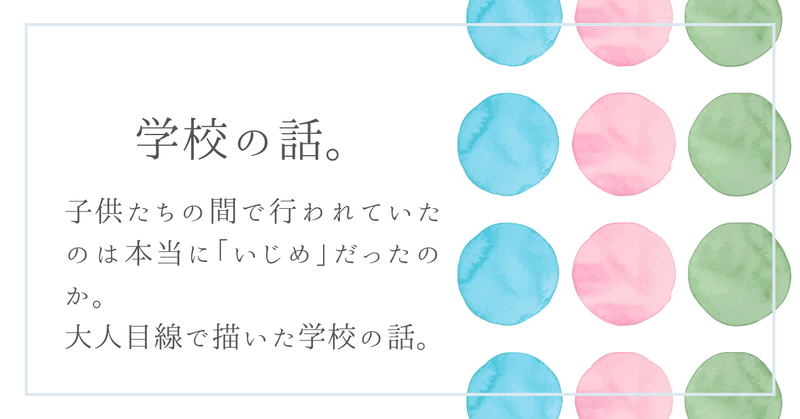
【小説】学校の話。<結①>
▼前話
1)
先週木・金と欠席した笹木 凛音は、週が明けて登校してきた。
久しぶりに顔を合わせた三人組は、初めこそ少々ぎこちなかったが、時間を追うごとに打ち解けていく様子が窺えた。
三人が揃うのは、先週問題を起こして以来だ。
そのための気まずさだったのだろうと、小渕沢は考えた。
(これに懲りて、大人しくしておいてもらいたいものだな)
眼鏡のズレを調整し、計算プリントの束を手に取る。
放課後を思うと憂鬱だった。
しかし、千乃が葵に文章を写させていたのは事実だ。小渕沢自身も目撃している。
そこを突けば大人しくなるだろう。
小渕沢は、若干の不安を打ち消すように息を吐いた。
指定時刻の約五分前に、中嶋一家は小学校を訪れた。
千乃が伴われているのは、夜間に一人で留守番をさせておけないという事情からであろう。
「Hi, 千乃」
通常と違う学校の雰囲気に硬くなっていた千乃が、頬の強張りを解く。
長くなることが予想される会談の間、オリバーが千乃と過ごしてくれるのだ。
「もう宿題終わっているの? goodだね。
じゃあ、ボクにオリガミ教えてくれる?」
二人を見送ると、千乃の両親が校長室に通される。
高い位置で黒髪を引っ詰めた母親は化粧も服装も地味、父親の方はシャツにチノパンといったスタイルである。一見穏やかそうで、電話口で怒鳴っていた人物とは思えない。
小渕沢は、話は思ったより早く終わるかもしれないと踏んだ。
「学年主任の及川です。この度は大変申し訳なく──」
小渕沢、瀬尾もこれに続く。
教師陣と千乃の両親は、校長室の大きなテーブルを挟んで向かい合っている。畠山教頭と、坂下校長も立ち会っていた。
「まず、現物を見せていただけませんか」
父親が静かに切り出した。
小渕沢が、クリアファイルから二枚の紙を取り出す。
【ひどい人がいるから 気をつける】
茶色の折り紙の裏。いずれも白い面に鉛筆書きされている。
大きなテーブルの中央に置かれたそれらを見るためには、両親が身体を乗り出さなければならなかった。
「これは、手紙ですか?」
腕を伸ばして折り紙を取り上げた父親は、ゆっくりとそれを掲げる。
順を追っての説明を考えていた学校側は、虚を突かれる形となった。
「それは、手紙ではないと言われればその……」
「イエスかノーで答えてください。
これは手紙ですか?」
「……」
父親は、二枚の紙をこれでもかと突きつけてくる。
有無を言わさぬ勢いであった。
「本当に、申し訳ありませんでした」
及川が頭を下げ、小渕沢も続いた。
「気づいてやれなかったことは、親である我々も反省しています。
夫婦共々、娘には心から謝りました。しかし」
父親は、未だ千乃への謝罪がないことへの怒りを露わにする。
問題が起きたのは先週の水曜。間違いが発覚したのが翌日の夕方。そこから既に丸四日経っている。
「これは私が止めたことでして」
畠山教頭が手を挙げた。自分が立ち合いの元で謝罪の場を設けたものの、千乃に断られてしまったと説明する。
「やり方が良くなかったんですなぁ。
こちらの作戦ミスです、ハハハ」
畠山教頭は、場を取りなすように微苦笑を浮かべて頭を掻いた。
「……作戦?」
これまで黙していた母親が声を上げる。
「教頭先生は、普段そういう目で子供を見ておられるんですか」
「ああ、これはその、言葉の……」
畠山教頭の声は尻すぼみになった。
母親の目に、刃物のような冷たさがあったからだ。校長室は、水を打ったように沈黙した。
「申し訳ありません!
僕はすぐにでも千乃さんに謝りたかったのです!
制止されたからと諦めたのは間違いでした」
沈黙を破って、小渕沢は訴えた。
両側から同僚の視線を感じるが、もはやどれだけ白い眼で見られようと構わなかった。
「そんなもの、後付けの言い訳だろ!」
憤慨してずっと立ちっぱなしだった父親は、ドッカリと腰を下ろした。母親が後を引き継ぐ。
「そちら様は、娘に“謝れなかった”のではなくて謝りたくないのですよ。とある事情でね」
何だ──?
小渕沢は背筋が冷たくなった。
「伊藤 葵ちゃんのお家から相談を受けたんでしょう」
「なっ! ですから個人的な情報は」
「個人情報なんか求めてません」
小渕沢の反論がピシャリと遮られる。
「そうじゃなきゃ辻褄が合わないって話です」
2)
(何度も頭を下げているだろう。
何故ここまで追及されなきゃならん?)
チラリと畠山教頭を窺えば、「自分はただの立会人だ」とばかりに茶を啜っている。
小渕沢は、思わず舌を打ちそうになるところを懸命に堪えた。
「まず、三人で娘を囲んだのは何故です?」
父親が話し始めた。
「たまたま通りかかった及川先生を、僕が呼んだのです」
「何故?」
「大きな問題だと思いましたので……その時点ではですね」
ここまで詰められる必要があるか。
中嶋夫婦は、まるで立場の弱い店員に何時間も説教するクレーマーのようだ。
小渕沢は、ボイスレコーダーを持ち込まなかったことを密かに悔やんだ。
「おかしいだろ。相手は手のつけられないような不良じゃない。
小学3年生の女の子だ」
「……そうですね」
ややあって、及川が応じた。
「途中から場に入ったことで、指導の基本がおざなりになったのは確かです。その後の対応につきましても」
母親は、及川の話を真剣に聞いているようだ。
コロッと引き込まれやがって。小渕沢は、内心で母親を嘲笑した。
及川は保護者、とりわけ母親の懐に入るのが上手いのだ。
(しかも、自分は途中から来た部外者だってさりげなく伝えてやがる)
「つまり、そちら様は」
母親が発言した瞬間、小渕沢はまた背筋が冷たくなった。
この地味な女のどこに恐怖の元があるのか、分からなかった。
「今回のことを大きな問題にしたかったわけですね。
学年主任の及川先生を呼んでまで」
校長室がグルリと回転したかのように感じた。
「そ、そんなことは……!」
「これ、写させてるってどうして分かりました?」
母親は、手元の折り紙を掲げてみせる。
「それは……葵さんが千乃さんの紙を覗き込んで」
「どのような言葉で命令してたのかしら。
娘は具体的にどんな指示を?」
「……」
「ほら。そちら様はね、娘のことを初めから問題児として見てるんですよ」
──あまり人をナメるなよ。
遠くで殿山の声がする。
「そちら様は、葵ちゃんのお家から何らかの相談を受け、問題が起こるのを待っていたんです。
そうじゃなきゃ、メモを手紙と決めつけ、学年主任まで呼んで叱責したことの説明がつきません」
3)
「放課後、私は学校に呼びつけられました。
今思えば、やけに素早い対応です」
こんな地味な女に主導権を握られるとは思っていなかった。
「娘には低学年でも泣くような厳しい指導をしたとか。
自分でおっしゃいましたね?」
何が起こっている?
どこで間違えた──?
「そちら様は、こうも言いました。
子供たちの間に力関係があると」
小渕沢は、自分の頬が痙攣するのを感じた。
この女が発言する度に感じる背筋の冷たさ。その気持ち悪さの正体が分かったからだ。
(そちら様、だと……!?)
学校全体のことか。いや、違う。
先程、及川のことは「学年主任の及川先生」と発言していた。
(こいつ……)
中嶋 千乃の母親は、自分を「先生」と呼ぶ気が毛頭ないのだ。
彼女は冷ややかに言った。
「鬼の首でも獲ったと思いました?」
──問題が起きたというのに、えらく嬉しそうなことで。
また殿山の声がした。
──無能が雁首揃えやがって。
自分のことを、絶対に「丈二先生」と呼ばない。
蔑むような目つき。
千乃の母親の言動は、いちいち殿山と被っていた。
自分は軽蔑されている。何故?
二十年以上、教師をやってきた。
仕事は嫌いではない。ずっと走ってきたのだ。
それが何故、こんな仕打ちを──。
「私が馬鹿でした。
娘を信じてやれずに、こんな──」
母親の視線が刺さった。
「そちら様は、娘のことをそういう子だと言いました」
「い、言ってない!」
口が勝手に開いた。
虫を払うような仕草で、小渕沢は椅子を後ろに引いた。
「言いました」
「言ってません」
「言いました」
小渕沢は、唇を戦慄かせた。
どこで間違えた? どこで──。
「言ってな……」
「もうやめてください、丈二先生!!」
悲鳴のような声が割り入った。
瀬尾が小渕沢を睨みつけている。
「ちゃんとご両親と向き合ってください」
「言いました。五限目の途中まで叱責したのに認めない、あれは相当だ、そういう子だと」
「……はい。すみません」
小渕沢は、項垂れて拳を握りしめた。
畠山教頭が天を仰ぐ姿が視界に入る。もう庇い切れないということか。
「妻が伊藤さんの件に拘るのは、娘の名誉のためだけじゃないんです」
父親が話題を変える。
「本当に分かってますか? 葵ちゃんがどういう子なのか」
何故、教師でもない奴に説教されているのか。
小渕沢は、馬鹿にされている気分だった。
「分かっていますよ。
ですから、なるべく発表の機会を増やし、本人も……」
小渕沢がムキになって言い返すと、父親は本当に馬鹿にするように鼻から息を吐いた。
校長室に白けた空気が漂う。
(何なんだ)
「丈二先生……ご存知じゃなかったんですか?」
そう言ったのは瀬尾だ。
彼女の表情からは、「担任なのに」という非難がありありと見てとれた。
「なに的外れなこと言ってんの」
小渕沢にだけ辛うじて聞こえる声は及川のもの。顔は前方へ向けたままだ。小渕沢の眼球は小刻みに震え出した。
何のことだ?
「葵ちゃんは、性格がおとなしいというだけじゃないんです。
千乃ちゃんとしか喋れないんですよ。
他の子が関わる時は、いつも千乃ちゃんを介してます。
凛音ちゃんに対してもです」
「通訳のような感じね」
瀬尾の後から及川が言い添える。
(馬鹿な──)
自分が把握しているのは、三人が連れ立っている姿だけだ。
「低学年まではそれでやっていけてた。
でも大きくなれば遊び方も変わるし、交友関係も広がります。
千乃ちゃんに悪気がなくても、葵ちゃんに注意を払えないことはあったでしょう」
瀬尾が続けると、母親は何度も頷いた。
「だから早く伊藤さんに連絡してと言ってるんです!
ただでさえ不安を感じてる筈なのに……どんな思いでいるか」
そう言って、こちらを一瞥する。
小渕沢は茫然となった。
「お願いですから、早く伝えてあげてください」
母親が苦しげに顔を歪ませた。
──墓穴を掘る趣味でもあんのか?
また殿山の声だ。
あの日、いじめの現場を押さえたと思った。いち早く双方の親に知らせた。それは、まったく意味のない仕事だった──。
(全部見通していたとでも言うのか。あんな奴が)
助けを求めるように視線を走らせれば、坂下校長も畠山教頭も気配を消して小さくなっている。
小渕沢は、砕けるほど強く奥歯を噛み締めた。
「娘は子守りじゃないんだよ。
葵ちゃんに気を配ってやるのは本来そっちの仕事だろ?
もうね、心から軽蔑しますよ」
「娘にとって、葵ちゃんは大切な友達なんです。
その気持ちを、上辺だけ適当に見てる人に悪く捉えられたのが不憫でなりません。私は許せない」
父母の語気が強くなる。
小渕沢の思考は凍りついた。
「本当に、申し訳ありません」
及川に続いて、辛うじて頭を下げる。
「担任が、お友達関係の背景を理解しないまま動いたことが最大の問題です」
葵の母親は、いじめの証拠を求めていたのではない。
おとなしい葵が友達に馴染めるかどうか。それだけが心配だったのでしょうと、及川は言った。
「葵ちゃんのためには、少しずつ交友関係を広げられるような、きっかけ作りや見守りが必要でした。
千乃ちゃんだけが頼みの綱になってしまっている親御さんについても、違う角度から助言すべきでした」
能力は認めるが、小渕沢にとって及川はいけ好かない女であった。
「学年末ですが、今からでもできることはあると思います」
及川の言葉に、千乃の両親はようやく納得の表情を見せ始めている。
この場にいない葵の話をするのは、本来ならタブーだ。状況を見ながら敢えてそれをする。
小渕沢が及川を嫌うのは、こういうところであった。
(上手いこと取り入りやがって)
簡単に言うが、クラスにいるのは葵たちだけではないのだ。
背景など知ったことか。
(教師は忙しいんだ。俺は忙しいんだよ!)
「まず伊藤さんに連絡を。ね」
話を振られ、小渕沢は慌てて頷いた。
及川の目が、お前が担任だろうがと言っている。いけ好かない。しかし。
思考が混乱している今、及川に救ってもらったのは事実だった。
小渕沢は、眼鏡のブリッジを押し上げた。
「そこは早急に連絡させていただきます。
この度は大変申し訳なく……」
「で。凛音ちゃんは大丈夫なんですか?」
父親がすぐさま言葉を被せてくる。
「は?」
「あの子も先生たちに囲まれたんですよね?
妻からもお話した筈ですが」
父親の態度は、小渕沢に対するものと及川に対するものでは明らかな違いがあった。
及川の話は頷きながら聞いているのに、自分の言葉は彼の耳を素通りしているかのようだ。
何故だ。
小渕沢は怒りを隠せなかった。
「問題はありません!
今日も三人、楽しそうにして」
「ご両親がおっしゃりたいのは、そういうことではないと思います」
またも自分の発言を遮られた。
今度は瀬尾だ。小渕沢の舌打ちは、もはや隠しきれずに校長室に落とされた。
「あんなことがあっても凛音ちゃんが元気でいられたのだとしたら、それは子供たちが頑張ったからです。とりわけ千乃ちゃんが」
「……」
「私たち教師側は、子供を傷つけただけで何もできていません」
「あー……何も、という訳では……」
畠山教頭が消え入りそうな声を出したが、気に留める者はない。
「対応が遅すぎました。今回の問題が起きてからも、それ以前も。
3年生の担当教員として本当に申し訳なく思います」
瀬尾に続いて、及川も深々と頭を下げた。
何なんだ。
何なんだ。
何なんだ。
俺の尻拭いをして恩でも売ってるつもりか?
得意そうな顔しやがって。
何もできていない?
学校側がそんなことを認めてどうするんだ、馬鹿なのか?
しかし、父親は瀬尾たちの答えに納得の表情だ。
そして信じられないことに、母親は瀬尾に向かって頭を下げたのである。
小渕沢だけが蚊帳の外であった。
(何なんだよ!? どいつもこいつも……)
何が違う?
あいつらと俺は何が──。
「話がまとまりましたかな。
いろいろありましたが、この小渕沢は大変情熱を持った教師でして……」
坂下校長が、立会人としての役割を果たすべく発言する。
しかし、唐突に放たれた言葉は白けた空気の中にポカッと浮いただけ。続く父親の発言が、それを吹き消した。
「どちらに向いた情熱でしょうね」
嘘くさい坂下校長の言葉で辛うじて自尊心を保っていた小渕沢は、ガックリと肩を落とした。
▼次話
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
