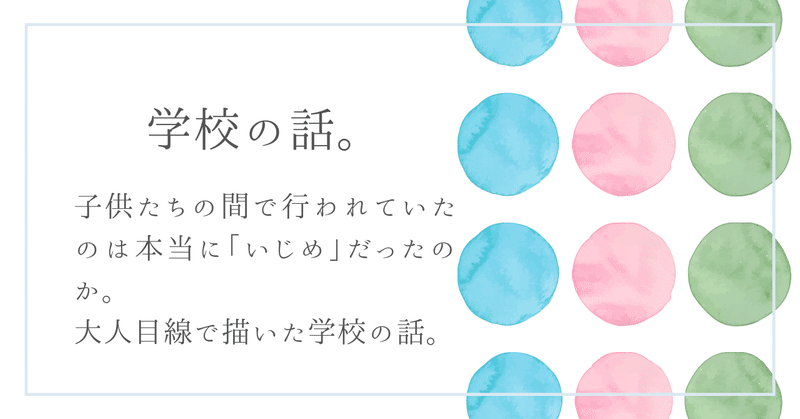
【小説】学校の話。<結②>
▼前話
1)
ノックの音が沈黙を破る。
畠山教頭が「はい」と応じると、校長室の重いドアが開かれた。
「千乃ちゃん」
及川が驚いて腰を浮かせる。入り口近くに座っていた瀬尾は千乃に歩み寄った。オリバーが、守るように千乃の背中に手を当てている。
「お話、長くなっちゃってごめんね」
瀬尾が椅子をすすめると、千乃は泣きそうな顔で首を横に振った。
「実咲先生、悪くないよ。
”何があったの?”って聞いてくれただけだよ。
それに、もう謝ってくれた」
千乃は、問題が起きた日のことを言っているようだった。
「パパとママが、何も知らずに実咲たちを怒ってると思ったみたいなんだ」
オリバーが言い添える。
千乃は、紺色のジャンパースカートをぎゅっと握り締めた。
「及川先生も、謝ってくれたよ」
(何だと?)
小渕沢は、瀬尾たちが既に謝罪していたことを初めて知った。
全員の視線が自分に注がれる。
(こいつら……!)
裏切りだと思った。この話は畠山教頭に一任されていた筈だ。
「我々は学校を吊るし上げようとしてるんじゃない。
間違えたら謝る。当たり前のことをしてもらいたかっただけです。
あなたは息でもするように謝罪しますがね。言葉に誠意が感じられないんですよ」
父親が言った。
「及川先生や瀬尾先生のように、誠意ある言葉を聞きたかった。もっと早くに」
小渕沢は、間違いが発覚してからの瀬尾と及川の言動を思い返していた。
冷めた目で自分を見ていた殿山を。
(俺だけが、何も分かっていなかったのか)
小渕沢は、ゆらりと立ち上がった。
「ごめんよ、千乃さん。
本当に悪いことをしてしまった。
ごめんね。ごめんなさい──」
そして、千乃に向かって深々と頭を下げたのだった。
2)
「バイバイ、とのっち。実咲先生、さようなら」
「おー。またな」
「はい、さようなら」
千乃は、友達と連れ立って元気に校門へ向かって走っていった。
今日から小学4年生だ。
「なーんか、小さくまとまっちまったな」
舞い散る桜の花弁に目を細めながら、殿山がポツリと言った。
「ええ。結局、学級委員にも立候補しませんでした」
「1年坊の頃は、もっと面白ぇヤツだったんだが」
表面上は異常なく見えるが、年度末の問題が起きて以降、千乃の様子が変化したことは瀬尾も気づいていた。
千乃の動きは、以前と比べてとても慎重に見える。
自分が先頭に立って行動したことで教師に押さえつけられ、友達や親まで巻き込むことになった。その経験は、やはり大きく影響しているようだった。
「殿山先生。学校って、何でしょうね」
影を落とす昇降口に、数枚の花弁が舞い込む。瀬尾は、その様子を目で追いながら呟いた。
「んお?」
「たくさんの人を傷つけながら、学校は何を守りたいんでしょう」
「……面子だろ。謝るのが負けだと思ってやがる。馬鹿どもが」
一つ大きなくしゃみをし、殿山は鼻を啜った。
相変わらずの口の悪さである。
「結局は人間同士の話なんだ。
腹を割って向き合わなけりゃ、前には進まん」
瀬尾は微笑した。
殿山の指導は、厳しさの中に楽しさがある。無論、合う合わないはあるが、彼を慕う児童や父兄は多い。瀬尾にとって殿山は、尊敬する教師の一人であった。
「あの件は俺も心苦しいよ。スッキリしねぇ結末だったな」
結局、凛音と葵へのフォローはなされなかった。理不尽な理由で教師に囲まれたにも関わらずである。取り掛かるには、あまりにも時間が経ち過ぎていた。
「葵は真似をしていたんだと思うよ。強制されたんじゃなくて」
いつかの居酒屋へもう一度足を運んだ時、オリバーはそう言った。
葵はいつも千乃について回っている。有り得そうな話だった。
「これは想像だけど、メモを書こうと提案したのは凛音じゃないかな。
自分もペンを出して書こうとしているところだったかもしれない。
もう真相は分からないけどね」
あの後、凛音は二日間学校を休んでいる。
自分が言い出したことで問題が起こってしまったとすれば、ショックは大きかっただろう。
元気を取り戻した今、フォローと称して話を蒸し返すことはできない。
悪いことをしていた訳ではないのだ。
あの日、瀬尾たちをカップルと勘違いしたお調子者の店員は、やはり勘違いしたままだった。
それでいい。日々、不特定多数の客をもてなす。
それが彼の仕事だ。
小渕沢は、そんな風に千乃たちの上辺だけを見て「力関係」と言った。
ただ、居酒屋の彼は瀬尾たちを大切な客として覚えている。
こちらが「カップルではない」と告げれば謝るだろうし、これからも親しみをもって接してくれるだろう。彼の接客ぶりを見ればそう思える。
小渕沢は謝罪を先延ばしにした上、「伊藤家へ連絡を」との再三の要求も突っぱね続けた。
間違えたら謝る。たった、それだけのことなのに。
及川から会談の内容を聞かされた殿山は言った。
対応をわざわざ遅らせるのは、『学校』という組織の悪い癖だと。
謝罪に一週間近くを要するなど、一般企業に置き換えれば有り得ない話である。
誠意を持って向き合っていれば、お互いがあそこまで疲弊することはなかった。
『学校』は、そこまで社会とかけ離れた存在になってしまっている。
「丈二先生は最後には謝罪しました。
証拠となる折り紙も処分していなかった……そこだけが救いです」
「教師としてのプライドはあったってことだろ。0.1ミリくらいだがな」
「ふふ。殿山先生にしては甘い見立てですね」
殿山の優しさが垣間見えて、瀬尾は少し笑った。
『学校』という特殊な組織の中で、殿山のようになりたくてもなり切れない人間はいる。
「本来の中嶋 千乃を取り戻すなら今年度が勝負だ。
あいつは良い担任に巡り会ったよ。なぁ、瀬尾先生!」
殿山に、ポンと肩を叩かれた。
照れ隠しなのか、瀬尾が「はい!」と応じた時にはもう背を向けている。
「んじゃ。俺ぁ、教室で仕事すっからよ……あ」
何かを思い出したように、殿山が振り向いた。
「前から気持ち悪ぃと思ってたんだが、奴は何で“丈二先生”なんて呼ばれてんだ?」
殿山のしかめっ面が可笑しく、瀬尾は吹き出した。
「赴任の挨拶で本人が言ったんですよ。ぜひ”丈二先生”と呼んでくださいって。苗字だと言いにくいからって」
「そういうことか」
顎を撫でる殿山の表情は、どことなく満足気である。
「うーん、”小渕沢先生”か。
そう言いにくこともないですね?
私も今年度からそうしようかな」
瀬尾が肩をすくめると、殿山は「ブハハッ」と豪快に笑った。手を振りつつ、今度こそ踵を返す。
校舎の前には瀬尾だけが残った。4年生が入る棟を見上げると、大きな雲が空を横切っていく。
これからも、組織の壁にぶつかることはあるだろう。
どれだけ抗えるかは分からない。
それでも自分は児童を守れる教師でありたいと、瀬尾は思うのだった。
悩んでいる暇はない。
明日になれば、ここはまた元気な声でいっぱいになるのだ。
新年度は始まっている。
瀬尾は真っ直ぐ前を向いて、校舎に足を踏み入れた。
《了》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
