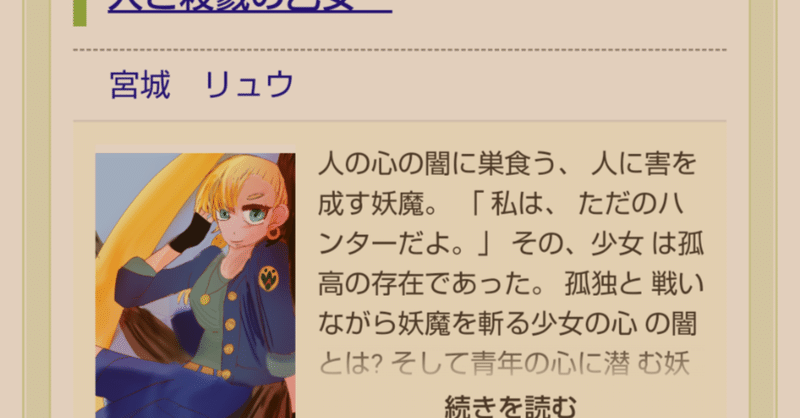
アルファポリスで、小説書いてます。(第21話)
醜いアヒルの子
オズワルドは、自分が只の人間でない事を昔から勘付いていた。
彼は、自分の本当の親は分からない。本名も分からない。と、言うより記憶がないー。ただ、父親はごく普通の優しく勇気ある人であると言われていた。ただ、物心つく頃から自分は周りと明らかに違っていたと言うことを認識していたのだ。彼には異母姉がいたそうだが、彼女もどんな人なのか知らずにいた。異母姉はダークネスであり、アルファと言われる少女との激闘の末、死亡したと聞かされている。彼は養護施設で育ち、7歳の頃、養父に引き取られた。
オズは、黄味がかった色白の肌にキレ長の目にやや丸みがかった鼻筋をしていた。そして、癖の強い黒髪に面長の顔立ちー。この界隈ではあんまり見ることのない風貌をしており、時折物珍しそうにこちらを眺める人々もちょくちょくいるものだ。
しかし、それだけではない。自分の思った事が実現してしまうことがあるのだ。それで、クラスメートが負傷や気絶してしまう事もしばしばあった。オズに関わる者達はみんな顔を尖らせ、ピリピリした空気が張り詰めていた。
養父も奇妙であった。180センチは優に超えるくらいの長身で、丸渕眼鏡の温厚そうな感じの人だった。そしていつもオズを気に掛けてくれていたが、彼に近付く度にゾクゾクした寒気が奔った。彼から硫黄の様な匂いに、ドライアイスの様な乾いた冷たい空気を感じ取ったのだ。
『お義父さん、どうして僕は皆と違うの?』
『お義父さん、どうして僕は皆のようにできないの?』
『お義父さん、僕は何処か変なの?』
『お義父さん、僕は化け物なの?』
これらの言葉は、何十回も何十回も言った事がある。しかし養父はただ微笑むだけでオズの頭を軽く叩いた。『君は不思議な力が備わってるんだ。君は今は醜いアヒルの子なだけだよ。あんな輩の言う事は一切信じては駄目だよ。もう一辛抱さ。』
と、養父は腑に落ちないモヤモヤした事を話した。それはずっと晴れない霧の中をさまよい続ける感覚であり、オズの心にずっと引っかかっていたのだ。
『醜いアヒルの子ー』
オズはその意味がずっとわからずじまいですあった。
そして、養父の書斎には入ってはいけなかった。養父は部屋の鍵を毎晩カッチリ締めては、オズが絶対に入れないようにしていたのだ。そして時計の短針が毎晩午後9時を回った頃、書斎から毎晩決まって卵や魚の腐った様な物と硫黄が混じり合った様な不快な匂いがドアの隙間から謎の黄土色の煙と共に漏れ出していたのだ。
それはオズは12歳になった頃の事だー、オズは暇つぶしにスーパーボールを地面に叩きつけて遊んでいた。
スーパーボールはコロコロ転がり、養父の寝室のドアの隙間の中に入り込んだ。オズは、スーパーボールを取りにいつも千錠してあるドアが開いたのだった。
スーパーボールはベッドの下に入り込みそれを掴むと、そのまま出口に向かった。すると階下の方からゆっくりと階段を登る足音が聞こえてきた。オズはドアを締め内側から鍵をかけた。そして手前の押入れの中に隠れ、ひたすら息を殺していた。オズの心臓がバクバク激しく脈打った。そこへ、扉が開き木の床が軋む音が聞こえてきた。ドアはキーと軋む音がし、養父が姿を現した。
彼はゆっくり前進しベットの前でしゃがむと、大きなスーツケースを3つ取り出した。ケースを開けるとそこには人の遺体が入っていた。
オズは悲鳴をあげようとする口を必死に両手で塞いだ。目の前の人間が実は化け物でよだれを垂らしながら美味しそうにムシャムシャボリボリ人肉を食らい付くしていたのだ。
すると辺り一面に卵や魚の生臭い匂いと硫黄が入り混じった匂いー、黄土色の煙が辺りを充満していた。オズワルドはその鼻をつんざく様な匂いに吐き気を催した。
すると、養父の姿が変貌していた。彼の背中には翼がー、頭部には角が生えているのだった。彼の背丈も2メートルを優に越え、彼の周囲を黄土色の炎が微かに取り囲んでいた。そして、彼の口からは牙が生えているようにも見えた。
オズは身震いをした。長年自分を育てあげた養父は実は化け物で、美味しそうに人間を喰らい尽くしているのだ。
すると押入れの奥から、薄っすらと白い物がコロコロ転がり落ちてきた。その白い物を手に取ると、それは髑髏でありオズは軽く悲鳴を上げた。その弾みでオズは尻もちをついてしまった。お尻の下が不安定でゴツゴツした感じを覚え、オズは右下に視線を下ろした。すると、そこには髑髏が積み上げられているのだった。オズは軽く悲鳴を上げた。するとカラカラと髑髏の山が崩れ落ちる音がした。
すると、養父はゆっくり押入れの方を振り返えった。
「ー見たな…」
養父は普段聞かないような、ドライアイスの様な低く乾いた声を発すると、彼の右半分が一瞬で溶け出し、蒸発して髑髏の様な姿になった。
オズはゾクゾクした寒気を覚え、悲鳴をあげた。そこからの記憶は彼は気絶をしており、定かではない。目を覚ますと、養父の遺体と数名の少女の姿がそこにあった。オズは組織に預けられ、そこで身体の精密検査を受けた。彼はそこでダークネスの血が入っているという事が発覚したのだ。彼の父親か母親のどっちかがダークネスであるというのだ。彼は、屋敷で暮らすことになり今に至っている。その自身の中にある不思議な禍々しい力は、父親か母親のどちらかから受け継いだ物なら、自分もいつか化け物になって人を食い殺す存在になってしまうのだろうかー?
彼は自分の両親がどのような者なのか、知りたくなった。自分の本当の名前を知りたかった。親の名前を知りたかった。親の顔を知りたかった。大半の者が知っているであろう事を彼は知らないで育ったのだ。
自分は何か運命付けられているように感じている。しかしそれは強く禍々しい不思議な力に引き寄せられている運命の様な物を感じたのである。
アリエルは、高台でため息混じりに頬杖していた。時頃は深夜十二時を回っていた。1ヶ月程前に例のダークネスの捕獲に失敗し、やきもきしているのである。
ここ、エメラルドシティの制圧とアルカナを殲滅する計画が残っている。計画がうまく行けば、大量に食料を集められ効率よくドールを精製する事ができる。ドールを精製したら、人間を殲滅させ例の自分の復讐を果たすことができるのである。
ふと、背後から赤い炎に囲まれたパンクファッション風の女が姿を現した。
「状況はー?」
アリエルは振り向きもせず、彼女に尋ねた。
「ああ・・・さっき、シャーリーから連絡が来た。例の準備は整ったらしい。」
パンクファッション風の女は、煙草をふかしながら右の手のひらにシャボン玉のような玉を出現させた。その玉は直径10センチ代になると、プカプカ浮き、赤い光を放った。彼女の右二の腕のタトゥーが赤く光った。
「あとは、あれだけかー。」
アリエルはほくそ笑んでいる。
ルミナが組織を離れて、1ヶ月以上経った。エメラルドシティのアルカナ支部では、ルミナの行方を探るも、殆どの者は諦めていた。というのも、組織の上層部にとってアルファとは手駒でしかなく彼女達を通してダークネスの情報さえ掴めればそれでいいと思う者も少なからずいたのだ。
アルカナ支部の研究所では、メリッサがひたすらキーボードをカタカタ打ち続けていた。
「ルミナの行方は分からずじまいか?」
エリアムはメリッサの書斎の中央のソファーに座りながら、新聞を拡げながら尋ねた。彼女はダークネスの情報やアルファに関する記事に目を通していた。
「ああ。ずっと音信不通なんだよ。」
メリッサは長身で色白、細身の体型にいつも白衣を身に纏っている。亜麻色の髪をポニーテールで高く結いあげており、何処かしら無機質で独特な雰囲気を漂わせていた。メリッサは紅茶を飲みながらキーボードを叩きながらモニターを覗いていた。
「ダークネスとはアルファだった者も混じってるんだろ?」
エリアムは視線を記事に落としたまま、淡々話した。
「ああ。死んで蘇った者も沢山いるんだが、中には、アルファだった者も沢山混じっているらしい。」
メリッサはしきりにモニターを睨み続けていた。
「ーなあ、聞いてもいいかー?」
「何だ?」
「もしかして、アリエルもアルファだったのだろうか?」
エリアムは低く重たい声で尋ねた。
「その可能性が高いなー。」
メリッサのキーボードを叩く指がピタリと止まった。
「良く、ダークネス迄、登りつめたものだな。」
エリアムは顎に左手を軽く添え、首を右に傾げた。
「やはり、魔王石が関係してるんだろうな。私も、元々は人間だったが、死んでどう言う訳かその石により、蘇ったんだよ。まあ、あいつは復讐の為に蘇っただろうが。ーまあ、彼女も私もいつガタがつくかは分からないがなー。私は只のしがない白衣の研究員に過ぎなかったのだがなー。」
すると、メリッサの顔の右半分が溶け、蒸発して髑髏の様になった。
「あのカイムも魔王石で転生したんだもんな。」
エリアムは微動だにせず、淡々と尋ねた。
「ああ、そうだな。しかし彼は罪を犯し、同胞達から吊し上げになってるそうだな。」
メリッサは軽くため息をつくと丸渕メガネを外し、席を立った。
「そう言えば、アリエルが奇妙な動きをしたらしいな。」
「ああ。そうだがー、お前分かってるんだろうな?」
メリッサはエリアムの向かい側に腰掛けた。
「分かってるさ。別に感情が先走るとでも?」
エリアムは新聞を閉じると脚を組み直した。
「なら、いいんだ。しかし、彼女はかつてはナンバーワンに上り詰めたアルファだぞ。奴の体内には無数の魔王石が埋め込まれているんだ。やつそのものが魔王石みたいなもんだよ。下手したらお前が火傷するぞ。」
メリッサは軽くエリアムを睨んだ。
「なら、間接的に奴を狙えばいい。あのー、爆弾女をー。」
エリアムは眉間に皺を寄せ、瞳孔は小さく揺れていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
