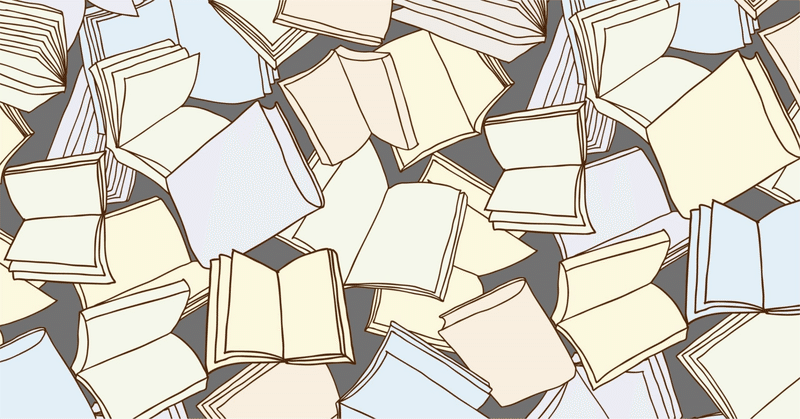
雑感記録(140)
【所謂「転向」について】
新天地に来てから初めての週末を迎える。どうも休日に早起きしてしまう癖が抜けず、今日も今日とて早朝に起床した。初めての週末なのだからゆっくり休めばよいものを…と思いつつも実は今日、仕事の関係で日本近代文学館へ赴かねばならなかった。いつもの平日と同じように朝食を済ませ身支度を整え家を出る。
日本近代文学館は駒場東大駅のすぐ近くにある。つまりは京王井の頭線に乗らねばならない。しかし、僕が住んでいる所からだと電車の乗り換えが面倒だ。まずは渋谷に向かわねばならないのだけれども、地下鉄で行くかJR線で行くかという選択から始まる。最初は地下鉄で行くことを考えもしたが、地上に出るまで多くの階段を昇らねばならないと考えた時に面倒で、結局僕は山の手線で渋谷へ向かった。
渋谷で降りて、「さて、井の頭線に乗るか」と思って早速迷子になる。僕はてっきりJR線の駅と井の頭線の駅が直結しているもんだと思っていた。所謂ハチ公前で適当に歩きながら駅を探す。灯台下暗しなんて言うけれど、随分と近くにあって驚く。この距離感で直結させないことに僕は1人苛立ちを覚える。また、人ごみの多さに更にイライラしながら改札へと向かう。
しかし、電車に乗ってしまえば案外早く着くもので、ものの数分もしないうちに着いてしまった。改札を潜るとスーツを着た多分学生なんだろうけれどもそこらへんを闊歩している。何だか懐かしさを覚えつつも「横になって歩くな!邪魔だろ!」と蹴りを入れたいのを我慢しつつ、彼らの後ろについて歩く。しばらくして公園が見えてきた。公園の中にどうやらあるらしい。僕は東門から入った。

何だか人んちの庭みたいなところをウロウロして、奥まった所に突如として現れた訳でもなかった。それなりの規模感の看板が案内していたので僕はただそれに従ったまでである。それにしても人っ子1人居ないというか、何物をも寄せ付けない雰囲気が建物から漂っており、実際入るのに躊躇してしまったが、ここでうだうだしても始まらない。それに仕事という大義名分で一応は来ているのだ。引き返すことなど出来る訳もない。
とは言うものの、実は結構ここに来るのが愉しみであった。それは自分が近代文学を専攻していたということも勿論あった訳だが、それ以上に特別展の内容が僕の心を刺激するものであったからだ。

特別展示で何とプロレタリア文学について展示されているということだった!これは見逃すわけにはいかない。何故だか「行かなければならない」というある種の使命感みたいなものが僕の中にあったことは紛れもない事実であるように思われる。ただそんなことを考える瞬間も無かったような気もしなくはない。パッと文字列だけ見て「あ、行こう」と反射的に動いてしまったような感覚だ。
受付に行くと若い女性が退屈そうに座っていた。受付のお姉さん。僕は話しかける。「この展示みたいんですけど」と声を掛けると「へ?」みたいな顔をされて「入館料300円です。」とぶっきらぼうに言われた。とりあえず支払いを済ませ入館のチケットを受け取る。これは僕の経験上の話であるが、大抵こういう時には館内の案内とかを簡単に説明される。僕はてっきりほんの少しでも説明があるのかなと一瞬待ち構えたが、何もなかったのでこれまたモヤモヤした気持ちを抱えたまま2階の展示室へと向かう。
2階へ向かうとまずお出迎えしてくれたのが川端康成のプチコーナー。僕はさして川端康成にあまり興味がない…と言ったら失礼この上ないがあまり通ってこなかった部類の人間である。所謂有名どころの作品しか読んでいない。『伊豆の踊子』や『雪国』『掌の小説』ぐらいなもんだ。しかし、そこに並べられている本の数々を見て興奮しない訳がない。復刻版とは言え発刊当時の装丁本を見られるのだから。
ちょろちょろと眺めた後、展示室に向かう。展示室入口に受付があり、再度受付をする。展示作品の一覧を受け取り、パンフレット片手にいざ展示に向かって行く。
展示室はかなり小さく正直15分もあれば全部見て回れるのだが、僕は1時間30分ぐらい滞在してしまった。同じところを何回も何回もぐるぐる回って見ては「おお、これがかの有名な…」と驚きと感動を味わうことが出来た。やはり自身が興味のある分野の展示と言うのは愉しいことこの上ない。何よりお客さんが僕だけだったというのもあったかもしれない。僕はラッキーだった。
それで色々と見て回ったのだが、やはりプロレタリア文学運動というものが如何に一過性のものであり、ただそれでも社会に与えたインパクトは計り知れないものだったのだなと改めて認識することが出来た。何と言うか「文学で社会を変えてやる」というある種の馬鹿げたまでの文学に対する信頼とそれに付随する作家それぞれの思考の技術が堪らなく最高で僕はそこがプロレタリア文学の魅力であると思っている。
現在では文学というものが社会を変え得るということはあり得なくなっている。厳密にはあり得るのだろうが、それ程までの強度を持った小説などと言ったものが現れていないということなのかもしれない。もっと言ってしまえば「そもそも現代に於いて"文学"なるものが存在しうるのか?」という問題にぶち当たるのかもしれない。少なくとも僕は今、この社会に於いて"文学"と言われるものが存在しているとは思えない人間である。"文学"は恐らく今の社会では必要とされていないような気がしてならない。
というような書き方をしてしまうと、文学はある種のプロパガンダ的な役割を持ったものでなければならないというように誤解されかねない。しかし、そこまで行かなくとも誰かの思想を大きく揺るがす思想的強度と言うものが求められてもいいのではないかと僕は思う訳だ。
プロレタリア文学というと大抵「マルクス主義」や「社会主義」「無政府主義」と言った言葉と直結されてしまう。勿論、そういった思想をベースにというか作品の根底には無論ある訳だ。ただ、僕はプロレタリア文学にそういった思想性を持って読んでいない。僕はプロレタリア文学が残した大きな功績だと思っていることが1つだけあると思っている。それは「生活を具に描き出す」という1点に於いてだ。
それまでの近代文学と言うものはどこか高等遊民というか、一般的な生活が描かれているという訳ではないと僕には感じられるのだ。無論、生活自体は描かれている訳だがそれはあまりにも離れているというか距離感がありすぎると僕には感じられていたのだ。森鷗外にしても夏目漱石にしても泉鏡花にしても…そこに描き出されている人物の思考にはどこかリアリティが欠けているような気がしてならなかった。
プロレタリア文学についてはそこに描き出される人物とそれを描く作者が同じ地平に立っているということが僕には刺さる。等身大の何かがそこにある。蔵原惟人が『プロレタリヤ・レアリズムへの道』という評論を書いている訳だが、それにここまで書いたことが収斂されているように思うので以下引用しておこう。
我々に取つて重要なのは、現実を我々の主観によつて、歪めまた粉飾することではなくして、我々の主観—プロレタリアートの階級的主観—に相応するものを現実の中に発見することにあるのだ。—かくしてのみ初めて我々は我々の文学をして真実にプロレタリアートの階級闘争に役立たせ得る。
即ち、第一に、プロレタリヤ前衛の「眼をもつて」世界を見ること、第二に、厳正なるレアリストの態度をもつてそれを描くこと—これがプロレタリア・レアリズムへの唯一の道である。
渡部直巳編『日本批評大全』(河出書房新書2017年)
P.273より引用
実はこの引用の前段には自然主義文学等の作品やブルジョアジー的な作品群とどう異なる態度を取るべきかと言うのが仔細に描かれている。本当はそこらあたりを全部引用したいのだが、そうすると全文になってしまうので辞めた。出来れば読んで欲しいのだが、中々手に入りにくい。現に僕も渡部直巳の『日本批評大全』からの孫引き状態になっている訳なのだから…。いずれにせよこの『プロレタリア・レアリズムへの道』はプロレタリア文学の方向性や態度を知る上では重要である。
本当は中野重治の『文学論』(ナウカ社)が1番分かりやすい気もするのだけれども、以前の記録に残した気もするのでその記録を貼り付けておくことにしよう。多分、この記録の最後に長く引用した気がする…。
プロレタリア文学の凄いところは、終りがある程度明確になっているという点である。この記録のタイトル内にもあるように所謂「転向」という現象である。獄中で転向したということの記事が新聞記事として掲載されているのだから大々的に社会的に終りを迎えたということがあからさまである点が凄い。
冷静に考えてみよう。例えば自然主義文学であったり硯友社文学とか色々な文学的ジャンルとでも言えばいいのだろうか。そういったような形で提示された文学は「気が付いたらなんか終わってた」という形で衰退していくことが殆どだ。つまりは現在の人が過去の文献などを漁り「んまあ、大体このぐらいで終わったよね」と現在時制に居る人たちがその終りを評定するのである。ところがプロレタリア文学は異なる。
プロレタリア文学についてはその時代を生きた当事者たちが終りを宣言することで終焉するのだ。さながら大正・昭和時代版の『今日から俺は』的な感じなのだろう(あそこまでポップでは決してないのだけれども…)。しかし、転向してしまえば転向してしまったで忘れ去られるのも速い。
ところで僕は先程から「転向」という言葉を使用しているが、簡単に「転向」について触れておこう。
転向とはなにか、については、すでに本田秋五が、その『転向文学論』のなかで普遍化した周到な定義をくだしている。本多によれば、転向の概念は、つぎの三種にきせられる。第一は、共産主義者が共産主義を抛棄する場合、第二は加藤弘之も森鷗外も徳富蘇峰も転向者であったという場合のように、一般に進歩的合理主義的思想を抛棄することを意味する場合、第三は、思想的回転(回心)現象一般をさす場合である。
P.285より引用
と引用してみたが、これまた本来ならば『転向論』を全文引用したいところなのだが…。いずれにせよ転向とひとえに言っても3種類あるということ。いずれにせよ第一の意味で語られることが多いだろう。つまり今まで共産主義的な、社会主義的なことを書いていた作家たちがこぞってそういうことを書くことを放棄したという意味で捉えて貰えれば表面的には十分である。
転向のスタートは佐野学と鍋山貞親が獄中から共同で発表した「共同被告同志に告ぐる書」である。この2人はこれまた簡単に説明すると当時の日本共産党の2トップな訳だ。つまりは最高幹部の2人である。そいつら2人が「僕たち転向します」と言ったらそれに連なっていた共産党員であったり、ナップやらコップとして参加していた作家たちも転向せざるを得なくなる訳で。結局、この昭和8年に掲載された2人の共同声明によりプロレタリア文学は同時に終りを迎える。
かのように思われているが、実は僕はここで終わったのはあくまで「プロレタリア文学"運動"」であってプロレタリア文学そのものが終った訳ではないと考えている。それは俗に言われる「転向文学」の出現が正しくそれの象徴であるように思われる。彼らは本当に「転向」したのか…という議論については僕なんかよりも吉本隆明の『転向論』を読んだ方が早い。
転向文学を語るうえで欠かせない作品の1つとして挙げられるのが中野重治の『村の家』である。僕はこの作品を読んだ時に「本当に中野重治は転向したんか?」と思われて仕方がなかった。もっと言ってしまえば、戦後あたりに書かれた『五勺の酒』なんか読んでもさらにこの僕の疑問は解消されることは無かった。しかし、作品自体としてはアイロニカルで面白い。
何を以て「転向」とするかは実は未だに僕は考えている。ある意味で「転向」というのは今までの思想を捨てることに等しい(訳ではないだろうが、今までのスタイルを変化させねばならなくなる)。僕等は今あらゆる場所から情報を簡単に得ることが出来て、あらゆる場所のあらゆる時代の思想を広範囲に学ぶことができる。今の時代に於いて「転向」とはなんだろうかと。
今までの思想を「捨てる」というと些か言いすぎな気もするが、しかし今までの考え方を180度転回させることが必要になってくる。プロレタリア文学当時に於いてはそれを国が主導で行っていた訳なのだから性が悪いと今では思えるが、当時は限られた情報源の中で戦っていたのだから仕方がないとも言えるような気がしなくもない。それに今までやってきたことをガラっと変えろというのは無理な話である。
新しい職場になってから僕は慣れない日々が続く。銀行業界と出版業界での慣習的な部分があまりにも異なるのでそれにいきなり変えろ、「転向」しろと言われるのは辛い。現に1週間働いた訳だがやはり慣れない。何と言うか銀行業界の慣習が如何に封建的なものであるかがよく分かったりもしたのでいい勉強にはなっている訳なのだが…。
僕のこの経験を「転向」と表現していいのかにはかなりの疑問がある訳だが、僕にとっては「転向」な訳だ。そういった中で今は徐々にその思想性に順応しようとあくせくしている所である。当時の彼らと同等であるとは決して言わないし、そんなこと考える方が烏滸がましいことこの上ないのだが、しかし何となくその「転向」することの苦労は分からんでもない気がする。自分の根底に培ったものを覆すのは困難を極める。
そんな訳で僕は展示を思う存分楽しんだ。写真が撮れなかったところが辛い所ではあるが、小林多喜二の『蟹工船』の生原稿が見れたことや、葉山嘉樹の『淫売婦』の伏字書き込み初版を見られたのは嬉しかった。また中野重治の書簡なども展示されており「あ、これは『愛しき者へ』に載ってのかな」とか考えながら見たりしていた。
衝撃的だったのは、まあこれはかなり有名だが小林多喜二の遺体の写真があったことである。教科書かなんかで見た記憶があるだけで、大きな写真で見たことが無かったので衝撃だった。結構鮮明に映っているんだな…と。しかし、写真に映し出された小林多喜二の顔面に殴られたあざがあることに複雑な感情を抱いてしまった。
本が影響を与える時代。多分その最後の象徴的事件が「風流夢譚事件」だったのではないかなと考えてみたりもする。偶然にもこれも右か左かというそういった思想に関わる話であり、僕は個人的にプロレタリア文学の残滓がここに来て精算されたような気がしなくもないなと思った。
大学生の頃、大学の図書館で当時の中央公論の『風流夢譚』を僕はコピーした。しかしそれを大学から実家に戻って来る引越しの合間に捨ててしまっていた。それが悔やまれ、地元の県立文学館で再度コピーをした。今でもたまに『風流夢譚』を読み返すことがあるのだが、やはりあのインパクトには驚かされる。あの『笛吹川』や『楢山節考』、『甲州子守唄』といったある種牧歌的な作品を残した深沢七郎がと当時は驚きを隠せなかったものだ。

『風流夢譚』については詳細は触れることはしないが、1度読んでおくことを敢えてオススメしておくことにする。
そんな訳で僕は日本近代文学館を思う存分味わいつくした。僕は博物館や美術館へ行った際には必ず記念としてポストカードを購入して帰る。購入する際にまた階下の愛想の悪い受付のお姉さんのところで購入せねばならなかった。お姉さんにポストカードを渡してお金を支払ったのだが、お釣りが違うのではないかと思い「お釣り〇〇円じゃないですか?」と言ったのだが、すぐにそれが僕の間違いであったと分かり「あ、ごめんなさい!申し訳ない!僕のミスでした…テヘ(*^▽^*)」みたいな感じで謝ったのだが、お姉さんは無言。挙句の果てに「はぁ~…そうですか…」みたいな感じで拍子抜け。愛想が悪いにも程があるだろ。
受付のお姉さんは苦手だが、日本近代文学館は好きだ。また行きたいと思った。
そんな今日1日の話。
よしなに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
