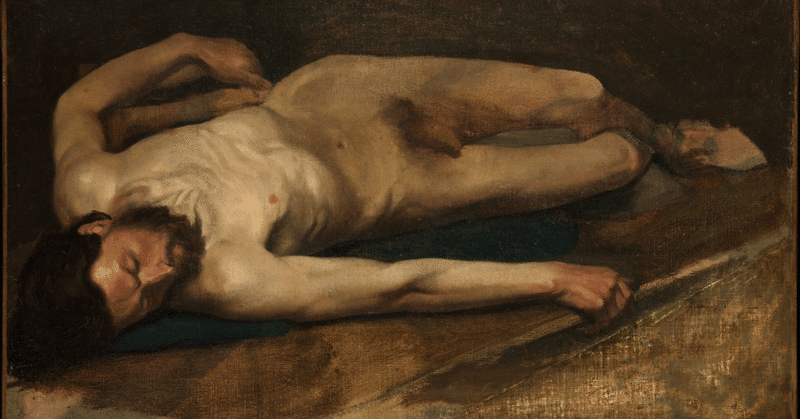
走れロドスここで飛べ
寒波本格到来につき底冷え甚だしく、寝醒めた後も暫く床から離れられず。十一時、濃い目の紅茶とうなぎパイ二枚いや四枚いや六枚、七枚、八枚、九まーい。積雪深いけど今日も行く。買い物に行くのが億劫なので冷蔵庫が空っぽだ。キーボードを打つのがつらい。
きのうはオスカル・パニッツァ『犯罪精神病』を読み了る。ことし読んだ中ではもっとも毒性の強い本。「正気」で書いているとは思えない文がそのまま収録されている。「狂気」「異常」「精神病」という診断的カテゴリーはどんな社会的歴史的文脈のなかで作られるのか、と考えざるをえない。研究し甲斐のある問題だ。となればミシェル・フーコーの『精神疾患とパーソナリティ』『狂気の歴史』『監獄の誕生』などを読みたくなる。
オスカルの書くものはどれもきっと「健全志向」の強い国では閲覧注意指定されてもおかしくない。日本がこういうことに比較的寛容な政治体制で良かった。こんな奇妙で「危険」な本が出版され世に出回ることを当然のことと思ってはいけない。検閲や禁書などの言論統制には長い歴史がある。
とりわけ秦帝国の初代皇帝(始皇帝 前221~前210)による焚書坑儒はなかなかえぐい。焚書とは、前213年、官の記録や農業医薬占卜などの実用書を除いたあらゆる書物を焼き払った事件。坑儒は、前214年、始皇帝に批判的だと疑われた学者460人余りが都の咸陽で坑(あなうめ)の刑に処せられた事件。ちなみに焚書坑儒から十年も経たぬうちに秦は滅亡している(前206年)。ざまーみやがれ。そこに単純な因果関係を見ることは避けたいけども、その文化的損失が滅亡要因を成しているとはどうしても思いたくなるよね。
というのも書く人間である以上に読む人である私は、たとえどれだけ「正当」な言論統制に対しても、生理的反発を覚えずにはいられないからです。日本でいう刑法175条「わいせつ物頒布罪」の存在理由も分からない。絶対的猥褻概念だとか相対的猥褻概念なんて些末な学説論議は滑稽にしか映らない。それはそれで調べると面白いんだけども。でも『チャタレー夫人の恋人』や『悪徳の栄え』が裁判沙汰になったなんて、今ではほとんどお笑い種と思いませんか。潔癖というより悪しき石頭だ。
なにを読むべきか読まざるべきかを決めるのはあくまで私であって、権力者や官僚ではない。反国家的言論にたいし極度に不寛容な国家はそのために衰微するだろう(しなければならない)。歴史を遡ってみれば、読書愛ほぼナッシングのフシアナ連中が検閲ならびに発禁における強い権限を有していたことも少なくない。読書愛の溢れる人間は決して出版物の制限などきっと望まないだろう。
ただ難しいのは、「焚書」などの文化破壊が必ずしも「野蛮人」の所業とは限らない事だ(フェルナンド・バエス『書物の破壊の歴史』紀伊國屋書店)。ながく書物を読んできてその影響力をよく知っている権力者ほど先回りして書物を破壊したがる、という皮肉も無視できないようだ。教養に乏しい人間は書物に特有の魔力に気づかない。書物から思想を注入され世界の見方を変えられた経験がないから、他の人間にそんなことが起こるとは夢にも思わない。とすれば、ごく単純に考えて、無教養度の高い権力者(あるいは権力集団)ほど出版物には寛容になるということか。もっともそこまで無教養度の高い人間たちが権力の座に就いてしまうことは別の点で大いなる問題になるのだろうけど。
さっきの秦の始皇帝はさすがに極端な例かもしれないが、時の権力者の独裁制が強ければ強いほど、体制の維持に不都合な書を排除しやすくなるのは本当だろう。印刷技術が確立し統制不可能のほど大量の出版物が流通する以前の時代なら尚更。いっぽうで出版統制の苛烈なそんな時代だからこそ、命懸けの著述意志による血の滲むような本が生まれ得るのかも知れない。ナチス占領下のフランス・レジスタンスによるいわゆる「地下出版」のような。
きょうはヴァルター・ベンヤミンの『パリ論/ボードレール集成論』の続きと、デイビッド・エイブラム『感応の呪文』の続きを読むか。ヴァルターの『パサージュ論』は愉しみとして取っておいたがもう我慢できない。今年の内に読みたい。いつまでもあると思うな読む時間。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
