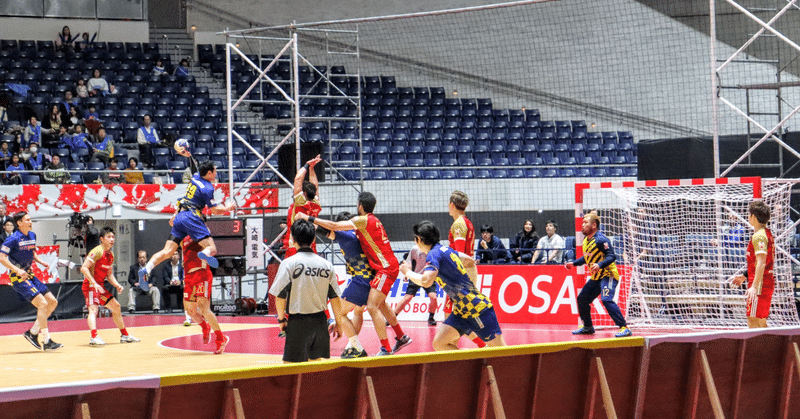
弱小校のハンドボール論
こんにちは!Recept代表の中瀬です。
私は今でも東京都の社会人リーグに出るくらいハンドボールをプレイすることが好きなのですが、学生の頃はどうやって勝つかを常に考えていて、そのことを最近思い出したので形に残しておこうと思います。
弱小校ならまずは守備
私は特に強豪校でプレイしていたわけではなく、大学時代もリーグ昇格などそれなりに良い時期もありましたが、関東大学4部というなんとも中途半端な成績が一番の実績です。
こういうチームで起きがちなのが、強豪校を経験した人材が集まらないことです。
スーパープレイヤーがいないチームにおいて試合設計をせずに臨むと個人プレーに頼ることになるのでやらない方がいいというのが私の考えです。
となると、ハンドボール(というかゴールを争うスポーツ)の原則にもどって考えるのです。
「多く点とった方が勝ち」
誰がなんと言おうとこのルールに則って勝ち負けは決まるので、点をたくさん取るか、取られないかしか考えることはありません。
となると、究極、点を取られなければ負けることはないです。
さらに、攻撃を頑張るか守備を頑張るか、ここで弱小校の人材不足の問題を考えます。
個人の質が影響しやすい攻撃よりも、組織で統率がとりやすい守備を極めようというわけです。
サッカーなどのゴールを追いかけるスポーツは大体そうだと思っていて、攻撃はメッシみたいな人がいればよいのですが、メッシほどの攻撃の再現性を求められるほど弱小校は成熟したチームではないです。
よってより再現性の高い守備を固めることになります。
また、守備を固めると何が良いかというと、強豪校にも勝ちやすくなります。
なぜかというと、ロースコアゲームに持ち込めば(ハンドボールでは20点入らないくらい)、ワンプレーの判断ミスがめちゃくちゃ響くからです。
勝ち負けを左右する運ゲーに持ち込める点で守備を固めることが、チームの基礎力を上げ、格上に勝てる可能性を高めます。
攻撃も再現性を求める
ハンドボールやサッカーもそうですが、攻撃はいくつかのパターンが存在します。
それが速攻とセットです。
速攻は相手の守備陣系が崩れていたり数的優位が作り出せている場合が多く、逆にセットはファールなど試合が止まった後の攻撃となり、相手守備陣系が整っていて数的同数です。
速攻はケースバイケースなので再現性は求められません。
そこで、セットの再現性を高めるためにハンドボールでは攻撃時のサインプレーが存在します。
これは「きっかけ」とも呼ばれていて、スペイン2005など、世界で有名なサインプレーも存在します。
攻撃の時に相手の守備の枚数が揃っている際に、向こうは組織的に守備をしようとしてくるので、こちらも組織的に攻撃の陣形を作って崩しに行く目的で行います。
私は司令塔のポジションだったので、いかにサインプレーを使って、人材難でも再現性高く点を取れるかを考えていました。
ハンドボールのサインプレーを考えるにあたって大事なポイントは以下です。
選手ごとの特性にあったサインプレー
サインプレーを作る時は、誰がフィニッシャーになるのか、このサインプレーのキメどころがどこなのかを考えます。
その時に、選手個人個人の特性にあったサインでないと成功しません。
判断が苦手なゴリマッチョはそのフィジカルが活きるサインプレーを与えるべきなのです。
分岐することができるサインプレー
基本的にボールを持った人が、シュート、パス、突破、など判断を行った結果、得点に繋がったり、繋がらなかったりします。
ハンドボールはコートプレイヤーが6人なので、1度のサインプレーで6人全員がボールを一度触るとすると、6回の判断が生じます。
6回の判断において、相手守備の配置や行動が異なります。
それぞれの判断のフェーズで敵がどういう配置の時はどのような判断をするべきかを洗い出して言語化します。
これは練習や実戦で新たに学べることもあるので、まずはチーム全体として羅針盤となる判断の分岐を共有して、効果的に思える新しい判断のパターンや必要のなくなったものを適宜更新するのです。
失敗しても別の切り口に変換可能な2段構成のサインプレー
また、サインプレーは何度もやっていると対策されます。
私もリーグ戦の後半になるとサインの番号を相手が覚えていて、サインに合わせて守備をされることがよくありました。
そんな時のために、サインプレーをダミーにしたサインプレーも用意します。
といっても試合の中で刹那にサインプレーを別のものに切り替えることは不可能なので、失敗した時のプランBを用意しました。
要はサインプレーでフィニッシュ(シュート)までありつくはずの工程でシュートで終われない、つまりボールを保持している場合そのサインプレーは失敗です。
しかし、サインプレーの中で相手の陣形や攻撃陣の陣形が一定変動します。
面白いことに、サインプレーが失敗した時のコートの状況は大体同じなので、その崩れた戦況を活かして、今度はサインなしに次のサインプレーのフェーズに移動します。
ここまですれば1時間の試合時間で結構な割合の時間はこちらが主導権を握った状態で攻撃を進められます。
まとめ
スポーツも考え抜くと、運動神経という範疇を超えた部分で対等に渡り合えるので楽しいものです。
しかし、その裏には再現性を保つための体力トレーニングやフィジカルトレーニングなど、泥臭い努力が存在します。
机上の空論では勝てなかったです。
私は大学でハンドボール部に入部してから15キロほど増えていて、体重の変化がそれを物語っています。
ちなみに今は10キロ痩せました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
