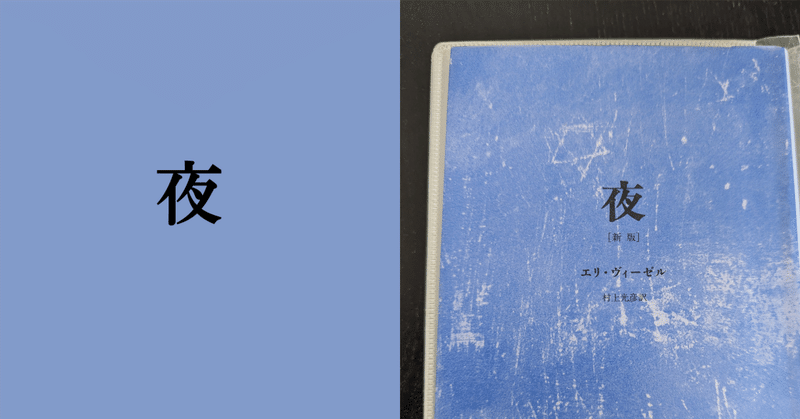
離れない死者のまなざし【夜】
「死者の気配が色濃く感じる」
本編だけでなく、著者の前書きから感じました。
死者たちを忘れようものなら、彼らを二度重ねて殺すことになろう。
証人がみずからの気持ちを押えて証言することを選んだのは、今日の若い人たちのためであり、また明日生まれでる子どもたちのためである。証人は、みずからの過去が彼らの未来になることを望まないからである。
どちらも前書きからの引用ですが、
「死んだ家族や大切な人のことを忘れてはいけない」
「自分の過去の出来事が、今の若い人やこれから生まれでる人たちの未来に起こらないでほしい」
そんな願いが伝わってきました。
メロディアスライブラリー2014.1.26放送。
・自分たちは大丈夫
主人公エリエゼルは堂守りのモシェと交流します。
ある日、モシェは他の地域に連れて行かれます。
命からがら戻ってきたモシェ。
エリエゼルにこんなことを話しました。
列車、トラックで運ばれ、森で大きな穴を掘らされました。その後撃殺されたと。
周囲の人間は誰も信じませんでした。
次第に、エリエゼルが住んでるシゲットにも、
ナチスの魔の手が
迫ります。
エリエゼルは父親にパレスチナへ移住することを提案しますが、断られてしまいます。
ゲットーに閉じ込められ、
後にアウシュビッツへ移送されてしまいました。
シゲットの人たちは、アウシュビッツの存在を知らなかったようです。
後世の人間から見ると、
「それ、強制収容所行きだから逃げて」
「モシェの助言に従って」
そう突っ込みたくなりますが、
当事者にはわかりません。
「戦争はいきなり始まらない」
「始まったときはもう外国に逃げることができない」
徐々に追い詰められていく様子に恐怖を感じました。
・死体のまなざし
母親と妹、一緒に過ごしてきた父親、
収容所で過ごしてきた仲間も亡くしました。
それ以外にも、逃亡を図るなどして
絞首刑になる人もいました。
読んでると、
感覚が麻痺してしまいそうになります。
本を閉じて、現実に戻ると
「こんなのが普通になってはいけない!」と
頭を振りました。
私の目のなかにあった死体のまなざしは、それっきり私を離れたことがない。
こう締めくくられてますが、
読んでる間、まさに死者の気配が色濃く感じました。
・驚かされた訳者あとがき
旧版と新版がありますが、今回新版を読みました。
旧版の後に新版のあとがきが追加されています。
「それを言っちゃう?」と
思わず突っ込んでしまいました。
ドイツ人はもともと合理的な国民のはずです。ところがヒトラーの立てたユダヤ人絶滅計画は、ナチス・ドイツの存亡を懸かる戦争遂行努力を阻害する非合理きわまる代物でした。
その根拠として
・貴重な輸送手段を、ユダヤ人移送に回した。
・飢餓状態の未熟練労働力を強制労働につかせても軍需品の生産増強に役立たない。
大量虐殺というと悲惨な印象で語られることが多いですが、効率の悪さから指摘されていたのに驚きました。
訳者は、著者の書籍を数多く翻訳しています。
そんな中で、こんなことを語っています。
私はこの本を親しい人たち、なかでも幸福で屈託のない人たちには読んでほしくないと思いました。(中略)
それでも、みなで考えてゆくためには、やはり読んでいただかねばなりますまい。
「幸福な人には読んでほしくない」一方で、
「それでも皆で考えていくためには読んでもらわないといけない」と葛藤を感じました。
・感想
Amazonレビューを見ると、
「金儲けが〜」などと言われ、マイナスの評価をする人もいました。
私は著者を知らない状態で読んだので驚きました。
ホロコースト文学というのを差し引いても、
「重厚な文学作品」と感じました。
悲惨なのに、考えさせられます。
信仰って何? 生きるってどういうこと?
頭の中でぐるぐる回りました。
敬虔なユダヤ教徒だった著者が、
生きたまま子どもが焼かれるのを見て
信仰をなくしたと話していたのが印象的でした。
以上、ちえでした。
プロフィールはこちらです。
他のSNSはこちらです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
