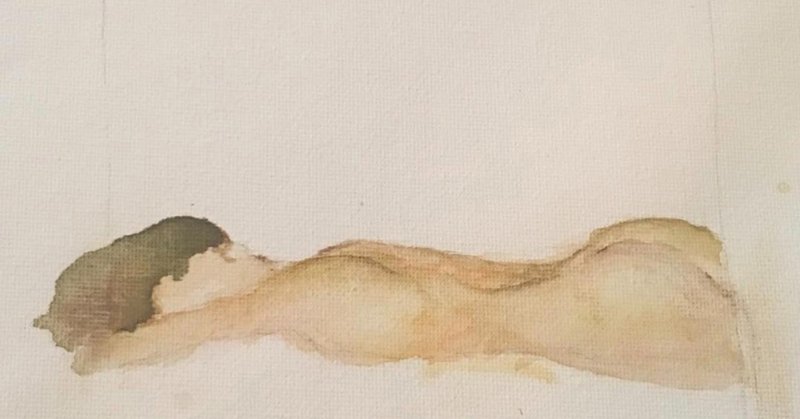
村上 ・ 「納屋を焼く」 (2)同時存在, 霊媒
私が大学で書いたものを転載しています。
3. 複数の世界と同時存在
「彼」は彼の哲学ともいうべき確固たる前提のもとに話している。「僕」は多くの「社会的」人間が属しているであろう「常識」的見解、意識のために「彼」の語りに驚き、驚かされ続ける。「彼」がこちらのジャッジに振れることはほとんどない。
僕は判断なんかしません。観察しているだけです。雨と同じですよ。雨が降る。川があふれる。何かが押し流される。雨が何かを判断していますか?いいですか、僕はモラリティーというものを信じています。モラリティーなしに人間は存在できません。僕はモラリティーというのは同時存在のことじゃないかと思うんです(68)
判断を否定することで「常識」によるジャッジから逃れるようである。「判断はしないがモラルはある」と語るのは、「彼」が同時存在しているがゆえに自己完結的にモラルが成立しているということだろうか。また、自らの存在(による行動やその結果)を自然に従うものとみなしている。これは、国や土地によって善悪の基準が異なるという原理を徹底し、何を犠牲にしてでも自らの快楽を追求することを自然の望みだと考えるというサド的な哲学 の匂いがする。我々がこれを危険だと感じるのは、我々の持つ種類の「倫理的常識」によるものであるが、「僕」は「彼」の意見に浅く寄り添うような姿勢で話を聞くことで、フラグメントをなんとかつなぎ合わせ理解しようとしているように見える。なお、この異質な空気の中に我々の感じる妙な安心感は、先に述べた「すばらしき日常」による効果であろう。これは我々を話の中に繋ぎ止めておく。
村上作品の語り手はしばしば、この世界(「現実」的世界)と、「そちら側」の世界(「夢」的で様々なものの輪郭が歪んでいるような混沌世界) の狭間に置かれる。「彼」の語ることは、いわば日本語の話せる異星人が説明しているかのような、我々の言葉を使った飛躍した思考という印象を受ける。しかし「僕」が自身の依拠している「常識」によって「彼」と衝突することがないのは「僕」がそれを、分かると言わないまでも、疑い切れないと感じているからではないのか。どちらともつかない存在として読者の目にうつることの多い「僕」は、双方の世界に生きているといえるだろう。
『羊をめぐる冒険(下)』において、語り手がそのように思いを馳せることがある。小屋で孤独な日々を送っているときである。
何もなければおそらく僕は今ごろどこかのバーでオムレツでも食べながらウィスキーを飲んでいるに違いない。(中略)そんなことをぼんやりと考えているうちに、この世界にもう一人の僕が存在していて、今頃どこかのバーで気持よくウィスキーを飲んでいるような気がしはじめた。そして考えれば考えるほど、そちらの僕の方が現実の僕のように思えた。どこかでポイントがずれて、本物の僕は現実の僕ではなくなってしまったのだ(140−141)
ここでも「すばらしき日常」が垣間見えるがさておき、ここでは軽く幻想のようにとらえつつも、先に述べた双方の世界に生きている、ということが都会のバーと今の山小屋という状況でわかりやすく二分されていることで、「彼」の語る「同時存在」という言葉に当てはまっていくようである。どこかでポイントがずれて、本物の僕は「現実」の僕でなくなってしまった、ということはあるのだろう。そして、その「ポイント」をずらす鍵となるものに、我々読者にとってはいくつか心当たりがある。
4. 霊媒的な存在
『納屋』にも見られるように、村上作品には語り手をこの世界から「そちら側」の世界へと誘う霊媒的ともいうべき存在がある。霊媒的というのは著者本人の言葉で、自身の作品における女性を「自分という存在を通すことによって、何かしらを引き起こす」としてその霊媒(ミディアム)的性質をみとめている。 それは奇異なことがおこる鍵なのである。しかしそれは仰々しいものではなく、彼女とのささやかな日常を過ごしているといつの間にかそちらに取り込まれているといった具合である。『納屋』ではガール・フレンドが「彼」を連れてくることにより「納屋を焼く」物語が始まり、この作品では彼女が消えるとすぐに物語は終わるが、他の作品では女性が去ったことにより(『ダンス・ダンス・ダンス』)、女性との再会により(『国境の南、太陽の西』)、女性が亡くなることにより(『ノルウェイの森』)、失踪することにより(『スプートニクの恋人』)、語り手のなか、また外で何かがおこる。―これらの作品中でも記載した以外に様々な絡み方がある― また女性というモチーフ以外に霊媒的なものは見られ、『納屋』において意識の流れ的に語られる、急に子狐の芝居を思い出すことを媒介するのはマリファナ(大麻煙草)であった。
おわりに
著者のインタビューを参照する。
――日常的な安心や、日常的な現実の価値の一切に対して、問いを投げかけたいということでしょうか。
(村上) 自分たちは比較的健康な世界に生きている、とみんな信じています。僕が試みているのは、こうした世界の感じ方や見方を揺さぶるということです。僕たちは、ときに、混沌、狂気、悪夢の中に生きています。僕は、読者がシュールレアリスティックな世界、暴力や不安や幻覚の世界に潜ってゆくようにしたい。そうすることによって、人は自分の中に新しい自分を見出せるかもしれません。
この世界とそれ以外の世界との境界は確固としたものでなく、人は容易にそちらへ行ってしまう。それを媒介するものとして、作品中では男性である語り手にとっての女性の存在や、その他のモチーフがある。整えられた「すばらしき日常」の中に大きくうごめくものがある。その中で揺さぶられる語り手の心情はわずかな描写にとどめられ、こちら側に引っ張られすぎることがない。
そしてこの構造は決して一つの物語の中にとどまるものでなく、我々が「この世界」と思っているものは夢の世界のような、捉えがたい混沌に満ちているということを示しているのだろうと推測する。見方を変えれば、それは「この世界」は「そちら側」の世界であり、我々はこの世界にあって、同時に「そちら側」の世界にいるという同時存在性、あるいはその複数の世界の融和性である。
Cited
村上春樹『蛍・納屋を焼く・その他の短編』、昭和六十二年、新潮文庫
『ダンス・ダンス・ダンス(上)』、1991年、講談社文庫
『羊をめぐる冒険(下)』、1985年、講談社文庫
『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集 1997-2011』、2012年、文春文庫
『国境の南、太陽の西』、1992年、講談社文庫
『ノルウェイの森(下)』、1987年、講談社文庫
『スプートニクの恋人』、1999年、講談社文庫
石井洋二郎『フランス的思考 野生の思考者たちの系譜』、2010年、中公新書
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
