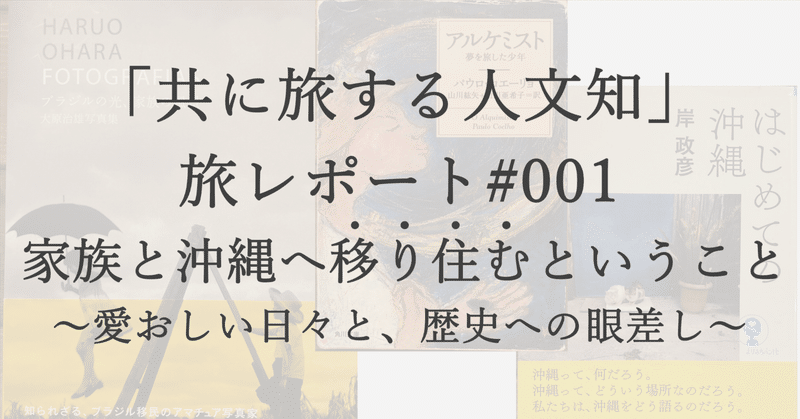
旅レポート#001:家族と沖縄へ「移り住む」ということ 〜愛おしい日々と、歴史への眼差し〜
言葉屋だというのに選ばれたのが写真集で、「なぜ写真?」「なぜそれを僕に?」が最初は頭から離れなかったが、深く納得した。僕の置かれた状況、僕が好みそうなこと、僕に刺さりそうなこと。それらを僕自身よりも把握していただいていると感じられるような選書だった。
********************************************
前提となる人文知や教養がないとなかなか中身が入ってこないような難解(僕にとっては)な文章も、並走していただくことで「教養がある人じゃないとたどり着けない深さ」で読み取ることができたかもしれない。
*********************************************
ワールドカップの試合を本田圭佑選手と一緒に観戦する、かのような贅沢な時間だった
Aさん/東京都(沖縄県)
みなさん、こんにちは。街の言葉屋です。新たな読書体験をご案内する「旅する人文知」。今回はその記念すべき1例目の事例報告をお届けします。
「共に旅する」と銘打った言葉屋の案内する読書体験ですが、今回のお客様はまさに「旅」がお好きな方。これまでも多くの旅を重ね、そしてまさに今、次なる冒険が目の前に控えているとのこと。しかも今度は、ご家族と…!
旅、移住、沖縄、生活、記憶、歴史といったキーワードが飛び交った今回の旅。果たしてその全容はいかなるものだったのでしょうか。その模様を描いた報告を、どうぞご覧ください。
【今回の旅人】
Aさん/東京都(沖縄県)/ホテル経営
【選択コース】

◎ 星空コース:聴取・選書・読解・相読
井戸コース:聴取・読解・相読
地図コース:聴取・選書
【回数・実施形態】
・ヒアリング
・70分セッション×3
・対面/オンラインのハイブリッド
【お値段】
モニター期間につき、お客様の付け値。
書籍購入に充てさせていただきます🙏
【今回のオーダー】
妻と2人の子どもの家族4人で沖縄に移住予定。
沖縄のこと(歴史など)を知りたい。
【今回のキーワード】
旅・移住・家族・沖縄・生活・記憶・歴史
【巡ったテクストたち(選書リスト)】

① 『大原治雄写真集 ブラジルの光、家族の風景』
② 今福龍太「『時間の歴史』を証す人」(既述写真集所収)
③ 岸政彦『はじめての沖縄』
【旅の記録】
●鍵となるのは『アルケミスト』

最初のヒアリング時に、Aさんの人生において一際大切な物語で、沖縄移住のきっかけにもなった本を紹介いただきました。それがパウロ・コエーリョ著『アルケミスト 夢を旅した少年』。このブラジル人作家の遺した物語が、人生の節々でAさんに大切な出会いをもたらしているというその事実が、今回の選書の大きなヒントとなりました。

まず入口としたのが『大原治雄写真集 ブラジルの光、家族の風景』、そう、写真集です。高知県に生まれた大原治雄さん(1909-1999)が家族と共にブラジルにわたったのち、農作業に従事するかたわら、手にしたカメラで撮り続けた日々の写真が収められています。大原さんは家族とブラジルへ、Aさんは家族と沖縄へ。場所は違えど、その行き先で家族と共に生きるという時間に想像を馳せて、まずはこちらの写真集を選び、一緒に読みすすめていきました。

次いで読んだのが、当写真集に収められた今福龍太さんの短い論考「『時間の歴史』を証す人」でした。その土地土地の歴史を知ることを、私たちは「〇〇年に〜〜があった」「〇〇という人が〜〜で〜〜した」など、年表にある出来事を知ることと思いがちです。けれども、それでは決して知ったことにならないのです。Aさんがこれから向かう沖縄は、確かにそこに生きた人たちがいて、今も生きている人がいて、これからも生きる人たちがいる「生きた時間と場所」なのです。だからこそAさんとは最初に「写真集」を読み、そこで強く感じられる「生きた土地/時間への眼差し」が、これから沖縄で家族と生きるAさんのヒントになることを願いました。
●「大きな歴史」ではなく、「小さな歴史」を。
歴史とは、年号や情報の羅列となったいわゆる「歴史」ばかりではなくて、そこに生き死にがある確かな「時間」でもあるということ。前者はしばしば「大文字の歴史」と呼ばれ、後者は「小文字の歴史」と呼ばれます。そして私たちはしばしば「大きな歴史」ばかりに気を取られ、「小文字の歴史」を蔑ろにしがちです・・・。このことを確認したのち、最後に読んだのが岸政彦さんの『はじめての沖縄』です。

「ナイチャー」(「沖縄以外の都道府県の人」を意味する言葉;本書p.10参照)たる著者が、研究者としていかに沖縄という土地と、そこに生きる人々を知ろうとしたのかが、ここに描かれています。作者が沖縄で出会った人や出来事について、どのように考えようとしたのか、その記録/記憶とも言えるでしょう。あくまで1人称を離れずに、沖縄に対して「上から目線にならないようにする姿勢」が貫かれています。そう、まさしくこれは、岸さん自身が「小文字の歴史」への眼差しをもって描こうとした「沖縄入門本」なのです。「沖縄とは〇〇というもので」とか「沖縄は〜〜年にこうなって、〜〜年にはこうだった」といったことを教唆しようとする「入門本」とは、はるかに異なるものです。そのことは、以下のような引用からも明らかでしょう。
沖縄の独自性を、単なるラベリングやイメージに還元しないこと。それは実在するのだ。(・・・)できるだけ世俗的に語ること。
「抵抗するウチナンチュ」のような、安易なロマンティックな語り方をやめること。しかし同時に、沖縄の人びとの暮らしや日常のなかに根ざしている、日本に対する違和感や抵抗や「拒否の感覚」を、丁寧にすくい上げること。
(・・・)沖縄の人々の多様な経験や、基地を受け入れさえするような複雑な意志を、そのままのかたちで描きだすこと。(・・・)
いまだ発明されていない、沖縄の新しい語り方が存在するはずだ。
●「小さな歴史」への眼差しをもって、沖縄へ
大原治雄さんと、今福龍太さん、それから岸政彦さんの「眼差し」を知り、Aさんとご家族が一体どんな沖縄での時間を過ごしてゆかれるのか。困難もきっとあることでしょう。ですが、大原さんの撮った写真にも現れているような、愛おしい日々が必ずやあるはず。そう予感して、勝手ながら大変楽しいものと想像しています。
また今回は、Aさんご本人が理系大学院にも在籍されていたとのことで、私自身も驚かされるような発見も多く教えてくださり、とても充実した時間となりました。最後に、Aさんの感想をお読みいただくことで、レポートの結びとしたいと思います。アンケートにて引用されている文章をみて、思わずAさん自身のご家族への眼差しを思いました。豊かな時間を、言葉を、本当に有り難うございました。
【Aさんのご感想】
● 印象に残った文章・言葉
端正に切りとられた情景の、それじたいは静謐な映像的小世界が、大地を刻みつづけるはるかな歴史の波動と深いところでつねに共振している。
「静謐」という言葉を初めて知った。単なる「穏やか」「平穏」とも違うニュアンスで、自分が好きだと思っていた空気感を形容できる新しい言葉との出会いがあった。
①
歴史は無名性のもとにその尊厳をあらわにする。無名性によって生きられた歴史。それを外部から掻き乱そうとする権力者や英雄たちの事々しい大文字の「歴史」Historiaの虚飾を暴きたてる、静謐かつ広大な領域がそこにある。
②
(・・・)野を舞台にする無名者たちの歴史とは、もうひとつの歴史estoriaである。小文字で記される、慎ましく繊細で、権威や正当性からキッパリと身を引き離した、潔い歴史である。
教科書に載るような、著名な人物によって起こされたイベントとしての「大文字の歴史」。教科書には載らない、その時代を生きる無名の人々が積み重ねた、日常としての「小文字の歴史」。それぞれを使い分けることができる表現との出会いがあった。
大原にとって生命の花こそ、妻である幸の放つ世紀と優美さであった。(中略)彼女の、どこかさびしげな、しかし穀然とした眼差しと微笑みが、少しずつ老いてゆく姿とともに写し撮られている。不幸にも、筋力を失っていく難病に冒された晩年の幸は、いかなる美しき花にもかならず萎れ、枯れてゆく時が訪れるという避けがたい宿命を大原に実感させたであろう。だが、孔雀の羽のような扇を持ってソファに体を沈める彼女の最後の笑顔をとらえた一枚の写真のなかで、幸はみずからが受け入れた人生の「歴史=物語(estoria)」を心から祝福しているように見える。そしてそのことを、彼女のうるんだ瞳の奥に映った夫も深く同意している。
同上. p.168
伝記に興味を持てない一方で、ホームレスの老人を見かけるとその人の人生についてしばらく物思いに耽ってしまう自分。その時の感情は、憐れみや自分への戒めなど決してネガティブな感情ではない。むしろポジティブな、敬愛に近いものであることが多い。
旅の中で観光地にさほど興味を持つことができず、一方でその土地と人々と織り成される異日常にどうしようもなく惹かれる自分・・・。自分が関心を持ってしまうのは、大文字の歴史ではなく小文字の歴史なんだろうなと理解できた。
● 日々の生活/学業/仕事に活かせそうな気づき
それまで自分の中にあった、言語化はできない概念や感情に、名前があることを発見した。 名前をつけることで、「近いけどそれではない」ものとの区別が明確につくようになり、自己理解が深まったし、自分が何を目指したいのかの方向性も少しだけクリアになった気がする。
● その他
言葉屋だというのに選ばれたのが写真集で、「なぜ写真?」「なぜそれを僕に?」が最初は頭から離れなかったが、写し撮られた数々の農業移民の家族の記憶と、添えられた今福氏の言葉を読んで、深く納得した。僕の置かれた状況、僕が好みそうなこと、僕に刺さりそうなこと。それらを僕自身よりも把握していただいていると感じられるような選書だった。
単語や概念や歴史だったりと、前提となる人文知や教養がないとなかなか中身が入ってこないような難解(僕にとっては)な文章も、並走していただくことで「教養がある人じゃないとたどり着けない深さ」で読み取ることができたかもしれない。例えるなら、「実はあのパスにはこういう意図があって」とプロ目線でものすごく興味の湧く解説をしてもらいながらワールドカップの試合を本田圭佑選手と一緒に観戦する、かのような贅沢な時間だったと感じた。
人文知や教養は一朝一夕で身につくわけではないが、それを深めた世界を垣間見ることができ、非常に満足。
ここまでお読みくださり有難うございました。皆さんも「共に旅する人文知」、ご一緒してみませんか?気になる方はどうぞお気軽に連絡ください。現在モニター期間中、いまなら付け値でお受けします。ご連絡、お待ちしております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
