
出版人がもつべき「器の大きさ」について。【オマケ】朝日新聞社での思い出①
【トップの画像は映画『クレージー作戦 くたばれ! 無責任』(1963年東宝)から。左から安田伸、犬塚弘、谷啓、植木等、ハナ肇、桜井センリ、石橋エータロー。クレージーキャッツが勢揃いで都心のビル街を意気揚々(いきようよう)と行く】
5秒でさとった「この出版社こそ日本一!」
ズバリ本題から書きます。
タイトルに掲げた「器の大きさ」を見せてくださった出版社があります。
中央法規出版株式会社さん(東京都台東区)です。
中央法規さんの本は一冊しか読んでいないけれど、もちろん中央法規さんと仕事したこともないけれど(私は元文筆業です)、中央法規さんの方とお会いしたこともないけど(電話でお話ししたことはある)、中央法規さんこそ日本一の出版社ですっ。
私はそう確信しました、パソコン画面を見て5秒で。
中央法規さんの本をベースにnoteに投稿
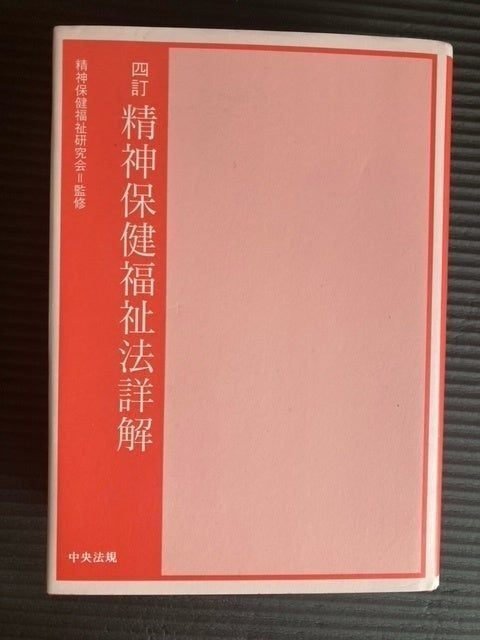
今年(令和5年)3月6日、私はnoteにある記事を投稿しました(よろしければ本文末をクリックされて下さい。お読みいただけます)。
その記事では、中央法規さんの本『四訂 精神保健福祉法詳解』(精神保健福祉研究会監修)からの引用をたびたび行なっています。この本の存在がなければ、記事自体まったく書くことができなかったでしょう。
というよりも、その拙稿は『四訂 精神保健福祉法詳解』について論じた(というほど大層なものではありませんが)作品と言っても過言ではないのです。
しかし、決して「この本は素晴らしい」と高評価しているわけではありません。
真逆です。
思いっきり罵倒しまくった私の投稿文
どんなふうに真逆か、私の投稿記事から引用してみます。
「(その内容の一部について)ハッキリ申し上げます。日本語として完全に破綻している迷文です。」
「いちいち例示しませんが、この『四訂 精神保健福祉法詳解』は、ツッコミどころ満載のおかしな日本語の宝庫です。」
「(ある箇所を引用して)みたいなおバカな屁理窟(理窟になってない理窟)を『牽強付会』というのです。小学生でも分かる言葉に置き換えれば『こじつけ』ですね。
まったく精神保健福祉法をどう研究なさって何を『詳解』しておられるのですか(笑)。」
いやー、強烈なコト、書いていますね。われながらそう思います。
「(監修者の)皆さんは、信じ難いほどに思考力も日本語力もお粗末な人たちです。」
「一体何が言いたいのですか。
(中略)
これはもう『愚昧』とか『悪辣』といった言葉で理解できる域を超えています。夢野久作『ドグラ・マグラ』の世界です。何が何だか訳が分かんない。」
もう、ボロクソですね。
私は初っ端から「これは驚くべき本です。私は度肝を抜かれました。」なんて書いていて、これが讃辞ではなく悪罵であることは言う間でもありません。
しかし何と言ってもトドメを刺したのは、この記述だと思います。
「こんな本(税別6,400円)で詳解されても意味がないのですよ、(中略)
ちなみにこの『四訂 精神保健福祉法詳解』、私が住む杉並区の区立図書館(13館)には一冊の在庫もありませんでした。」
これは他の文と違って、主観的評価ではなく客観的事実に軸足を置いた文です。
ですが〈価格〉と〈売上〉にかかわるこんなデータをネット上で公開されるのは、とても嫌なことであるはずです、誰だって。公務員の方は別ですが、業種を問わず、民間企業にお勤めの方ならお分かりになるはずです。
私の度肝を二度抜いた中央法規さん
「『四訂 精神保健福祉法詳解』を読んで度肝を抜かれた」という私の記述に嘘偽りはありません。「度肝を抜かれる」なんてことは、人生でそう何度もあることではないでしょう。
ところが、この本の読了後さほど月日を経ぬ今年3月9日に、私はもっと度肝を抜かれる事実に遭遇したのです。
それは、noteクリエイターであられる中央法規オンラインショップ担当さんが、同日16時32分に、私の記事にスキしてくださったことです。
自社の本を貶(けな)しまくった私の文章に、中央法規さんがスキしてくださったのです!
ぬ、ぬ、ぬわんという器の大きさなのでしょう。
形容する言葉を、私は知りません。

狭いムラ社会、料簡も狭い出版界
「悪評でも罵詈雑言(ばりぞうごん)でも、とにかくnote投稿記事で自社の本を取り上げた文なので、宣伝になると思ったのさ」
なんて思われた方がいらしたとしたら、それは出版の世界をご存じない人の、勘違いしまくりの感想です。
一般の方は、出版人たちの狭量さをご存じありません。
業界自体が狭いムラ社会です。「クリエイティブ(創造的)な仕事をしているのだから自由闊達なマインドあふれる世界なのだろう」とか思われているとしたら、それは単なる幻想です。
因習にとらわれ筋道の通らぬこと、実にしばしばです。
作家の真樹比佐夫さんは、ある小説を某大手会社から出版する予定だったのですが、お兄さんの梶原一騎さんが暴行事件で逮捕されたさいに、その社からご自身のペンネームを変えるように要求されました。真樹さんが憤然となって原稿を引き上げたことは言う間でもありません。
いろんな会社(みんな大手)のそれどころの騒ぎではない酷い話を、私は一冊の本(数冊でも良いかな)が書けるくらい記憶しているのですが、書くと情報源がバレて恩義ある人たちに迷惑が及ぶおそれがあります。情報源が私怨や興奮のために針小棒大なことを言った可能性も完全には否定できず、その裏取りは不可能。情報源がマスメディア(大衆伝達媒体、つまり理論的にはすでに情報公開済み)である場合も数多くありますが、それらは他資料による確認(ダブル以上のチェック)が困難な活字媒体(明らかなガセネタの掲載もある)だったり、まずアーカイブ化されていないテレビ・ラジオ番組(出演者がちょろっと洩らした話)だったりします。そういうわけで、どちらにしろここには書きません。
自社批判があったとしたら神経を尖らせるのは、まあ自然な感情と言えます。けれどもそれどころか、自社の内情や歴史について知られることにすら、明らかに不必要なくらい、極端に神経過敏です。
私は二十年ほど前、自分の原稿の正確さとクオリティーを上げるために、少女小説(とか漫画など)の出版・編集の歴史を取材したくて(国会図書館で調べても分からない謎が山ほどあるのです)、大手出版社で私に原稿発注した担当者に(調べたい作品群の企画を昔担当していた)社のOBの連絡先を照会しました。
ですがなぜか露骨に嫌がられて、それでおしまいでした。まったく同じ経験を複数社でしており、その程度の「器」と感じさせられたこと、一度や二度ではありません。
犯罪者でも何でもない私人のプライバシーには平気で踏み込むのに、自社にかかわることは、とにかくアンタッチャブル・ゾーン(不可触領域)としておくのが習わしとなっていたようです。
あたり前のことですが、取材希望時にそれらの出版社を批判したりあら探ししたりする意図など、私には微塵もありませんでした。反対に、取材が叶ったらさり気なくヨイショのパウダーを原稿にまぶしたことでしょう。
たぶん、いずれも今となってはタイムリミットを過ぎて取材不可能になっている案件です。
実在の「世界一のレディー」が手塚漫画に登場

私は1998年に、編著書(構成・文)の『手塚治虫キャラクター図鑑』(手塚プロダクション監修/全6巻)を朝日新聞社から出版しました。
これは講談社版手塚治虫漫画全集を底本として、手塚漫画のキャラクターをまとめ、併せて作品解説などを載せたものです。ほぼ全ページに手塚先生が描いた絵を掲載しており、ビジュアルがメインの構成となっています。

以下はその制作中の話です。
『ザ・クレーター オクチンの大いなる怪盗』という短編(もちろん手塚漫画です)には、実在人物のジャクリーヌ・オナシスが実名のまま登場します。
ジャクリーヌ・オナシスといっても、今はご存じない方が多いでしょう。しかし『キャラクター図鑑』の刊行当時は、大人ならばたいていの人が知っていたと思います。その30年前ならば、その知名度は100%。イギリスのエリザベス女王を除けば、世界で最も有名な女性だったと言っても過言ではありません。
彼女はかのジョン・F・ケネディ大統領の夫人だった人です。アメリカ大統領夫人で史上名高い人にはエレノア・ルーズベルトとヒラリー・クリントンがいますが、ファーストレディー時代のジャクリーヌの存在感はこの二人をはるかに凌ぐものでした。
「ジャッキー」の愛称で親しまれ、その美貌※でアメリカのみならず世界じゅうから熱狂的といえる人気を集めていました。世の女性たちは競って彼女の装いを真似、「ジャクリーヌ・ファッション」がブームを呼びさえしたのです。空前絶後と呼べるほどのスター性と華があったのですね。
1963年11月のケネディ暗殺事件は、頭蓋骨の一部と命を失った大統領とじくらいに、熱愛する夫を失ったジャッキーへの同情を集めました。
ところが5年後の1968年に、彼女への評価が一気に逆転します。世界じゅうの評価が、です。
※当時は世界じゅうの人がジャクリーヌのことを「美人」と思っていたのですが、私は美人ではなくファニー・フェイス(ちょっと変だけど魅力のある顔)だと思っています。

当時アメリカで発表したら莫大な賠償問題が?
23歳年上のギリシアの大富豪オナシスと結婚したからです。オナシスは「二十世紀最大の海運王」と呼ばれた人で、小学生だった私の記憶によると、おそらく正確なデータによるものではないでしょうが「世界一の大富豪」とも報じられていました。ちなみにフルネームはアリストテレス・ソクラテス・オナシス。
これだけでジャッキー・ファンは大幻滅してしまいました。世界一素敵なレディーから財産に目が眩んだサイテー女へ。大衆人気の急降下ジェットコースター現象です。
その後も続々プライバシーに属する悪評が報じられ、女性に対する最悪の形容(ここには書けません)すら活字になりました。
で、われらが手塚治虫先生がジャクリーヌをどう描いたかといえば、これがハッキリ言ってめちゃくちゃです。
現実味ゼロの奇想天外なSFの中に勝手に描いた上、「世界でいちばん幸福な運命にめぐまれているやつ」とか言っておいて(このフレーズ自体すでに悪意がこもっているのですが)、その未来は「病気」「失望」「離婚」「孤独」といった運命しかない、と決めつけていました。
ちなみにジャクリーヌとオナシスは離婚していません。
病気についていえば、ジャクリーヌは実際にリンパ腫による長い闘病生活ののちに亡くなっています。
しかしながら、そもそも医学博士(手塚先生は医師免許と医学博士号をおもちでした)が、まだ彼女が健康美にあふれていた当時に、コイツは嫌な女だから病気で苦しむ運命が決まっている、なんて書いちゃダメでしょ。
『ザ・クレーター』シリーズの諸作はみなそうなのですが、この短編も作品として評価すれば間違いなくおもしろい。奇抜なアイデアが秀逸です。
しかし、存命中の実在人物に対し、このように極端な悪意をむき出しにした描き方は…うーん。
スキャンダリズムが作り上げたイメージを無批判で鵜呑みにしたとしか言いようがありません。
私は天才・手塚治虫先生の子どもっぽさが悪い形で出たものと思っています(もちろん良い形で出た作品のほうが圧倒的に多いのですが)。
私は言いたい。ジャクリーヌの心弱さを責めるのなら、亭主だったケネディの女癖の悪さは一体何だったんだよ、と。
学識豊か、文才抜群だった私の担当編集者
私はこの作品と登場キャラクターのことを書くために、担当編集者を通じて朝日新聞社の資料室(この部署名の記憶は不正確な可能性がありますが、以下そう記述します)に問い合わせてみました。参考文献となる書籍『ジャッキーという名の女』の在庫はありませんか、と。
その本を手に取ったことはないのですが、タイトルは以前に新聞広告で見たおぼえが確かにあったのです。
ほどなくして担当編集者が私に伝えた返答は「資料室は『そんな本はありません』と言っていた」というものでした。
これは、明らかに「朝日新聞社の資料室にそんな本はありません」ということではなく、「そんな本は出版されていません」という意味の言葉です(この点につきましては間違いありません)。
私は(資料室の人、怒ってるんだなー)と感じました。そういうニュアンスって口伝(くちづて)でも伝わるものです。
私の限られた経験によるものですが、当時の朝日新聞社内の各部署は、他部署からの問い合わせに明らかに冷淡なように感じていました。
その以前に、別の手塚漫画に関連する史実を知りたくて、運動部の詳しい人(相撲担当)に問い合わせようとしたことがあります(事情は省きますが私はその人の名前を知っていました)。
返答は三十秒または一~三行で済むことです。
すると私の担当編集者から「外部から問い合わせた形にしたほうが親切に対応しますよ」とのアドバイスをいただきました。つまり内部からの問い合わせには不親切に対応する、ということですね。
この担当さんはとても人柄が良く、サブカルチャー全般については私なんかよりよっぽど詳しい方でした。ただ、退職されていますから書いても良いと思うのですが、社内では完全に浮いている人でした。そういう人でなかったら、朝日新聞社は私の担当なんかに着けません。
この方は社外の媒体に時折随想などを寄稿していらしたのですが、そうした文の一節に、ご自分のことを「左遷の経験がある」と明記しておられました。
著書も複数冊おありで、私の担当に着かれていたときにも一冊上梓されました。
当時の朝日新聞社内には、目立つところに大きなガラスケース(ショーウィンドウみたいなもの)があり、社員が本を出版すると「朝日人が書いた本」として、そこに陳列していました。朝日新聞社員は自分たちのことを「朝日人」とも称していたのです。ケースには常に十冊ほどが並べられていたように思います。展示期間については知りませんけど。
しかし、私の担当さんの新刊は一秒たりともそこに置かれませんでした。
その本の存在自体を朝日新聞社は黙殺したのです。とてもおもしろい本だったのに。
ちなみにタイトルを記しますと『悲しきネクタイ 企業環境における会社員の生態学的および動物行動学的研究』(地人書館)でした。
その中に忘れられない「作品」が収録されていました。もちろん担当さんがお書きになったものです。
その本が手許にないので不正確な可能性がありますが、私が記憶しているままを書きます。文部省唱歌『朧月夜(おぼろづきよ)』と似通った語感がありますが、内容的にはまったく関係ありません。
脳の中ばらけて 意識薄れ
ぼけだす 視野脳波
かすみ 暗し
(原本からちゃんと引用できていたら、もちろん太字にしていました)
これが(私が記憶する)全文です。続きはありません。
どうですか、この身体が震え出すような表現力。
これが、散文では表現不可能なリリック(抒情詩)の力です。この三行には、私が十万字書いても敵いっこない。
ずっとのちに知ったことですが、この才人編集者は東京大学OBです。
私は当時の担当さんのことを思い出すにつけ、こんな感慨にひたります。
「この人が朝日新聞社社長になっていたら、日本の国もどれだけ良くなったことだろう」と。
そ、そういうことだったのか⁉(真偽不明)
話を戻しますが、担当さんの親切で思慮深いアドバイスにしたがって、私は相撲担当記者への質問状を、しこしこと私物のワープロ専用機で作成しました。
礼を尽くし(「ご繁忙のさなかに誠に恐縮ではございますが」とか)、ご機嫌を取る(「日本相撲協会に照会して不明だったのですが、相撲に関する凡ゆる事績に曉通していらっしゃる〇〇様ならばご存じのことと拝察申し上げ」とか)ことにそれはもう神経を使ったものです。出来上がるともちろん担当さんに託して運動部に届けていただきました。
結果は完全なシカトでした。相撲担当だけに肩透かし。
そうした経験がありましたから、私の照会が資料室の人の気分を害したとしても不思議とは思いませんでした。私がお世話になっていた出版企画室とか、シカトこかれた運動部とは異なり、資料室は製造作業を行なっていないバックアップ部門ですから、「照会に答える」ことが仕事なはずですが、公立図書館の窓口だって常に来館者に親切とは限りません。
一度だけお断りしておきますが、資料室の人がそんなふうに感情的に反応したというのは、もちろん私の得た感触ですよ。ですから、事実かどうかは断言できません。裏取っていませんから。
私はその本のタイトルにつきましてはかなり鮮明な記憶があったので、
(ないわけはないんだけど、単純な見落しミスかな。ボクは国会図書館まで行かなきゃならないのかな、ヤだなあ)
なんて考えてしまいました。
国会図書館は貸し出ししていないので、開館時間内に読み終わらなければなりませんしね。
とか思いつつ、とりあえずブルー(憂鬱)なダメ元気分で私が住む杉並区の区立図書館で調べてみました。
すると、あらま。
拍子抜けがするくらい、あっさりと見つかりました。
クレメンス・デビッド・ハイマン著、広瀬順弘訳、上下巻。
そして。
版元は読売新聞社でした。
私は怒ることもできずにヘナヘナと脱力して。
「だから『そんな本はありません』なんて言ったのか…しょーもねー」
と、嘆息とともに呟いたのであります。
なぜ私ごときが『朝日』について語れるのか
私の呟きが真実(ほんとう)だったとしたら、「幼稚園児の意地の張り合い」みたいな話です。大新聞社社員だったら、というよりも名の通った会社の社員だったら、というよりもいい歳こいた大人だったら、そんなコトするわけねえだろ…と思われる方は多いと思います。それは常識的な感想です。
しかし、もはや真偽のほどは確認するすべのないことなのですが、私が反射的にそのように思ってしまったのは、当時の(今のことは知りませんよ)朝日新聞社のカルチャーと言いますか体質と言いますか朝日人のメンタリティーと言いますか…に、「そういうコトもあるかもなあ」と思わせるものを肌で感じていたからなのであります。
これを読まれて、一般の方よりもむしろライターとか作家とか印刷所とかの出版関係の方のほうが、こんなふうに思われることでしょう。
「嘘つけ、たかが原稿書いて納品しているだけの業者に、そんなトコロまで皮膚感覚で分かるはずなど、あるものか」と。
それは一般論としてはまったく正しい。
しかし当時の私は全然一般的ではない経験を経ていました。
たぶん朝日社員でもそんな経験はせずにキャリアを終える方のほうが圧倒的に多いと思います。
『手塚治虫キャラクター図鑑』の企画スタート当初の数箇月(5カ月弱くらいかな)、私は朝日新聞東京本社に寝泊まりし、三食「アサヒのメシを食って」暮らしていたのです。
つづく
【予告】
私はまだ、中央法規さんの本当の凄さ、素晴らしさをまったく書いていません。それが明らかになるのは次回以降です。
次は、私が身近に見た花田紀凱さん(当時『uno!』編集長、元『週刊文春』編集長、現『月刊Hanada』編集長)や清水建宇さん(当時朝日社内で私がいた隣の部署の管理職、のちに朝日新聞論説委員、『ニュースステーション』〔テレビ朝日〕コメンテーター)の、知られざる意外なエピソードも本邦初公開。
お楽しみはこれからだ(和田誠&アル・ジョルスン)。

(1950年代にアメリカで活躍されたプロレスラーのPenny Bannerさん)
#出版社
#器の大きさ
#朝日新聞社
#中央法規
#精神保健福祉法
#noteクリエイター
#スキ
#中央法規オンラインショップ担当
#出版界
#狭量さ
#ムラ社会
#手塚治虫
#ザ・クレーター
#ジャクリーン・オナシス
#ケネディ暗殺
#アメリカ大統領
#ファーストレディー
#医学博士
#女癖
#左遷
#朝日人
#文部省唱歌
#朧月夜
#抒情詩
#東京大学
#読売新聞社
#皮膚感覚
#文藝春秋
#花田紀凱
#月刊Hanada
#清水建宇
#ニュースステーション
#和田誠
#お楽しみはこれからだ
#アル・ジョルスン
#女子プロレス
#厚生労働省
#国立精神・神経医療研究センター病院
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
