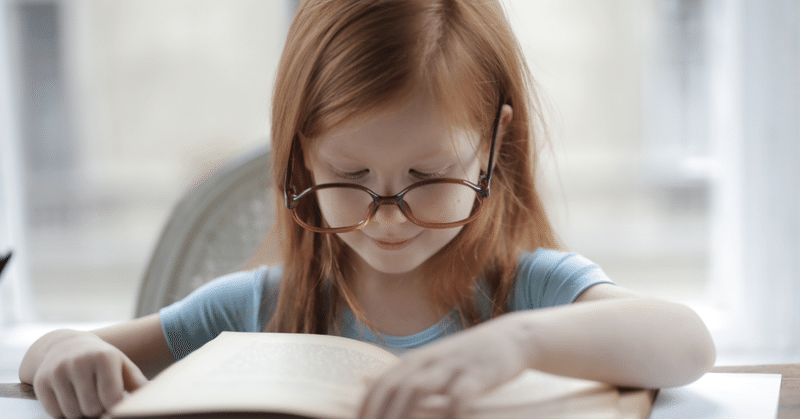
「どうしたいのか?」と自分にも問う:【学びと気づき:最新の脳研究でわかった! 自律する子の育て方】
日曜朝のZoom勉強会、2冊目の書籍は「最新の脳研究でわかった! 自律する子の育て方」です。
実は、最近の私は仕事で「自分の部下(後継者)を育てる」という超重要な課題があります。
もう1年くらい棚上げしてしまっています。
今回の勉強会で取り扱われた2冊書籍の大きなテーマは「育てる」。
棚上げしている課題について、「そろそろ本気でやろうよ?」と言われているのかもしれません。
・勉強会アウトプットの内容
書籍のタイトルである「自律する子の育て方」の「自律」の意味を勉強会の後に調べてみました。
自律:他からの支配・制約などを受けずに、自分自身で立てた規範に従って行動すること。
カントの道徳哲学で、感性の自然的欲望などに拘束されず、自らの意志によって普遍的道徳法則を立て、これに従うこと。(goo辞書)
つまりは、自律は自分自身が判断、決定をするということですね。
勉強会の中では、自律する子を育てるためのキーワードとして「心理的安全性」と「メタ認知能力」の2つがあげられました。
「メタ認知能力」は自分を俯瞰してみること、客観視する能力のことを指して言います。
そして、子どもに自分を客観視させ、自己決定を促すための3つの言葉かけが紹介されました。
・「どうしたの?」(「なにか困ったことはあるの?」)
・「君はどうしたいの?」(これからどうしようと考えているの?)
・「何を支援してほしいの?」(「なにか支援できることはある?」)
私は子どもはいませんが、会社でのこと、日常生活の中での自分の意志決定の場面を思い出しながら、これは子どもだけでなく、自分自身に対して、大人にも大事な問いかけではないかと考えていました。
・「どうしたいの?」って聞かれると私も考えてしまう
発表を聞きながら、「どうしたいの?」と自分が聞かれたとき、どう答えるかを思い返していました。
私の場合ですが、「どうしたの?」は、時系列や出来事を整理して説明はできます。
でも、そこから「どうしたいの?」と言われたときに、答えで自分の意見や考えをすぐに出せるのか?と言われると正直怪しいです。
もちろん、すぐには答えが出せない難しい問題もありますが、本当は「どうしたい」が自分であるはずなのに、言えなかったことも今まで少なからずありました。
意思決定が自分にあることが不安になる、自分の決定に自信がなかったり、他人から責任を負わされるのではないかという恐れがあったりするとき、ついつい他人のせいにしたくなってしまうのです。
さらに、その後に「何を支援してほしいの?」と続くと、「どうしたいか」が答えられないと、次のステップへ自分の意志で進むことはできないですよね。
他人のせいにすることは楽です。でも、それが続くと、どんどん人生が自分のものではなくなってしまう感覚に陥ってしまうのではないでしょうか。
・マレーシアで言われた「You shouldn’t pamper」の意味
「どうしたの?」という言葉かけは、私も仕事で部下が困っている様子のときにすることがあります。
そして、以前は部下の状況を聞いてアドバイスをしたり、代わりに仕事を引き受けたりしていたのですが、それに対して1年程前に上司からのフィードバックを受けていたことを思い出しました。
「You shouldn’t pamper your team(チームを甘やかすな)」
当時の私自身は、まさに「どうしたいのか」「支援が必要なのか」を相手に聞く前に答えを教えたり、部下の代わりに仕事をしてしまっていたのです。
大人になってからも仕事での「自律」は必要です。
仕事の内容や状況によっても異なり、そこでの小さな自分での意思決定、成功体験を積むことで経験値となって個人個人が成長していくのは、チーム全体の成長のためにもとても大事なことではないでしょうか。
今回の勉強会での発表を聞きながら’、以前の私はみんなの「自律」や「成長」の機会を奪っていたのだなと密かに反省していたのでした。
・今日の学びのまとめ
「最新の脳研究でわかった! 自律する子の育て方」は、今までの教育の常識を覆す内容です。「手をかけるほど子供の自律を阻む」というのは、大人にも言えることですね。
自身の反省をしつつも、さて、これから私は「どうしたい」か?
勉強会の後に色々考えていましたが、今日の勉強会の内容はきっとご縁ですね。
次の上司との1on1では、次の3つをちゃんとやってみたいと思います。
・自分の中の「どうしたい」という意思を確認、言語化すること
・部下の立場から上司にきちんと課題として「伝えきる」こと
・助けが必要なことはちゃんと頼ること
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
