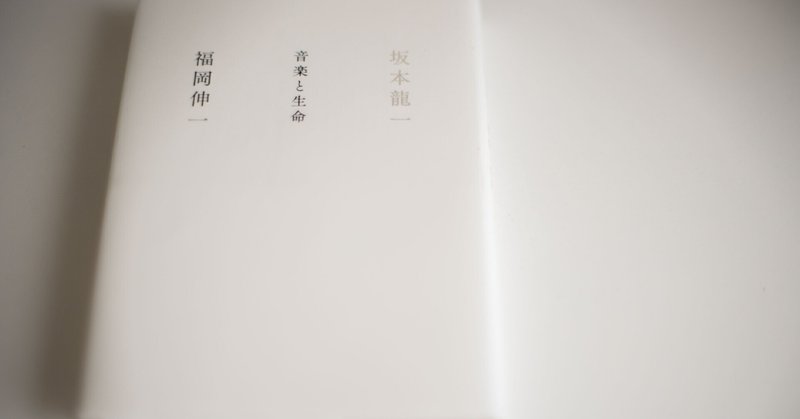
知ることで見えなくなるもの
「音楽と生命」の続きである。
わからないものを、わからないままに触れる。
この重要性を学びの最前線に置き定めることがいよいよ大切になってきたのではないか。
科学の世界では「わからないことは罪である」という感覚があるように思う。
研究の最先端ではそうでもないのかもしれないが、学びの場では殊更そのように捉えられていないだろうか。
知識偏重、採点主義といった学力評価の仕組みがそのような意識を増長させている側面もあるだろう。
決して科学の世界に限ったことではない。
文学や美術の世界でも、表現をどのように理解”すべきか”というある種の正解が提示され、それが理解できなければ劣等というレッテルを貼られてしまうのが、残念ながら学びの現状だ。
無知の中で触れあう感覚、そこから惹起される内なる自然との共鳴に意識を向けていく。
それこそが、これからの時代に我々が学ぶべき価値の本質になっていくのではないか。
漠然とではあるが、これまでの分析科学的アプローチ…明示的な根拠に支えられた意思決定の方法論に虚構感を覚えている。
もともと芸術表現とは、表現者の意図を正確に伝えることに意義があるのではなく、表現者が受けたインスピレーションとパッションを何らかの具象として表現したときに、コミュニケーションとして受け手に特異な感情を惹き起こすことにその本質がある。
その点において、表現者が何を意図したのかはあまり需要ではなく、受け手が何をどう感じたかに主題が置かれるべきなのだ。
それをアカデミズムという名の権威でいたずらに囲い込み、あるいはメジャープロデュースという権力で市場を牛耳りながら、あたかも表現者の側に価値があるかのように見せかけているのが現代商業芸術の現実だろう。
現代人は、わからないものに無知のまま触れることを無意識的に恐れているのではないだろうか。
WEBを手繰ればあらゆる情報が手に入る時代である。
ランチに出かけるにしても事前にお店の情報を調べ、旅行に行くにしても下調べを入念にして綿密な計画を立てる。
決してそれが悪いとは思わないが、どこか必要以上に失敗を避けようとする心理が働いてはいないか、あるいは損や後悔を避けたいという自己防衛意識が働いてはいないだろうか。
美術館で作品を鑑賞する態度にも似たようなところがある。
ボクはあまり先入観なく作品を眺めるのが好きだが、多くの人々はその作品にどのような意味があるのかを「知り」たがる。
「感じる」より「知る」ことを求めてしまうのは、とても勿体無いことだと個人的に思っている。
もちろん「感じる」背景にも情報は常につきまとう。
ピカソのゲルニカに触れれば作品が描かれた時代背景を思わずにはいられないし、その重苦しいメッセージはボク自身が持つ知識から派生していることを疑うことができない。
だからこそ、そうした事実背景を知らない人たちがこの作品に触れ合った時の感覚を貴重に思うし、それこそ作者が伝えたいと思ったメッセージが自然の理の中で真っ直ぐに届くのかを確かめる唯一の手段だとも思っている。
ピュシス(physis:自然)とロゴス(logos:理性)。
本来そこに在る全体を、人はまるっと認識することができない。
ロゴスは言語化し得る情報である。
一方のピュシスには、言語化し得ない膨大な情報が存在する。
そのギャップを常に意識することが大切なのだろう。
卑近な例で申し訳ないが、「食レポ」とてもわかりやすいと思う。
美味しさの表現にどれほど言葉を費やしても、その美味しさは実際に食べてみなければ知ることができない。
食べてみてどう感じるかにこそ、本当の価値が存在する。
悔しいけれど、その感覚のすべてを言葉にする術を人類は持ち得ていない。
その事実を謙虚に受け止め、言語化し得ない感覚のすべてをもっと尊重すべきなのだ。
誰かが「美味しい」とレポートしたものを食べにいく。
それはそれでいい。
ただ、実際に食した時に、誰かが言葉にした美味しさだけを確かめ、それで満足してしまってはいないだろうか。
真に豊かな体験とは、言葉にならない知覚やそこから惹起される感情に意識を凝らし、自身なりの気づきや発見を得ることだろう。
知ることで見えなくなるもの。
知っている情報を確かめて満足してしまえば、本来そこに在る豊かさや複雑さを見失ってしまう。
知識あるが故の盲目である。
知ることで「全てを理解したつもり」になってはいないか。
知り得た情報の奥に、まだまだ知らないものごとが幾らでも存在している。
それらを「知らない」と認めることに対する罪悪感もあるだろう。
あるいは言語化できないことに劣等感を覚えることもあるかもしれない。
裏返してみれば、知り得たことの言語化には優越感が伴う。
無知への劣等感と対になって他者へのマウントを招きやすい。
無知に対する罪悪感や劣等感は、社会生活の中で無意識的に身につけてきてしまったものだった。
しかし、世の中には「無知であるが故の豊かさ」というものが存在する。
なんでもわかっているような気分になれてしまう時代だからこそ、知らないことの自覚に大きな意義が生まれてきていると思う。
ソクラテスは知らないことの存在を知覚することが真の知であると述べた。いわゆる「無知の知」である。
ただ、ソクラテスの前提は、それらはいずれ「知り得る」性質のものであるという認識にあった。
今という時代に知るべきは、世の中には永遠に知り得ないもので溢れているという感覚なのかもしれない。
故に「知っている」という感覚に対する危惧を、より強く意識すべきと直感している。
「知らないこと」に、もっとワクワクできないものだろうか。
そこから始まる体験には、言語化不能な豊かさがたくさん詰まっていると思うのだ。
