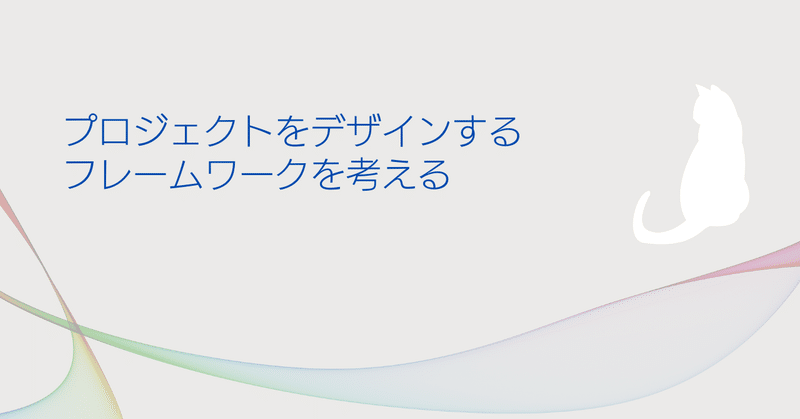
プロジェクトをデザインするフレームワークを考える
プロジェクトをデザインの力で”楽しくて面白くて”、”推進力が上がって”、”成功確率も上がる”。
そんなプロジェクトデザイナーの方法論の体系化を進めています。
プロジェクトの地図を描く
最初は白地図から始まります。何処にいくのか?いま何処にいるのか?道はあるのか?難所はどこか?地図の縮尺はどのくらいか?
プロジェクトの地図の解像度を上げていく。最初は解像度が粗く曖昧な部分が多い、この視点を受け入れることが大事です。
プロジェクトの地図を描く行為そのものが、プロジェクトの全体像を視覚化し、計画段階から実行、モニタリングに至るまでの全プロセスをナビゲートするための道具になります。地図には、プロジェクトの目標、重要なマイルストーン、リスクゾーン、リソース配置なども含みます。
2つのデザイン
プロジェクトの地図に描くために、デザインの力を用います。ここでのデザインは「設計」と「意匠」です。
設計: 計画と構造、プロジェクトの骨格を形成する要素であり、目標達成のための道筋、プロジェクトの範囲、タイムライン、リソース配分などが含まれます。
意匠:美的要素とスタイル、 プロジェクトの視覚的、文化的側面を強化し、プロジェクトのアイデンティティを形成します。ここには、デザインの要素、コピー、ユーザーエクスペリエンスなどが含まれます。
デザインの力
やりたいこと、面白いこと、様々な課題、プロジェクトに関わる多種多様な構成要素を、目に見える形で可視化する。可視化のメタファーは「プロジェクトの地図」。
具体と抽象を行き来するのではなく、具体と抽象のグラデーションを可視化する。なぜなら人によって具体と抽象のレベルが異なるから。
冒険の準備
プロジェクトの地図を描いただけでは冒険には出られない。手元には何があるのか?(手中の鳥の原則)プロジェクトの冒険に出ることができるのか?絶対に必要な物を忘れていないか?
地図の更新は続ける
プロジェクトが始まれば、様々な事が分かってきます。あると思っていた道がない。3日で行ける距離と思ったら、1ヶ月くらい必要な距離だった。目標となる場所がそもそもなかった。など様々な情報を地図に加えていきます。地図の解像度を上げていきます。
プロジェクトを進めることで地図を詳細化していくというプロセスが大事です。
キャンプ
定期的に休みましょう。そしてプロジェクトの地図を見ながら冒険の振り返りをしましょう。
地図の情報も見直して、今何処にいるのかを確認します。明日は何処までいくのか?その道や方向も確認しましょう。
アレとソレを組合せてみたらコノ課題を解決できるソリューションができるよね?と言うパズルをやるような思考回路です。サポートして頂いた費用は、プロジェクト関連の書籍購入やセミナー参加の資金にします。
