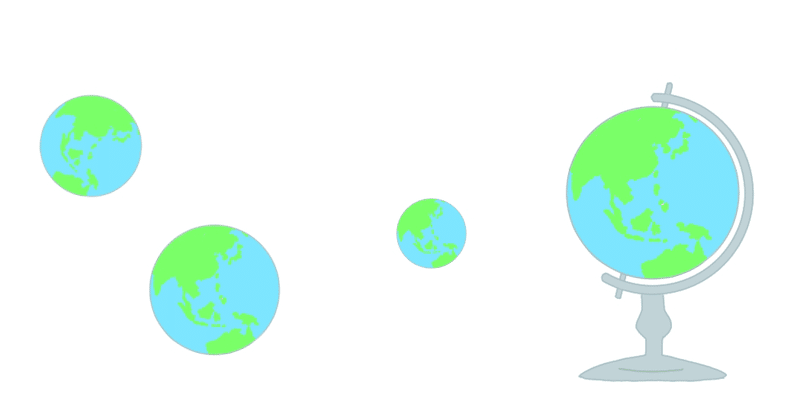
【小説】詐欺師の娘たち-終
私は部屋で地球儀を回す。初めて位置関係というものを知る。国と国の間の、あるいは地球上にいる誰かと、いまの自分の間の。
ここがロシア、こっちがウクライナ。ウクライナはロシアより遠い。首都のキエフはここ。ルーマニアはこっちで、首都はブカレスト。島国の日本と違って、国境線が接している。中国はロシアの南。ここにも国境線がある。父の持っている本にはこう書いてあった。「ウクライナはかつてソビエト連邦に属していました(1922~1991年)。とはいえ望んだ併合ではなく、またソビエト側は何度か大飢饉によるウクライナ人の虐殺を試み、これを『ホロドモール』と呼びます」。バレエ団の話はどこにもなかった。あのときビデオの中にいた華やかなダンサーたちの名前を、私は少しも思い出せない。パリ・オペラ座だったら少しはわかる。あのときのスターはニコラ・ル・リッシュ。オペラ座の最高位である「エトワール」の称号を手にして間もなかった。エトワール、フランス語で「星」。
バレエ団にはそれぞれ階級があって、オペラ座の場合は下から「カドリーユ」「コリフェ」「スジェ」。スジェまで来ると、一人で──ソロで踊る役が任されるようになる。その上が「プルミエ・ダンスール」、主役級の役はこの人たちが踊る。そうして、昇進試験もなく、いつ誰がなるかもわからない特別な地位があり、それこそがエトワール。
あの古いアパートで私に饒舌にそれを教えた人は、もうどこにもいない。
教えられたことがぜんぶ嘘だとしても驚かない。仮にオペラ座の序列の名前が「ソシュール」「ココア」「ベントウ」でも、そもそもパリにバレエ団なんてなくても、私は最初の父を責めたりしない。彼の出身が、本当はどこなのかもわからない。東ヨーロッパの情報は日本にいる限りほとんど入ってこないし、私は積極的に知ろうともしなかった。そこではやっぱり、踊り殺したり、あるいは死んだりするんだろうか。緑の目が当たり前なのだろうか。父の瞳の周縁は何色だったろう。
母は私を覗き込んで、ちょっと茶色っぽいのねと言った。髪も真っ黒ってわけじゃないし、やっぱりこっちの色のほうがいいわよ。
なんの話かと想ったら、母は私に似合う洋服を探していた。青みがかった色が似合う人と、温かい色が合う人がいるらしく、母は前者、私は後者なのだと結論づける。残念、娘なら同じ服を着まわしできたりするのかと思ってたけど、まあいいわ。あんたあたしと違って優しい感じがするから、そうね、やっぱりこっちね。
そうして私は、柔らかい素材の、首元にフリルが付いたブラウスを買ってもらう。母が着ている直線的なジャケットとは大違いだ。私の体は薄く、母は厚い。いざとなったら誰にも頼らず生きていけるのは、やっぱり母のほうだろうと私は思う。女にたかった詐欺師の、その商売道具として人生をスタートさせた娘とはワケが違う。母にはなれない。それでもいい。
部屋には地球儀の他に本棚が入り、本棚が増え、辞書が何冊かそこに入った。エトワールの綴りはétoile、そして彼の言ったことに間違いはなかった。やがて両親は離婚を決め、父が親権を取る。理由は性格の不一致。父は言う。
離婚はするけど、お母さんはお前のお母さんだ。
母は何も言わなかったけれど、体格のいい男性と並んで歩いているのを一度見た。母は一人の女性として男性の腕に寄り掛かり、少女のように無邪気に笑っていた。離婚手続きは穏便に済み、私はいつもと同じように、時々父と出かけ、時々母と出かける。父の友人は家に遊びに来るようになり、そういう日には私は家を空け、遅くなってから帰宅した。
最近になって、また黒い重い夢を見る。それは本当にあの女性たちだけのものだったんだろうか。人の暗闇にはいつも手が届かない。目の中に淋しい光のない人は、ただ単に他人を欺いているだけなんじゃないかと思う。私は強い、私は孤独なんかじゃない。そんなの嘘だ。華やかな世界にいようと温かい家庭に恵まれようと、人はいつも一人。私は夢の中でいつもどこまでも深く黒い沼を沈んでいくけど、その泥沼の中にあなたもきっといる。互いに見えないだけで。
そうだ、「パパ」を見つけたら伝えなきゃいけないことがある。私は貴婦人にはなれなかった。それから箸が正しく使えるようになった。料理ができるようになった。欲しいものを欲しいと言えるようになったし、自分で買えるようにもなった。それは全部、正式な戸籍上の両親が教えてくれたことだ。私と彼の関係を示すものは、紙一枚残っていない。それでも。
私はその人の娘だった、と自分で決める。母が私を娘と決めたのと同じように。事実じゃないけど嘘じゃない、その曖昧な間。
(終)
前回までの記事はこちら
本を買ったり、勉強したりするのに使っています。最近、買ったのはフーコー『言葉と物』(仏語版)。
