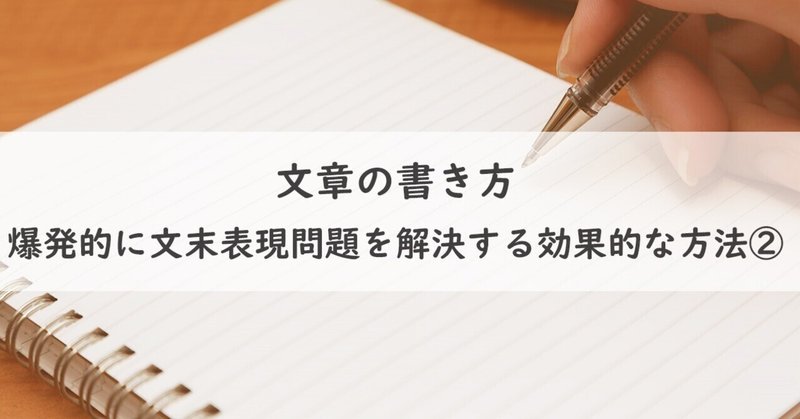
文章の書き方/爆発的に文末表現問題を解決する効果的な方法(2) 翻訳書を読む
「文章の書き方/爆発的に文末表現問題を解決する効果的な方法(1) 外国語の習得」の続きです。
<前回の概要>
日本語は、文末が単調になりがちな言語ですよね。
同じ文末の連続になってしまったり、同じ文末言葉を多用してしまったりします。
日本語の文末表現については、これまで多くの書籍で触れられてきました。
文末に注意しよう
①「~でした」「~でした」「~でした」と同じ文末が連続しないようにする。
②「思います」を使いすぎないようにする。
文末が単調だと読者を退屈にさせてしまい、読む気をなくさせてしまう傾向にあります。
そこで、文末表現問題を爆発的に解決する方法として、前回「外国語の習得」を紹介しました。
爆発的とは、簡単ではないけれど効果的という意味で使っています。
今回は、後半編「翻訳書を読む」を紹介しましょう。
■ この記事を書いている人
Webコンサルタントで、大学の非常勤講師。
大学ではWebライティングの講義を受け持っています。
翻訳書を読むメリット

「文末表現に配慮した文章」を書けるようになるための方法として「日本語に訳された翻訳書を読む」を述べましょう。
前回「外国語の習得」を挙げましたが、外国語ができる人は、日本語の文末表現問題に注意を払う傾向にあります。
ただ、外国語ができる人がすべて翻訳ができるわけではありません。
直訳はできますが、意訳できるとは限らないのです。
読みやすく適切で表現力の高い翻訳ができる人はさらに少なくなります。
日本人に読みやすいように配慮された意訳されている書籍、特に、名作の翻訳書を読むことをおすすめします。
おすすめの本1選
語尾が変化に富み、リズミカルな名訳書を1冊紹介しましょう!
私がおすすめする翻訳書は、サマセット・モームの『月と六ペンス』金原瑞人さん訳(新潮文庫)です。
<書籍そのものについて>
100年も前に書かれたものなのに、いまでも売れ続けている大ベストセラー。
2017年には全世界Amazon文庫本部門ランキング第7位にランクインしました。
何部門だったか、この年なのか記憶がはっきりしませんが、いま世界中で売れていることは事実です。
衰えることのない名作と言えるでしょう。
MEMO
何か挑戦したいことがある人、自分らしく生きられるようになりたい人にとっては背中を押してくれる一冊になるに違いありません。
なぜおすすめなのか?
簡潔で、日本人に分かりやすい

文末表現に注目して読んだのですが、簡潔で分かりやすく、読みやすく、軽やかに読むことができました。
先へ先へとスムーズに読むことができますので、おすすめです。
文末に変化があり、メリハリがあります。
【ポイント】
・簡潔、シンプル
・日本人に分かりやすい伝え方
■ 探した方法
海外の名作の翻訳書を、書店と図書館で探しました。
片っ端から1ページ目を読んでいき、最終的に1冊に決めました。
※このため、読み比べているわけではありません。
※ほかの翻訳者さんを否定しているわけではありません。
私が感じたポイントについては、ご本人もあるコラムで述べられていました。
翻訳者さんの名前で検索してみつけたコラムです。
「翻訳をする際、どちらでもいいこと、というのがある。」と始まるコラムから2つの具体例を紹介します。
少し長いですが、そのまま紹介させてください。
① 「トムは言った」とか「ジェインは言った」とか原文には書いてあるんだけど、 それをそのまま日本語に訳すと、うざったいことが多い(英語の場合、男言葉、女言葉の差があまりないし、 終助詞なんてものはもともとないから、どうしてもそうなる)。
そういう場合「トムは言った」とか「ジェインは言った」とかは削っちゃっていいのか。
② マイルやガロンやポンドはそのまま訳したほうがいいのか、それとも、 キロメートルやリットルやキログラムに直したほうがいいのか。
(中略)
たとえば、①の場合、青山南さんは昔は削っていたけど、そのうち削らないことにしたとエッセイに 書いている。ときどき読者から、「トムは言った」という訳が抜けていますという投書がくるように なったからというのがその理由。ちなみに、金原はその手の言葉は徹底的に削る。削れるだけ削る。 そのほうが日本人には読みやすいし、そのぶんインクも紙も節約できるからだ。
(中略)
たとえば、②の場合、金原はキロメートル、リットル、キログラムに直す。 基本的に読者を信用してないからだ。たとえば、学生に英文和訳をさせていて、 「あ、きみ、時速50マイルって訳したけど、それって何キロくらい?」とたずねて、いままでちゃんと 答えられたのはせいぜい20人に1人か、それ以下だった。
「金原 瑞人 (翻訳家・法政大学教授)「気になること、気にならないこと」
(https://www.e-ecrit.com/column/relay-column/511/)
・「トムは言った」等の余分な言葉は削る、削れるだけ削る。
・物の単位は日本語の単位に置き換える。
シンプルに、日本人に分かりやすいように配慮して翻訳されているために、大変読みやすいのだと納得しました。
特に原作英語の書籍は良書が多い傾向にある
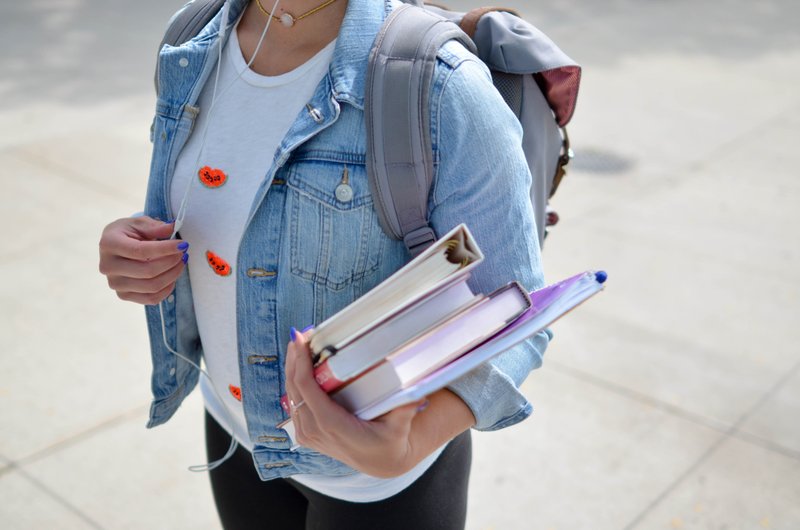
原作が英語の書籍が良い理由は、レベルの高い翻訳家さんが多い傾向にあるからです。
もちろん、ほかの言語でもレベルの高い人はいます。
私は学生時代 語学を専攻していましたが、最も卒業が難しい言語が英語でした。
知り合いの英語の先輩は大変優秀な方でしたが、なかなか卒業できず苦戦されていました。
何回も留年され、やっとのことで卒業されました。
英語だけなぜ非常に高い語学力を求められているかと言うと、先輩がおっしゃるには、「英語はほとんどの日本人ができるから」です。
「他の言語を専門とする人は、その言語と英語ができる。
英語専攻の人間は英語しかできない」
このため他の言語よりも非常に高いレベルを求められるのだそうです。
英日翻訳家さんは、豊かな表現力をお持ちの方が多いことに気づきます。
■ おすすめの本一覧(原作英語)
イギリス文学やアメリカ文学等、原作が英語の翻訳書だと高確率で読みやすい本に出合えるのではないでしょうか。
英語の名作をいくつか紹介しましょう。
サマセット・モーム(イギリス)
『月と六ペンス』『人間の絆』
エミリー・ブロンテ(イギリス)
『嵐が丘』
アガサ・クリスティ(イギリス)
『そして誰もいなくなった』
アーネスト・ヘミングウェイ(アメリカ)
『老人と海』
オスカー・ワイルド(アイルランド)
『ドリアン・グレイの肖像』『幸福な王子』
※サマセット・モームの『人間の絆』(金原瑞人さん訳)も『月と六ペンス』同様すばらしいのですが、(上)(下)と長編のため、『月と六ペンス』を読んでからがおすすめです。
同じ文末表現の連続って本当にだめなの?

ところで、同じ文末表現の連続って本当にだめなのでしょうか?
同じ文末が連続すると苦痛に感じやすいのはなぜでしょうか?
「ます」「ます」「ます」や、「でした」「でした」「でした」等、同じ文末表現が連続しないほうがよいとしている文章術本が多いことを前回述べました。
3回以上続かないほうがよいと指摘されています。
ちなみに、広島市立大学情報学部の調査では、連続回数5回の文章は単調であると判断できたものの、6回、7回ではなぜか不自然さを与えないと指摘されています。
「連続回数5回の文章は単調であると判断可能である。しかし、『天声人語』のデータから予想された6回、7回の水準には有意差が認められなかった。一定回数以上の繰り返しは読み手にリズム感を与える等、単調さを減少させる方向に働く可能性があるとも考えられる。」
「5回連続する文章を、単調な文末を持つ文章であると考えることとする。」
回答者が大学生100名と少なく、『天声人語』のデータであり、さらに20年以上前の調査。
これだけでは明言できるレベルではないですが、このような論文もあることをお伝えしておきます。
再度話を戻しますと、書籍やWeb上では「同じ文末表現」(「です」「ます」等)を「3回以上繰り返さない」ほうがよいことが一般的とされています。
ただ、10回以上連続しても秀逸な文章は存在します。
金原瑞人さんの『月と六ペンス』では10回以上「た」が続く部分がありましたが、気になりませんでした。
志賀直哉の『暗夜行路』も「た」が続きますが、気になりません。
私が自分に祖父のある事を知ったのは、私の母が産後の病気で死に、その後二月ほど経って、不意に祖父が私の前に現われて来た、その時であった。私の六歳の時であった。
或る夕方、私は一人、門の前で遊んでいると、見知らぬ老人が其処へ来て立った。眼の落ち窪んだ、猫背の何となく見すぼらしい老人だった。私は何という事なくそれに反感を持った。
芥川龍之介のある書籍は、最初から最後まですべて「た」で終わります。
それでもおかしくないどころか、名作です。
知り合いのライターさんの文章を読み返してみると、「た」が4回連続、11回連続している部分があることに気づきました。
以前気づかなかったということは違和感がなかったということです。
私の感覚ですと、たんたんとしていたほうがよい、感情を抑えたほうがよい場合は、同じ文末表現を続けたほうがよいかと。
最近の様々な文章術の本、過去には谷崎潤一郎、三島由紀夫、丸谷才一、井上ひさし、筒井康隆らが日本語の文末表現の連続は問題であると指摘してきました。
前回紹介した文末表現を徹底解説された『書くための文章読本』では、同じ文末の連続でも名文は存在すると説明しつつも、やはり変化させたほうがよいと説かれ、本自体はこれでもかと文末が変化に富んでいます。
こんな文末表現があるんだと大変勉強になりました。
もうひとつ、日頃著者の方はこんな喋り方しないんだろうなとも感じました。
これまでの研究結果により得られた膨大な文末の形を提示してくださっているのでしょう。
踊るような軽快さがあります。
一方で、様々な言い回しをされることにより、文章としては時々「ん?」となり、つっかえてしまう箇所がありました。
文末を変えすぎると文章が踊りすぎてしまい違和感が生じるようです。
もちろん、この違和感はあえて様々なタイプの文末言葉を総動員させてくださっていることに起因します。
世の中には、文末をすべて変えて読みやすい文章もあり、変えないで読みやすい文章もあります。
私は2週間前から、文末表現について538本の論文を調べたのですが、文末表現の連続について述べられた論文は10本もありませんでした。
どこで「同じ文末表現は3回以上繰り返さないほうがよい」と言われ始めたのか分かりませんでした。
私は、同じ文末表現を繰り返しすぎてはいけないとか、そういうことが問題ではないと感じています。
まとめ

日本語の文末表現の文章力を上げる方法として、「翻訳書を読む」を紹介しました。
名作で、原作が英語の翻訳書がおすすめです。
翻訳書を読むことにより、より豊かで適切な文末表現を知ることができるでしょう。
おすすめの書籍として『月と六ペンス』を挙げました。
ぜひ読んでみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
「スキ」「Twitterシェア」していただけると励みになります。
▼この記事を気に入ってくださったら「文章力を上げる意外な本1選」もぜひ見ていってください!
▼「『思う/思います』多用問題を徹底解決する3つの方法」もおすすめです!
2022年3月、私が3年間大学で講義したレジュメをもとに、10代から大人まで幅広く学べるようにまとめた書籍を刊行しました。
\おかげさまで読売新聞に掲載されました!/
【新著】『一生使える Webライティングの教室』(2022/3/23発売)
もし気に入っていただけたらサポートいただけると嬉しいです。クリエイターとしての活動費に使わせていただきます。
