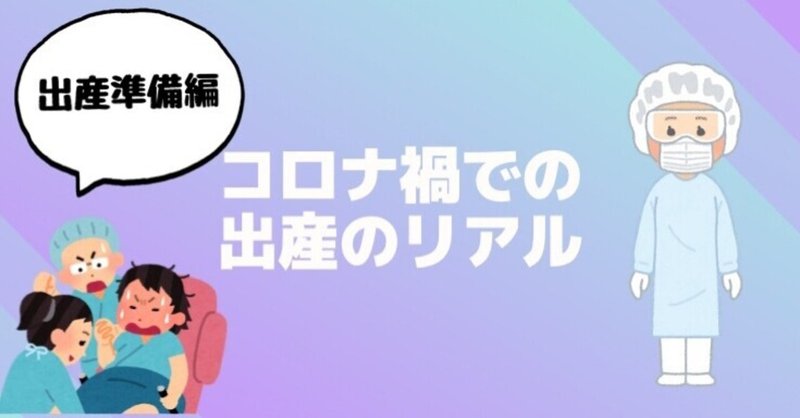
コロナ禍での出産*出産準備編
「出産までの妊娠中どう過ごしたらいい?」「出産に向けてどんな準備をしたらいい?」そういった疑問にお答えします。
コロナ禍で、「母親学級がなくなって、妊婦健診も時間が短くなったように思う。」という方もいるのではないでしょうか?施設によっても様々かと思いますが、出産に向けた準備として何をしたらいいかをお伝えできればと思います。
●施設からもらう冊子や資料などは1度のみでなく2-3回は熟読しよう
施設からもらう資料は、その施設がどういったお産をしているか、どういった産後のケアをしているかなどの情報がたくさん詰まっています。
どういった時に病院に連絡するか、どういった手続きが必要かなど記載されていると思いますので熟読しておきましょう。
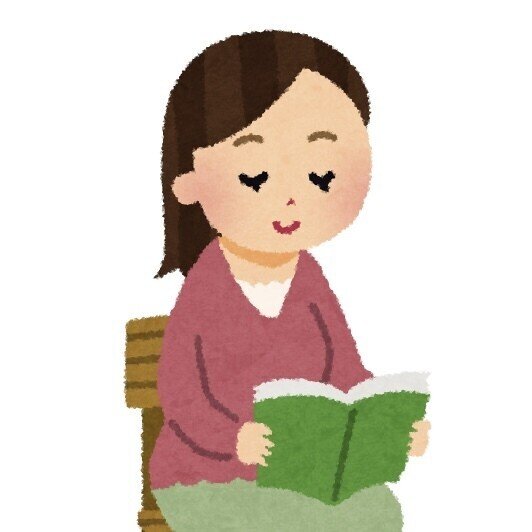
●育児書や育児雑誌などを見て妊娠中の変化や、お産の経過はどういうものなのかを知っておこう
妊娠中は様々な身体の変化があります。
どういったことに注意する必要があるか、どんなマイナートラブルがあるのか、対処法はあるのか、、知っている方が知らないよりも余裕が持てますよね。
自分の身体と向き合ういい機会でもあります。ご自身の身体を労りましょう。
また、お産はどういったことから始まるのか、お産はどういう風に進んでいくのか。
お産の時に行う可能性がある医療処置はどういったことがあるのか。帝王切開はどういった時にされるのか。
そういった内容が記載されている育児書などで予習しておくことが必要となります。
母子手帳も貰っただけになっていませんか?母子手帳の後ろ側には妊婦さん向けにたくさんの情報が載っていますので目を通しておきましょう!
母子手帳は外出先で何かあった場合に、情報を得ることのできるとても大事なツールとなります。最初から数ページはご自身の情報を書く欄があるので必ず書いておき、外出時は必ず持ち歩くようにしましょう!

●お腹が張るなど少しでも心配なことがあれば病院に電話をして確認しよう
妊婦健診はしょっちゅうある訳ではありません。週数により1ヶ月に1回、1ヶ月に2回、1ヶ月に4回など回数は変わっていきます。
ただ、
「ちょっとお腹が張るけど次の健診まであと3日だから様子をみよう。」
「胎動がいつもより少ないけど明日健診だから様子をみよう。」など、自己判断で過ごされる事は危険なこともあります。
切迫早産となる、赤ちゃんが元気じゃなくなる可能性もあるので、少しでも「あれ?おかしいな。どうしたらいいかな?」と不安になることがあれば夜中でも病院に電話をして相談をしましょう。
結果的に問題なかったとしても、万が一を見越して行動する方がとっても重要となってきます。
少しでも不安があれば、躊躇うことなくかかりつけの病院に電話相談をしましょう。
●「これってどうなんだろう?病院に電話するまでもないけど不安だな、自信ないな」と思うことがあれば
オンライン相談などを活用しよう
例えば、
「マイナートラブルで腰が痛い。骨盤ベルトってした方がいいの?どうやって使うの?」など、緊急性はないけど腰痛が辛い、不安があることについては
自治体や民間が行っている助産師オンライン相談などを活用してみましょう。無料で実施しているところもあれば有料でじっくりとお話を聞いてくれるところもあります。

●産後の育児に向けて必要な準備をしておこう
産後は赤ちゃんのお世話で手一杯となり、寝不足の日々が続くことが多いです。
妊娠中の時間のある時に、産後の育児をサポートしてくれる人を確保しておくことが大切です。
実母さんや義母さんが遠方で支援が望めない、里帰りの予定が里帰り出来なくなったなどコロナ禍ならではの産後のサポーター不足となる可能性も多いにあります。
「夫がテレワークだから家事をやってもらう」などお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、
"夫の産後うつ"があるということも言われている現代社会において、夫婦共倒れとならないように夫以外にもサポーターをお願いしておくのとしておかないのでは大きく違うと思います。
親や親戚の支援が望めない場合、自治体や民間の社会資源を利用するとよいです。
*ベビーシッター
*ファミリーサポート
*ホームヘルパー
*産後ドゥーラ
などの訪問型の支援や、
*ネットスーパー
*コープデリなどの宅配サービス
*ウーバーイーツ
など食事に関する支援、
*乾燥機付き洗濯機
*お掃除ロボット
*食洗機
など家事を効率化する家電の利用など
どういうところに手が必要なのか考えてみることが大事になってきます。
また、訪問型の支援などは事前に登録や、面談が必要なこともあるので余裕を持った準備が大切になってきます。自身の自治体にどういったサービスがあるのかをまず確認してみましょう。
●入院グッズや育児グッズを準備しておこう
「予定日まで日があるからまだ準備しなくても大丈夫〜」と思っていませんか?
健診に行ってそのまま入院、となることも中にはあります。出血や破水はいわゆる臨月となる正期産となる前に起こることもあります。30週〜遅くても35週までには入院グッズをまとめておきましょう。
施設によっては面会制限により荷物の受け渡しもNGとされているところもあるので、入院グッズを1人で持って移動できるよう、スーツケースに準備するなどして玄関に置いて頂くと良いかもしれません。
育児グッズに関しては、赤ちゃんと一緒に退院してその日からすぐに生活ができるようにイメージをして準備をしてもらうと良いですね。
赤ちゃんをどこに寝かせるかイメージしてお部屋のレイアウトを考えておきましょう。
ベビーベッドを使うのか、お布団なのか
ベッドは買うのか、レンタルか
など、赤ちゃんの寝る場所ひとつをとっても選択肢は沢山あります。
赤ちゃんはおしっこうんちの回数が多いですし、よく吐き戻しもすることもあります。
赤ちゃんのお着替えやガーゼハンカチなどはお洗濯の頻度にもよりますが、多めに準備しておくこともいいですね。オムツなど消耗品は何パックか事前に準備しておくことも良いですね。
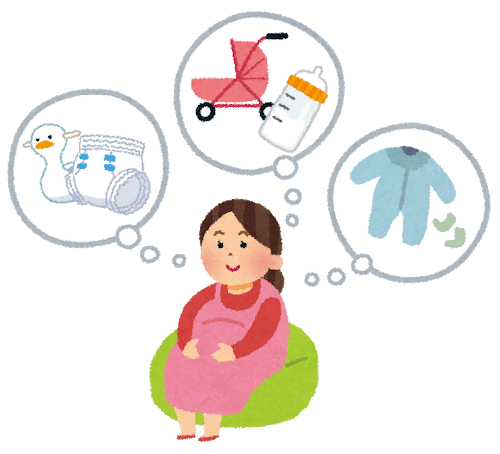
以上、出産に向けた準備についてお話させて頂きました。
お仕事をされている方もいらっしゃると思います。「産休に入ってから準備しよう〜」と思っていらっしゃる方、案外たくさん準備することがあると思うので、
産休に入ってから全部準備するのではなく、日々少しずつ準備して頂けると心に余裕が出来ると思います。
コロナ禍で
・母親学級がなくなった、
・里帰りできないから実母の支援が受けれない
という事があると思うので
*積極的に妊娠、出産、産後についての情報を得る
*産後の生活をイメージして、使える社会資源などは事前に登録しておく
というところがとても大事になってきます。
この記事を参考にして頂き、少しでもお役に立てると嬉しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
mimi*
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
