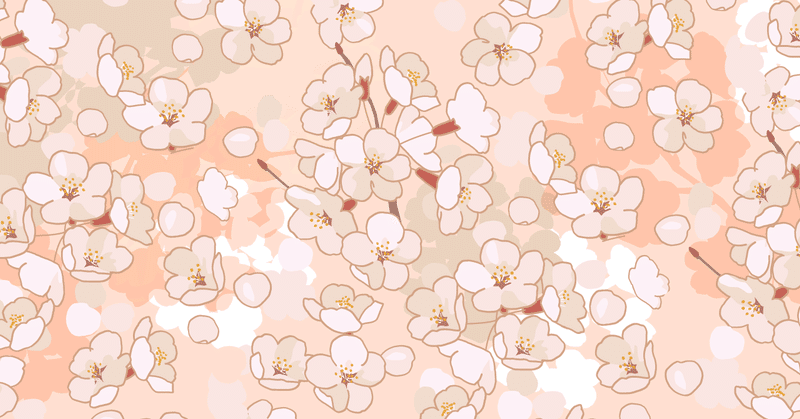
小説『蝶と花時雨(しぐれ)』
あの日も、桜の花が咲いていた──。
*
せっかく「お花見しよう」と誘いをもらい、電車を乗り継いでここまでやってきたのに、昼が近づくと、突然雨が降り出した。
雨は苦手なんだ。この時期の雨はまだ冷たいし、偏頭痛も現れる。
それに、心の憂鬱とは裏腹に、癖毛の髪はここぞとばかりに愉快に踊り始めて、今朝、一時間かけてストレートに伸ばしたさらさらなセミロングも、今や立派なウェーブのボブヘアになってしまった。
傘を持っていなかった私は、これ以上濡れるまいと、目に入った小さなカフェに飛び込む。
扉に小さな蝶の絵が描かれた、倉庫を改築したような小さなお店。
店内には大きな窓があり、その窓から外を眺められるように備え付けられたカウンターに椅子が三つだけ添えてあった。
真ん中の席の木目の美しい椅子に座ると、背もたれに寄りかった私を慎ましく受け止めて、身体にとても馴染んだ。
「急に雨が降り出して、大変でしたね。良かったら、タオルをお使いください」
そう言って私に声をかけ、タオルを渡してくれたのは、この店の女主人だ。
「ありがとうございます」
タオルを受け取る際に、女主人の顔をみると、それはそれは優しく微笑む人であった。
初めて会ったはずなのに、どこかほっとして心を許してしまいそうな、そんな気分になるのは、きっと彼女の心の柔らかさが、その表情に、声に、所作に表れているからだ。
彼女の腰にかかるほど長い黒髪も、羨ましいほどに真っ直ぐ美しく輝いていた。
「何になさいますか? 温かいものが良いかしら。うちは、決まったメニューは置いていないの」
「……何でもいいんですか?」
「ええ。お好きなものを仰ってくださいね」
「そうしたら……、サーモンとクリームチーズのベーグルと……、ブレンドコーヒーを」
「かしこまりました」
女主人がキッチンへ下がると、やがて焼きたてのパンの香りと、珈琲豆の爽やかな香ばしい香りが漂ってきた。
ふと、窓の外を眺めると、春の雨は先程よりも強く窓を打ち付けて、外の世界を朧気に隠している。
隅々まで磨かれた窓ガラスには、しっとりと雨に濡れ、みすぼらしくなった私の姿だけが、はっきりと映し出されていた。
啓介との約束の時間までは、まだあるはずだ。張り切りすぎて、予定より一時間も早く家を出てしまった。いつもは時間ぴったりに着くようにしているのに、何で早く出たんだっけ。それよりも、どうせ早く出るんなら、もっと早く出るんだった。もう一度家に帰る時間があれば、髪を直せるのに。このうねりにうねった髪の毛は、大問題だ。こんな姿を見たら、啓介は幻滅するかもしれない。
「お待たせいたしました。サーモンとクリームチーズの焼き立てベーグルと、当店オリジナルブレンドコーヒーです」
その時、美味しそうな匂いの湯気を漂わせながら、女主人が料理を私の前にそっと置いた。
「……他に、ご要望はありませんか?」
私の顔を見た女主人は、そう付け加える。
「禧螺さん、私、このままじゃ啓介に会えないです」
自然と、私は彼女の名前を口にしながら、涙を流していた。
初めて会ったはずの彼女に、なぜこんなことを言っているのだろうか。
「わかりました。そのままでも十分美しいけれど、髪を結ってみましょう。あなたが自分を愛せるように」
禧螺さんは、私の真後ろに椅子を持ってきて座ると、ゆっくりと優しく猪毛のブラシで髪を梳いてくれた。
シルバーのアンティークブラシの柄には、細かな薔薇が彫られていて、まるで映画のお姫様にでもなったような心地がする。
少しボリュームの収まった髪を、禧螺さんがサイドから丁寧に編み込み始めると、やがてふわふわとした可愛いシニヨンヘアーが出来上がった。
「特別なリボンもつけましょうね」
そう言うと、彼女はシニヨンの根元に藤色のレースのリボンを結んでくれた。
「ありがとう、禧螺さん」
大好きな藤色が髪の先からひらひらと揺れて、私はみるみるうちに上機嫌になっていく。
──ああ、これで、やっと啓介に会いに行ける。
*
チリン、チリンとドアベルが鳴り、誰かがやって来たことを知らせた。
「いらっしゃいませ」
禧螺さんは、変わらず柔らかな笑顔で客を迎え入れる。
「あ、すみません。客じゃないんです。ちょっと尋ねたいことがあって……。あの、ちょうど二年前の今日、この女性がお店に来ませんでしたか?」
男はトレンチコートの肩に乗った雨粒をハンカチで払うと、胸ポケットから取り出した写真を禧螺さんに見せた。
「実は、彼女、二年前にこの近くで車の事故に遭って……亡くなってしまったんです。あの日は、僕と花見をする約束をしていて、駅で待ち合わせていたのに、なんでこんなところまで来たのか、ずっと気になっていて。恥ずかしながら、今頃になって、やっとあの日の彼女の足取りを追い始めたんです。ずっと、僕のせいで彼女が死んでしまったと、ちゃんと向き合うことができていなくて。でも、彼女が夢に出てきて、『私を探して』と言うんです。こんな話、信じてもらえないかもしれないけど……」
男は、時々鼻をすすりながら、写真を懸命に見せている。
禧螺さんは、男の手から写真をするりと抜き取ると、「どうぞ。あちらに」と、揃えた指先を私の方に向けた。
「え? 何ですか? 僕が聞きたいのは、彼女のことで……」
男はこちらに顔を向けると、最初は戸惑っていたが、やがて私を見つける。
「ああ、綺麗なアゲハ蝶ですね」
「メスクロキアゲハというんですよ。漆黒の羽に、尾の部分の藤色が揺れて綺麗でしょう」
「ええ。まだ肌寒いのに、珍しいですね。それに、窓の外には、随分立派な枝垂れ桜が咲いているんだ。……晴さんが、好きそうな景色だな」
「晴さん」と名前を呼ばれて、私は男の肩にとまる。
景色がはっきり見えないほど雨が降っていたのが嘘のように、雨は止み、カフェの庭の大きな枝垂れ桜の花が窓いっぱいを埋め尽くしていた。
そう、私は、こんな桜が見たかった。
確か、誰かと……。それは、誰だったか……。
そういえば、この男の人の顔、どこかで……。
──ああ、そうだ。
彼は、「啓介」だ。
私があの日、会いたかった人。
変ね。蝶になったら、色々なことを憶えていられなくなる。
今、彼の名前を思い出せたことが奇跡だ。
「啓介さん、良かったら、そのベーグルとコーヒーを召し上がりませんか?」
禧螺さんが話しかけると、啓介は驚いて振り返った。
「え? なんで、僕の名前を……?」
「晴さん、時々、この店にいらっしゃっていました。啓介さんのことを、お話しをされていたこともあります。あの日、『お花見用にスモークサーモンとクリームチーズのベーグルと、ホットコーヒーを二人前、テイクアウトで』とお電話を頂いていて。お時間になってもいらっしゃらないから、雨でお花見が中止になったのかと思っていたのですよ」
「そうでしたか……」
啓介は、さっきまで私が座っていたカウンターテーブルの真ん中の席に腰をかけると、ベーグルとコーヒーの載ったプレートをじっと見つめた。
「まだ焼き立て、淹れたての熱々ですよ」
禧螺さんに促されて、啓介はふわふわのベーグルを一口頬張る。
「……晴さんと一緒に見たかったなあ。満開の桜を」
啓介はそう言うと、子どもみたいにわんわん泣き始めた。人前で泣くなんて、啓介にとってきっと嫌なことなのに、珍しい。
肩にとまったまま、啓介の顔を見上げると、涙に桜の花の色が映って、私に降り注いだ。
その涙の雨は、蜜のような甘い香りで私を満たす。
そうだった。
あの日、一時間早く家を出て、駅から離れた禧螺さんのお店に頼んでいたベーグルとコーヒーを取りに向かったら、突然雨が降り出した。
啓介が好きな女優が真っ直ぐサラサラの黒髪だから、私、会う時はいつもストレートアイロンを念入りにかけていた。
でも、その日は、雨のせいですっかり癖毛は元通り。
気分は落ち込んで、家に一度帰ろうかなんて思ったけれど、癖毛のことを気にしているのは私だけで、啓介は私の髪型なんて変わっても気付かないことも分かっていたから、お店に向かうことにした。
けれど、お店に向かう途中で、今日があなたの誕生日だったことを思い出した。
仕事が忙しかったとはいえ、啓介の誕生日を忘れるなんて最低よね。
だから、私、大急ぎで家に戻ることにした。
言い訳じゃないけど、プレゼントだけは二か月前から用意していたの。
あなたが大学院を修了して、四月から大学で教鞭をふるうと聞いて、学生たちから侮られないように、モンブランの万年筆を選んだ。
馬鹿よね、そんな大事なものを、誕生日の当日に忘れるなんて。
私は、啓介の周りを羽ばたいて、何度も「ごめんね」と言う。
あの日、一緒に桜を見て、適当なベンチを見つけたら一緒に座って、作り立てのベーグルを食べたかった。
コーヒーは、啓介はブラックで、私はミルクと砂糖を少し入れて。立ち昇る湯気で眼鏡を曇らせるあなたを、私は微笑みながら見つめるの。
そして、自分の誕生日さえも忘れているだろうあなたに、プレゼントを渡す。
「覚えていてくれたの?」なんて、あなたは聞いて、「当たり前じゃない。私を誰だと思ってるの?」と、私は得意気に答える。
そんな一日になればよかった。
ハンカチで涙を拭った啓介は、窓から差しこんだ光が眩しくて顔を上げると、庭に咲く枝垂れ桜に残った雨粒が煌めくのを黙って見ている。
ハンカチと共に胸ポケットから取り出した、重厚感のあるモンブランの万年筆を握りしめながら……。
「晴さん、ここに連れて来てくれて、ありがとう」
啓介は、私に向かって言った。
私は、彼の万年筆の上にふわりと移ると、三回羽を羽ばたかせてから、「お誕生日おめでとう」と囁いた。
(了)
🌸本作は、交流のある禧螺ちゃんからイメージした創作物語です。
お正月に、とっても丁寧に描かれた素敵なイラストの年賀状を頂き、お礼をしたいと考えていて、やっと贈ることができました😊
禧螺ちゃん、いつも学びと真心をありがとう♡
蝶たちはきっと、いつも禧螺ちゃんに愛を伝えていると信じています🦋✨
🦋禧螺ちゃんのクリエイターページは、こちら。HSPの学びや、感性に触れる素敵な記事に癒やされています🍀
いつも応援ありがとうございます🌸 いただいたサポートは、今後の活動に役立てていきます。 現在の目標は、「小説を冊子にしてネット上で小説を読む機会の少ない方々に知ってもらう機会を作る!」ということです。 ☆アイコンイラストは、秋月林檎さんの作品です。
