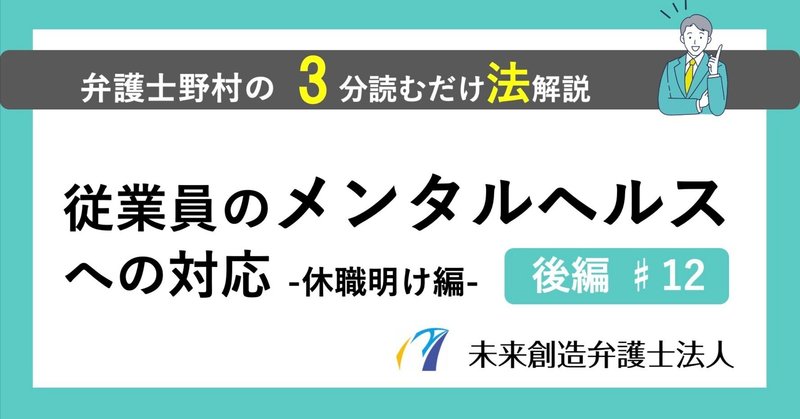
知っておきたい『従業員のメンタルヘルスへの対応~休職明け編~ #12』
前回は、 『従業員のメンタルヘルスへの対応1:休職まで』についてお伝えしましたが、今回は、『従業員のメンタルヘルスへの対応2:休職明け』についてお伝えいたします。
【事例】
社員数3,000人の自動車部品メーカーのA社において製造工場の現場主任をしていたXさんは、家族に先立たれたことでうつ病になってしまい、会社を休職することになりました。
A社の就業規則では、最長2年間の休職が可能となっており、2年以上経っても復職できない状態が続く場合には、自然退職となる規定になっています。
1. 復職希望が出ていると元の職場に復職させないといけない?
(1)復職希望があったら診断書を提出してもらう
A社人事担当者Yさんに、Xさんから「来月から復職したいので、よろしくお願いします。」と電話連絡がありました。
Yさんとしては、復職の判断にあたって診断書の提出を求めましょう。
※会社が、復職の判断を独自に行い、復職した結果、従業員のうつ病が再発し、当該従業員が自殺した事案で訴訟になったものがあります。(参考:名古屋地判H18.1.18)
(2)主治医の診断書に『簡易作業なら可』とある。どう対応すべき?
復職する場合、原則は、休職前の職場に復帰させる必要があります。
仮に、休職前の職場に復帰できない場合であっても、Xさんが「当該労働者の休職前の職場よりも軽い職場に配置転換できて、当該労働者が軽い職場で働きたい」と言っている場合には、軽い職場で復職させなければなりません。(参考:最判H10.4.9)
⇒Xさんの主治医の診断書に『簡易作業なら可』という記載があるのであれば、A社の規模であれば『製造工場の現場主任』としてではなく、『事務職等』での復職を行う必要があるため、配置転換できる部署がないかは検討しなければなりません。
会社としては、
1.元の職場に戻して問題がないか、
2.問題があるとしてより軽い職場に戻すことはできないか
を順を追って検討する必要があります。
2. 復職について主治医と産業医の意見が割れている場合はどうする?

診断書
Xさんの主治医:『簡易作業なら復職可』
A社の産業医:Xさんと面談したところ、『まだ復職するのは難しい』
との意見を述べています。
主治医の診断書も、産業医の診断書も復職の判断の一つの資料です。
一般的に労働者の主治医は、労働者の勤務実態について詳細を知りません。しかし、産業医はXさんの勤務実態や、どのような仕事が会社にあるかを主治医より詳しく知っています。
⇒そのため、主治医の診断書での判断が疑わしいという合理的な理由がある場合には、主治医の意見を否定して復職不可との判断を下すことになります。
その時に有用なのが、リハビリ出勤や慣らし勤務といった『リワークプログラム』です。(参考: 厚生労働省 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引1)
Xさんが、短時間でのリハビリ出勤において、
・感情の起伏
・始業時間に出てこれない
・一定時間のデスクワークも出来ない
といった業務遂行能力に疑わしい点がある場合には、記録化して復職の可否の判断の一材料にすべきです。
その結果、復職するXさんの治療の妨げや、周囲の人たちとの関係においても問題が生じると疑われる場合には、主治医の判断に合理的な疑いがあると考えていいでしょう。
3. 復職できない場合、自然退職だから復職期間満了を待てばいい?

Xさんの復職を認めず、あと2ヶ月で2年が経過しようとしている場合、A社の就業規則では、休職期間満了までに復職できなければ自然退職となります。
しかし、休職期間満了直前に復職可と記載のある診断書がXさんから提出されても、A社では復職可否の判断をする余裕がありません。
そのため、少なくとも休職期間満了の1ヶ月前には、休職期間が満了すると自然退職になる旨をXさんに通知しておきましょう。
期間満了直前に復職希望を出した労働者に対して、会社が復職を認めなかった事例が一番紛争化するため、期間満了が迫っている労働者に対しての判断は、産業医・主治医・弁護士を含めた専門家と人事担当者で密に連携をとって対応する必要があります。
弊所も、復職の可否について産業医の先生と一緒に協議して会社の判断にアドバイスを行っております。
以上のように、メンタルヘルスの問題を抱える従業員は多く、休職制度を利用する労働者も年々増えているようです。

弊所では「Law Room」という福利厚生サービスを提供しております。
ご契約いただいた企業の従業員さんのプライベートな悩みの法律相談を無料でお受けしております。
従業員の皆様が、悩みをもったまま働くとパフォーマンスが落ちるだけでなく、休職に発展してしまう恐れがあります。こちら、企業側の導入費用も無料ですので、お気軽にお問合せください。
⇒ 詳細は こちら
【次回】
「SNS規程およびSNS研修について~人事労務と広告規制の観点から」についてお送りします。
【未来創造弁護士法人】 www.mirai-law.jp
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
弁護士 野村拓也(神奈川県弁護士会所属)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
