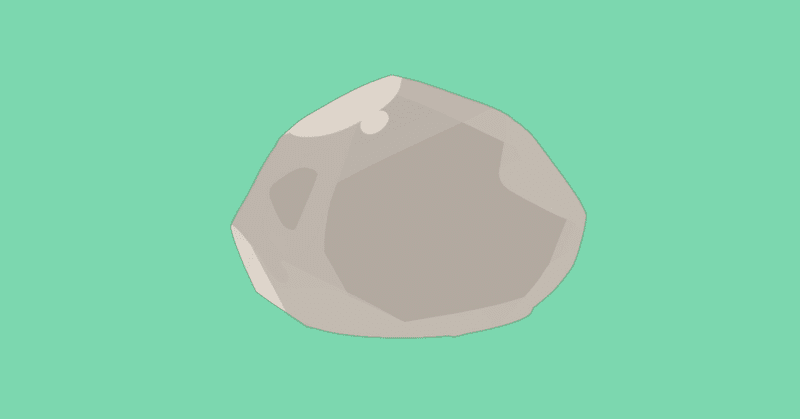
石ころの訪問。
スーパーの買い物袋が、左の腕にぐいっとくいこんでいる。いたい、重い。でも、あともう少し。アパートまで、足をずりずりとひきずりながら、歩いていく。今朝は小雨がふっていたせいで、仕事に行くのに自転車ではなく、バスを使ったのだ。バス停が近くにないのが不便ではあるものの、その分、家賃が安いのだから、文句ばかりも言ってはいられない。右手ににぎったカサを杖代わりにしながら、美琴はひたすら歩く。自転車が一台、追い越していった。
「はあ、やっと到着」
部屋のトビラの横にカサを立てかけて、肩からつるしていたカバンの中を、ごそごそとかきわけてカギを探していると、足元から小さな声が聞こえた。
「やっと帰ってきましたね。ご苦労さまです」
だれ?顔をあげて、あたりを見まわすもののだれもいない。気のせいかな。すると、
「早くしてください。もう待ちくたびれましたよ」
さきほどと同じ声が、トビラの下から聞こえた。そこにあったのは石だった。丸くて灰色の、どこにでもありそうな石だ。石がわたしに話しかけてるの?コンクリートの上で、石はカタカタとゆれている。今、待ちくたびれたって言ったよね?とにかく、部屋に入らなくちゃ。美琴はカバンの底からあわててカギを取り出し、ドアを開けた。同時に石を拾い上げ、部屋の中に持ちこんだ。
どこに石を置いたものかと迷ったものの、床の上はまずいだろうと美琴は判断した。台所の食卓の上に、石をころんと座らせた。それでよかったみたいだ。石は、さっきとはうってかわった穏やかな調子で話し始めた。
「いやあ、これほどの長旅になろうとは、思ってもみませんでしたよ」
石は少し湿っていた。夕方近くまで降りつづいていた雨のせいで、ぬれてしまったのだろうか。
「そこでちょっと、待っててくださいね」
相手はただの石なのに、なぜか敬語になってしまった。自分の家にお客さんがくるなんて、めったにないことだ。緊張しているのかもしれない。美琴は「ふうう」としずかに深呼吸をして、カバンをいつもの場所におき、カーディガンをぬいでハンガーにかけた。それから買い物袋の中身を、次々に冷蔵庫の中にしまいこんだ。
「できれば、冷たい飲み物でも一杯いただけますか?」
冷蔵庫の前でしゃがみこんでいる美琴に、石がたのんだ。
「あ、はい。わかりました」
石がどうやって飲むの?何を出したらいいの?まさかビールなんて飲まないよね。無難にお茶でいくか。美琴は冷蔵庫から麦茶を出して、二人分コップに注いだ。
「どうぞ」
「いただきます」
目の前にコップを置くと、石はなにやらカタカタとゆれていた。その場でゆれているだけなのに、コップの中の麦茶は少しずつ、量が減っていった。
「はあ、美味しいです。冷えた麦茶、サイコー」
「はあ。それは良かったです」
美琴も、自分の麦茶をごくんごくんと音を立てて飲みほした。
さて、あれから一時間が経過したところだ。先ほど和んでいた空気は一転して、今は険悪な空気が部屋に満ちている。
「でも、ワタシはアナタに頼まれていたから、はるばるやってきたんですよ」
「さっきから何度も言ってるんですけど、わたしのほうは、あなたに何かお願いした、なんて覚えはないんです」
二人の話は平行線をたどっていた。話がまったくかみ合わない。石は、美琴の依頼を受けて訪問したと強く主張するのだが、美琴にはそんな依頼をした記憶はない。石に頼みごとをする人間なんている?いるわけないじゃないの。
石は、依頼した事実を美琴が認めないかぎり、何を頼まれたのか、石がこれからどうするつもりなのか、明かすつもりはないようだった。石の表面から、うっすらと湯気が上がっている。カッカする怒りをなんとか抑えようとしているのが、美琴にもわかった。
(でも覚えてないんだから、わたしにもどうしようもないわよ)
このまま会話を打ち切ってしまいたいけれど、これは仕事ではないし、ここは自分の部屋だ。逃げようにも逃げられない。そんな美琴の気持ちを察したのか、石がコトリと体を少し動かして、こう言った。
「一旦、休憩にしましょう。先に夕食でも済ませますか?結論が出るまで、まだ時間がかかると思いますから」
仕事のできるサラリーマンのような、きっぱりした口調で言った。
「それならわたし、先にシャワーを浴びてきます」
「どうぞ、遠慮なく」
美琴もいい加減、腹が立っていた。お腹がすいていると、どうしても怒りっぽくなってしまう。こんな時は、まず気分をかえる方がいい。シャワーを浴びてさっぱりしたら、石に帰ってもらう何かいい案が出てくるかもしれない。
ふだんより丁寧に、シャンプーした髪をタオルでくるみ、部屋に戻ると、スー、スーと寝息が聞こえる。どうやら石は眠ってしまったようだ。眠っている石は、ただの石だった。顔があるわけでもないし、胴体があるわけでもない。丸くて全体が石なのだ。寝息さえなければ、食卓の上に石が転がっている、それだけのことだった。夢を見ているのかもしれない。でも寝息は聞こえる。わたしは今、起きている。つまりこの寝息は、石が眠っているという証拠というわけだ。声には出さず、美琴は自分の頭の中を整理してみた。
(さて。どうしよう?)
夕食でもいただくとするか。美琴に大したレパートリーはない。夕食はめん類か、野菜炒め、買ってきたコロッケや冷奴、そこに味噌汁だけは手作りで添えるのが定番だ。今夜は野菜炒めを作るつもりだった。それだけじゃなく、お刺身も買ってきていた。夕方のセールで安くなっていたから。たまに飲むビールは自分へのごほうびだ。疲れているし、今日は自分で作るのはあきらめ、コロッケとお刺身、冷奴をならべて、ビールと一緒にいただくことにした。
ビール一缶で、美琴の頬がほんのりと色づいた。お腹がふくれると、ほわんと気持ちもゆるんできた。汚れたお皿はあとから洗おう。美琴はソファに転がってのんびり寛ぐことにした。スー、スー。石ころの寝息は、静かにつづいている。よくみると石のわき腹のあたりに苔が生えている。その反対側にはうっすらヒビが入っている。
(小さな子どもみたいだな)
ほんとうはテレビでも見たいところだが、うるさいと石を起こしてしまうかもしれない。長旅だったと言ってたな。ずいぶん疲れているのだろう。このまま眠っててくれたらいいのに。朝になれば、仕事に行くからって説明して、石には帰ってもらえばいいし。
美琴が読みかけの推理小説を読み始めて、三十分ほど経ったころ、電話が鳴った。
「あら、おかあさん」
夜、おそい時間に電話がくるなんてめずらしい。
「久しぶり」
受話器の中から、いつもの声がした。
「別に用事はないんだけど。きゅうに美琴の声が聞きたくなってね」
お父さんは、とっくにお酒を飲んで寝てしまったらしい。
「そう、何か変わったことある?」
「別にないわよ。おじいちゃんもおばあちゃんも元気にしてる。そっちは?仕事忙しい?」
「うーん、それほどでもないよ」
就職してまだ一年と少しだから、慣れたとは言えない。でも全くわけがわからない状況からは、ようやく抜け出しつつある。お母さんは最近こっている料理のメニューや、近所の人のうわさ話をした後、付け足しのように言った。
「それにしても、あの怖がりだった美琴が一人暮らししてるなんて、笑っちゃうわね」
「失礼ね。わたし、そんなに怖がりだった?」
「忘れちゃったの?寝る時にかならず母さんをベッドのわきまで連れていって、おやすみの挨拶させてたじゃない」
言われてみると、そんなこともあったかなとおぼろげな記憶がよみがえる。
「子どもの頃、おばけが怖かったからなあ」
「部屋を真っ暗にするのもいやがって、中学生になっても常夜灯付けたままで寝てたよね」
お母さんは、なつかしそうに昔の話をどんどんふってくる。思い出すと、芋づる式に出てくるのが、人の記憶というものだ。
「そろそろ寝ないと。明日も仕事あるし」
「ああ、ごめん、ごめん。じゃあ、またね」
電話が終わると、美琴はぽんと、自分の体が静かな空間の中に投げ出されたような気持ちになった。ひとりっきりだ。こんな感覚が昔は怖かったのかもしれない。うまく言葉にできないんだけど。自分が全くのひとりぼっちで、まわりはいろんな物にあふれているのに、そのどれともつながっていないような気がして、さっきまで、家族のだれかと楽しくおしゃべりしていたことすら、遠い昔の出来事のような、時間の感覚もあやしくなって。無防備な自分が、どうしようもなくたよりなかったのだ。
台所に戻ると、食卓の上には相変わらず石が転がっていた。ただの石ころだ。あれ、さっきとちょっとちがう。何だろうと美琴は思った。
(寝息が聞こえない)
さっきは小動物のように息をたてていた石は、本来の、固い鉱物に戻っていた。石のくせにやわらかな印象を与えていた輪郭も、冷たくはっきりとしたものかわっていた。どうしたんだろう。石をそっとつまんで、美琴は自分の手のひらの上に置いてみた。ひんやりして気持ちのよい重さが、そこにあった。
「この石、わたし、知ってる」
ようやく美琴は思い出した。昔、子ども部屋に置いていた石のことを。子どもの頃から、なぜか石が好きで、山登りや、海水浴など、出かけた先でさわり心地のよい石を見つけると、持って帰っていた。お守りみたいなものだった。神社やお寺で売っている人間が作ったお守りよりも、自分でみつけた石のほうが、目に見えない力を秘めていると思っていた。強い石に自分の願いをこめたら、石がその願いを叶えてくれると信じていた。
「石さん、石さん、どうかお願い、夜のおばけをやってつけて。わたしをひとりぼっちにしないでね」
美琴が、その石のことを思い出したのは、石に白いハートのような印がついていたからだ。これは家族で海水浴にいった時に、岩かげでひろったものだ。海でひろった石だから、海水が中までしみこんでいるかもしれないと、持ち帰ってからお風呂場で、何度も真水につけた覚えがある。心がざわついた時、自分の部屋で、石をじいっとにぎっていると心が落ち着いた。世界の何ともつながれていない自分というちっぽけな存在が、にぎっている手のひらの中の石ころとだけは、つながれている。そこが世界と自分との接点だった。
「この子の名前、なんだったっけな」
美琴は、眉間にしわをよせながら考えた。うーん、この子の名前は…。
「石ごろう」
「…はい」
そのとたん、石がぱちっと目を覚ました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。サポートしていただけるなら、執筆費用に充てさせていただきます。皆さまの応援が励みになります。宜しくお願いいたします。
