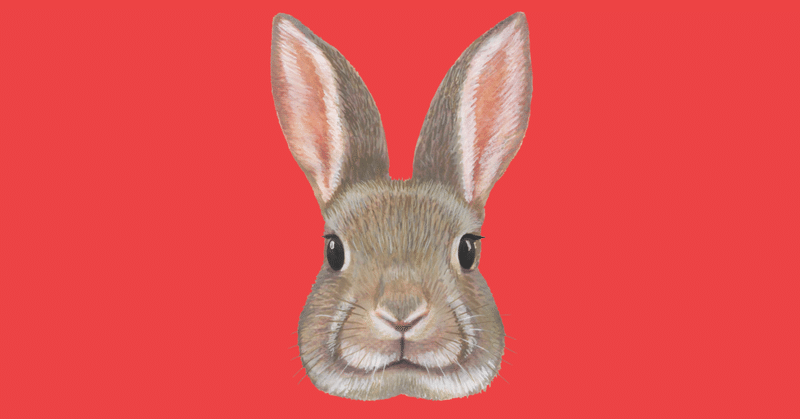
マフラーを巻いたうさぎ。(2)
< 2 >
週末になるのが、こんなに待ち遠く感じられるのは、久しぶりのことだ。もちろん学校が休みであることは、いつでもうれしい。でもそれはワクワクする気持ちとは、ちょっと違う。
(こういう感覚、小さい頃によくあったな)
まだ小学校の低学年だった頃、休みの日になると、いつもより一時間以上早く目が覚めて、家の中をうごきまわり、お母さんに叱られた。
「たまの休みくらい、ゆっくり布団で寝かせてよ」
眠たい時のお母さんは、すごく機嫌がわるいのだ。
「はあい」
素直に返事だけはするものの、小さなまい子のワクワクを止めることはできなかった。
(今日は何してすごそう)
思い出してみると、休みの日だからといって大したことはしていなかった。子ども向けのアニメをみたり、庭でままごとをしたり、ちょっと遠出の買い物にでかけたり、たまにお母さんといっしょにクッキーを作ったり。それでも一日という時間を思いっきり使いきったような充実感が、あの頃のまい子にはあった。自分が中途半端かもしれないとか、このままの自分じゃ不十分かも、などと感じたことは一度もなかった。
今のまい子の気持ちは、あの頃の気分に近い。身体の内側からエネルギーが湧いてきているような気がする。
(そうだ、調べもののことも考えなくちゃいけないんだ)
死んだ人がどこに行くのかなんて、今まで真剣に考えたことはない。飼っていたハムスターが二年くらいで死んでしまった時は、悲しくて一晩泣いたけど、お母さんといっしょに庭にお墓を作って埋めたら、それ以上は気持ちを引きずらなかった。でも、だからといってまい子が全く死について考えていないというわけでもない。
(もし突然、お父さんが死んでしまったら。お母さんがいなくなってしまったら)
寝る前にふとよぎるそういった想像は、まい子にとって恐ろしさ極まりない類いのものだ。一人っ子のまい子には、親がいなくなる不安を共有する兄妹もいない。だから、そんな怖いことは考えないほうがいい。心配性のお母さんは、遠くに住んでいるおじいちゃんやおばあちゃんの体調が気になって仕方がないみたいだけれど、
「こればっかりは、なるようにしかならないだろう」
と、いつもお父さんになだめられている。
それにしても。目に見えない世界って本当にあるのかな。まい子には霊感らしきものはない。おばけをみたこともない。
(わたしが手伝う、なんて自信たっぷりにいっちゃったけど、なんにも役に立たないかも)
そう考えると、心がしぼみそうになる。ダメダメ、こんなんじゃ。あんなに年取ったうさぎさんが、たったひとりで何とかしようとしてるんだもの。まだ調べる方法はわからないけど、きっとなんとかなるはず。
「まい子、準備ができたわよ」
台所の片付けを終えたお母さんが、階段からまい子を呼ぶ声が聞こえた。今夜からマフラーの編み方を教えてもらうのだ。お母さんに言い渡された条件はひとつ、編み物をする前に、その日の宿題を終わらせておくこと。
「はあい」
まい子は元気に返事をして、リビングにかけ降りていった。
「ほら、こうして、こうして。ね、簡単でしょ?」
「ちっとも簡単じゃないよ。もう一回、今のやってみて」
「だから、こうして、こうして…」
初心者のまい子に、お母さんはメリヤス編みからおしえてあげるといった。両方の手でそれぞれ編み棒をにぎり、左手の人差し指に毛糸をひっかけて、作った編み目に通していくのだけれど、まい子にはもうなにがなんだかさっぱりわからない。
「もっとゆっくり手を動かしてくれないと、よく見えないよ」
「あんたねえ、おばあさんじゃあるまいし」
「おばあさんだと思って、ていねいにやさしくおしえてよ」
焦りを通りこして、早々に諦めたくなったまい子に、
「今年はまず練習して、マフラーは来年完成させればいいんじゃない」
と、お母さんが言った。
「…いやよ、ぜったい今年、マフラー仕上げるから」
くっそー。そんなこと言われるとまい子だってひくにひけない。
******
土曜日の午後、図書館の片すみで、まい子とうさぎの調べものが続いている。日当たりの良すぎる窓際の、いつもの席で。こちらも編み物以上ののんびりペースだ。
「ほれ、これを見てごらん」
うさぎは古い本を開いて、まい子に見せた。
「極楽について書かれておる。もしかするとエリーはここにおるのかもしれんぞ」
「…極楽ねえ」
まい子も本のページをのぞきこんだ。
「なになに、極楽浄土ともいう。阿弥陀仏のすむ西方十万億土のかなたにある。そこには苦しみも悲しみもなく、すべてが楽しいことばかり…」
「楽しいことばかりというのが、なんともいいじゃないか」
「でも、西方十万億土ってどのくらい遠いところか、想像もできないよ」
まい子が少し投げやりな返事をかえすと、
「ほれ、ここを読んでごらん」
うさぎが得意げに、次の行を指さした。
「阿弥陀仏を信じて、念仏を唱えれば、だれでも死後、極楽往生できる」
「さよう」
うさぎは、あごを手でさすりながら、続けてこう言った。
「つまり、念仏を唱えさえすればいいと、この本には書いてあるのじゃ」
(うさぎさんったら、かなり能天気なタイプだわ)
まい子は、なるべく落ち着いた声を出そうと意識しながら、うさぎに話しかけた。
「そうだね、そう書いてあるわね。でもその後のところに、「死後」って書いてあるわよ。念仏を唱えつづけていたら、死んだ後、そこに行けるってことでしょ。生きたままでいけるなんて、書いてないわ。うさぎさんには無理なんじゃないの?」
「あちゃー、こりゃしてやられた」
うさぎは、自分の額をコンコンと二回たたいて笑ってみせた。
「まあ、こんな失敗もある」
話がひと段落すると、うさぎは手元の本から顔を上げ、まぶしそうに目を細めた。
「あんたは本当に、若いころのエリーにそっくりじゃ」
そう言って、懐かしい人をみるようなまなざしでまい子の顔を見つめた。そういえば初めて会った時、そんなことを言ってたな。
「あんたに声をかけたくなったのも、きっとエリーに似ていたからじゃな」
「エリーって、中学生だったの?」
「わしは、小学校のうさぎ小屋で生まれたんじゃ。何匹も兄弟がおって、子どもたちがわしら子うさぎを引き取ってくれてな、わしを引き取ってくれたのが、エリーじゃった。その頃、エリーはまだ四年生だった」
うさぎは、遠い記憶をたぐりよせながら話をつづけた。
「とても静かな女の子でな。友だちが少ないのをエリーのお母さんは気にしていたよ。でもわしは、エリーがとても好奇心がおうせいで、おてんばなところもあることもよく知っていた。ずっと一緒にいたからの」
「エリーさんとは、いつまで一緒に暮らしていたの?」
「そうじゃなあ。エリーが二十歳の成人式をお祝いするころまで、生きておったと思う」
「自分のことなのによく覚えていないの?」
「ほっほっほ」
うさぎは、また大きな声で笑った。
「さよう」
うさぎが死んだ時、エリーは何日も泣き続け、ご飯も口にしようとしなかったらしい。
「うそつき、ずっとそばにいようねって言ったじゃないって、エリーが泣きながらわしを責めるのが、つらくての。わしはもう死んでいたけれど、たましいは地上に残っておったものじゃから」
「それでどうしたの?」
「わしもエリーのことが心配でしかたなくてな。それなら、エリーが死んで地上を旅立つときまで、そばで見守ってやろうと思ったんじゃ」
「たましいとして?」
「さよう」
どうやらうさぎは死んでいるらしい。まい子の頭の中はたちまちこんがらがってきた。死んだのにどうしてわたしの目の前にいるの?わたしは何を見ているの?まい子の目がぐるぐる回っているのも気づかないで、うさぎは話を続けていった。
エリーは少しずつ年をとり、何十年も経っておばあさんになり、一ヶ月ほど前に死んでしまったという。
「エリーはずっと一人暮らしじゃった。でもさびしくはなかったはずじゃ、わしがずっとそばについていたんじゃから」
「エリーには、あなたのことが見えていたの?」
「それは、どうかな」
うさぎにも分からないようだ。
「時々、じっとわしのことを見ているように感じる時もあったが、全く気づいていないようにも見えたな」
(そんなことって、あるのだろうか)
夢みたいな話を聞かされて、まい子のほうが途方にくれてしまった。
「じゃあ、つまり、あなたはユーレイってことなの?」
「まあ、生きているとはいえないじゃろうな」
「死んでいるなら、どうしてエリーが死んだ時に再会できなかったの?」
「なんでじゃろう?それはわしにとっても最大の謎じゃ。あんまり長いことこんな姿で、地上をさまよっていたから、エリーのたましいが消えていく時にうまく着いていけなかった。消えていくたましいを見失ってしまったんじゃ」
「だから今、こうしてエリーの行き先を調べているのね」
ユーレイうさぎが、人のたましいの行き先を追っているなんて。分かるような、分からないような不思議な話だ。まい子はもうひとつ質問してみた。
「それならどうして、あなたの姿があたしには見えるの?」
「それはわしのほうが、あんたに聞きたいくらいじゃ」
うさぎはそう言うと、また別の本を手に取ってながめ始めた。気持ちの切り替えが早いらしい。
(うさぎなのに人間の言葉を読んだり話したりできるって、どういうこと?)
「あのね」
本をめくっているうさぎに、まい子は話しかけた。
「人が死んだらどこにいくのか調べるのは悪くないんだけど、そもそもうさぎさんのお仲間、つまりうさぎとか猫とか、動物が死んだらどこにいくのか、それは知ってるの?」
うさぎは手を止めて、まい子の顔をじっと見つめた。
「それはなかなか鋭い質問じゃ」
すっかり関心している。
「そうだな、わしはたしかにうさぎで人間ではない。でもなあ、わしがほんもののうさぎかどうかと聞かれると、ちょっと困ってしまう」
「え、ほんもののうさぎじゃないの?」
今度はまい子のほうが目を丸くする番だった。
「いやいや、身体はうさぎだ。うさぎに間違いない。ところが、心はどうかと聞かれると、そこはよくわからんのじゃ」
うさぎさんは、エリーと暮らしている間、一度も自分の仲間を見たこともないし、仲間と交流したこともないと言う。
「兄弟たちと生き別れて以来、ほんもののうさぎを見たことは一度もない。それよりも、わしの心はエリーと共にあった」
なるほど、そういうことか。まい子にも少しは想像がつく。
「わしはうさぎの餌を食べ、うさぎとして生きた。年に二回は毛が生え変わったし、若い頃は歯がニョキニョキと伸びた。毛が生え変わる時は、かなり体力を消耗したな。エリーが毎日せっせとブラッシングをしてくれたよ。歯が伸びつづけるから、歯の先がすり減るように、固いものはゴリゴリよく噛んで食べたものじゃ。でもな、わしはエリーと暮らしてきた。エリーがわしに話しかけ、わしもエリーの心を理解しようと日々努力を重ねた。エリーが悲しい時、わしも悲しくなったし、エリーが嬉しいことがあると、わしも跳びはねたくなった。わしの心はいつもエリーと共にあった」
「じゃあ、うさぎさんの心は人間の心と同じってこと?」
「さあ、そっくり同じとは言えんじゃろうの。でも全く別ものということもあるまい。だからこうして、わしは人間の言葉を理解し、文字を読めるようにもなったわけだから」
うーむ、なるほど。身体は人間だったりうさぎだったりしても、目に見えない心の部分はどうかなんて、本当のところは分からない。うさぎさんの言うことが正しいなら、エリーがなくなった時に、どうしてうさぎさんはエリーと再会できなかったのか。同じ心と心なら、すぐに会えそうなものなのに。うさぎも同じことを考えていたようだ。
「でもまあ、エリーを見失ってしまったということは、結局、わしの心は人間と同じではなかったんじゃろう。わしの心は人間と同じでもないし、うさぎと同じでもない。中途半端なできそこないじゃな」
ふたりが話していると、館内に閉館の音楽が流れはじめた。土曜日の図書館は五時にしまるのだ。
「もうこんな時間か」
まい子は立ち上がって、しわのついたスカートをはたいてのばした。うさぎは上着のチョッキの内ポケットから懐中時計を取り出して、
「おや、わしの時計はまだ三時だぞ」
とけげんそうな顔をした。
「その時計、ネジを巻かないとダメなタイプなんじゃない?」
まい子が言うと、
「おかしいのう。ネジは毎晩、欠かさず巻いておるんじゃが」
うさぎの耳がしゅんと折れ曲がった。外はすっかり暗くなっていた。親子連れが手をつないで楽しそうに帰っていく。
「それじゃあ、またね」
「ああ、さよなら」
うさぎはまい子に背を向けると、くるりと反対側をむいて、ひょこひょこと二本足で歩いていった。まい子には、その小さな背中がちょっと寂しそうに見えた。
(つづく)
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。サポートしていただけるなら、執筆費用に充てさせていただきます。皆さまの応援が励みになります。宜しくお願いいたします。
