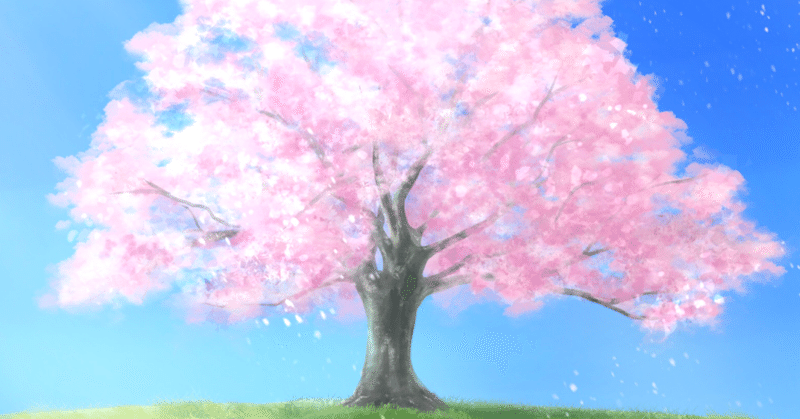
ハルタと桜色の夢。(1)
<1>
楽しそうな明るいわらい声で、ハルタは目をさましました。葉っぱの上でうっかりねむっていたようです。ちょうど子どもたちの下校の時間のようで、川ぞいの道を、色とりどりのランドセルをせおった子どもたちが、にぎやかに歩いていきます。
「あぶない、あぶない。あいつらに見つかったらたいへんだ」
ハルタは草むらにかくれながら、川の上流へとむかいました。おなかが空いたので、何かえものをさがそうと思ったのです。お日さまの日差しと秋の風が、ここちよい季節です。このところ雨がふっていないので、川の上流では、ほんの少し水が流れているだけです。小さなコオロギとハエを何匹かとらえ、おなかをみたしたハルタは、内側から力がみなぎるのを感じました。
「うまいものをたべるのって、しあわせだ」
夜になると、空には星たちがまたたいてみえます。さむさの中で空気がすみわたると、より一層そのきらめきは引き立ち、目をうばわれるほどです。
「うわ、すげえ」
草むらをとびはねながらも、ときおり立ち止まっては、ハルタは空を見上げます。すいこんだ空気が、おなかの底までしみこんできます。ハルタはからだ中が、土の匂いや葉っぱのかおりに、満たされていくのを感じました。こんなおだやかな気持ちでねむりにつけるのなら、ハルタにも冬眠するのがこわくはないかもしれません。
「でも、でも…」
ハルタはねむるたびに夢に出てくるあの場面を、また思い出していました。
その晩は、まんまるな月がとてもきれいな夜でした。月の光が、水田にきらきらと反射して、あたりはまぶしいほどでした。生まれてまもないハルタには、何もかもがめずらしく、うごいているものを見ると追いかけずにはいられません。
「あれはなんだろう」
ほそ長いからだ、針のように長い足をくの字にまげた生き物が、草の上にとまっていました。バッタです。ハルタはそばに近よってみたくなりました。
「まちなさい、ハルタ。もっとまわりをよく見て」
注意をうながすお母さんの声も、ハルタの耳にはとどきません。ハルタはバッタの方に向かって、ぴょんぴょんと高くとびはねていきました。と、目の前にいきなり大きなぐねぐねしたものが現れました。蛇でした。蛇はするどいまなざしで、正面からグッとハルタをにらみつけました。蛇に見つめられたハルタは、急にからだが石のようにかたまって、うごけなくなりました。舌さきをチョロチョロと出したりひっこめたりしながら、蛇は、じわりじわりとハルタににじりよってきました。
(たべられる)
そう思った時、ドンと何かがぶつかってきて、ハルタをはじきとばしました。お母さんでした。
「ハルタ、走ってにげて」
コロンととばされたと同時に、またうごけるようになったハルタは、夢中でにげました。グワッと、にぶい音がうしろから聞こえてきました。それはお母さんがたべられた時の音でした。
ハルタはひとりぼっちになりました。もうだれも自分を守ってくれるものはいません。ハルタはもう、葉っぱの上を気軽にとびはねたりはしません。空をとぶ鳥たちにねらわれているからです。地上をいどうする時も、周囲に目をこらします。蛇やとかげ、いたちなどが、いつおそってくるかもわからないからです。ハルタの心は、一日中電気が走っているかのようにピリピリとはりつめています。だんだんと、ハルタは昼も夜もぐっすりとねむることができなくなっていきました。夏のあいだ、夜の田んぼで仲間たちが楽しそうに肩をくみ、生きている喜びを大きな声で歌っていても、ハルタがその輪にくわわることはありませんでした。自分は歌ってはいけないような気がしたのです。
つかれはてたハルタがねむりにつくと、きまってお母さんが蛇にたべられる夢をみます。ほんとうは目にしていない場面なのに、まるで見ていたかのようにはっきりと、夢の中のハルタにせまってくるのです。お母さんは泣いていました。いたい、こわい、助けて、と叫び出しそうな顔で、ハルタのことを見つめながら、蛇の真っ赤な口の中にのみこまれていくのです。
「母ちゃん!」
夢からさめると、ハルタの目はいつも涙でぬれています。でも、どんなに名前をよんでも、お母さんがハルタのもとにもどってくることはないのです。
(おいらのせいで、母ちゃんがしんでしまった)
苦しみつづけるハルタをなぐさめてくれるものは、だれもいませんでした。
<2>
それから何週間かがすぎ、風も冷たさをましてきました。ある日ハルタは、寝床からそれほど遠くない林の中で、何匹かの仲間たちが冬眠にはいるところに出くわしました。
「ああ、さむい、さむくてしにそうだ」
あるものは枯れ葉のうらにもぐりこみ、そのままうごかなくなりました。またあるものは、黒くしめった土をほりおこし、その穴にもぐっていきました。
冬眠中、カエルたちは長い夢をみながら、春のおとずれをまちます。その夢が楽しいものであっても、おそろしいものであっても、ねむっている間は自分の夢からのがれることはできません。もし冬眠中に、おそろしい夢をみて何度も目をさますようなことになれば、体力をうばわれ、いずれしんでしまうことでしょう。
ハルタは考えました。今の自分はたったの一晩ねむるだけでもこわいのに、何ヶ月ものあいだ、くらい、くらい土のなかでねむりつづけるなんて、不可能にちがいない。
「おいらに冬はこせやしない。きっとこごえてしんでしまう。ごめんよ、母ちゃん」
このまましんでしまう前に、やりのこしたことはないだろうか。さむさでからだがかたくなり、うごけなくなる前に、行っておきたい場所はないだろうか。ハルタには、お母さんとの大切な思い出の場所がありました。それは、年をかさねて幹がまがっている、大きなさくらの木が立っている土手でした。
西の空には夕陽にてれされた雲が、ほんのりとオレンジ色にそまっています。川からつづく土手をぴょんぴょんとはねて、ハルタは傾斜のきゅうな土手をのぼっていきました。ハルタは息をきらしながら、やっとさくらの木の下までたどりつきました。
「あいかわらず、でっかいなあ」
豆粒ほどの小さなからだで、ハルタは大きなさくらの木を見上げました。夏にきた時には、枝という枝にあおあおとした葉がしげり、風になびいてサラサラとゆれていましたが、今、目の前の老木には、赤くひからびた葉が、ほんの少しついているだけです。とがった枝の先はむきだしになっています。
「こんな枯れそうな木が、もう一度花をさかせることなんて、できるのかな?」
ことし生まれたばかりのハルタには、冬を越したさくらの木が、春に見せるすがたを想像することはできません。
「来年はいっしょに、満開のさくらの花を見ようね」
ここにくる度に、お母さんはハルタにそう話していました。でもお母さんはもういない、それに自分も、来年の春まで生きてはいられないだろう。木の根元にたどりついたハルタは、ふかいため息をつきました。
「そんなところで、何してるんだい?」
まわりには、だれもいないと思っていたハルタは、おどろきました。ふりむくと年老いた大きなヒキガエルでした。背中にこぶのあるカエルが、木のそばの大岩の上にすわっていたのです。
「おまえさん、まだわかいアマガエルのようだね」
ハルタの顔を見おろしながら、年よりガエルがしゃがれ声でいいました。
「こんなにさむい日に、のんきに散歩なんかしてていいのかい?」
「散歩にきたんじゃないよ。さくらの木にあいさつにきたんだ」
ハルタがこたえると、
「ホッホッホ」
ヒキガエルは、ゆかいそうにわらいました。
「おもしろいことをいうね。その木にあいさつするのは、春が一番いいに決まっている」
「それができそうにないから、今きてるんだ」
「おやおや、春までまてないのかい」
「…」
ハルタの打ち明け話をきき終えても、ヒキガエルはしばらく何もいいませんでした。息をするたびに、喉のあたりをふくらませて、なにか考えているようでした。
「ばっかばかしいねえ」
ヒキガエルがやっと口を開きました。
「こわがって、さくらの花も見ずにしぬつもりなのかい。生命がもったいないねえ」
ハルタはゴクンとつばをのみこみました。年よりガエルのいうとおりです。
「臆病者のままで、あの世にいっても、あんたの母親がよろこぶとは思えないけどね」
ヒキガエルは、まるでいたずらをしたハルタを叱りつけるお母さんのような口ぶりでした。
「おいら、おいら…」
何か言い返したくても、ハルタはなんといえばいいのか、わかりません。口をとざしているハルタを横目でみながら、ヒキガエルがまた話し始めました。
「そういえば昔、ピンク色をしたカエルに会ったことがあったねえ」
「ピンク色のカエル?」
「それはそれは、きれいな肌だったよ。ツルツルしたひふの表面が、しっとりした温かみをおびていてね。やさしく灯るろうそくの明かりみたいな色だった」
ハルタはだまって、話に耳をかたむけました。
「ピンク色になれば、冬眠している間、ずっと幸せな夢に守られるって、そのカエルが話していたよ」
(ピンク色になれば、こわい夢をみないですむのか)
みどり色の自分の肌を、ハルタは自慢に思っていました。でも今は…。ハルタはそのカエルをとてもうらやましいと思いました。自分のからだもピンク色であったなら、冬を越えることができるだろうに。ハルタがだまりこんでいるのをみて、ヒキガエルがいいました。
「おまえさんも、なれるんだよ」
「え、何になれるの?」
「ピンク色のカエルにさ」
「どうやって?」
おどろいたハルタが大きな声を出すと、年よりカエルはクックックとわらいました。
「川むこうに住んでいる人間にたのめばいいと聞いたよ。変わり者のじいさんだという話だったけどね」
人間。ハルタはみぶるいしました。自分たちをねらう敵よりも、もっとおそろしい人間。たった一匹で人間にちかづいて、ピンク色のカエルにしてほしいとお願いすることができるだろうか、こんな弱虫の自分に。臆病者の自分に。
「おばあさんも、ピンク色にしてもらいに行くの?」
ハルタがたずねると、今度こそ可笑しくてたまらないという風に、ヒキガエルはわらいました。
「あたしゃ、この目でもう何回も満開のさくらを見たよ。十分に楽しませてもらった。こっちは、もうそろそろ神様によばれるのを待っているのさ」
ヒキガエルはそういって、去っていきました。
ハルタは顔を上げ、目の前のさくらの木を見上げました。ほそい枝をのばし、じっと春を待つその姿は、力づよい何かをうちに秘めているようでした。ハルタはさくらの木にとびつきました。木肌にふれていると、ハルタの心にお母さんが話してくれた言葉がよみがえってきました。
「この木はね、何百年も生きている長寿のさくらなのよ。春になると、数えきれないほどの花を咲かせてね、青い空に浮かぶピンク色の花たちが、ほんとうにきれいなの」
あきらめかけていたハルタの心に、かすかな希望の灯りがともり始めました。
(おいら、この目でさくらの花を見たい。母ちゃんの分まで)
じっと木にしがみついたまま、ハルタの心臓がドクンドクンと音をたてました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。サポートしていただけるなら、執筆費用に充てさせていただきます。皆さまの応援が励みになります。宜しくお願いいたします。
