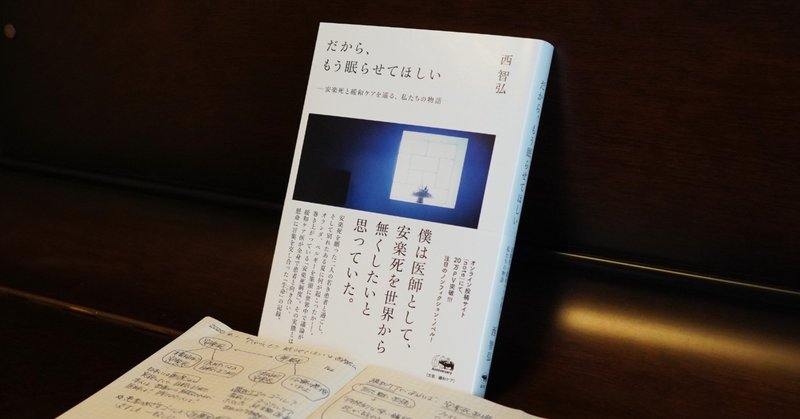
だから、その時がきたら、どうか私を眠らせてほしい。
死にたいと思ったことが、あるだろうか?
私はある。
1度や2度ではない。
こどもの頃のそれは、甘い誘惑だった。
「死ねば、もう悩まないで済む」
「明日の朝、目が覚めなければいいのに」
父は、それを「逃げ」だと言った。
逃げたいんじゃない。負けたんじゃない。
つらい毎日を終わらせたいだけだ。
友は、それを「残される人への復讐」だと言った。
復讐・・・復讐? そうかもしれない。
期待を裏切られて。悔しくて。苦しくて。
死ねば、その苦しみに気付いてもらえるような気がしたのかもしれない。
友のその言葉を聞いた瞬間、死にたい=私は誰に復讐したかったんだろうか?という新たな思考回路が開通した。
その思考回路を通ってしまうたび、いつも思うのだ。
やっぱり終わらせたいだけだ。誰かに復讐したいわけじゃない。
でも、自死を選べば、私の身近にいた人たちを、苦しめることになるのだろう。
「最後に話した言葉は」、「別れたときの表情は」、「なぜ気付かなかったのか」、「もっと話を聞いていれば」・・・身近な人が亡くなったとき、誰のときでも感じたことだ。
もしも、それが自死だったとしたら。
後悔以外の何物でもなくなるだろう。
人は、多かれ少なかれ人とのつながりのなかで生きている。
自死を選ぶということは、“そのつながりを自ら断つこと”も含めて選んだように、他者からは見えてしまうだろう。そうなれば、自分にはそのつもりがなくても、身近な人たちに復讐したのと同じことになってしまう。
残念ながら、自分の人生を、生命を、肉体を、流れ星が燃え尽きて宇宙の彼方に消えていくようにシューッと消すことなんてできないのだ。
魂の抜けた肉体は消しゴムでは消せないし、私の人生のかけらは関わった人の記憶の片隅を漂い続ける。おそらくは、思い出したくもない苦い後悔とともに。
友のその言葉は正直きつかったし、正しくはないかもしれないけれど、結果、私の死にたい願望を押しとどめ、私の足を地面に留め置いているのだから、案外いい言葉なのかもしれない。
今、死ななくても、どうせいつか死ぬ。
“死ぬわけではないけれど痛くてつらい”病をいくつか経験し、人生の折り返し地点を過ぎて、そう思うくらいには図太くなった。
決してネガティブではなく、ポジティブな意味で。
そんな折に出会った、この本。
緩和ケア医 西智弘氏の、noteでの連載が書籍化されたものだ。
noteで書き始める前から気になって、マガジンをフォローして読んでいた。
気になった理由は3つある。
➀自分が病気・老衰で死ぬときに傍らにいてほしい人と、何度となくこのテーマについて話してきたから。
どちらかといえば、安楽死ではなく、延命治療の拒否や緩和ケアについてだったけれど。
➁ともに70歳でがん患者となった両親が、抗がん剤治療を明確に拒否していたから。
ちなみに、ふたりは薬剤師で、父は抗がん剤を数多く開発している大手製薬会社のMRだったし、母は調剤薬局で日頃から多くのがん患者に服薬指導をしている。患者が抱えるがんという病と、抗がん剤が患者の病態とQOLに与える影響に、それぞれの立場から向き合ってきた医療者だ。
➂このマガジンに登場する2名の患者のうちのひとり、吉田ユカが“死にたい”過去をかかえたがん患者だったから。
内容については、できるだけ多くの方に読んでいただきたいので、ここでは多くは触れないが、概要を少しだけ。
西先生はこの本のなかで、安楽死を望んだ2名の患者との関わり、そして信頼できる看護師との意見交換と、それぞれの抱える苦悩・葛藤を描いている。
また、安楽死の意志を表明しながら精力的に活動を続けている写真家の幡野広志氏をはじめ、ジャーナリスト・精神科医・緩和ケア医にインタビューを試みながら、安楽死と尊厳死の違い、患者を社会との関わりのなかでとらえていく社会的処方という考え方、緩和ケアの最終段階である“持続的な深い鎮静”の条件、患者と医療の間の家族という存在などについて、解りやすい言葉で語っている。

刊行された本を手に取り、改めて最初から読んだのは、8月に入ってすぐの週末。
折しもその少し前に、京都のALS患者の安楽死に関わったとして、2名の医師が嘱託殺人の容疑で逮捕され、大きく報道されたところだった。
この本を、休憩をはさみつつ4時間ほどで読み終えたとき、私の胸のうちを占めていたのは、感想ではなく3つの疑問だった。
医療の力を借りて、死期まで眠って過ごすことを許されるほどの“耐え難い苦痛”とは、どのような状態を指すのか?
誰のために、“安楽死”または“持続的な深い鎮静”を選ぶのか?
誰のための医療なのか?
頭のなかでぐるぐる考えたって、答えは出ない。
当たり前だ。
私は、まだ当事者じゃないのだから。
それでも考え続けていると、その3つの疑問が不意に小さくなった。
私にとっての“耐え難い苦痛”って、どんな状態なんだろう?
もしも未来の日本に安楽死制度があったとしたら、私は利用するだろうか?
もしもこの2人のような末期のがん患者だったとしたら、私は何を選ぶだろう?

問いが手の平サイズになったところで、簡単になったわけではない。
その時がくるまでに考えは変わるかもしれないけれど、今の自分の感覚をここへ記しておこうと思う。
私にとっての“耐え難い苦痛”の最たるものは、本の中の吉田ユカと同じだ。
排泄のコントロールが出来なかったり、自力でトイレに行けなくなること。
導尿用のカテーテルはつけたくないし、硬くなった便を掻き出されるのもイヤだ。
でも、それだけではない。
痛みのコントロールが困難になってきたとき。
そして、脳をがん細胞や薬に侵されてコミュニケーションの質がネガティブに変化していったり、身近な人たちの顔が判らなくなったりしたときも。
でも、残念ながら、その時には自分からそれを“耐え難い苦痛”だと伝えることができるかどうか、わからない。
この物語の中には、吉田ユカの“持続的な深い鎮静”を開始するための条件について、カンファレンスでスタッフの意見が食い違うケースが描かれている。
“自分の理想の最期”を考えたとき、その“条件”が一番ネックなのだと感じた。
患者それぞれで異なるだろう“耐え難い苦痛”を、医療スタッフと私を見送る側の人たちが“私にとって耐え難い苦痛”だと認めてくれるかどうか。
これには、西先生が細やかに心を配られたように、そこへ至るまでの深い話し合いと相互理解が不可欠で、どちらも、とても一朝一夕に成し得るようなことではない。
周囲の人や医療スタッフとの対話、そして、自分の意思を積極的に伝えようとする姿勢の大切さが身にしみた。
もしも、日本に安楽死制度があったとして、私が安楽死を選ぶとしたら、それは自分の美意識のためだろう。
排泄のコントロールが出来なかったり、自力でトイレに行けなくなったり、脳をがん細胞に侵されてコミュニケーションがネガティブに変化していく私の姿を、愛する人たちの目にさらしたくない。
そうなる前に、人生と生命の幕引きは自分で決めたい。
でも、本当にそれでいいのだろうか。
私が生命の終わりを決めることで、周りの人たちを傷つけはしないだろうか。
それが気になる。
私が“持続的な深い鎮静”を選ぶとしたら、それは愛する人たちと自分のためだ。
死期が来るまで眠り続けることで、「少しでも長く生きていてほしい」と願うだろう人たちの傍らに寄り添ってあげられる。話すことも手を握り返すことも肩を抱くこともできないけれど。
今まで祖父母・友人・同僚・・・大切な人を何人も見送ってきた経験から、見送る側にとって、少しずつ諦めて、徐々にお別れをしていくというプロセスは、とても意味のある時間だと思っている。
鎮静が始まって旅立つまでの、私が眠っている時間。
「うたちゃん、この部屋、暑くないかな」
「うたちゃんの爪、伸びてるから切っておいてあげよう」
「誰が会いにきてもいいように、眉毛、描き足しといてあげよう。いつも眉毛ないの気にしてたから」
「うたちゃん、よく眠ってるなぁ。もう苦しまなくて済むんだね」
「あーだこーだ言いながら一緒にごはん食べることは、もうないんだなぁ」
「あぁ・・・うたちゃんと、テレビや映画を見ながら笑ったり、歌ったり、話したりすることは、もうないんだなぁ」
「もう充分、苦しんだもんね。ここまで、よく頑張ったね。よく生きたね」
・・・そうやって、だんだん私と生きることを諦めて、私を手放して、私とお別れしていってほしい。
突然の不在は、残される側にはダメージが大き過ぎるから。

でも、それはあくまでも、私に大切な人たちがいる場合のことだ。
もしも、みんなが先に旅立ってしまって、ひとり残されていたとしたら・・・私は安楽死を選びたい。
どちらかを選べるように、その時までに制度ができていたらうれしい。
その時、私が孤独のなかにいたのなら、苦痛の終わりが生命と人生の終わりで、ちょうどいい。
結局、人とのつながりの中で、私は生かされているのだ。
じっくりと「どのように死にたいか」を見つめ続けたら、いつの間にか「どのように生きたいか」を考えていたことに気付く。
私が死にゆくときに、大切な人たちが諦めていくだろうと考えた行為。
「相手がどうだったら心地良いか考えて、世話をやくこと」
「あーだこーだ言いながら一緒にごはん食べること」
「テレビや映画を見ながら笑ったり、歌ったり、話すこと」
言葉にすると、何でもないこと。
「何でもないようなことが 幸せだったと思う」と昔、誰かが歌っていたけれど、その「何でもないようなこと」を大切に生きたいと、改めて気付かされた。
きっと何度でも忘れてしまうだろうから、何度でも読み返して気付き直そうと思う。
そして、大切な人たちと生きる私の人生を、私は愛そう。
だから、いつかその時がきたら。
どうか私を眠らせてほしい。

ここまで読んでくれたんですね! ありがとう!
