第25段 飛鳥川の淵瀬常ならぬ世にしあれば。
徒然なるままに、日暮らし、齧られたリンゴに向かいて云々。
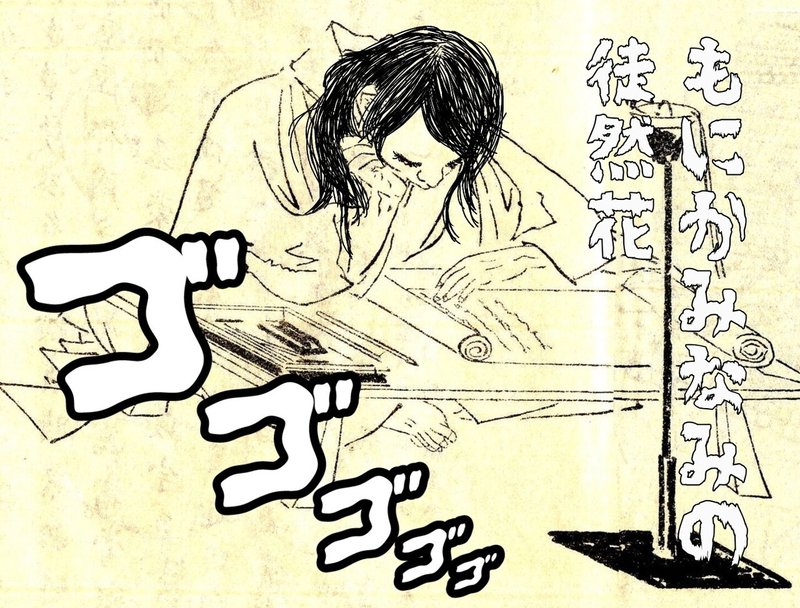
世の中には変わるものと変わらないものがあるという。小さい頃から見てきた街並みが、ふと気がつくと全く知らない風景になっていることがある。自分自身も気がつくとあっという間に変わっていて、それに付随して魂や心も変わっていってしまうのかと思うことさえある。仮に何かしらの理由で自分自身が傷ついて、しかしながら何とかしてそれを乗り越えることで強くなり、そうして再び同じような目にあった時にはうまくその事態をかわすことができるようになったとしても、その瞬間は嬉しくもあるがどこか淋しいようなところもあるような気がしてならない。人間という生き物は常に変化を求め、そして実際には変化そのものを非常に恐れるものだ。私の人生は絵を描くところから始まった。絵を描き、言いたいことを言ってきた。特段言葉が得意という体質ではないため、言葉以上に伝えたいことは総て絵を描くことで伝えてきた。油絵を専門とし、100号サイズの巨大な絵を長年描き続けていたが、ある日を境にぱったりと遠ざかった。理由はいろいろあるが、ダンスをはじめたことは大きな理由の一つだと言っても過言ではない。その頃のわたしは絵の中に「こうなりたい」という女性像を描いていた。キャンバスのなかに憧れの美女を描くことで己の鏡として現実を錯覚していたのだ。だがある日、ひょんなことから実際にその女性になることができる方法を見つけた。それが、ベリーダンスだった。ベリーダンスを踊っている時の自分はまさに、「こうなりたい」女性そのものだった。そのためか、実質、絵を描くということは自分には必要のない行為へと成り下がってしまったのだ。絵を描いているとき、わたしの性別は両性になる。女にもなるし、男にもなる。ある意味そこまで気にしなくていいので楽といえば楽だ。だか同時に、絵は闇という闇に引きずり込まれる感覚がある。闇の最果て、というものが実際にあるとしたならばそこにたどり着くと言ってもいいだろう。それは手触りも何もない世界、ブラックホールに近い。浮力もなければ重力もない世界。そこで永遠にさまよい続けることになる。わかりやすく言えば、自分自身がどこか絵のなかに閉じ込められていくような感覚がどこまでも続くといってもいいのかも知れない。だからなのか、昔から「絵を描いていて楽しい」と言える人が羨ましかった。もちろん根本では自分もそうだ。絵を描くことが好きで、楽しい。だが、あまりにも闇の期間がきつすぎると素直にそれを言えなくなる。じゃあ描かなければいいと思うかも知れないがそれは違う。描くことで生きている。描くことで生き延びることができる。描かないと息を吸うことができない、呼吸ができないのだ。だからこそ美大時代は時として地獄だった。辛すぎてとなりのパフォーマンス学科の人たちとよくつるんでいた。女優の卵や俳優の息子、芸人志望の子やダンサーの子達と一緒にいるほうがずっと気楽だった。あれはある意味で現実逃避の一つだったのだろうと思う。あまりにも彼らとつるみすぎて、教授ですらわたしがパフォーマンス学科の人間だと思い込んでいた。試験のためだといって演技クラスの補講にぶちこまれたこともある。いま思えばとても楽しくエキサイティングな時間だった。6号館でうつうつとデッサンをしているよりもずっとずっと、有意義で楽しい時間だった。30を境にまた再び絵を描く生活をするようになるだろう、という予感があった。現にそうなっている。体調を崩し少しずつ復活していく過程で、絵を描いている友人や知り合いが増えた。漫画家の先生、擬人化や星詠みをしながら絵を描く人など、実に様々な人たちが今周りにいる。そして不思議なことに、絵を描いて欲しいと言われる機会も増えた。今更自分に何が描けるだろうかと不安になることもあったが、実際に描いてみたことによって過去の自分のトラウマのようなものに終止符を打つことができた。絵を描いている友人の一人に過去の作品を見てもらった。私は彼女に絵を見てもらいたい、という欲求がある。それは彼女の描く絵が好きだからという理由と、彼女の感性が好きで絶対の信頼を置いているということもある。彼女は私の絵を見てこう言った。『何やらこの絵からは、執念を感じる。線の一本一本、あと黒く塗っているところもベタ塗りでなく線で描いているところがすごい。』とても嬉しかった。ああ、私の芸術は『執念』なんだと思った。執念と聞くとおどろおどろしい感じも受けるが、私にはなんだか勲章のようにその言葉が響いた。絵を描くということは、決まった画角の中で総てを終わらせなければならない。本来はどこまでも広がっている白い紙の上でどこまでも続く線を引いていたい気持ちにかられる。だが実際には紙には限りがある。地球上に埋め尽くされた白い紙の上に永遠に絵を描くことは物理的には難しい。だからこそ、決められた大きさの中でいかにそれ以上のものを表現するかという話になる。だからこそ決断力や冒険心も必要になってくる。小難しい話はたくさんあるが、一番大切なのは夢中になることだ。夢中でそれを描くことができるか。気が狂うほどその絵に熱中できるのか、その熱意こそが筆先に乗り、そして紙に乗る。ある意味で口寄せにも近い行為だと思うのだが、シャッターを切る代わりにペンやインクで遺すという感覚はやはりそう大して違いはないように思う。やはり見えないものを見て、それを見える形に遺す、それが私のこの世界での役割であり、そしてあなたと私で、ということがより確固たるものになっているような気がする。絵も写真も、そしてダンスも、結局行き着く先は『抱き合い心中』なのだ。私は何も変わらない。3歳の頃から変わらない。いつまでも芸術家でいつまでもブックマンだ。歴史の傍観者であり、体は常に空っぽで、目の前のあなたのことを全身全霊で感じ切る。そして形にする命なのだ。時を経ても変わらないもの、三つ子の魂百までとはよく言ったものだ。話を少し戻すが、私はこれから先三つの顔を持つことになるだろう。一つは踊り子としての顔。もう一つは写真家としての顔。そしてもう一つは、原点である絵描きとしての顔だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
