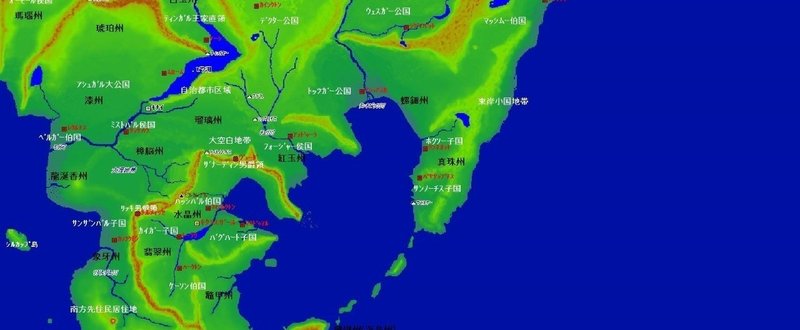
ティルドラス公は本日も多忙② 新伯爵は前途多難(31)
第六章 略奪の許可(その5)
『バーズモンが作ってくれた食事がなつかしい。』
即位前、魔の森・シュマイナスタイにあるアーネイラの岩屋で食べた食事。あの時は父・フィドル伯爵の喪中ということで酒にも生臭物にも手は出さなかったものの、作りたての温かい料理が食べられるのはそれだけで嬉しかった。朝食に食べた汁かけ飯――漬け物の汁や野菜の煮汁の残り、温め直した羮などを前日の冷や飯にかけた、ミスカムシルの庶民の一般的な食事――も、生まれて初めて口にしたが、大変に美味かったと思う。
だから、ネビルクトンに戻ってから、宮廷の食事でも汁かけ飯を出してくれるよう膳部係に頼んだ時、相手が示した反応には正直戸惑った。膳部係が言うには、汁かけ飯など「卑しき田夫野人が食す卑しき食物」であり、そんな物を口にするなど「伯爵家の恥であり、王家や他の諸侯に対して顔向けができない」という。後からチノーに聞いたところでは、彼にそんな物を食べさせたということで、バーズモンまでが、わざわざ兵営から大膳官の役所まで呼びつけられて大目玉を喰らったという。以来ティルドラスは、食べたい物についてうっかり口に出せずにいる。
冷えてまずくなった食事をぼそぼそと食べ、箸を置いて席を立つと、ただちに給仕たちが食卓に駆け寄り、半分以上食べ残した膳部を恭(うやうや)しく捧げ持ちながら去っていく。ここでも、残り物は残り物で、どこかで誰かの役得となるような仕組みができており、半分は食べ残すようにという暗黙の決まりがあるのだ。聞くところによると、食事を食べ残さないばかりに台所の者から恨まれて料理に毒を入れられた君主も他国にいたというから、馬鹿馬鹿しいと笑ってばかりもいられない。「伯爵、ご退室ぅぅ。」背後で響く式部官の声。日がな一日、ティルドラスの一挙手一投足を周囲に報せるだけのあんな仕事をさせられて、彼は人生が楽しいのだろうか。
午後からは、あちこちから届いた書簡や報告書類に目を通し、返事を書いたり決裁を行ったりする時間となる。例によって些末な内容で言葉ばかりが仰々しい文書の束に一通り目を通したあと、ティルドラスは一昨日届いた二通の書状を取り出す。
片方は、ユニが公式の経路を通じて送ってきたものだった。今回のバグハート家との戦いの経緯についての報告書だが、文章の半分以上はリーボックの不遜と独断専行を訴える内容で占められていた。功を頼んで将軍の命に服さず、逆に指図めいたことさえ口にすること。接収した兵糧を勝手に占領地の住民に配ったこと。バグハート家の降兵を自身の配下に組み入れて私兵のように扱い、軍中の取締りの権限さえ与えていること。あまつさえ、伯爵自身から命令を受けていると称して兵士の略奪を妨害し、軍中に軋轢を生んでいること……。
もう片方は、リーボックが腹心の部下に持たせて密かに送ってきたものだった。ツクシュナップは占領したものの、エッフェナー将軍が兵士たちの声に押されて街の略奪を許可してしまった。捕虜のバグハート兵たちの力を借りて略奪を阻止し、さらに伯爵から取り締まりの権限を与えられていると将軍を言いくるめて今のところ食い止めているが、デューシン将軍の援軍が到着すれば、もはや自分の力では如何(いかん)ともしがたい。略奪の禁止に不満を抱く者たちが私を闇討ちして排除することを考えている節もある。ここは伯爵自らの出陣を仰ぎ、軍の抑えとなっていただきたい……
「ふむ。」ティルドラスの表情が険しくなる。それは、普段彼が人前で見せる柔和で呑気な表情とは違う、厳しく鋭い顔つきだった。
実はこの書状を受け取った直後、書状の存在は伏せたまま、彼自ら軍を率いてバグハート領に向かうことをサフィアに申し出たものの、一言のもとに撥ねつけられる。
「三日後に、デューシン将軍が兵を率いてネビルクトンを進発いたします。わざわざ伯爵ご自身が出陣なさらずとも、将軍にお任せいただければ事足りましょう。」
そのデューシンにお任せしたくないから自身が出陣するのだ、などとは、むろん口にできない。かといってこのまま手をこまねいているわけにも行かない。少し考え込んだあと、ティルドラスはチノーを呼び寄せ、書状の内容について相談する。
「気になるのは、リーボックの闇討ちを企む者たちがいるらしいことだ。何らかの手を打たねばならぬ。」難しい顔で書状に目を通すチノーに、ティルドラスは言った。
「リーボックどののもとに密かに忍びの者を送り、護衛に当たらせることができればよろしいのでしょうが……。しかし、我らが命令を下せる者がおりませぬ。」とチノー。
現在、ティルドラスが自身の判断で使える忍びの者は一人もいない。むろん、彼の周囲で護衛の任に当たる忍びはいるものの、伯爵家お抱え忍群の指揮権は全てサフィアが掌握しており、彼が直接命令を下すことは許されていなかった。
「いや、二人いる。」
「どこに左様な者が……。」
「これから行く。少し待て。」そう言うと、ティルドラスは机の上で何かの書類を二枚、手早くしたため始めた。内容を読み返して公印を押し、「ついてくるが良い。」とチノーに声をかけると、彼は書類を手に、足早に部屋を後にする。
二人が向かったのは、宮殿の一角に設けられた牢獄の建物だった。門衛の役人に扉を開けさせ、先導の牢番が掲げるランタンの灯りを頼りに、彼らは牢獄の地下、重罪人たちが収監されている場所へと階段を下りていく。
「ティルドラスさま、」驚いたように声を上げるチノー。「まさか――、」
「まさかも何も、他におるまい。」とティルドラス。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
