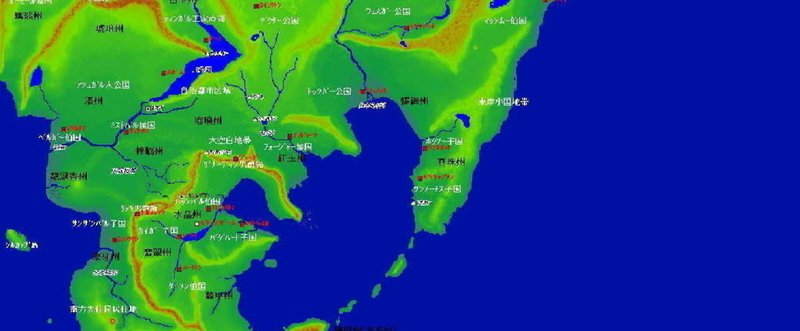
ティルドラス公は本日も多忙② 新伯爵は前途多難(1)
第一章 宮廷の日々(その1)
春先に降り続いた長雨が嘘のように、ハッシバル伯国の国都・ネビルクトンでは、このところ乾いた暑い日々が続いていた。
来る日も来る日も、雲さえ希な快晴の空から太陽が灼けるように照りつける。道はからからに乾いて、少し風が吹けば猛烈な砂埃が立ち、道ばたの雑草も日に日に色つやを失ってしおれていく。春先には満々と水をたたえていた溜め池や川も、このところ急激に水位が下がってきており、領民の間では早くも旱魃への不安が囁かれ始めていた。
暑いのは伯爵家の宮殿も例外ではない。もともと「地相が良い。覇王の地である。」という占い師の言葉だけを根拠に、多大な労力を費やして低湿地を埋め立てた場所に建てられたネビルクトンの宮殿は、湿度が高い上、夏には地中から吹き出す沼気が立ちこめる。その悪臭を防ぐために窓を閉め切り、臭い消しに香を焚いたりするから、酷暑の盛りなど気が遠くなるほどの息苦しさである。
そんな暑苦しい宮殿の一室で、伯爵家の新当主・ティルドラス=ハッシバルは、それがさらに暑苦しくなるような話を聞かされていた。
「これはもう謀反に等しい罪と申せましょう。」分厚い書類の束を抱えて彼の前に立った法官が、口から泡を飛ばしながら力説する。「教化を破り、伯爵家への不忠を勧め、終(つい)には国を亡ぼさんとするもの。重罰に処し、今後の禍乱の根を絶つべきでございます。」
「………。」彼の言葉にティルドラスは眉根を寄せる。
ティルドラスへの反逆を企んだ陰謀家についての話ではない。キクラスザール近郊の小さな田舎町で逮捕され、ネビルクトンの監獄に繋がれている、どうと言うことのない田舎芝居の一座への処分についてである。罪状は伯爵家に対する不敬と誹謗。上演していた芝居の内容が法に触れるとのことだった。
物語の舞台はどことも知れない田舎の村、道楽者の大地主が世を去り、少々頭の足りない長男と乱暴者の次男が家督を巡って争う中、巻き添えを喰った使用人や小作人たちが大いに迷惑する――、というドタバタ喜劇だという。「この内容からして、先日の伯爵とダン公子との騒動を風刺したのは明らかでございます。」憤慨に堪えないといった面持ちで法官は息巻いてみせる。
「なぜ、そう思うのか。」
ティルドラスの言葉に法官はなぜか慌てた表情を見せたものの、「そればかりではございませぬ!」と、ごまかすように声を張り上げた。「劇中の言葉は下品、描かれております風俗は卑俗、忠孝の勧めも自己犠牲の麗しき物語もなく、ただ衆を惑わし世を乱すのみの、けしからぬ芝居でございます。」
セリフも、随所に伯爵家への当てこすりや批判が込められ、しかも、それがまた観客に大受けして大喝采を浴びているという。さらに物語の最後では、地主の遺体が川に落ちて死んだ飲んだくれのならず者の遺体と入れ替わってしまい、ならず者の遺体は豪奢な棺に収められて盛大な葬儀が行われ、一方の地主の遺体は棺代わりの空き樽に詰められて、町はずれでゴミと一緒に焼かれるのだった。
どの社会にも、権力者になり代わって不逞の輩を罰することに情熱を傾ける忠義の士がいるものである。そうした手合いの一人がたまたまこの芝居を目にし、あまりのけしからぬ内容に驚いてただちに当局に注進、捕り手が一座を残らず逮捕した。事は伯爵家の体面にも関わるということで、逮捕された者たちは国事犯扱いで国都に護送され、座長から端役の少年までが厳しい尋問にかけられた末、ティルドラス自身による裁可が求められたのである。
「芝居は座長のマリオン=ホッホバルが書いたものでございますので、この者は市中引き回しの上梟首(きょうしゅ。さらしくび)の刑。ほかに主立った者三人を、二度と舞台に立てぬよう鼻削ぎの刑に処し、余の者は棒打ち二十の上、全て国外追放としてはいかがでございましょう。何とぞご裁可を。」言い終わって、法官は深々と頭を下げた姿勢のまま、ティルドラスの「よし」の一言を待つ。裁可が下りると同時に、けしからぬ芝居を書いた座長が刑場へと送られる手はずが、すでに整っているのだろう。
だが、ティルドラスは首を横に振った。「いや、処罰の必要はない。不問に処す。全員釈放せよ。」
「しかし――」法官は目を見張る。「しかし、これは伯爵ご自身を貶(おとし)め、伯爵家の威徳を傷つけるもの。かような振る舞いを野放しにしては、伯爵家の権威が――。」
「良い。」ティルドラスは繰り返す。「そもそも、たかが一編の芝居で権威や威徳が傷つくというのは、芝居に非があるのではなく、おそらく国を治める者の行いに至らぬところがあるのだ。役者たちに罪はない。ただちに釈放せよ。」
「では、せめて、この芝居の上演を禁ずるべきかと存じます。」法官はなおも食い下がる。「脚本は全て取り上げて焼き捨て、一座の者たちをきつく叱り置いた上で、この度だけはお情けを以て召し放つ旨を説き聞かせれば、役者どもも伯爵の威光と恩徳に感じ入り、二度とかような怪しからぬ振る舞いはせぬかと……。」
「その必要はない。」ティルドラスはうんざりした表情になる。「今後は、芝居や物語や絵草紙のことで役者や戯作者を罪に問うたりせず、むしろ盗賊の害や商人の不正を除くことに力を入れるよう、各地の官吏に周知させよ。」
「……御意のままに。」不承不承頭を下げたものの、法官は不満げだった。自分の努力を無にされたように感じたのだろうか。
「脚本の写しは残していってほしい。なかなか面白そうだ。少し読んでみたいと思う。」
「……かしこまりました。」いったい何を考えているのか、と言わんばかりの表情で、顔をしかめ頭を振りながら法官は退出していった。伯爵家の権威だの尊厳だの言っているが、どうやら彼自身はティルドラスに対して、権威も尊敬の念もあまり感じてくれてはいないらしい。ティルドラスはため息をつく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
