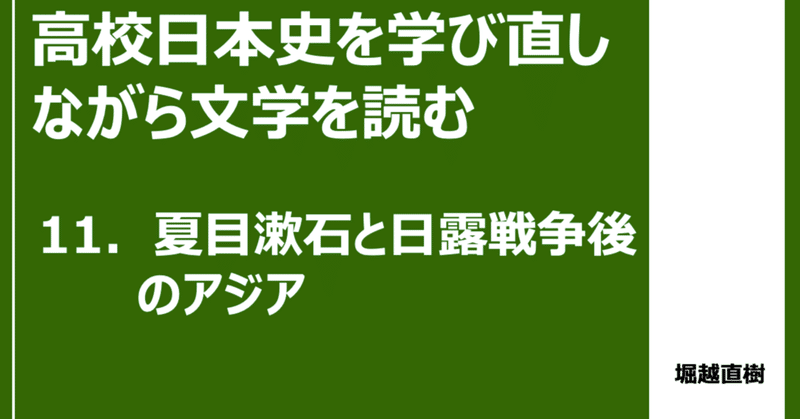
夏目漱石と日露戦争後のアジア【高校日本史を学び直しながら文学を読む11】
前回の森鷗外に続き,今回は夏目漱石です。日本を代表する文豪とされる人が続きます。夏目漱石はこれまで様々な角度から研究されていますので,僕の方から新説を出すようなことはできませんが,高校レベルのわかりやすい日本史とともに夏目漱石を読んでいくことには意義があるのではないかと思っています。夏目漱石の小説・評論・随筆・紀行文・書簡などの一部分だけを切り取ると,植民地主義者として描くことも,反戦平和主義者として描くことも可能になってしまうので,我田引水的な切り取り方にならないように気をつけたいと思います。できる限りいろいろなものに目を通した上で,その中のいくつかを紹介しながら夏目漱石という人物について考察する流れをつくれればと考えています。
そうは言っても,人間は無色透明な存在ではないので,完全中立的な立場での読解はできないものです。僕の立ち位置をはっきりさせておくと,夏目漱石はかなり好きです。10代のときは太宰治が大好きで,自己肯定感が低く多感な時期であることも手伝って『人間失格』の雰囲気に引き込まれたり,『駆け込み訴え』のリズム感に「天才っているんだな」と感じたりしていました。太宰治は今も変わらず好きですが,夏目漱石は年を重ねるたびにじわじわと好きになっていった人です。そのため,少しひいき目な見方になってしまう可能性はありますが,先ほども述べたように,我田引水的な切り取り方をするだけの内容にはならないように注意していきます。
1904年,日露戦争が始まった直後,日本は韓国に日韓議定書を強要しました。日露戦争を有利に戦うため,韓国内での軍事行動の自由を認めさせたのです。日露戦争後に韓国併合への動きが始まったのではなく,日露戦争開戦直後に内政干渉が始まっていたという事実は重要です。さらに,日露戦争中に第1次日韓協約を結び,韓国の財政・外交に関して日本人顧問を採用させました。
ポーツマス条約締結後の1905年には第2次日韓協約を結びました。日本が韓国の外交を管理するために統監府が設置され,韓国は外交権を喪失しました。初代統監には伊藤博文が就任しています。韓国は自ら条約を締結することなどができなくなるので,主権がしっかり存在する国家と呼べる状態ではなくなり,日本の保護国という扱いになります。保護国というのは,形式上は独立国なのですが,宗主国が主権を奪っている状態のことです。「植民地」という言葉を使わないものの,事実上の支配下に近い状態と言ってしまってよいと思います。
日本が韓国を保護国化したことによって,日本の暴走が国際社会で非難されて孤立するのかというと,そうではなく,帝国主義国どうしの外交の流れの中で行われていました。1905年,桂・タフト協定によってアメリカのフィリピン統治と日本の韓国保護権を相互に承認し,第2次日英同盟によってイギリスのインド支配と日本の韓国保護権を相互に承認しました。つまり,日本はアメリカ・イギリスのお墨付きのもとで韓国を保護国化したわけです。この件はだからよいということでは決してなく,むしろ保護国や植民地になった側の立場で考えてみれば,許し難い行為ではないでしょうか。現地の人たちの了解も得ずに,他の国どうしが勝手にアジアのやまわけを認め合っているのです。
日本の動きに対し,韓国の皇帝である高宗はオランダのハーグで行われていた第2回万国平和会議に密使を送り,第2次日韓協約の無効を訴えようとしました(ハーグ密使事件)。しかし,日本と取り引きをしていたアメリカ・イギリスをはじめ,平和会議の参加国は密使に取り合おうとしませんでした。「平和」や「人権」などの言葉づかいをする国々が,その言葉の中には保護国・植民地の人々を含めていなかったのです。
高宗の動きに憤慨した日本政府は,高宗を退位させたうえで第3次日韓協約を結びました。韓国の内政権を掌握し,韓国軍を解散させるという内容です。韓国は主権の多くを日本に奪われたことになり,ほぼ植民地状態です。これに対して韓国内では反対闘争がおこり,全国に広がりました。統監府は義兵運動を弾圧しますが,その中で韓国の民族主義者である安重根により伊藤博文が暗殺される事件がおこりました。伊藤は完全な植民地化を求めていたわけではなく,韓国にある程度の自治を認める構想を持っていました。しかし,日本政府は韓国の完全併合を構想し,伊藤はやむなく同意せざるを得ない状況でした。1910年に韓国併合条約が成立し,韓国は「日本領朝鮮」となります。伊藤の暗殺が韓国併合につながったかのような言説がありますが,それは誤りで,日本政府の予定通り韓国併合が断行されたと考えるのが妥当です。
日本は韓国併合に際して,列国に打診をしていました。アメリカ・イギリスをはじめ列国は反対表明をしませんでした。
統監府は朝鮮総督府と改められ,寺内正毅が陸軍大臣兼任で初代総督となりました。日本の統治は,全土に憲兵などの警察網をめぐらす軍事的性格の強いもので,典型的な武断政治(武力によって圧伏させる政治)でした。また,1910年から日本の地租改正にあたる土地調査事業を実施しています。土地所有権を確定させるための事業ですが,申告制をとったため,申告されない土地は国有地として没収し,多くの朝鮮農民が没落しました。
石川啄木は日露戦争を美化していましたが,その後は自己批判し,韓国併合に際しては若山牧水が主宰していた雑誌『創作』の1910年10月号で次のような歌を掲載しました。
地図の上朝鮮国にくろぐろと
墨をぬりつつ秋風を聴く
啄木が朝鮮の植民地化を嘆き悲しんでいることがうかがえます。しかし,当時の日本は全国の小学校で9月1日の始業式を利用して帝国版図の拡大を祝うという状況でした。
ポーツマス条約には,「旅順・大連の租借権,鉄道(東清鉄道南満洲支線)の長春以南の権利およびその付属利権をゆずる」という項目がありました。日本はこの内容を1905年に清に承認させています。しかし,満洲(中国東北部を指す旧称)に日本が進出しようとする中,アメリカも動いていました。「門戸開放」を唱えてきたアメリカは,満洲という市場をねらっていたからこそ,日露戦争とその講和条約締結の際に日本寄りの行動をとっていました。アメリカで鉄道王と呼ばれたハリマンが鉄道を共同経営したいと提案します。アメリカ側は日本が獲得した鉄道利権に入り込むことがねらいであり,日露戦争後に賠償金が得られなかった日本としては鉄道を経営する資本力に乏しかったので,当時の日本の首相である桂太郎とハリマンが非公式ながら覚書を交わしました(桂・ハリマン協定)。ところがポーツマス条約締結後に帰国した外務大臣の小村寿太郎が,賠償金が得られなかったからこそ鉄道利権を日本が独占すべきであるとして猛烈に反対します。その結果,ハリマンとの約束は反故にされ,1906年に日本は単独で南満洲鉄道株式会社(満鉄)を設立します。
日本がアメリカの「門戸開放」要求に配慮せずに,南満洲権益を独占したことに対し,アメリカの反発が強くなっていきました。カリフォルニアは日系移民が多く,この時期には3万人~4万人に達していたと考えられていますが,日本人移民が差別を受けることが増えていきます。サンフランシスコ市では,公立学校で日本人の入学を拒否するような例もみられました。黄色人種への人種的偏見,黄禍論のアメリカへの波及,移民の安価な労働力で仕事が奪われるという危機意識などもあり,日本人移民排斥運動が高まっていきました。日米関係が緊張する中,日本は少し前まで戦争相手国だったロシアに接近していきます。南満洲での日本の権益,北満洲でのロシアの権益を,話し合いにより利害調整するようになり,1907年に第1次日露協約を結びました。その後,1909年にアメリカが「満洲鉄道中立化案」を提案しますが,日本はそれを拒否し,満洲からアメリカを排除するためにロシアとの関係を強化し,1910年に第2次日露協約を結んでいます。
ここまで日露戦争後に日本が大陸で膨張していく過程をみてきましたが,ここからは日露戦争に対するアジアの反応をみていきます。
日露戦争で日本が勝利すると,韓国の民衆の中にはそれを喜ぶ人もいました。帝国主義国の膨張とそれに対する抵抗を,白色人種と黄色人種というような人種の構図で整理してとらえていたことがその要因です。アジアの新興国であり黄色人種の国である日本が,大国ロシアに勝利したことを,アジアの希望のように受けとめたのでしょう。
インド独立後に初代首相となったネルーは,自伝において「アジアをヨーロッパへの隷属から救いだすことに思いを馳せた」と述べています。ベトナムの独立運動家ファン=ボイ=チャウは,フランスの植民地となったベトナムの独立のための人材を育成しようと日本への留学運動をはじめます。これはドンズー(東遊)運動と呼ばれます。また,1905年に清を打倒して共和制国家の樹立をめざす革命派の孫文が来日すると,歓迎大会がひらかれ,中国同盟会が東京で成立しました。
日露戦争での日本の勝利が他のアジアの人々を勇気づけたと言われることがよくあり,実際にそのようなことが確認できるわけですが,それでは日露戦争というのを「義戦(正義の戦争)」として語るべきでしょうか。
孫文ら革命派の動きに危機感をもった清政府は,運動をおさえるよう日本政府に求めました。ここで拒否をして,清とアメリカが接近するようなことは避けたいと考えた日本政府は革命派への抑圧を強めています。1907年に日仏協商が結ばれると,日本政府はベトナムからの留学生に国外退去を命じています。ファン=ボイ=チャウは,小村寿太郎にあてた手紙の中で次のように述べています。
私がひそかに思うのは,もしもアジアの黄色
人種がことごとくクオン・デ(追放されるベ
トナム人の皇族で留学生)のような心情を持
てば,数十年後には,必ずや欧米を併呑して
わが黄色人種の繁殖地となすことができるで
あろう。それに比べれば,征露の一役(日露
戦争のこと)などは,歴史上どれほどの価値
があるというのか。(中略)雄覇(覇権のあ
る強国),文明を自称する大日本帝国が,罪
なく功ある黄色人種の一皇族をあえて受け入
れず,白人種の気炎をはてしなく助長してい
る。悲しいことである。他方,我らすべての
東洋人には権利がない。由々しいことであ
る。
インドのネルーは著書の『父が子に語る世界歴史』において,日露戦争の結果は,日本が帝国主義グループの一員に加わったにすぎなかったと評しています。
安重根は伊藤博文暗殺事件後,獄中で「東洋平和論」を書き,日本・韓国・中国が連帯して東洋平和を守るべきであり,同じアジア人どうしでありながら隣国を侵害するならば,いずれ見放されるだろうという警句を残しています。しかし,日本はアジアの連帯を選択せず,帝国主義国としての行動を優先させるようになるのです。
日露戦争直後は刺激を受けたアジアの人々も,その後の日本に共感したわけではなく,冷静に日本の行動をみつめていました。
ここからは日露戦争後のアジアを意識しながら,夏目漱石をみていきたいと思います。戦勝国・征服者としてのおごりがみえる部分もあれば,冷静に社会をみつめる部分もあります。さらに,その後はどのような思想に至ったのか,また至らなかったのかをみていきます。
①『三四郎』
まず,『三四郎』を取り上げます。1908年に『朝日新聞』に連載された小説です。主人公の小川三四郎は,東京帝国大学に合格し,九州から上京します。三四郎は都会で様々なことを経験し,恋愛模様も描かれます。青春小説として,登場人物に感情移入しながら楽しみやすい小説ですが,登場人物を通じて日露戦争後の社会への批評もみられます。
三四郎は汽車の中で広田先生と同席し,知り合いになります。広田先生は「いくら日露戦争に勝って,一等国になっても駄目ですね」と言います。三四郎は「しかしこれからは日本も段々発展するでしょう」と弁護するのですが,それに対して広田先生は一言,「亡びるね」と言い放つのです。
国家主義や愛国心が高まり,「一等国」としての意識が広がっている時期に,社会を冷徹にみている広田先生は興味深い人物です。この広田先生の言葉には,漱石自身の考えが反映されているのかもしれません。
また,この小説には「ストレイシープ」という有名なキーワードがあります。三四郎がおもいをよせる里見美禰子が迷子の英訳としてこの言葉を三四郎に教え,それ以降,三四郎はこの言葉を意識するようになります。このキーワードは登場人物とその状況にあてはめて考えることはもちろんできますが,もっと大きな「日露戦争後の日本」というものにあてはめて考えるという読解の仕方も可能なのではないかと思います。
②『満韓ところどころ』
次に『満韓ところどころ』という紀行文をみていきます。夏目漱石は1909年,南満洲鉄道株式会社(満鉄)の第2代総裁になっていた旧友の中村是公という人物に招かれて,満洲と朝鮮を旅行しました。そのときの見聞をもとにして書かれたのが『満韓ところどころ』です。この紀行文は,あまり評判がよくありません。日本の対外政策への批判的な姿勢がみられず,漱石自身が差別表現を使っていたり,中国人・朝鮮人への蔑視をうかがわせる内容を書いていたりするのです。漱石らしい文学的な表現もあるのですが,そういう部分だけを引用して漱石を評価するようなことは避けたいと考えています。むしろ,ここでは漱石のファンが読みたくないような箇所をあえて引用します。
河岸の上には人がたくさん並んでいる。けれ
どもその大分は支那のクーリーで,一人見て
も汚ならしいが,二人寄ると猶見苦しい。斯
う沢山塊ると更に不体裁である。
これを見てもまだ無理やり好意的な解釈をしようとする人もいて,そのような人は,アジア人の力強い生活をユーモラスに描いている,などと評するわけですが,それはさすがに無理やりが過ぎるだろうと僕は思います。どう見ても,植民地主義がむき出しになった文章ではないでしょうか。また,この紀行文の中には「チャン」という中国人への蔑称も使用されています。前年に連載していた小説で広田先生を登場させた人物と同一人物なのかを疑ってしまうような紀行文です。ただ,僕はこの段階で漱石という人物の限界を論じようとは思いません。人間というのは変化することができます。このあとの漱石がこのまま変わらなかったのか,それともよい方向に変化できたのかどうかまでみていきたいと思います。
③書簡,「私の個人主義」,「点頭録」
第一次世界大戦勃発後の1914年10月17日の書簡を掲載します。清の湖北省の日本領事館にいた橋口貢に宛てた手紙です。
私の病気は例の胃です。一ケ月以上寝て昨今
漸く起きかけましたが,まだひよろひよろし
ます。筆を持つのも退儀です。私の装幀した
本を送らうと思ふが,もう少身体が丈夫にな
る迄待って下さい。今日は是だけしか書けま
せん。
戦争は悲惨です 以上
「戦争は悲惨です 以上」の部分は,水川隆夫『夏目漱石と戦争』(平凡社新書)の本の帯に大きく書かれたことで有名になりましたし,インパクトのある言葉です。これだけをみると,晩年の漱石は反戦平和主義者に変貌を遂げたのかと思ってしまいますが,他の書簡にも目を通せば,あまり好意的な解釈をし過ぎるわけにはいかないなと思わされます。8月25日の鬼村元成宛の書簡では,「戦争が始まりました。たまにはあんな事も経験のため好からうと思ひます。欧州のものどもは長い間戦争を知らずにゐますから」という,戦争に対して他人事の姿勢を示しています。
1914年11月,漱石は学習院の学生組織の依頼で,講演を行いました。この講演は,のちに「私の個人主義」と題されて有名になります。ここで漱石は「自己本位」の立場を表明します。自己本位というのは,自我の内面的要求に基づいて生きるという意味での個人主義のことです。さらに,講演では「自己の個性の発展を仕遂げようと思うならば,同時に他人の個性も尊重しなければならない」と述べています。自己本位とは,自己中心主義(エゴイズム)とは全く違うものです。エゴイズムは他人の犠牲をかえりみない独善的なものですが,自己本位は自己の個性はもちろん,他者の個性の発揮をもうながすものなのです。
漱石は1916年に亡くなりますが,その年に「点頭録」を発表して,第一次世界大戦と軍国主義について論じています。
独逸は当初の予期に反して頗る強い。聯合軍
に対してこれほど持ち応えようとは誰しも思
っていなかった位に強い。すると勝負の上に
於て,所謂軍国主義なるものの価値は,もう
大分世界各国に認められたと云わなければな
らない。そうして向後独逸が成功を収めれば
収めるほど,この価値は漸々高まる丈であ
る。英吉利のように個人の自由を重んずる国
が,強制徴兵案を議会に提出するのみなら
ず,それが百五対四百三の大多数を以て第一
読会を通過したのを見ても,その消息はよく
窺われるだろう。
漱石は「個人主義」と「国家主義」は共存できるものと考えていた人物であり,リベラル的な要素と保守的な要素の両方を持っていた人物だと思いますが,「強制徴兵制」をともなう「軍国主義」は個人主義を破壊するものと考え,絶対に許せなかったのです。漱石は学生時代から軍隊式の体操を拒絶し,徴兵制への嫌悪は一貫していました。
④『こころ』
最後に『こころ』についてみていきます。1912年,明治天皇の死によって明治という時代が終わりました。その後,国民から人気のあった軍人の乃木希典が殉死をします。つまり,前近代の武士のように主君の後追い自殺をしたわけです。漱石は1914年に新聞で『こころ』の連載を始めます。
すると夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になり
ました。その時私は明治の精神が天皇に始ま
って天皇に終わったような気がしました。最
も強く明治の影響を受けた私どもが,その後
に生き残っているのは必竟時勢遅れだという
感じが烈しく私の胸を打ちました。(中略)
それから約一ヶ月ほど経ちました。御大葬の
夜私は何時もの通り書斎に坐って,相図の号
砲を聞きました。私にはそれが明治が永久に
去った報知の如く聞こえました。後で考える
と,それが乃木大将の永久に去った報知にも
なっていたのです。
『こころ』は,明治なかばに大学を卒業した「先生」と,明治天皇の最後の「行幸」となった帝国大学の卒業式に列席した「私」との交流,という構成をとっています。つまり,明治時代を生きた「先生」が,大正時代の新しい社会に飛び立とうとしている青年の「私」に対して,明治人のこころを語り聞かせる話です。
「先生」は,かつて親友K(KoreaまたはKoreanの含意ではないかという説があります)を裏切り,死に追いやった過去を引きずっています。罪悪感にさいなまれて生きる「先生」は,自分を慕ってくる「私」に,こころの底に沈めてきた過去をあらいざらい書き綴った遺書を残します。そして「明治の精神」に殉死することを決意するわけです。
「先生」の「明治の精神」については様々な解釈がなされています。乃木将軍こそが理想の国家の体現であると漱石が考えて,それを「明治の精神」という言葉で表現したのではないかと考える人もいれば,儒教精神・武士道精神などが残っている「明治の精神」を乗り越えていくべきだと漱石が考えていたのではないかという解釈もあります。
僕は,『こころ』の連載と「私の個人主義」の講演が同じ年だったことを重視して考え,「明治の精神」とは,日露戦争後に日本人の間で増幅した「エゴイズム」であり,それは「個人主義」が乗り越えていかなければならないものとして漱石が考えていたのではないかと思っています。「先生」も,そして作者の漱石自身も,自分自身が醜いエゴイズムを内在させてきた存在だと気づいていたのではないでしょうか。だからこそ,そのような醜いものは明治時代で終わらせ,新しい時代に受け継がないでほしいと考えたのではないでしょうか。ただし,「先生」は死を選びますが,漱石は次の大正時代を生きているので,完全に「先生」と漱石を同一視するわけにはいきません。漱石には,新しい時代を新しい価値観で生きるよう望まれている「私」も含まれるはずです。
僕はこれまで何度も『こころ』を読み返してきました。その度にこころが苦しくなります。現代の僕たちは,「明治の精神」を乗り越えてよりよい時代を築けているでしょうか。自己正当化よりも、自己批判のできる国になっているでしょうか。むしろ醜いエゴイズムの時代に回帰しているような気がしてしまうのです。だからこそ,この作品は現代でも読み継がれていく価値のあるものであり,僕は今後もこの作品を読み返していくのだと思います。
主要参考文献
・夏目漱石『三四郎』(岩波文庫)
・夏目漱石『こころ』(岩波文庫)
・三好行雄編『漱石文明論集』(岩波文庫)
・三好行雄編『漱石書簡集』(岩波文庫)
・藤井淑禎編『漱石紀行文集』(岩波文庫)
・『漱石全集 第十六巻』(岩波書店)
・『漱石全集 第二十四巻』(岩波書店)
・久保田正文編『啄木歌集』(岩波文庫)
・高校教科書『日本史探究』(実教出版)
・原田敬一『日清・日露戦争』(シリーズ日本近現代史③ 岩波新書)
・小林和幸編『明治史講義【テーマ篇】』(ちくま新書)
・原朗『日清・日露戦争をどう見るか』(NHK出版新書)
・飯塚一幸『日清・日露戦争と帝国日本』(日本近代の歴史3 吉川弘文館)
・伊勢弘志『明日のための近代史』(芙蓉書房出版)
・海野福寿『韓国併合史の研究』(岩波書店)
・趙景達『近代朝鮮と日本』(岩波新書)
・岩崎育夫『近代アジアの啓蒙思想家』(講談社選書メチエ)
・ネルー『父が子に語る世界歴史4』(みすず書房)
・十川信介『夏目漱石』(岩波新書)
・小森陽一『漱石を読みなおす』(岩波現代文庫)
・柄谷行人『新版 漱石論集成』(岩波現代文庫)
・姜尚中『姜尚中と読む夏目漱石』(岩波ジュニア新書)
・水川隆夫『夏目漱石と戦争』(平凡社新書)
・小森陽一『戦争の時代と夏目漱石』(かもがわ出版)
・石原千秋編『夏目漱石『こころ』をどう読むか』(河出書房出版)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
