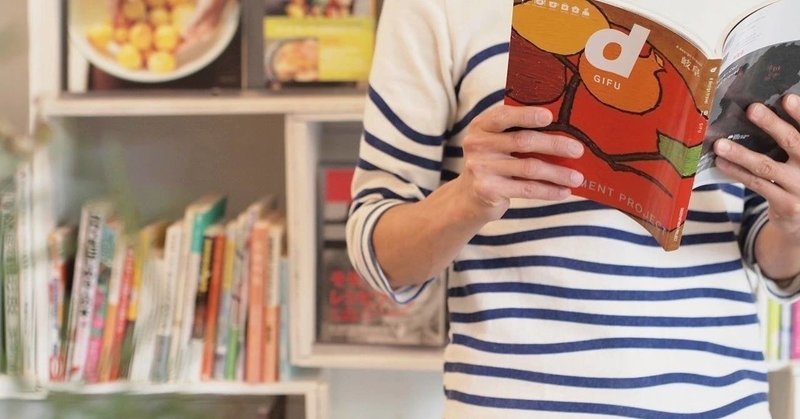
2020年8月に読んだ書籍一覧📚
📚世界的優良企業の実例に学ぶ 「あなたの知らない」マーケティング大原則[足立 光・土合 朋宏]
いわゆる○○マーケティングのような局所的なものではなく、大局観としての全方位的・本質的なマーケティングを足立さんと土合さんが共著で書かれた本です。
冒頭には「困った時にすぐ使える本」と書かれているように、とても体系的にまとめられており、常に手元に置き、「こんな時はどうしよう?」という疑問が湧いたら参照する、という逆引き辞書的に使うのが良いと思います。
本書は「起承承承」型の4部構成になっており、Part1=マーケティングの基礎、Part2=4Pのうちのprice,product,placeの3つ、Part3=promotion、Part4=販促やその他活動、という内訳になっています。
冒頭に「最初から最後まで順番に通して読む必要は無く、必要な部分だけ困っている部分だけを抜き読みしてください。」と、書かれているように、すでに何らかの形でマーケティングに関わっている方はPart2以降から読み進めた方が手っ取り早いですね。
また、18まである各章それぞれの最後に『絶対原則』という「まとめ」が1ページで載っているので、まずは『絶対原則』を読んでからその章を読む、を繰り返していくと理解が早いと思います。
また、各所に名だたるマーケターの方との対談も載っているのですが、元スマニューの西口さんとの対談の中で、「大企業のマーケターも、駅前の屋台と同じように、シンプルにお客様のことを考え抜いて商売しましょうよ。」と西口さんが語っていたのがとても印象的でした。
どんな技術や思考法ができても、やはり常に第一線の現場で向き合い続けることこそがマーケティングの本質ですね。
📚経営戦略4.0図鑑[田中 道昭]
これからの世界をどう見据えていくのか。また、どんな未来を予測していくのか。
移り変わりが激しいこの世の中で、見通しを立てていくための1つの方法として、「世界の最前線に立つ企業の"戦略"を"戦略4.0"と名付け、そこから未来へのヒントを見つける」ことをテーマとして書かれた本です。
本書は「起承承型」の3部構成になっており、起にあたるPART1は今、世界の最前線で起こっていることを、キープレイヤーを例に挙げながらビジネスモデルやテクノロジーについて解説しています。
承にあたるPART2は戦略を読み解く・作るうえでの重要かつ一般的な知識や考え方をおさらいするページです。経営戦略やマーケティング戦略等のフレームワークがメインですが、今現在の企業や政治を例に開設しているのでわかりやすいと思います。
最後のPART3が本書のメインとなっており、まずはここから読み始めることをおススメします。
GAFA・BATHと呼ばれる各企業に、日本とアメリカの企業を加えた合計15社を1社ずつ戦略を俯瞰しながら紐解き、未来へのヒントを探っていきます。また、すべての企業に対して「NEXT(次の一手)」も書かれており、すでに予備知識のある企業においてはこの部分から読んでも良いと思います。
📚アフターデジタル2 UXと自由[藤井 保文]
前著から1年ちょっとのタイミングで続編が出ました。
著者曰く、早期に前著のアップデートを図りたかったこと、また、OMOという概念が広まったものの、正確な理解に繋がっていない事例も見受けられるようになり、改めてDXに必要なUXにフォーカスして伝える必要がある、ということで書かれたそうです。
前著では特にふんだんな中国の事例を元に、OMOやアフターデジタルの概念を解説していましたが、今回はさらに踏み込みアフターデジタルで必要なのは「精神」と「ケイパビリティ」であると言及し、OMOを推進していく我々にとって持つべき心構えと能力を説いており、この前提が無いと間違った方向に進んでしまうということです。
やはり改めて我々が意識すべき提言はこちらですね。
データは売上や利益に貢献できるというのは幻想である。(むしろ過去のデータを持っていてもほとんどリスクとコストにしかならない。)
データはユーザにUXとして還元する(サービスの提供価値を高める)ことで、ユーザとの信頼を作る。→それが結果的に売上に繋がる。
著者は前著から一貫して徹底的な「顧客視点」を貫いており、OMOやDXはそもそも顧客が起点となければならないことを常に警鐘しています。
本書内でも「ただ単にオンラインとオフラインを融合させればよいという考え方は、本質を失ったただの連携であり、アフターデジタル時代に必要な視点に転換していない。」と書いており、改めてOMOやアフターデジタルの世界を実現するには、知識や技術等の前に徹底したビジョンや心構えが必要であることを再認識することができました。
本書は5章構成で、1章は前著の振り返り的な章なのですでに読んでいる方は後回しにしましょう。2章は様々な企業を事例としたアップデートの解説で、ここも追加知識として後から読んでも良いと思います。
メインは3章からで、改めてOMOの定義のおさらいから始まり、日本でビジネスをするうえで、中国事例の焼き増しではない本質的なエッセンスの抜き出し、そして持つべき「精神」と「ケイパビリティ」の解説に繋がっていきます。
また、最後の5章は実際に日本でビジネスをしている企業やサービスの試行錯誤を事例としながら解説しているので、個人的にはまず5章を読むことでイメージが付きやすくなるのでは、と思います。
📚ワークマンは 商品を変えずに売り方を変えただけで なぜ2倍売れたのか[酒井 大輔]
著者は日経クロストレンドの記者ですが、様々な仕掛人としてメディアにも取り上げられている土屋氏をメインとしてワークマンという企業の躍進の裏側を解き明かしています。
記者があとがきで「お前はまだグンマを知らない」という漫画のタイトルを引用して、著者自身「お前はまだワークマンを知らない」状態だったと書いておりますが、読んだ感想としては「お前はまだ土屋哲雄を知らない」という表現の方がより適切だと感じました。
ワークマンプラスを皮切りに一気にメジャー企業としての地位を確立しましたが、それはあくまでも1つの事例であり、ほかにも店舗づくりや商品づくり、物流や人材育成等、あらゆる面で特筆すべき点があり、特にベンチマーク企業調査やフィールドワーク、顧客調査等の地道な裏方の部分にまで土屋氏が関わっているあたり、まだまだ私自身の仕事の徹底度が半人前であると再認識させられます。
本書は全9章で構成されており、はじめにと1章でワークマンという企業の振り返りがありますが、2章移行は大まかなカテゴリ毎に章が作られているので、目次を見ながら気になる章から読み進めるのが手っ取り早いと思います。
以上。
============================
こちらも是非。
[週刊]フード・デリバリー関連ニュースマガジン
様々な体験をまとめたマガジン
============================
twitterはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
