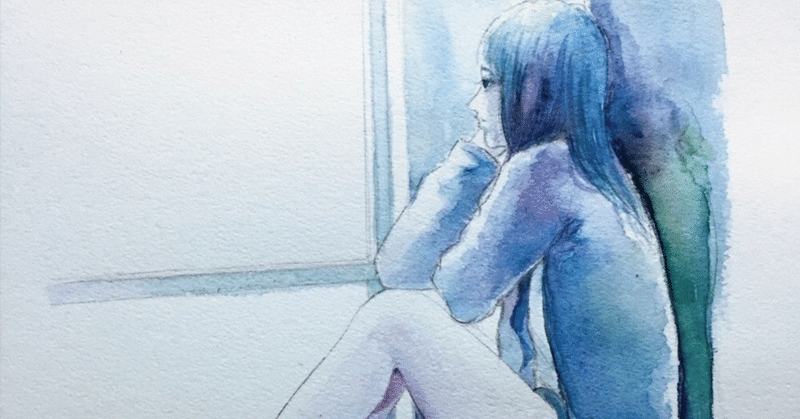
女性に対する伝統的な考えに対して少し距離が出てきた。
自己意識と悪の関係について。自分は少し考えている。
それは、自己意識を持つことが悪になるのかという問題である。
自己意識を持つと、それは悪になるのか。
たぶんそれはそんな一概には言えない。
一概には言えないというのは、自己意識は悪なのかという問いを私は持ったことがあるということである。
自分の意識は悪なのか。それは問いである。
自己意識を持ちつつ、それを悪ではない形に組織化することはできないのか。
それは問いとしてある。また、その点についてはジャン・ナベールの『悪について』という本がとりわけ参照点になるような気がする。
悪とはどういうことなのか。ただ、それはジェンダーと結びついた時に、男性と女性にそれぞれ善と悪を振り分けてしまう安易な概念と接続されてしまう気がする。
ショーペンハウエルが「女について」というタイトルで本を書いたことは知られているだろうか。
その内容はかなり保守的な女性についての観念を確かめる内容となっているが、私自身はその本を持っている。
その本の内容と、また自分が読んだもののなかでギュスターヴ・モロー展(「ギュスターヴ・モロー展:サロメと宿命の女たち」というタイトルで2019年にパナソニック汐留美術館、あべのハルカス美術館、福岡市美術館で開催された)で、次のようなテクストを読み、自分は考えているところがある。
モローの芸術のなかで、女ー悪ー死と、(男は)英雄ー善ー生であるとして、その両者が対比されているという考えと自分の考えは関連しているところがある。
倫理が抗えば抗うほどに増していく、反倫理の吸引力。「悪」として図式化された女性が、絵の中で「善」なる男たちを幻惑し、従わせ、命すら差し出させるーーそこに立ち上る得も言われぬ官能性と頽廃美ーー絵画というフィクショナルな空間で、無意識の願望を成就さえ、現実世界での抑圧から自らを解き放つことを可能にしたからこそ、モローの絵は、図式的な倫理観との内なるせめぎ合いに揺れた世紀末という時代に輝きを放ったのではないだろうか。
モローの絵には「男と女、善と悪が不可分なかたちで溶け合うところに生まれる稀有な神秘性と幻想性」(同上、172頁)というものがあるとしている、と上の記事ではされている。
この「善」=男/「悪」=女という図式はかなり今だと叩かれるものになるだろうが、実際に精神分析でもラカン派では、社会を生きる女性はみなhomme(人間=男)であるという見方があったような気がする。(この点については参照文献がないのを許して欲しい。)
ラカン派における女性については、例えば次の本がある。
男と女の関係性、そこはかなり重要な問題があるように思う。
考察をしていきたいが、自分自身はショーペンハウエルの女性観とも近いものがあったことを認めないといけない。
とにかく、その女との関係〔=ショーペンハウエルの女との関係〕は、恋愛というよりは、愛欲もしくは情欲というに近く、相手は、女性そのものというよりは「性欲の対象としての女性」という観を持っていたことは争えない。
この「性欲の対象としての女性」という考えは自分もかなり思春期の頃から、もちろん女性には女性の尊厳があると思っていたけれど、性欲の問題、性欲が女性に向いてしまうことの葛藤をずっと感じていた自分とも近いところがある。
もちろん、その言葉は女性を不快にさせるかもしれない。
また、自分の場合、特に自分のアイデンティティの状態は変わっても、自分の性指向が女性だったということに変わりはない。
だから、「性欲の対象としての女性」という考えはかなり自分を苦しめるものであることは確かである。
そのなかで自分は何ができるのか。男に寄せることが良いのか。
それは分からないが、自分のなかでとりあえず上記を参考にしていることは確かであり、自分は性別の面からするとむしろ保守的な考えに近かったと言っておく。
セクシズムにかなり自分は寄せられていたのかもしれない。
それがこのところ少し中和されつつある。
そんなことが分かっている今日このところ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
