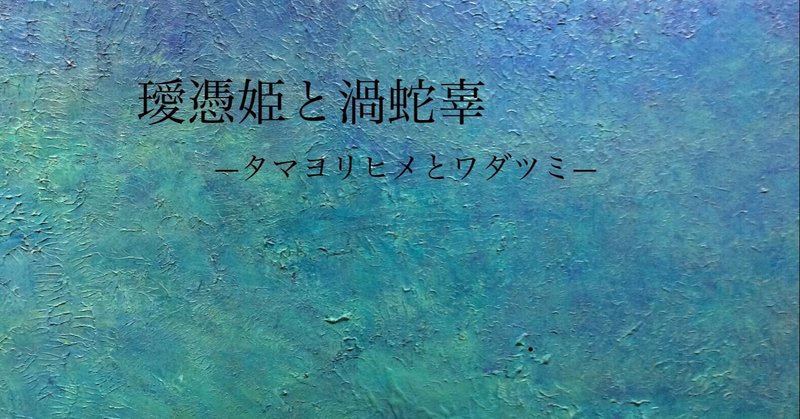
璦憑姫と渦蛇辜 1章災厄来りて①
「おまえが唄ってくれるなら、星のないどれほど暗い海だって、おまえの元に帰れるんだよ」
海彦のお父さは漁師だったが時化の海で死んだ。お母さは山で蛇に噛まれて死んだ。白砂の浜から上がり一丁も行かぬ大きなデイゴの木の下にある漁師小屋に、海彦は親代わりの婆さと妹のタマと暮らしていた。
八つ下のタマは妹とはいっても拾い子だった。あの日、海霧が立ち込めた夕刻、空が赤いような黒いような変な色に染まり海も天も地も定かではなくなった浜辺から、人の呼ぶ声がした気がして海彦はうちを出た。
「おめぇはおつむが足りねぇ」と海彦は云われる。婆さからも漁師達からもことある度にだ。そのことを話しても「おつむが足りねぇからほんとうの事と夢ん中のことがわからねんだ」と云われるが、海彦には到底夢だとは思えない。
―おらはちゃーんと見たんだ。
つぶつぶした白い泡の襞がなめる渚に、女がひとり立っているのを。
女の長い着物は潮に濡れることなく軽やかに遊色を帯びてなびき、水底にある神域の使いかと思うほどその佇まいはみやびだった。
女は藻草を抱いていた。立ち込める霧の薄い膜の向こうを、もっと見ようと海彦は目を凝らした。女は渚にしゃがみ込むと藻草をそっと砂のうえに置いた。
「そりゃ魚か!?」
海彦には大きな鯛に似た紅色の魚が藻草に包まれているように見えた。女はその声に顔を上げたかと思うと、あっという間に霧の海へと消えていった。
海彦が駆け寄って藻草を暴くと、中にはようよう歩くばかりになったほどの乳飲み子がいた。
老いた女ひとりの手では子どもふたりも食わせていけぬと、婆さは最初渋ったが、海彦が頑固なのとタマが可愛いのとでしまいには婆さも折れた。それから海彦の働きはすごかった。
小さい体で朝から晩まで漁師の男たちの手伝いをし、十八の歳には数こそろくに数えられないが潮をよむのも船をかるのもいっぱしの漁師と変わらぬほどになった。
中天に太陽が昇りつめ、陽光が鋭い影をつくる森の中の湧水でタマは真水を汲んでいた。小さな島に井戸はなく、ひとつきりの水場に朝夕島人は水汲みにやってくる。頭に一つと右手に一つ、桶を下げてタマはガジュマルの気根が迷路のように蔓延る細道を、慣れた足取りで下って行った。森が開けると紺碧の海が輝く。
水天一碧のその彼方に舟影を見つけタマは思わず叫んでしまう。
「おーい、兄ィさああああ、聞こえるかあああ。見えとるぞおおお!」
聞こえるわけないと分かっていても、どうにかして兄は自分の声を聞き分けている気がするのだ。
風が運ぶのか海が運ぶのか知らない。ただ声は真っ直ぐに海原を突き抜けて、兄に届く。そうタマが心の隅っこで信じるには訳があった。
海彦が仲間と沖合まで漁に出たある日、突然海が荒れ始めた。仲間とちりじりになり、命からがらで嵐をやりすごした時には、星影ひとつない真っ暗な海にひとりぽつんと小舟に揺られていた。
島影はなく、海鳥も眠り、波ばかりが嵐の余韻で手荒く小舟をゆすった。
海彦は怖ろしかった。海は真っ暗で波の手は今しも自分を怖ろしいものの棲む『下海』、海の底のその下へ引きずりこもうとしているようだ。暗闇とひとりぼっちの恐怖が、海彦の子どものままの心に化け物の影を伴って押し寄せてきた。
「助けてくれよ。助けてくてよ。お母さお父さ婆さ………タマ。おらはおっかなくてたまんねえよ」
大きな体を丸めて小舟の真ん中で震える海彦の耳に、ふと声が聞こえた。
顔を上げたが辺りは闇だ。しかし、声は節回しをつけてどこからともなく聞こえてくる。
「……タマの声でねえか?」
海彦は船の櫓に手をかけた。
ゆっくり漕ぎ出せば、声はさきほどよりはっきり聞こえる。聞き覚えのある唄だ。婆さが赤ん坊だった頃のタマに唄って聞かせた子守り唄だ。それをタマがどこかで唄っているのだ。
耳をそばだて、唄声だけを頼りに海彦は真っ暗な海を進んだ。糸を手繰るように声を無心に手繰った。もう怖いのはどこかへ消えていた。真っ直ぐに真っ直ぐに声を目指して進むうちに、夜が明けた。
朝日の中に懐かしい島影が浮かび、そうなると疲れた腕にも力がみなぎり、浅瀬まで来ると船をすて浜めがけ走った。デイゴの木の下のうちが見え、その手前の波打ち際に黒い松明の跡とうずくまって眠るタマの姿があった。
海彦を案じて、夜通し火を焚き唄っていたのだ。
そんなことがあってから、海彦とタマはお互いを一層頼りにするようになった。
浜にあがった海彦は今日の得物をいちばんにタマに見せてくれた。南海の魚は色鮮やかで、婆さが手早くそれを捌く脇でタマは海彦にじゃれついた。
「聞こえた?おれが坂の上から兄ィさ呼んだの聞こえた?」
「聞こえたかのぉ?海があんまり澄んどるもの、きれいな貝でもないかと底ばかり見とったでの」
「ぼーっとしてたら人魚にいたずらされようよ。で、あったの?」
「なんが?」
「きれいな貝」
ああとつぶやいて海彦は腰に吊るした魚篭に手を差し入れたが、ひゃあと叫んで尻もちをついた。
「なん?」
きれいな貝が出てくるとばかり思っていたタマは、這い出たタコに面食らった。タコは海彦の腕に絡みつき、身を延ばし縮ませ這い上ってくる。くすぐったがって身をよじる海彦の首にタコはしがみついて、引っぺがしても器用に脚を絡ませ離れようとしない。
「くそ、タコが取れん」
「兄ィさはタコに好かれよるね。タコを嫁取すればいい」
いやじゃいやじゃと海彦は床に顔を押し付けながら、タコから逃れようとする。
「いやじゃ、タコの嫁はいやじゃ。嫁ならタマがいい」
「ふふ。そうじゃが、タコはどうする?」
意地悪く笑うタマに、海彦は半べそをかきながら、
「タコは……、タコは、食うてやる」
と恨めし気に云った。
「タマは妹でねえか?」
婆さはそう云いながらタコのあたまに刃を突き立てた。硬直したタコをはぎ取ると、
「こいつは干物にしようかのう」
と土間に思いきりたたきつけた。タコは気を失いだらりとのびた。
「きょだいでも親が違えば、夫婦になれると言ってたぞ、次朗太が」
次朗太は漁師仲間で先日、嫁を迎えた。
「タマは器量がええ、島を出て、どこぞの金持ちに嫁いだほうが……」
婆さは云いかけて口をつぐんだ。
「婆さはタマがこのうち出ていくほうがええんか?」
「いやあ」
婆さは口の中でもごもご云った。孫二人の仕合せに余計な口出しはいかんと思った。タマも年頃になれば考えも変わるだろう。そそくさと伸びたタコを板に張り付けると日向へ持っていった。
「貝は見つけられんかった」
「じゃあ、今度な」
「じゃが、タマの子安の貝殻よりきれいな貝はどこにもないぞ」
海彦は神妙な顔で云った。その貝はタマを拾ったとき、藻草の中に一緒につつまれていたものだ。大きな貝殻の一部だろうか、外は瑠璃紺の瑪瑙に似た縞模様で内側は真珠質で模様か文字のようなものがある。それはいつも宝物のように寝床の奥に据えてあった。
「知っとるよ。でも兄ィさがとってきたものが欲しい」
「分かった」
海彦は真っ白い歯をみせて大きな笑顔になった。
つづく
読んでくれてありがとうございます。
