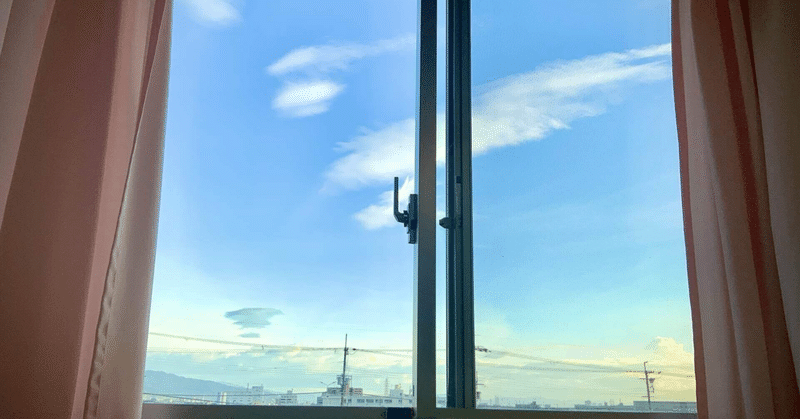
追憶【掌編小説】
拳の記憶よりも、愛の追憶は遥か深い。
ボクシング世界タイトルマッチで僅か1R59秒で惨敗を喫した松下タツヤは絶望の淵にいた。
古びた病院の個室にはユリがずっと付き添っている。両親のいない彼はユリ無しでは生きられない。この試合に勝てばプロポーズをするつもりだったのだ。そんな絵に描いたような幸せを目前にしたまさかの出来事・・・一命は取り留めたが、医師からは引退勧告を受けざるを得なかった。
「タツヤ君、彼女を幸せにしてあげなさい」
聖母のような優しさは彼の見知らぬ母を思わせた。
「先生がこれだけ強く言うんだから、ボクシングはもう辞めて!」ユリは泣き叫びながら、手を握った。ユリと出逢った日を思い出していた。タツヤは思わず目の前に立っている大柄の男性を見やった。
「タツヤ、よくここまで頑張った」
彼はタツヤが所属するボクシングジムの会長だ。名を山本と言う。会長は目を真っ赤にして声を震わせていた。
頭が痛い。思わずタツヤは後頭部を押さえた。まるで、金属棒が貫通したような感覚だ。何かに襲われるような恐怖は自らを激しく責め立てる嫌悪感に変わっていた。
「命があるから、また明日を生きることが出来る」
女医は透き通るような美声だった。今、見下げられている。いや、生きる意味を問われているんだ。そんな気がした。悲しいけれど、悔しいけれど、死の淵を彷徨わないと愛を知ることは出来ないのか。大切なものには気がつかないのか。
「タツヤ、私も頑張って仕事するから」
現実を直視させるようなユリの言葉が何より身に沁みた。彼女のほうが現実を見ている。
「もう闘わない松下タツヤになって」ユリは泣くことを止めるように呟いた。
「ありがとう。ユリ」
タツヤは目に涙を浮かべながら、ユリの手を強く握った。強く生きなくてはならない。きっと、ユリとなら幸せに人生を歩めるはず。いや、幸せにしたい。
「退院したら、就職活動だな」
会長はガハハと笑うと、腕組みをした。
「会長! 俺、雇って貰えますか?」
【BOXing】と書いた赤いTシャツがタツヤの視界に入った。会長の笑顔に釣られて、何が何だか分からない儘に勢いで言ってしまったのだ。ユリは女医と目を合わせて笑っていた。
真顔になった会長は、何かの結末を訊くように渋々と言った。
「もう一度訊く。タツヤ、お前本当に昨日試合だったことを覚えていないんだな?」
病室にいる会長、女医、ユリ全員の目が鋭く彼に向いた。
「はい。全く記憶にございません。そもそも、さっきから連呼するボクシングって何ですか?」
タツヤ以外の3人はハアという表情をした。
「お前、ボクシング忘れたらトレーナー出来ないだろ」と言いつつ、(まさか、こいつ俺が誰だか覚えてないんじゃ・・・)と訝しんだ。
会長はウッと言った後、また一つ高笑いをした。
【了】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
