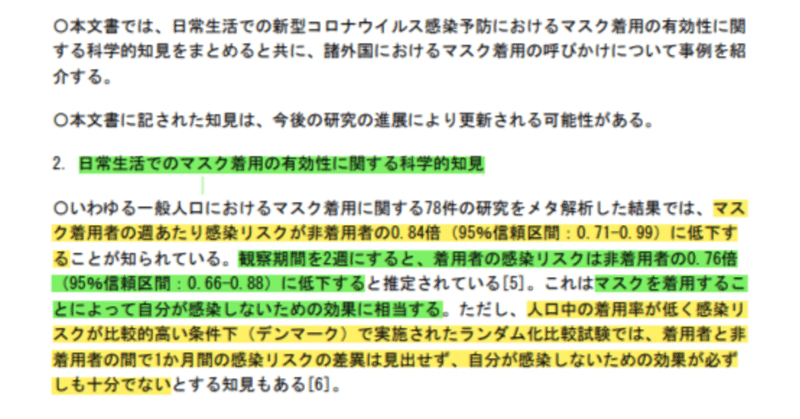
3月13日以降、マスク着用は「個人の判断が基本」だが「本当にマスクを外して大丈夫?」
*最適な介護を、自分で選ぶための情報紙*
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌日本介護新聞┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
*****令和5年2月19日(日)第155号*****
◆◇◆◆◆─────────────
3月13日以降、マスク着用は「個人の判断が基本」だが「本当にマスクを外して大丈夫?」
─────────────◆◇◇◆◆
◇─[はじめに]─────────
もうすぐ学校等の「卒業シーズン」を迎えますが、それに合わせるように政府は2月10日、これまでのマスク着用のルール「屋内では原則着用、屋外では原則不要」を、今から約1ヶ月後の「3月13日以降は改める」ことを発表しました。
具体的には「行政が、一律にルールとして求めるのではなく『個人の主体的な選択』を尊重し、マスクの着用は『個人の判断』に委ねることを基本とする」との方針を示しました。
同時に政府は「各個人のマスク着用の判断に資するよう、感染防止対策として『マスクの着用が効果的である場面』などを示し『一定の場合』は推奨する」等と述べています。
これを受けて厚生労働省は、同じく2月10日に、介護施設等で「一定の場合」の事例として「高齢者施設の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨する」と、都道府県に対して通達しました。
ところがこの通達では、その後に「マスクの着用は『個人の判断』に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上、または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容される」とも指摘しました。
この内容を素直に受け取れば「個人の判断よりも、事業者の判断の方が、事実上優先される」と読み取れます。これでは、介護現場で混乱が生じるだろうと危惧しましたが、厚労省はさらに2月15日、この内容に修正を加えた形の通達を出しました。
今度は「周囲に人がいない場面や、利用者と接しない場面であって、会話を行わない場面等においてはマスクの着用を求めない、といった判断が想定される」等と指摘しました。
2月10日からわずか1週間程度で、政府や厚労省の「判断」はかなり揺れ動いたように思われます。現在、新型コロナの新規感染者数は減少傾向にあり「第8波」も終息に向かっている印象を受けます。
その一方で、2月10日の政府発表を事前に察知していたかのように、厚労省の新型コロナ専門家会議のメンバーを中心とした有識者が2月8日に「マスク着用の有効性に関する科学的知見」(以下「本文書」)を公表しました。
その内容は、弊紙発行人のように、いまだに新型コロナの感染に脅威を感じる者が「本当にマスクを外して大丈夫なのか?」と抱く疑念に対し「科学的知見からの回答」を示してくれています。
そこで今回の本紙では、読者の皆さんが「マスク着用は必要か、不要か?」を考える材料として、専門家等が2月8日に発表した内容を取り上げることにいたしました。この記事が皆さんの「個人の判断」を下すための手助けになれば幸いです。
どうか最後まで、ご一読頂ければ幸いです。
日本介護新聞発行人
──────────────────◇
今回の本紙は、上記の「はじめに」で述べたように、2月8日に開催された厚労省の「新型コロナ感染症対策アドバイザリーボード」(厚労省専門家会議)で発表された「マスク着用の有効性に関する科学的知見」の内容をご紹介いたします。
内容の一部については、読者のみなさんが読みやすいように本紙で修正を加え、難しい用語には注釈を付けましたので、どうかこの点をご了承の上、お読みいただければ幸いです。
◆───────────────────
「新型コロナは、発病しない無症状者や、軽症の感染者から感染が広まりやすい」
───────────────────◆
▼マスクの着用は、会話や咳の際に、自分の感染性粒子を飛ばさないようにする(=他者を感染させない)こと、そして周囲の感染性粒子を吸い込むことがない(=自分を感染させない)ことを目的としている。
▼季節性インフルエンザでは(感染した)有症状者が、高い発熱と全身の倦怠感を伴う症状のため、2次感染(=感染等によって抵抗力が弱っているところへ、さらに別の菌の感染をうけること)が起こり得る間は、自宅以外での他人との接触は限られていた。
▼一方、新型コロナ感染症では、発病前の潜伏期間に「2次感染の、約半分に相当する感染が起こる」ことが知られている。また「発病せずに無症状のままでいる」者や「軽症の感染者から、感染が広まりやすい」ことが知られている。
▼2020年6月以降(新型コロナは)病原性が高いこと、そしてワクチンの供給前や供給途中の状況で、感染によって免疫を得た人が少なかったことから、できる限り感染機会を減らすために「マスクを常に装着すること」が約2年にわたって推奨されてきた。
▼2022年5月24日に、政府は「屋外のマスクの着用は不要」であることを示した。これらの経緯を踏まえ「本文書」では、日常生活での新型コロナ感染予防における「マスク着用の有効性」に関する科学的知見をまとめた。
▼それとともに、諸外国における「マスク着用」の呼びかけについての事例を紹介する。なお「本文書」に記された知見は、今後の研究の進展により更新される可能性があることをご留意いただきたい。
◆───────────────────
「マスク着用を地域全体で推奨すれば、感染者数・死亡者数等を減少させる効果が…」
───────────────────◆
▼いわゆる、一般の方々における「マスク着用」に関する78件の研究を、メタ解析(※)した結果では、マスク着用者の1週間あたりの感染リスクが「非着用者(=マスクを着用しない人)の0.84倍に低下する」ことが知られている=画像・厚労省HPより。緑色と黄色のラインマーカーは、本紙による加工。
【※本紙注釈=「メタ解析」=過去に行われた複数の研究結果を統合し,より信頼性の高い結果を求める統計解析手法のこと】
▼このメタ解析の観察期間を2週間にすると、着用者の感染リスクは「非着用者の0.76倍に低下する」と推定されている。これはマスクを着用することによって「自分が感染しないための効果」に相当する。
▼ただし(その地域の)人口中のマスク着用率が低く、感染リスクが比較的高い条件下で実施されたランダム化の比較試験(デンマークの事例)では、マスクの着用者と非着用者の間で、1ヶ月間の感染リスクの差異は見い出せなかった。
▼また「(マスク着用で)自分が感染しないための効果が必ずしも十分でない」とする知見もある。新型コロナ感染症の対策では、原則として有症状者に着用を推奨していた従来と異なりコミュニティー全体で、症状の有無に関わらずマスク着用が推奨された。
▼さらには、義務化されたりすることがあった。それは、上述の通り無症状の感染者から2次感染が起こり、また多くの感染者が発病前に感染性を有するとき、自宅以外での屋内空間で、他者を感染させる性質があるためである。
▼感染者が不織布マスクを着用することによって、以上のように2次感染のリスクは軽減される。これは「他者に感染させないための効果」に相当する。本課題に関する論文で、その効果が指摘されている。
▼それによると、マスク着用を「コミュニティー全体で推奨」した際、新規感染者数・入院患者数・死亡者数をそれぞれ減少させる効果があることが示唆された。
◆───────────────────
「諸外国の研究事例でも、地域・学校等でのマスク着用により、感染防止効果が……」
───────────────────◆
▼例えば、バングラデシュにおける地域レベルでのクラスターランダム化比較試験(※)で、マスク着用によるコミュニティーの感染リスク低減を認めたが、着用勧奨段階でバイアス(※)混入の可能性も指摘され、因果関係は十分に立証されてはいない。
【※本紙注釈=クラスターランダム化比較試験=研究対象である各個人を対象に、ランダム(無作為)に割り付けた後に,両群の評価項目を比較すること】
【※本紙注釈=バイアス=「傾向」「偏向」「先入観」といった、その人の思考や判断に特定の偏りをもたらす思い込み要因や、得られる情報が偏っていることによる認識の歪みのこと】
▼小中学校では、米国マサチューセッツ州の15週間に渡る観察研究で、マスク着用の義務を解除した学校と、義務を継続した学校の児童・スタッフを比較した時、着用義務を解除した学校では「感染リスクが1千人あたり44.9人増えた」と報告されている。
▼この米国における研究では、流行対策の一部として「マスク着用が有効である」ことが示唆されている。着用者が10%増加することにより、そうでない場合と比較して流行を3.53倍、制御しやすくなる。
▼つまり「マスク着用率が10%上昇することで、実効再生産数が「1」未満に落ちて、流行が制御下に置かれるという度合いが3.53倍増す」(=流行が制御しやすくなる)と推定されている。また、世界6大陸の着用状況と流行制御の関連を分析した研究もある。
▼ここでも「公共の場におけるマスクの着用」は、平均的なマスク着用率を達成している場合、着用なしと比較して、実効再生産数をおおむね19%下げることに貢献してきたとされる。
◆───────────────────
「マスク着用は、諸外国の多くが『義務』だったのに対し、日本は『呼びかけ』……」
───────────────────◆
▼諸外国では、多くの場合マスク着用は強制力をともなう「mask mandate(着用義務)」として、マスク着用が対策の一部として実施されてきた。日本での「呼び掛け」とは大きく異なる扱いであった。
▼マスク着用に関する文化的背景が日本と大きく異なる欧州では「流行状況が悪化した場合にのみ、マスク着用を呼び掛ける」ことがある。例えばドイツでは、欧州で最後までこれが継続されたが、長距離の交通機関のマスク着用義務を2023年2月に解除した。
▼しかしドイツの保健相は「自発的に、マスクを着用する」ことを推奨することを呼び掛けている。これまでの集団行動動態に関する研究を通じて、マスクの着用は文化的な背景もあわせて、国によって大きく異なる経過をたどっている。
▼その「集団内でのマスク着用の度合い」は、公的機関からのマスク着用の指示と、社会的特徴(社会規範や同調傾向)の2つの要因に依存することで知られる。そのいずれかが弱まると、マスク着用率は「低下した状態」で、安定的に推移することになる。
▼韓国では、公共交通機関や病院、薬局など一部の施設を除いて、屋内でのマスク着用義務を解除する対応をしているが、多くの市民は継続しているとされる。一方シンガポールでは、2022年8月以降は屋外・屋内ともに「マスク着用は義務ではない」とした。
▼しかし、公共交通機関および病院、高齢者施設においては「必ず着用する」ことが推奨されている。マスク着用に関するこのような推奨の変更は段階的に行われており、上記に先立って2022年4月にまず「マスク着用義務」が屋外でのみ撤廃されている。
▼また台湾では、2022年12月1日以降、屋外空間については「マスクの常時着用」の規定を撤廃した。ただし、年末のカウントダウンなど、屋外で行う大型イベントについては「別途判断する」こととした。
▼一方、屋内(車内・船内・航空機内を含む)ではこれまで通り「マスクの常時着用」を義務付けている。ただし、次の<1>>から<4>>の例外については、屋内であっても「マスクを着用する必要はない」としている。
<1>運動をする場合、歌を歌う場合、個人・団体で写真撮影を行う場合。
<2>自分で運転し、車内の同乗者すべてが同居家族である場合、または同乗者がいない場合。
<3>ライブ放送・ビデオ撮影・司会・レポート(報道)・スピーチ・講演・講義など、会話や談話に関する業務や活動の、正式な撮影や進行をする場合。
<4>温泉・冷泉・ドライタイプのサウナ・スパ施設・サウナ・スチームルーム・ウォーターアクティビティなど、マスクが湿ったり濡れやすい場合。
▼さらにカナダの事例では、マスクの着用は「個人の選択であり、他人の選択を理解し、敬意を払うように」としながらも、屋内の公共スペースでは「マスクの着用を推奨」している。
▼また「重症化リスクを有する人や、その周囲の人、集団生活をしている場所に訪問する場合、混雑や換気の悪い場所では、マスク着用が特に重要」としている。さらに、長期的に「流行」がある場合には、マスク着用の必要性を訴えている。
▼特に「新たに懸念される変異ウイルスにある場合や、地域の流行レベルが高い場合には、市民のマスク着用に強く頼る必要も生じる」としている。
◇─[おわりに]─────────
今回の「マスク着用の有効性に関する科学的知見」では、専門家等は「マスク着用の必要と不要のケース」について、淡々と「科学的知見」は述べていますが、これらを踏まえ、我が国に当てはめた場合の「意見」は、明確には打ちだしていません。
しかし推測すれば、専門家等は本当は「政府は3月13日以降、マスク着用は『個人の判断が基本』との方針を示そうとしているが、もっと具体的な内容を示さないと『混乱』が生じるのではないか?」と、問いかけているように感じます。
厚労省もそれを感じ取ったのか否かは不明ですが、介護事業者向けには2月15日に「周囲に人がいない場面や、利用者と接しない場面であって、会話を行わない場面等においてはマスクの着用を求めない」と指摘し、都道府県等へ通達しました。
一方、介護施設の業界団体も、2月7日に加藤厚労大臣に宛てて意見書等を提出し、この中で今後のマスク着用について「一般社会と高齢者施設等で『著しい格差』が生ずるおそれがある」等と懸念を示しています。
これら専門家や介護施設業界団体の動きに対し厚労省は、2月15日にようやく「新たなマスク着用のルール」を周知するための国民向けのパンフレットを公表し、都道府県等に示しました。
その中で「高齢者施設などを訪問する時は、マスクを着用しましょう」と呼びかけています。いずれにせよ「マスク着用」の新たなルールが適用される3月13日までは、まだ1ヶ月弱の時間があります。
それまでに厚労省には、介護サービス利用者や介護事業所が「混乱」しないため、また一般社会と高齢者施設等で「著しい格差」が生じないためにも、今回のパンフレットだけで終わらず、さらに丁寧な説明と、その内容の周知が求められます。
──────────────────◇
◆日本介護新聞・本紙(エンドユーザ─版)バックナンバー=
http://nippon-kaigo.blog.jp/
◆日本介護新聞「ビジネス版」バックナンバー(2022年4月分まで)=
http://nippon-kaigo-b.blog.jp/
◆ホームページ=http://n-kaigo.wixsite.com/kaigo
◆Twitter=https://twitter.com/Nippon_Kaigo
◆Facebook=https://www.facebook.com/nipponkaigo/
(C)2023 日本介護新聞
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
