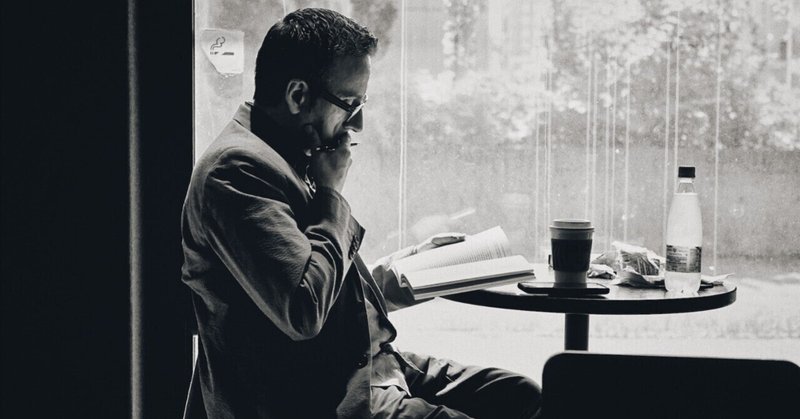
読書とは何か(読書基礎論)
本記事は全文無料公開しております。価格表示についてはただの字数に応じた設定です。投げ銭とでも考えていただければ幸いです。
『Core Magazine』購読で購読月の有料記事は月額980円で読み放題となります。購読月以外の有料記事は別途購入となります。
これまでも読書についてテクニカルな話題は割と扱ってきたが、そもそも読書とは何なのかということを、改めて問うてみたい。
ジェイラボの活動として研究員の皆さんに定期的に書評を書いていただいているが、何故僕がそんなものを義務付けているのかについての答えでもある。
読書は論文の査読ではない。
読書は、科学的「事実」との照合ではなく、己の信じる「真実」との対面である。
では「真実」とは何か。
僕は「それ」を、読書を通じて自分なりに「解釈」してきた。解釈とは、すなわち言語を経由して自身の脳内にイメージを想起するということである。こういった話は以下のマガジン
の一連の文章でそれなりに伝えてはきたが、改めてその部分を少し補足的に話をしてみたい。
特に、哲学書などの抽象的で「難解」とされるような文章群を読む際に、「解釈」とは何かという部分は、否応なくかなり意識されると思われる。「ライト」なエッセイのようなものを読んだときに何故それが意識されないかというと、日常当たり前に行なっている解釈の手続きの範囲を出ないからである。つまり、自動化された手続処理で言語の解釈を行なうため、それが「自動的である」ことを意識していない。自動なのだから意識しないのは当たり前である。今僕が書いている文章も、これくらいならまだ「自動的に」読めているはずである。
文章群が「難解」になってくると自動的に(無意識に)は書かれていることが解釈できなくなってくる。その時に、言語の持つ作用、すなわち「抽象化された記号による意味の伝達」というものと向き合う必要が出てくる。
抽象化された記号で何が伝達できるか。
もちろん、伝達されるものは抽象化された記号のみである。
つまり、それをどう解釈するかは基本的に放り投げて受け手に任せるしかない。高度に抽象化された記号群の最たる例としては、数学や物理学の専門書をイメージすればよいと思う。それらは解釈の訓練(文脈に沿った記号運用の訓練)要するに学問として、知識として、その範疇で用いられる論理展開を修めていることが絶対的に求められるため、非専門家がその記号群を即時的に解釈することは不可能である。
日常言語で書かれているはずの哲学書などが「難解」である理由は、日常の徹底した意識化の要求ゆえである。そこに多少の専門性はあろうかとは思う。
哲学書に書かれた内容が理解できない。その段階では、まず言語的にその論理展開を追ってみるということが、当然必要になる。この段階で躓くようであれば、まず徹底して論理を追う訓練は必要だろう。それは僕も若い頃からずっとやってきた。そして、そうした訓練は、場合によっては他の専門分野に足を突っ込む際にも役に立つ共通のスキル(技能)にはなるだろうと思う。「この文章むずかしいなあ」というレベルで文章と向き合う段階では、真面目に書かれていることが「一般的な意味で」何を意味しているのかという部分にしっかり注力して読めばよいと思う。それは、その次の段階に進むための訓練である。
そして、ある程度その訓練が進めば、言語運用と自覚的に向き合うという意識が自然と芽生えるはずである。つまり、「言語と自分がまるでそっくりそのまま一体である」かのように感じて生きてきたこと、それが実は「全く一体ではない」ということが意識され始めてくる。言語とは事象の抽象化ツールであるため、実はコミュニケーション手段としては不完全な物である。直接目の前で語りかける言葉、たとえば単なる挨拶、「おはよう」という言葉ですら、各人の生きてきた文脈の中でその言い方、イントネーションなどで異なった印象を受け手に伝えることになる。
そして、読書に難しさを感じる理由の大半はここにある。すなわち、
言語と自身を切り離せていない。
もちろん、言語を運用している主体は自分である。自分なしに言語はあり得ない。しかし、自分の感じている感覚をそっくりそのまま言語によって「情報化」して「伝達」することは、不可能だ。当たり前である。僕は三叉神経痛という非常に面倒臭い病気のせいで日常的にずっと「痛み」を感じて生きているが、その痛みを言語で伝達することは絶対にできない。
(痛みに関してはいま別記事で書いている途中なので書きあがったら公開します)
それが身体的に理解できたとき、おそらく自身の書く文章にも強い影響が出るはずである。文章を書くということに関する様々な指南が世の中にあふれているが、そのほとんどにおいて、それを書いている作者自身すら、文章を書くということの作用を理解していない。つまり、「書けて」いない。
文章を書くとは、その一連の記号群を放り投げたときにそれが改めて異なる時空で他人の脳内にどんなイメージを想起する(全く新しく創造し直す)かということを設計するということである。
では、過去の偉大なる哲学書たちが、本当にそのように「書かれて」いるかというと、実はそうでもない。もちろん、ウィトゲンシュタイン氏のように徹底的に言語の作用にこだわって書いた人もいるが、ふわふわとした運用のまま言語群を投げている人もいる。しかし、過去の哲学書たちの偉大さは、その設計の完全さにあるのではない。多少なり不完全であろうとも、圧倒的なオリジナリティが在ること。そこにこそ、その価値がある。
これに関しては、以下の記事を多少参考にしてほしい。
繰り返すが、「文章群」というのは、自身の身体とも著者の身体とも切り離されたものとして目の前に存在し、その基本的な作用は意味の「想起」である。ただし、その意味の「想起」という部分を無意識でやっている限り、得られる情報はほとんどない。何故かというと、無意識でできる作業というのは、既に脳内にある回路での処理であり、何も新しい回路を生まないからである。同じ庭でただぐるぐるしているだけということになってしまう。
冒頭で述べた「真実」とは、敢えてこの文脈で表現し直すなら、自身の脳内の「回路」のことである。思考パターンと言っても良い。自身の回路内での処理ではなく、著者と自身の回路を照らし合わせるというメタ行為。自身の庭を少し広げること。これこそが読書の意味であろうと思うし、文章を書く意味でもあろうと思う。
この文章の目的(基礎論という名目)に沿って、極めて簡単なまとめを最後に残しておく。
訓練 そもそも文章が難解で解釈の段階でてこずるなら、文章を読む訓練が足りていない。まずは、書かれている内容の把握(言語の非自動的運用)に集中すべきである。つまり、日常の言葉で勝手に自分なりの意味で読まずに書かれている言語群が表していそうな意味を意識的に探ってみようということである。
吸収 ある程度内容が把握できる段階になれば、そこに書かれている内容や論理展開などを知識として吸収しておくということも今後に活きる。僕にとってはもはや読書は知識の吸収の場であることは少ないが、訓練の段階としてはとりあえず受け売りで丸呑みしてしまうという段階ももちろん存在するし、それがあったからこそ僕も自身の回路が形成できたわけではある。
対峙 自分の中に自覚的な回路がたくさんできてくると、著者の回路と向き合うことができるようになってくる。この段階からが、漸くの読書の始まりである。そこに書かれている内容が正しいとか間違っているとかいう「浅い」一次判断ではなく、その意味そのものと向き合うという段階である。正しい間違っているという感覚は、多分に「感情的」なものである。正しいから賢い。間違っているから馬鹿。読書の目的はそういうことではないということだ。
体験 僕はたまに、著者の思考を「追体験する」ことが読書の目的であるという趣旨の発言をすることがあるが、それは時空間的に当時の著者の心の在り方をトレースしようという意味では、全くない。追体験といったところで、それはどこまでいっても、己の脳内による勝手創造である。むしろ、勝手な想像であることを自覚することこそが追体験である。難解な文章であればあるほど、著者が苦しみながらそれを書いたことが読む側としても、著者とは切り離されたものとして「想像」できる。その想像を自動(無意識)的にではなく意識的に行なうこと。それが、著者の思考の追体験である。それは、著者の思考そっくりそのままの体験であろうはずがない。著者が残した文章群によって、自身も新たに「体験」するということ。それが僕が皆さんに読書をすすめる最終の段階である。
メタ的に言うなら、今僕が書いているこの記事すら、皆さんには「体験」に落とし込むことを僕は要求してしまっているので、向き合っていただくための段階が生じてしまっているとは思う。これはもう、言語の限界である。許してほしい。
一応、こういう段階を踏まえて、僕が本を「質的にも量的にも」たくさん読めと言っていることを理解してほしい。自動的に読める本をチョイチョイ読んでも言語運用は何も身につかない。
本を読め。
そして、きたる将来、もし人類がいまの言語の限界を超えるような新たなコミュニケーションツールを発明したとき、言語の限界を知っていることはまた大いなる財産となるはずである。
ここから先は
¥ 300
私の活動にご賛同いただける方、記事を気に入っていただいた方、よろしければサポートいただけますと幸いです。そのお気持ちで活動が広がります。
