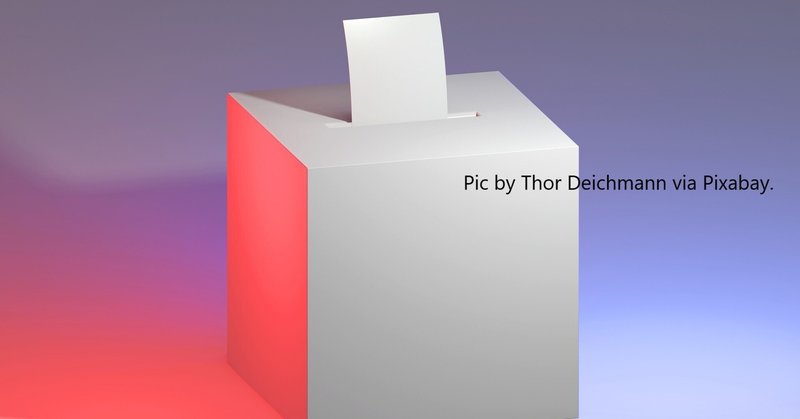
民主主義を教えるということ
ソ連とウクライナの戦争の報道を見ていると、民主主義って、というよりも民主主義教育って何なのだろうと考えてしまう。
あ、もちろん今は「ソ連」ではなくロシアなのだが、ソ連の頃と大差ないじゃん、と思いながら書いていたら、そのままソ連と打ってしまった。
ソ連が崩壊してロシアになったのは1991年。それから30年とちょっと。
ちょっと待て。ワタクシが社会人になったとき、1年数ヵ月間ではあるが、まだソ連があったということか。この辺りの記憶が曖昧だった。
さてと、これはちょっと前の話だ。ワタクシは、2月に北海道新聞に載った記事の内容に、少なからずショックを受けた。
いずれリンクは切れてしまうだろうから、要約を載せる。
この記事は、2月23日の北海道新聞朝刊の「小中高生の文でつくる新聞 ぶんぶんtime」という企画の中に掲載された。「悩みごとナビ」というコーナーに寄せられた、小学5年生の女子児童のお悩みだ。
学校の児童会役員選挙に、彼女のクラスメイトが立候補した。担任の教師は「みんなで応援してあげよう」と言ったが、彼女は隣のクラスから立候補した児童の方が適任者だと思ったため、後者に投票した。
翌日、担任教師から「このクラスから、同級生に投票しなかった人がいたのが残念だった」と言われた。裏切りを責められたような気がする。
「なんだこりゃ」と思った。児童会選挙というのは、それまでのクラス内の学級委員選出などから一歩外に踏み出して、人生で初めて参加する選挙らしい選挙であろう。
文面から察するに、誰が誰に投票したのかまでは開示されていなかったようではあるが、それにしてもだ。こんなへなちょこな難癖を大人から浴びせられたら、それはそれは自責の念に苛まれるに違いない。この教師は、民主主義を何だと思っているのだろうか。
投書本人の彼女は何も悪くない。
あるポストに対し、立候補者が複数名いた。そこから、彼女は自分が最適任者と見なした人物を自分の意志で選んで投票した。
それだけのことだ。選挙権を持つ成人が様々な選挙で行使する「自由意志による投票」と何ら変わらない。
学校というのは、人間が家庭の次に得る社会だ。その社会の中で、先生と呼ばれる大人は、子どもにとってほんとうの社会で役に立つこと、必要なことの予行練習をさせなくてはいけないはずなのだ。
なのに、その正しい行為をよりによって社会の大先輩で師でもある立場の人によって否定されるとは。
この悩みを投書をした女子児童が、これからの選挙人生に向けて、心に傷を負わないことを祈る。5年生は11歳。あと7年で選挙権を手にする。7年なんて、あっという間だ。
ワタクシがこんなところで心配しなくても、新聞では回答者の方が「あなたの行為は正しく素晴らしいもの」と答えていらっしゃるので、大丈夫だと思っている。
どうか、忖度に振り回されない人生を歩んでいけますように。このお嬢さんのような子どもたちが、20年、30年先のこの国を作っていくのだから。
ワタクシがこのお嬢さんの親だったら、この話を聞いたら担任教師に詰問するな… うん。
興味を持ってくださりありがとうございます。猫と人類の共栄共存を願って生きております。サポート戴けたら、猫たちの福利厚生とワタクシの切磋琢磨のために使わせて戴きます。
