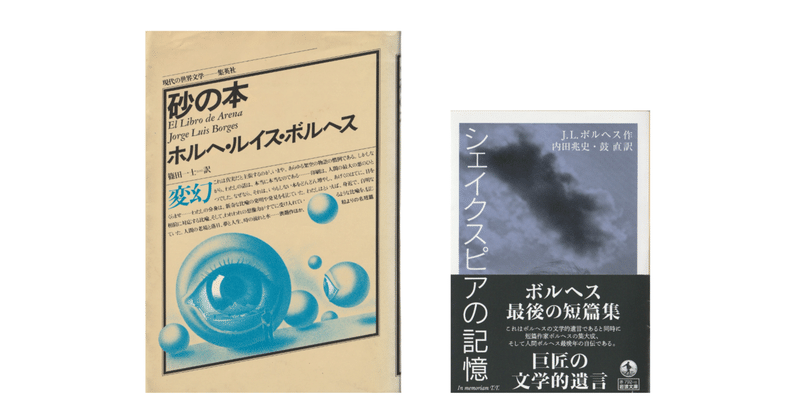
ボルヘス『シェイクスピアの記憶』
☆mediopos3328 2023.12.28
ボルヘスの最後の短篇集
『シェイクスピアの記憶』が訳出されている
収められているのは
「一九八三年八月二十五日」
「青い虎」
「パラケルススの薔薇」
「シェイクスピアの記憶」の四篇
一九七七年に刊行された『薔薇と青』は
「パラケルススの薔薇」と「青い虎」の二篇のみであり
「バベルの図書館」シリーズの一巻では
「シェイクスピアの記憶」が入っていないが
本短篇集はボルヘスが亡くなった後の
一九八九年に全集の続刊が出る際
『シェイクスピアの薔薇』というタイトルのもと
単独の短篇集となっている
帯にも記載されているように
本短篇集はボルヘスの「文学的遺言」であり「集大成」
そして「人間ボルヘスの最晩年の自伝」ともなっていて
分身・夢・記憶・不死・神の遍在といったテーマが
作品間で響き合っている
「一九八三年八月二十五日」では
「いったい誰が、誰を夢みているのだろう?」と
異なる年齢の二人の「ボルヘス」が出会うが
かつて発表された同様のモチーフの短篇では
二人ともボルヘスの経験上の二人だが
本短篇ではまだ作者自身も知らない自分を
かつての自分と立ち会わせている
この経験は実際には起こるかどうかわからないが
ある程度だれにでも想像できる経験かもしれない
ある年齢の自分をそれより若い自分と対話させる
しかし自分がまだ経験していない自分が
ある年齢の自分と対話するとどうなるだろう
ひょっとしたら私たちは常に
そんなことを無意識にあるいは夢で行いながら
生きているのかも知れない・・・
「青い虎」では
「芸術の象徴でありつつ現実の象徴」である「虎」が
不条理な姿の「石」となってあらわれる
ボルヘスにとって「虎」は重要な象徴的存在だが
私たちにもそうした象徴的なものが存在するのではないか
不条理なまでの姿で繰り返しあらわれてくる
ある意味じぶんの分身でもある存在であり
そうした存在を知性や条理やでとらえることはできない
「パラケルススの薔薇」では
賢者の石に達する道を求め
弟子になろうとパラケルススを尋ねてきた者が
灰にした薔薇を元にもどす奇跡を見せてくれるよう求めるが
パラケルススはそれにあえて応えない
賢者の石をつくる錬金術は
いわゆる超能力なるものを得るためのものではない
それは魂の精練の結果として得られるものであって
結果を得んがための探求はその当初において錯誤している
「シェイクスピアの記憶」では
「シェイクスピアのすべての記憶を与えられた者が、
だからといってシェイクスピアとなるわけではないことが
明らかにされる」
記憶とはなんだろう
だれかの記憶をじぶんのものにしたところで
それはじぶんのものといえるだろうか
さらにいえばじぶんの記憶だと思っている記憶は
はたしてじぶんの記憶だといえるのだろうか・・・
本短篇とは関係しないが
映画『ブレードランナー』の
記憶をインプットされたレプリカントを思いだした
レプリカントにとってその記憶は
じぶんのアイデンティティそのものであるにもかかわらず
インプットされたものにすぎないことが明らかになり
みずからの死に向きあったときの深い悲しみが胸を打つ
ボルヘスの数々の小説や詩を読むと
その迷宮のなかを
さまざまな思いをめぐらせながら
さまよいはじめるじぶんを見つけることになる
ボルヘス最後の短篇集である本書には
ボルヘスの紡いできた話のモチーフの核が凝縮され
「記憶」に残るだろう一冊となっている
■J.L.ボルヘス(内田兆史・鼓直訳)
『シェイクスピアの記憶』(岩波文庫 2023/12)
■ホルヘ・ルイス・ボルヘス(篠田一士訳)
『砂の本』(集英社 1980/12)
(『シェイクスピアの記憶』〜「一九八三年八月二十五日」より)
「「私は上の中庭に面した十九号室で君を夢みている」
「いったい誰が、誰を夢みているのだろう? 私が君を夢みていることはたしかだが、君が私を夢みているかどうかはわからない。アドロゲーのホテルはずいぶん前に、二十年前に、いや三十年前に、取り壊されてしまった、たしか」
「夢みているのは、この私だ」挑むような調子で私は答えた。
「大切なことは、夢みる一人の人間が存在するのか、それとも二人の人間が夢みているのか、その点を明らかにすることだということに君は気づいていないようだ」
「私がボルヘスで、宿帳の君の名前を見て、ここへ上がってきたのだ:
「ボルヘスはこの私で、マイプー街で息を引き取りつつある」」
(『シェイクスピアの記憶』〜「青い虎」より)
「ブレイクはその有名な作品の一節で、虎を光りかがよう炎と〈悪〉の永遠の原型に仕立てている。私はむしろチェスタトンのあの言葉を好ましいと思う。彼は、この上ない優雅のシンボルと虎を規定している。そのほかに、何百年も前から人間の脳裏に宿っているあの形象、虎の記号たり得る言葉は存在しないのである。(・・・)おそらく虎への愛着ゆえに、私はアバディーンからパンジャブへ引き寄せられたのである。私の日々はなんの変哲もないものであり、夢ではいつも虎を見ていた(今では別の形をしたものがそこには蠢いている)。」
「子を産むという石だ、こいつは!」と彼は叫んだ。「今でも大変な数だが、まだまだ増えるぞ。形は満ちているときの月の形で、色は夢でしか見ることのできないあの青い色を帯びるんだ。わしの親のそのまた親が小石の力の話をしていたが、あれは嘘ではなかった」」
(『シェイクスピアの記憶』〜「パラケルススの薔薇」より)
「パラケルススは一人になった。ランプを消し、使い古した肘掛け椅子に腰を下ろす前に、わずかな灰を手のひらにのせて、小さな声である言葉を唱えた。薔薇は甦った。」
(『シェイクスピアの記憶』〜「シェイクスピアの記憶」より)
「私は一語一語はっきりと口にした。
「シェイクスピアの記憶を、いただきましょう」
なにかが起こったことは疑いようもなかったが、私にはそれが感じられなかった。
ほんの少し、疲労の先がけのようなものを感じたが、ただの思い込みかもしれなかった。
ソープが私に言ったことははっきり覚えている。
「記憶はすでにあなたの意識に入りました、とはいえそれを発見する必要があります。それはあなたの夢のさなかに、眠れない夜に、書物の頁をめくる折りに、あるいは道を曲がったそのときに浮かんでくることでしょう。焦ってはなりません。記憶を作り出そうとしてはいけません。神秘的なできごとによくあるように、偶然が手を貸してくれることもあるでしょうし、あるいはその瞬間を遅らせることもあるでしょう。私が忘れていくにつれて、あなたが思い出すようになっていくのです。いつまでにと、お約束することはできませんが」」
(『シェイクスピアの記憶』〜内田兆史「解説」より)
「時期的にも、系統的にもその『砂の本』に連なる本書『シェイクスピアの記憶』について、まずはその成り立ちからふり返っておこう。『砂の本』の二年度、一九七七年にスペインのセドマイ社から、『薔薇と青』と題された短篇集が刊行される。短篇集と言っても収録された作品はわずかに二篇、ともにこの本が初出となる「パラケルススの薔薇」と「青い虎」だった。一九八〇年にはイタリアのフランコ・マリア・リッチ社から、同社はボルヘスに編纂と序文の執筆を依頼して一九七五年から刊行を開始した世界文学選集「バベルの図書館」シリーズの一巻として、「一九八三年八月二十五日」と「パラケルススの薔薇」、「青い虎」、そして『砂の本』所収の「憑かれた男のユートピア」、さらにマリア・エステル・バスケスによる一九七三年のインタビューが収録された『一九八三年八月二十五日、およびその他の短篇』がイタリア語で出版される。このシリーズは日本でも八〇年代終わりから九〇年代初頭にかけて国書刊行会から刊行され、当該するボルヘスの巻は『パラケルススの薔薇』という書名を与えられており、本書はこの日本語版を礎としている。(・・・)
「シェイクスピアの記憶」が発表されたのは一九八〇年の五月、『クラリン』紙上でのことだった。一九七九年七月のアントニオ・カリソとのインタビュー『記憶の人、ボルヘス』で「シェイクスピアの薔薇」という短篇を二年かけて書き終えた、と述べ、同年十一月下旬に東京で受けたインタビューでは「近く出ることになっている私の一番新しい作品」と紹介している(「迷宮の森をさまよって」)。
(・・・)
最晩年の短篇四篇については、『薔薇と青』では二篇を欠き、「バベルの図書館」シリーズの一巻にはインタビューや書誌情報が含まれる上に『砂の本』と一篇が重複し、なにより「シェイクスピアの記憶」には帰属する短篇集がない、といった問題があったが、ボルヘスが亡くなった後の一九八九年に全集の続刊が出る際にこの四篇が『シェイクスピアの薔薇』というタイトルのもとにまとめられ、現在では単独の短篇集として流通している。
「バベルの図書館」シリーズの『一九八三年八月二十五日』(日本では『パラケルススの薔薇』)に、『砂の本』から収録された「憑かれた男のユートピア」は、先に挙げた詩「くたびれた旅人が手にするのは」とともに、ボルヘス自身が死の直前に編んだ自選集(・・・)にも収録され、自身が「その憑かれた男とは私のことだ」と述べるとおり、晩年のボルヘスの偽らざる心情を吐露した作品である。本書は、作品の数こそきわめて少ないが、その「憑かれた男のユートピア」以上に、ボルヘスの文学的遺言であると同時に短編作家ボルヘスの集大成、信仰告白でもあり、同時に人間ボルヘスの最晩年の自伝であるとも言えるだろう。」
(「一九八三年八月二十五日」)
「同じく異なる年齢の二人の「ボルヘス」が出合う短篇「他者」(『砂の本』)では、七十歳に手が届こうとするボルヘスが、ハーバード大学の近くで、ジュネーブにいる十代のボルヘスと出会う。相手がかつての自分であることを証明しようと老いたボルヘスがジュネーブの家の書架に並んでいた蔵書をあげ連ねるなど、いかにもボルヘスらしいモチーフに溢れたこの短篇が発表されたのは一九七二年で、どちらのボルヘスも、作者が「経験」しているボルヘスである。それに対して「一九八三年八月二十五日」は七十年代の終わりに書かれており、作家は過去の自分を、まだ作家自身も知らない年齢の自分と立ち会わせている。」
(「青い虎」)
「虎は、芸術の象徴でありつつ現実の象徴でもあり、それゆえ宇宙が人間にとって整然たるコスモスではなく不条理なカオスであることを表すモチーフとなっている。」
(「パラケルススの薔薇」)
「「パラケルススの薔薇」は、ド・クインシーの語るパラケルススのエピソードに想を得ながらも、むしろ作中のパラケルススは、人間には神の創った世界を変えることなどできない、神の力に対して人間ができることはほんのわずかである、という信念に基づいて錬金術を行う。」
(「シェイクスピアの記憶」)
「「シェイクスピアの記憶」では、シェイクスピアのすべての記憶を与えられた者が、だからといってシェイクスピアとなるわけではないことが明らかにされる。シェイクスピアはその経験によって、その記憶によってシェイクスピアになったわけではなかった。(・・・)むしろシェイクスピアは何者でもなかったのだ。そしてそれゆえ、あらゆる人であり、それこそがシェイクスピアをシェイクスピアたらしめていた。それでもゼルゲルは、シェイクスピアの記憶に彼自身の記憶が呑みこまれることを恐れ、ゼルゲル自身であろうとする。」
「ボルヘスはしばしばみずからの不幸を嘆いているが、彼の作品は世界の読者に読む喜びを、そしてボルヘス自身には書くことによる癒やしを与え、彼自身を救い続けた。ボルヘスもまたゼルゲルであり、そして、それ以上に、「人間ならだれもが経験する」些末でおそろしいことを寓話に、「何世代にもわたって受け継がれる」作品への移し替えることができたシェイクスピアだったのだ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
