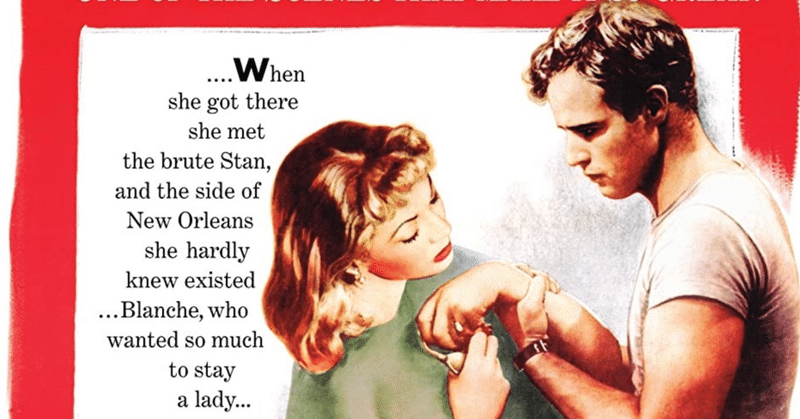
欲望と時間/俳句、ジョン・ケージ、ジャック・ケルアック
私事ですが、欲望の主体(※1)によって人間を論じることに限界があるということに気付きました。新しい主体性の在り方、あるいは主体を必要としない存在論というものについて、ちょっと考えてみたいと思います。その前に、少しだけ欲望の主体についてお話をしましょう。
1
今日では、わたしたち人間の存在は欲望が規定するものと考えられています。現代社会において、わたしたちの自己同一性は、欲望がなければ規定できません。
それ故、わたしたちは幼少期から繰り返し「何が好きなのか?」「何がしたいのか?」を尋ねられてきました。好きな色、好きな食べ物、好きな動物、行きたい場所、就きたい職業、目標とする人物…
わたしたちが誰なのかを決めるのは欲望とその対象なのです。面接官は尋ねます。
「この会社で何がしたいのか?」。恋人は尋ねます。「わたしのどこが好き?」カフェ店員は尋ねます。「ご注文は何になされますか?」わたしが店で何かを買うのは、わたしがそれを欲しいからだと誰もが思い、そう判断されます。メディアで発表されるあらゆるランキングが、「人々が何を求めているのか」を表し、その指針を示します。あるいは恋愛観。異性愛なのか?同性愛なのか?あなたが欲望の対象としている人物は、社会的に適切な相手なのか?人が何を欲望するのかが、社会的に大きな問題となります。
近現代において、人間の自律性とは、欲望の発露によって保証され、それと同義的なものとされてきました。欲望を持たない人間はいません。ヘーゲルに言わせれば、欲望がなければ意識もなく、もしそうであれば、世界も何も存在しないということになります。なぜなら、何かを知覚するということは、その対象を自己意識として同一化しようとする欲望があるということと同義だからです(※2)。欲望と同義的なものとして捉えられた場合の志向性は、意思に先立つものとして、アプリオリな領域で、人間の世界理解の地平を生み出します。近現代において、世界とは欲望を照らし出す鏡であり、それがわたしたちの生のすべてだと考えられるようになりました。
そのことは、ヘーゲルからフロイト、コジェーヴ、サルトル、ラカン、フーコー、バトラーなどを通して、近現代における一貫したテーマだったと言えます。
率直に言って、その間ずっと「わたし」の存在とは、欲望の存在論、その志向性の矢印の束のことだったのです。そして、他ならぬその欲望と主体性の等式こそが、近現代的な社会システムである「資本主義」と「民主主義」を持続し得るものにしたのでした。
それらの社会システムにとって、欲望の論理 ー すなわち、抑圧と解放 ー は、社会を滞りなく運動させるための歯車です。
しかし、このことは、様々な問題を生み出しました。なぜなら、わたしたちの欲望が解放されるたびに、逆にわたしたちの存在の方が、欲望に拘束されてしまうという事態を引き起こすことになったからです。わたしたちは、わたしたちの存在を示すために、常に何かを欲望していなければなりません。欲望しなければ「わたし」はなく、欲望されなければ「あなた」はいません。これが、「欲望の存在論」なのです。
2
欲望には時間がありません。欲望とは、対象を「いますぐに」、まさに「そのときに」、欲するものです。欲望は時間を押し潰します。欲望が時間を支配し、踏破しようとするところから、合理性という観念が生まれてきました。合理性は、時間を押し潰し、切り刻み、常に最短を目指します。最短を目指された時間は、己の時間のすべてを、対象に明け渡そうとします。そこでは、己のために残された時間というものはありません。その場合、時間はすべて、欲望された対象を手に入れるために、欲望を実現するための過程として、対象の性質に還元されてしまうのです。(※3)
資本主義、合理的経済とは、まさに「時は金なり(※4)」です。時間は金に還元されるものとして計算の対象になります。現代社会におけるわたしたちの苦しみとは、時間の苦しみなのです。
しかし、これを「時は鐘なり」と読み換えるとどうでしょうか。少し違った世界が見えてくるように思えます。
それについて少し考えてみましょう。
「鐘」とは何でしょうか。それは多くの場合、時を報せるために鳴らされます。その「時」とは、所謂時計で示されるような時間とは異なります。「鐘」が報せる「時」とは、一つの時機、要するにタイミングのようなものです。
正岡子規の有名な俳句に
「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」
というものがあります。
俳句には季語を入れなければなりません。なぜでしょうか?
季語とは、一つの時間性であり、出来事と、それを記述する主体、そして世界との間のパースペクティブを規定する役割を果たします。俳句の中に季語があることによって、俳句はわたしたちの存在に、実在性を持つものとして関わることができるようになるのです。
また、俳句は五七五で構成されています。これはリズムです。音楽の三拍子や8ビートなどと同じものです。リズムもまた一つの時間性です。五七五のリズムは、個々の俳句の持つ固有の時間を表しています。要するに、それを詠む(読む)人 ー 俳人だけではありません ー が「いま」「ここ」で体験する時間、それが五七五のリズムなのです。それは、例えばベンヤミンの言うような「いま」「ここ」ではありません(※5)。俳句には、作者の持つアウラは宿っていないのです。そこでは、俳句を「読む」人が、「詠む」ことを、その時間性を、追体験することによる、その人の「いま」「ここ」が、俳句の持つ「いま」「ここ」と結びつく、ということが起きています。それはもちろん俳人が俳句を詠むときに体験した時間です。しかし、その時間性からは、俳人の主体性は、注意深く取り除かれています。俳句、特に名句と呼ばれるものは、「まるで作者がいないかのように」詠まれているのです。これは、ある意味でデリダ的な言語論が背景にあるように思えます。俳句にあるのは、応答であり、超越論的な能動性ではありません。もう少し簡単な言い方をすると、そこには普遍的で絶対的な独立した自己存在などというものは、どこにもいないのです。
俳人が俳句を詠むのは、世界が俳人に対して、そのように呼びかけたからです。俳人は、その呼びかけに対する応答として、俳句を詠むのです。それは、彼固有の時間です。しかし、俳句には、それを読む人の応答可能性が常に留保されています。なぜなら、それは俳句の中で説明されていないからです。俳人は俳人の感じたままの世界、そこに存在したものをただ羅列するのです。俳句の中の事象は、すべて切り離されたままで、そこに置かれています。俳句が五七五のリズムで読まれるとき、それらは初めて一体性を持つものとして体験されます。五七五のリズムが、俳句に表された事象の時間を動かします。すなわち、リズムという時間性が、それを読む人を俳句の時間に誘い込むのです。それは、詠む人と読む人の間の応答可能性ではなく、世界と読む人との間の応答可能性として提示されています。すなわち、それを読む人は自分の主観性を通して世界と出会うのであり、俳人の世界を追体験するわけではないのです。わたしたちが別々の人間であり、それぞれが異なった時間性を持っている、ということが、俳句にとってとても重要なことなのです。
改めて、「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」を見てみましょう。
季語は柿です。柿は秋の季語です。すなわち、詠み手が柿を食ったのと、鐘が鳴ったのは、秋の出来事だったということが分かります。秋は繰り返し訪れるものです。柿も毎年実をつけます。わたしたちは、毎年柿を食べることができます。それは秋なのです。そこで鐘の音が響きます。鐘が鳴るのは、それを鳴らす人がいるからです。それは、それを鳴らす人の任意によって鳴らされます。毎日決まった時間に鳴らすのかもしれませんが、それは分かりません。柿を食ったことと、鐘が鳴ったことの間には、何の因果関係もありません。しかし、柿を食ったときに、鐘の音は鳴ったのです。その鐘の音には、秋であるということと、柿の味が、それを体験する人の知覚に、同時に響いています。その瞬間がそうであり、その瞬間だけがそうです。その時間はただの一度だけ、詠み手によって体験されました。鐘の音が、まったく無関係に存在していた「秋」「鐘」「詠み手」を結びつけたのです。そして、それらはまたバラバラの時間性に帰っていきます。 その時間は、俳句として結晶しました。その瞬間、世界はそのようにありました。鐘が確かに、秋の音を奏でたのです。時間とはそのようなものであり、それは体験でしかあり得ないのです。それは法隆寺の鐘でした。
ここで重要なのは、柿は秋を象徴しているわけではない、ということです。柿は秋に実をつけます。だから、柿の実を食べると、秋を感じるのです。柿の実は、毎年秋とともに訪れるのです。季語が表現するのはそれだけのことです。季語は季節を象徴する言葉ではありません。ハウス栽培によって、柿の実が冬でも食べられるのであれば、もはや柿は秋の季語ではありません。なぜなら、冬に柿の実を食べるのであれば、柿の味に秋を感じることはないからです。
もう一つ俳句を見てみましょう。
閑さや岩にしみ入る蝉の声
今度は松尾芭蕉です。季語は蝉です。蝉は夏の季語です。この蝉はニイニイゼミだと言われています。蝉の声を聞いているのは俳人ですが、俳句の中には俳人の姿はありません。蝉の声は岩にしみ入っています。すなわち、俳人の目にはそう見えたということです。ここでは、聴覚で捉えられるものとしての音が、視覚に還元されたものとして、あるいは、聴覚と視覚の区別を跨ぐものとして提示されています。すなわち、蝉の声は耳だけで感じられるものではなかったということです。俳人は、蝉の声を聞きながら、同時に閑けさを聞いています。要するに、聞こえないということを聞いています。ここには、視覚と、聴覚と、聴覚の不在が提示されています。俳人は、閑けさによって蝉の声を聞き、蝉の声によって閑けさを認識しています。そして、それは岩にしみ入っているのです。俳人がいなければ決して現象しない場面が描写されていますが、そこには俳人の姿はないのです。先程と同様に、閑けさ、蝉の声、岩という無関係に存在しているものたちが、俳人の体験する時間によって、一つになっています。この俳句は、音と、無音と、その印象が投影されたものによって詠まれています。とても音楽的な俳句だと言えるでしょう
20世紀を代表する前衛音楽家ジョン・ケージの作品に、時間の名前が付けられた最も有名な曲があります。『4分33秒』がそれです。これは、この俳句と類推的に見ることができる作品です。この作品は無音の曲です。第三楽章まである楽譜には、休止の指示が3つ書かれてあるだけです。しかし、仮に演奏者が奏でる音が無であっても、鑑賞者の置かれた空間が無音であることは決してありません。鑑賞者は、演奏者が何も奏でないことによって、空間の中に響く音 ー 空気の流れや、衣摺れ、あるいは風で草葉の揺れる音 ー などを聴くのです。『4分33秒』は、演奏者が音を奏でる時間ではなく、奏でない時間に名前が付けられた曲だということです。
以上のことから、この俳句とこの曲には、よく似たところがあるということが分かります。
しかし、異なる点もあります。この作品に出てくるものは、「(演奏をしない)演奏者」、「鑑賞者」、それとその「外部」です。この曲の核となっているのは、「演奏者」「が」何も奏でないことによって、「鑑賞者」「が」それによって「外部」の、こう言って良ければ、ノイズを聴く、ということです。そこにあるのは、表現/知覚主体としての「演奏者」であり、「鑑賞者」であり、音はあくまでもその「外部」としてのノイズなのです。この曲においては、ノイズが積極的なものとして音を奏でることはありません。無音もまた、演奏者が演奏をしないことによって、消極的に姿を現すだけなのです。あくまでも、ノイズと無音は、主体が沈黙することによって非主題化されたものとして姿を現わすだけなのです。『4分33秒』は、人間の主体性が沈黙する時間であり、その時間が経過した後には、演奏者達は音を出すことを許されます。その時間は、もちろん時計によって計られるものです(この曲のタイトルは、時計が発展した後でなければ、決してつけられなかったものでしょう)。
一方、子規の俳句には、主体がどこにもありません。そこには、主体と客体、能動性と受動性の二項対立が、読む人に見えることはないのです。いずれ分裂を約束された中動態のようなものすらありません。閑けさは閑けさです。岩は岩です。蝉の声は蝉の声です。そして、それは偶然にも同時にありました。それだけです。
ジョン・ケージの作品では、音のための場が、一つの闘争とせめぎ合いの場として示されています。ある音が退場し、ある音が現れる。ある音はある音によって隠蔽され、抑圧されている。正しい音、美しい音に対立する形で、雑音や不快音があるというのがこの曲の主題です。作曲者や演奏者、あるいは鑑賞者が、いずれの音に与するにせよ、そこに提示されているのは対立する音と音の関係なのです。
しかし、芭蕉や子規の俳句には、そのような解釈が入り込む余地はありません。複数の音、複数の存在を繋いでいるのは、ただ時間だけなのです。それが同時であるか、継起的であるか、持続的であるのか。そういった時間の体験だけが、音と音、存在と存在の関係を記述しているのです。
3
わたしたちの主体性を構築しているものは、そのすべてが元々はノイズとしてあったものです。人は、それらのノイズの中に法則 ー 共通する何かを持つ複数の対象/印付けられたタイミングによって区切られた時間性を持つものとして捉えられる現象など ー を発見することによって、それを秩序付けようと欲します。ノイズをあるまとまった形を成すものとして統一するためには、その基準となるものが必要とされます。それは、変わらないもの、同一性を持つもの、繰り返されるものでなければなりません。わたしたちが拠り所とするもの、すなわち客観的時間性とは、「陽はまたのぼり繰り返す」ということ、「月は満ちまた欠ける」ということ、あるいは四季の変遷と循環などです。
わたしたちの固有の時間としての主観的時間性は、それだけではまとまりを持った統一性を実現し得ません。主観的時間性は、上に挙げたような客観的時間性と並走しながら、その中にリズムを産出します。この繰り返されるものとしてのリズムが、知覚する主体としての「わたし」を形成するための土台となるのです。それは、夜眠り、朝起き、その度に持続するものとして確認される意識と記憶なのです。
そこでは、ヘーゲルやバトラーが記述した「欲望の主体」が一つの役割を果たすこともあるでしょう。しかし、その役割はあくまでも端役としてです。欲望は、主観的時間性を狂わせるリズムの変調として登場するのです。
わたしは、欲望の主体に代わる主体性の記述を、時間によって行いたいと考えています。
ここで言う時間とは、「何時何分」のような時刻や、「何時間何分何秒間」のような尺度によって計測されるものではありません。
わたしは時間という言葉を、音楽でいうリズムのようなものとして考えています。音楽における時間の継続性は、拍によって分割され、規定されます。この拍の起源は心拍、すなわち心臓の音だと言われています。心拍は、身体と精神の関係を繋いでいます。心拍が早まると精神は焦燥し、緊張します。また、心拍が安定すると、精神もまた同じように安定します。逆もまた然りです。これがそれぞれの人の固有の、主観的な時間性の起源です。この心拍を基礎とした主観的時間性は、現象、対象、他者、あるいは、病気や知覚できない様々なものと密接に関係しています。固有の時間性とは、自分以外のあらゆるものの影響とともにあります。それは先述した通り、客観的な時間性 ー 太陽、月、季節などの変遷 ー と並走しているのです。それらのものが「客観的」であるのは、主観がそれを繰り返されるものとして意識するからであり、それは変わらず、何度も何度も反復され、途絶えることがないからです。時計が示す時間のように、「それがそう定められているから」では決してありません。
このあらゆるものとの関係としての主観的時間性と、客観的時間性との並走によって、欲望に代わる主体性の記述が可能になります。リズムとは、精神と身体、それらを取り巻くあらゆるものと対話するための「拍=点」の集積なのです。しかし、その「点」の集積は、決して数学的記述のような直線を描きません。もちろん時計が刻むような時間性は、この点を直線的に配列し、一次元的なものとして捉えるように主体に指示します。しかし、主観的な時間性とは、決してそのようなものではないのです。
そのことを説明するために、今度はホットケーキの話をしたいと思います。わたしが子供のころ、わたしの家では、朝食としてホットケーキが焼かれることがありました。わたしはホットケーキがそれほど好きではありませんでしたが、兄は大好きで、わたしもホットケーキが好きだと言った方が子供らしく見えて大人から好かれると思ったので、喜んでいる振りをしていました。その振りが上手くいっていたのか、それとも親はわたしの心情が分かった上でのことだったのか分かりませんが、わたしの家ではたびたびホットケーキが朝食に出ました。以上がわたしの持っている太宰風の「ホットケーキの記憶」です。この記憶は、わたしにとって「流れ去るいま」として刻印されている記憶です。要するに、これはわたしの過去なのですが、この記憶は、数年にわたって年に何回か行われてきたわたしの家での出来事によって刻印されている「ホットケーキの記憶」です。この記憶は繰り返し反復されてきた複数の「流れ去るいま(※6)」によって刻印されていますが、わたしの記憶としては一つです。すなわち、この記憶は、互いに交換可能な不特定の時間位置を持つものとして刻印されているため、直線的に配列された記憶の点の集積の中に特定された時間位置を持つことはありません。記憶とは、そして時間とは、得てしてそういうものなのです。
4
わたしは、わたしの過ごしてきた時間について、すなわち、わたしが体験したものとしてのわたしの過去について知っています。わたしは、わたしの未来については知り得ません。わたしが知っているのは、わたしの過ごしてきた時間についてであって、わたし以外の人物、すなわち他者の過ごしてきた時間については知り得ません。以上は非常に単純なことですが、わたしはこのことについて忘れがちです。わたしの過ごしてきた時間は、わたしだけが知っているのであり、他の誰にも知り得ません。わたしの時間と、他者の時間は、交換することはできません。また、わたしの時間を、他者の時間として考えることもできません。先の場合と同様に、逆もまた然りです。しかし、多くの場面で、わたしはこのことを忘れています。このことを忘れるということは、すなわち、わたしがわたしの過ごしてきた時間を忘れているということです。そのとき、わたしはわたしの過ごしてきた時間が、わたしの過ごしてきた時間ではないように感じています。同時に、わたしは誰かわたし以外の人物の時間を知っているように感じています。しかし、それは端的に間違えています。わたしにはわたしの過ごしてきた時間以外を、知るすべはないからです。わたしの過ごしてきた時間とは、わたし自身のすべてです。そして、それはわたし以外のあらゆるものによって作られた時間でした。わたしがわたしの時間を、わたし以外の人物の時間だと感じているとき、わたしは無意識です。これは、フロイトやラカンが精神分析学的な意味で言う「無意識」と同じ意味で使っています。彼らは無意識が錯誤を作り出すと考えました。しかし、無意識はそれそのものが錯誤であると考えた方が都合が良いように思います。すなわち、精神分析学的な意味における無意識は、自分の時間を自分の時間ではないように感じてしまう錯誤によって生み出される虚の時間だということです。
ここで再び俳句の話をしましょう。
かつて、日本の俳句に興味を持ち、これを英語で詠んだ人物がアメリカにいました。『路上("On the Road")』の著者として日本でも有名なジャック・ケルアックがそうです。ケルアックは、英語と日本語の文法の違いに留意しながら、短い三行詩を俳句として詠みました。日本語の俳句は、五七五の音節がリズムとして規則付けられていますが、彼はリズムの異なる英語の場合には、そのことに拘る必要はないと考えました。
幾つか、彼の書いた俳句を見てみましょう。
2 traveling salesmen
passing each other
On a Western road
二人の営業マンが 西の道で 互いにすれ違っている
A balloon caught
in the tree – dusk
In Central Park zoo
夕暮れどき セントラルパークの動物園で 風船が 木に引っかかった
And the quiet cat
sitting by the post
Perceives the moon
そして 寡黙な猫は ポストの上に座って 月を感じる
Alone, in old
clothes, sipping wine
Beneath the moon
月の下 古着を着て 一人で ワインを啜っている
A raindrop from
the roof
Fell in my beer
屋根から 雨粒が わたしのビールの中に落ちた
Answered a letter
and took a hot bath
- spring rain
春の雨 手紙の返事を書き 熱い風呂に入った
英語には、完了形など日本語にはない多くの時制があります。英語は、日本語に比べて、動詞と時間の関係がより厳しい言語だとひとまず言っておきましょう。
しかし、ケルアックの俳句を見ると、この時制の表現がかなり制限されていることが分かります。
ケルアックが俳句表現において好んで使う時制は、現在形、現在進行形、過去形の3つです。
彼の俳句に描かれているのは、多くの場合、過去と、その先端である現在、それだけのように思われるのです。そして、それらの時制によって表現されたものは、同時性ということによってのみ結びつけられています。彼の俳句には、二つの離れた時間を結ぶための完了形や、まだ起きてないことについて語るための未来形が使われていることが極端に少ないように思えます。すなわち、これが、彼の発見した「俳句の方法」なのだと思われるのです。
なぜケルアックの俳句には、未来形と完了形が使われていないのでしょうか。
英語で未来形は、"will"を使って表現されます。"will"は、「意志」すなわち、志向や欲求を表す言葉です。未来とは、バトラーやマラブー(※7)がヘーゲルを正しく読解しながら指摘している通り、「意志」によって開かれるものです。俳句の描く世界には、この「意志」というもの、すなわち欲望が開く未来というものはありません。少なくとも、ケルアックにはそう感じられたのではないでしょうか。英語には必ず主語があり、動詞があります。しかし、その二つは意志によって結ばれるのではなく、偶然性によって結ばれているのです。
では、完了形はどうでしょうか。先述した通り、完了形とは、二つの隔たった時間を結ぶためのものです。そのためには、主語が異なる時間性の中で、同一性を持続させる必要があります。そうでなければ、主語と動詞が必ずセットになる英語の文法において、完了形を実現させることは出来ないからです。ケルアックは、この主語の同一性を表現することに対して抵抗を感じているのです。わたしがわたしであること、(同じ意味ですが)わたしの捉えた対象が異なる時間の中で同じものとしてわたしの前で現象し続けることは、偶然の同時性の世界を描く俳句の世界では、非常に稀有なこととして考えられるのです。
ケルアックは、俳句が、音楽的なものであることにも気付いていました。
その証拠に、彼がジャズ奏者と共演した音源『Blues&Haikus』(※8)があります。ジャズの即興演奏には楽譜がありません。すなわち、演奏者が「この後で何を弾くのか」という「未来」が決まっていないのです。その意味で、ジャズは過去の集積による現在の音楽と言えます(※9)。ジャズの即興演奏とは、「前に鳴った音=過去」を意識しながら、現在においてそれと対話する音楽なのです。ジャズの即興における演奏は、演奏者による後ろ向きの意識によって進行します。ケルアックが解釈した俳句もまた同様に後ろ向きです。これは、「現在」を生きる意識にとって、当然のことなのです。なぜなら、わたしたちは過去のことしか知らず、そのことについてしか表現することはできないからです。
ケルアックは、50年代のアメリカにおける文学活動であるビート・ジェネレーション(Beat Generation)/ビートニク(Beatnik)の代表的な作家と言われています。
英語のビート(Beat)は、音楽のリズム、拍子などの意味と、心臓の鼓動、動悸などの意味を合わせ持つ単語です。ビートとはつまり、主観的な時間性と客観的な時間性を結んでいる言葉なのです。
俳句を書いているとき、ケルアックはどのような生活を送っていたのでしょうか。彼の代表作である『路上("On the Road")』は、過去・現在・未来が意志によって繋がっていました。それが"Road"という言葉の持つ意味です。
しかし、彼の俳句を読む限り、この頃の彼は移動せず、日々の暮らしを淡々と過ごしているような印象を受けます。ケルアックがこれらの俳句によって伝えていることとは、俳句が描写する自己は一回限りのものであるということ、すなわち、自己とは事故である、ということであり、それは決して持続しないということなのです。
少し長くなりました。以上が、わたしが欲望と時間について考えたこと、その序文です。
※1ジュディス・バトラー『欲望の主体』…ヘーゲル『精神現象学』、コジェーヴ『精神現象学入門』などを基に、「欲望の主体」の生成変化を記述しつつ、そのフランス哲学における受容について論じたバトラーの博士論文。
※2「ヘーゲルは、「自己意識一般は欲望である」と主張している。これによってヘーゲルが言わんとしているのは、欲望は、意識の反省性reflexivityを意味するということ、つまり意識が自分自身をしるためには自分とは別なものになる必要があるということである」(ジュディス・バトラー『欲望の主体』53頁)
「欲望がこのような反省性の原理であるということはつまり、意識にとって外にあるものとの関係が主体自身の本質的な構成要素となっていることが見出されたときに、欲望は満足させられるものであるということだ。……ヘーゲル的主体は、その冒険の道のりにおいて他者性を通じて拡がっていく。主体は自分の欲望する世界を内面化し、当初は自分に対する他者として向き合っていたものを包含し、みずからそうしたものとなってしまうまで拡大する」(同上55,56頁)
※3その意味で、資本主義と共産主義は、同じ時間概念を共有していると言うこともできるでしょう。計画経済という考え方は、欲望の経済から合理性のみを抽象したものです。しかし、合理性の理念は、欲望と切り離すことができません。共産主義が挫折するのは、当然のことだったということが分かります。
※4「時は金なり」の語源は、"Time is money"です。要するに、翻訳であって、その元は日本語ではありません。
※5ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』
※6「「生き生きとした現在」は、自我機能として生起する幅のある現在であり、原印象と未来予持と過去把持とをいわば位相契機として含む直観的前野である。この拡がりをもつ現在は、絶えず流れの場所としてそこに立ち臨む「立ち止まるいま」と、絶えず時間点として過ぎゆく「流れ去るいま」という二つのいまの相互に依属しあった統一的事態である。「立ち止まるいま」は恒常的な「いまの形式」であり、「流れ去るいま」は内容的な、時間位置的な「いま」であり、絶えず複数化してゆく「いま」である。「立ち止まるいま」は「流れ去るいま」の場所であり、「流れ去るいま」は「立ち止まるいま」をくぐり抜け流れ去ることによって互いに交換不可能な一定の時間位置を刻印される」(新田義弘『現象学』210,211頁)本文中の「ホットケーキの話」は、これに対する反駁として書かれたものです。
※7カトリーヌ・マラブー『ヘーゲルの未来――可塑性・時間性・弁証法』
※8ジャック・ケルア『Blues&Haikus』https://youtu.be/UyktuCjOisc
※9「フリー・ミュージックは……音楽的創造の瞬間、つまりその場のグループの現前を強調する。哲学的には、これは超越的なものを意味し、そこにいるものは時間の外、つまり社会的に構築された時間と空間の外に連れ出され、そしてそれゆえ分析や評価や批判から逃れた自己充足的なものとなる」(ポール・ベガティ『ノイズ/ミュージック 歴史・方法・思想 ルッソロからゼロ年代まで』95、96頁)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
