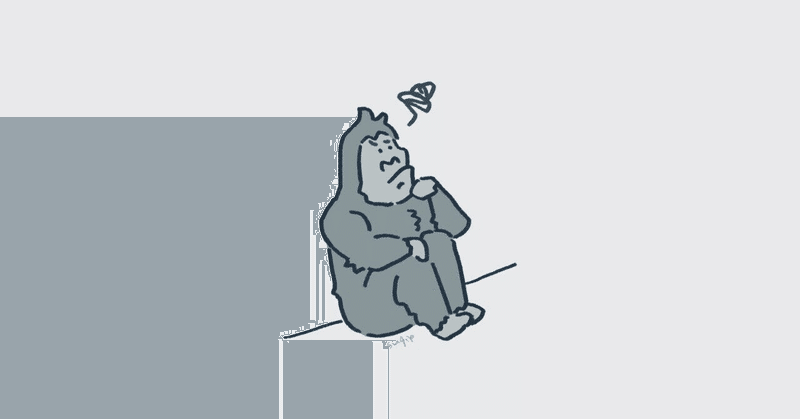
うつ状態の原因は後頭下筋群の凝り?!〜頸の機能を向上&回復させるセルフケア〜
【本要約】アゴを引けば身体が変わる〜腰痛・肩こり・頭痛が消える大人の体育〜
かなりの要約下手ですが、自分の理解を深めるためにもnoteにまとめてみました◎
今回は頸(くび)の筋肉である後頭下筋群は何なのか、後頭下筋群の凝りの症状、頸の機能を回復させるためのセルフケアなどについて。※4700字ほどあります。
第4章:『頸(くび)の痛みと全身の不調』
頸の痛みはマイナー?
肩こりや腰痛に関する書籍は山のようにあるけれど、頸の痛みに関する書籍は圧倒的に種類が少ない。
それは、頸と肩はつながっていて別々に扱うものではないから。
頸部は頭の重さを支えながら脊髄を保護しつつ、可動性(動きやすさ)を保たなければいけないため、とても複雑でデリケートな構造になっている。
腰痛の治療で事故に発展するリスクは低いけれど、頸の治療は事故につながってしまうこともありうるため、頸を扱うことは難しい。このことが、頸の痛みをテーマとして扱うことが敬遠されてきた一つの理由。
後頭下筋群とは?
後頭下筋群(こうとうかきんぐん)とは・・・頭と首の境にある4筋肉の総称で
(大後頭直筋、小後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋)顔や頭の向きを細かく調整している筋肉群のこと。
後頭下筋群の役割とは・・・姿勢のバランスを保つために必要な情報を「視覚系、前庭器官(内耳にある平衡を司る器官)、感覚運動系」と連携しながら、脳に送っている。

参考:URL
後頭下筋群の凝りによる症状
顎が上がっていたり前に出たりした状態で、後頭下筋群が短縮して硬化したり、蓄積疲労や頸の外傷などで後頭下筋群や周辺の筋肉が凝り固まると・・・
↓
脳への血流が低下するだけでなく、他の器官から集められた情報と誤差が生じて
・めまい
・姿勢の不安定性
・眼球運動の機能低下
・頭部のふらつき
よって、後頭下筋群が凝ると、さまざまな器官からの情報が脳に伝達されても、それを瞬時に処理する能力がなくなってしまう。
他にでる症状としては、
見ている景色と思考が分離して、まるで映画のスクリーンを見ているような感覚
雲の上を歩いているようなふわふわとした感覚
やる気はあるのに頭の中の歯車が噛み合わず、喋っていても自分の中の他人が喋っているような感じになる
自分の存在にリアリティがなくなり、今まで意に介さなかったような些細なことでもストレスに感じたり、悲しくなったりする
目がうつろで覇気がなくなる
など。
これまで心身症を患っている人を大勢面談してきたが、皆アゴが上がって後頭下筋群にストレスを掛ける姿勢になっていた。
このことから心身症やうつ病を患っている人の中には、後頭下筋群の機能障害が発症のきっかけになり、症状の改善を妨げているケースが多いと考えられる!
頸の凝りと頭痛の関係
頚椎は7つの骨で構成されていて、上から3つを「上位頚椎」下4つを「下位頚椎」と呼ぶ。
上位頚椎の役割・・・頭部の重さを支えながら、その動きをコントロールすること。
上位頚椎に付着する組織に問題が生じると、全身的な不調とメンタルへの悪影響が出る。それだけでなく頸の凝りが原因で起こる「頸性頭痛」を患うリスクが高まる。
🍉頸性頭痛の特徴・・・目の奥に生じる痛み。耳の後ろに生じる突き刺すような痛み。
下位頚椎の役割・・・土台として頭頸部の重さを支え、頸部全体を動かすこと。
下位頚椎に付着する筋肉や靭帯、関節に問題があると、腕や手に痛みや痺れが広がる傾向がある。
🍉頭痛を生じる理由・・・頭蓋骨に広がる大後頭神経は頸の後ろにある筋肉の隙間を通っている。この筋肉が不良姿勢によって硬くなると圧迫されて、後頭部から頭のてっぺんにかけて頭痛が生じる。
後頭下筋群は身体の中でもっとも繊細! 重要な役割を担っている筋肉
” 後頭下筋群はインナーマッスルであり、主にアゴをあげる、うなずく、頭部を回す、頭を傾ける役割を担っている。そして、600以上ある全身の筋肉のうち、後頭下筋群にもっとも多くの筋紡錘があちこちにある。”
🍉インナーマッスルとは・・・
深層にある筋肉のこと。サイズが小さいため骨を動かす力はないが、脊椎(背骨、身体を重力から支える役割を持っている)と関節の安定・支持(ささえてもちこたえること)に貢献している。
またこのインナーマッスルには、筋肉の長さや張力を感知し、中枢(中心となる大切なところ)に情報を送る『筋紡錘』というセンサーが多くある!
🍉筋紡錘とは・・・

筋繊維の中にある筋肉が、伸びる縮むを感知するセンサー。
筋肉に強い負荷がかかった時、損傷を防ぐため極度な伸長や収縮にブレーキをかけるメカニズム。
筋肉が引き伸ばされると、その長さを感知し脊髄に情報を送る。
そして筋肉が伸びすぎて断裂しないように縮むように指令を出す。
参考:URL
” 頭部を回す下頭斜筋(後頭下筋群の下の方にある筋肉)には、1g中242個の筋紡錘が含まれている。※尻の筋肉:1g中7個。肩の筋肉:1g中2個。手の親指を動かす筋肉:1g中16個。 ”
この筋紡錘の数から、いかに後頭下筋群が繊細で重要な役割を担っている筋肉であるかがわかる!またこの筋紡錘の数が多い筋肉は、細い動きに対応することができる。
歯の噛み合わせと目の疲れも後頭下筋群に悪影響を与えている
アゴ関節と第一〜二頚椎は強い関連性があるため、噛み合わせや噛み方に問題があると下アゴがズレて、後頭下筋群と上位頚椎の関節に大きなストレスがかかる。
第一頚椎にズレが生じると、その方向に頭部が移動するため、体全体の重心が狂ってしまう・・・
後頭下筋群は眼球運動に関与しているので、眼精疲労が後頭下筋群に凝りを生じさせる。
合間に、熱いお湯で濡らしたタオルを目にあてがうと、目の周りの血流が改善されるのでおすすめ。
うつ状態は頸のつまりや後頭下筋群の凝りが原因?
パニック障害の人が暗所や閉所、大勢の人が集まっている場所に近寄れなくなる原因の1つとして、
・くびの筋肉が緊張して脳への血液供給が低下すること
・後頭下筋群の機能障害によって頭に入ってくる情報をタイムリーに判断できなくなっていること
が考えられる。
追突事故や落下によって、くびを痛めてしまった人の多くは、いつまでも原因不明の不調に苦しめられ、冬や梅雨時に症状を悪化させている。痛みと緊張で頭と頸を動かせなくなると、全身がロボットのようにギクシャクとした動きになり、症状が徐々に悪化していく。頭を動かすと目眩がするので外出できなくなり、自宅にこもりがちになってしまう人もいる。
気の毒なことに、頸が原因で起こる体調不調は、精密検査を受けても原因がはっきりとしないケースが多い。
注意すべきは、後頭下筋群の凝り(血流不全)を的確に治療すれば、症状が改善するはずの人でも、自分が心身症だと思い込んで、本当に鬱状態になってしまうこと。
軽度のパニック障害と抑鬱状態であれば、くびの緊張を改善するマッサージとストレッチ、くびの機能を回復させる運動を並行して実践すれば、症状が緩和する可能性は十分にある。また、同時にくびに負担のかからない作業環境の見直しを図ることも大切。
頸の機能を向上&回復させるセルフケア7つ
①椅子の背もたれのふちを使った” フリーズした頭を解凍する後頭下筋群のマッサージ ”
⑴ 座面の前方に座り、背もたれに寄りかかりながら、背もたれのふちに後頭部を引っ掛けるように押し付ける。
⑵ ズーンと響くところで30〜60秒間圧迫し続ける。途中、顔を向ける方向を少しずつ変える。
②くびの前のストレッチ
💡アゴがずっと前に出ていた人がアゴを引けるようになるためのストレッチ。頸の前の皮膚と筋肉の緊張を緩めて、頭を後ろに引きやすくし、脳への血液循環を改善する。
⑴ 両手を胸骨の上に置いて皮膚を固定する。ゆっくりとアゴを真上にあげて、頸の前面をストレッチする。
⑵ つっぱり感がでる角度で、20秒以上固定して伸ばす。顔の向きを変えるとストレッチされる場所が変化する。
③アゴ下の筋肉のマッサージ
💡マッサージした後、顎が簡単に引けるようになる。
親指の腹で優しく労るように、「えら」からアゴの先端までほぐす。(アゴの先に両手の人差し指を引っ掛ける、親指以外は軽く曲げる)
④頸部が楽になる胸椎のモビリゼーション
💡胸椎&頚椎の可動性(動きやすさ)を回復する
⑴ バスタオルを丸めて拳ほどの大きさにする
⑵ 丸めたバスタオルを床(だいたい腰あたりのとこ)に置き、その上に仰向けに寝て膝を曲げる。
⑶ 足の裏で床を押して、胃の高さから頸の位置までタオルを一つ分ずつ移動していく。この時は鼻で呼吸しながら、1か所につき30秒くらいを目安に行う。
⑤肩甲骨の動きを改善するダイナミックストレッチ
💡肩甲骨の可動性の回復。このストレッチを習慣化すると、肩甲骨の動きがスムーズになり、その動きを意識しやすくなる。
⑴ 壁の角に背骨を当てて寄りかかる(普通に肩を回すと、上半身が一緒になってブレてしまうため)
⑵ 色々な角度から肩を後ろに大きく回す
⑥くびのインナーマッスルの働かせ方
💡円滑な頸の動きを取り戻すため(頸の痛みを抱えている人は、インナーマッスルの機能が低下していることが多く、アウターマッスルだけを使ってることが多い。この状態が続くと、頸を痛めてしまう)
⑴ 仰向けに寝て片手を頸の前面に置いて、『表面の筋肉が働いていないかチェックする』。舌を上アゴにつけて口を閉じる。※歯は噛み締めない
⑵ 視線は下に移し、鼻で息を吐きながらうなずいていく。うなずいた姿勢を10秒間維持。頸部に置いた指の腹で、『頸の前面の筋肉が緊張しすぎていないかチェックする』。
🔼正しく行えていれば、頸の表面の硬さは変化なし。
・鼻呼吸
・1セット10回×1日2〜3セット
⑦四つん這いで頭と頸の屈曲(折れ曲がること)エクササイズ
💡前面のインナーマッスルを働かせて、アゴを引く持久力を養うこと
⑴ 四つん這いになる。
⑵ 口を閉じて、舌の3分の1を上アゴにつける。
⑶ 軽く頷いて、頭を後ろにひく。脊柱がニュートラルポジションになるようにする。
(※ニュートラルポジション‥‥身体 ( 関節、筋肉、靭帯 ) への負担が最小限で全身の運動機能や循環機能の働きがバランス良く円滑に発揮し易い状態のこと。 一般的にニュートラルボジションの配列は耳孔から肩峰、大転子、足踝までの配列がほぼ垂直線上に並んでいる身体の状態。)
⚠️鼻呼吸でゆっくりした呼吸をしながら、アゴが上がらないようにする。
⚠️頭から尻まで一直線を意識する。
まとめ
①うつむく姿勢が頸の痛みの根本的な原因
②後頭下筋群が緊張・硬化すると、全身的な不調を起こす
③頸の凝りが元で起こる頭痛がある
④眼精疲労が後頭下筋群に凝りを生じさせる
⑤背もたれのふちで後頭下筋群をマッサージする
✳︎✳︎✳︎
この本を読めば読むほど、身体って全部つながってるんだなってわかりました。1つが良くても1つが悪ければ、そこを軸にどんどん悪くなっていって全身の不調やメンタルにまで影響するし・・・
1つの不調を軽く見ちゃいけないなって思いました。改めて自分の状態を知ること、不調を放って置かないことなど自分の身体を大切にしたいなと気付けました◎
⏬第1章〜第3章まで無料のマガジンにしています。要約は時間がかかるし下手くそですが、自分の理解を深めるためにもnoteにまとめてみました。この本はめちゃめちゃためになることが沢山書かれていたので、読んでもらえたら嬉しいです^^
❶やる気スイッチはアゴにあり
❷お尻を締めよう〜腰痛予防〜
❸呼吸で人生は変わる〜正しい呼吸と悪い呼吸〜
