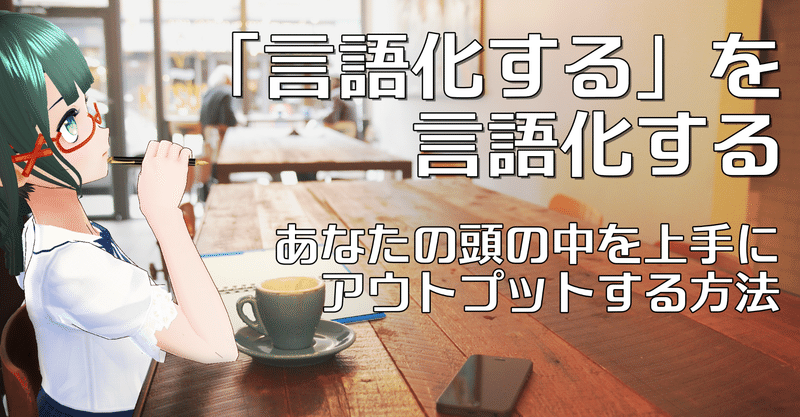
「言語化する」を言語化する:あなたの頭の中を上手にアウトプットする方法
私、思惟かねは、一応文筆をメインに活動しています。クイズ大会を主催したり、セルフポートレートを楽しんだりしていますが、あくまで本業は文筆です。誰がなんと言おうとも。
さて、物を書く者にとって言葉とは筆も同然です。筆がなければ一節たりとも書くことはできませんし、言葉もまた然りです。と同時に、言葉とは筆を使うのと同じぐらいに、あるいは形なきが故それ以上に「無意識」に使うものでもあります。
ここに、言語化という行いの難しさがあります。
例えば箸の使い方であれば、「人差し指と中指の間に片方を挟み、もう片方を薬指と親指で抑えて保持し、主に中指の動きで開閉する」と具体的に説明することもできるし、手取り足取り教えることもできる。人の見様見真似で習うこともできます。
しかし「言語化」はそうではありません。誰もが経験的に、なんとなく行っているのであえて説明されることはなく、教えることは難しく、また物理的な実態がないので真似ることもできません。
であるにもかかわらず、「言語化」とは人間の高度な知的活動には必須の能力です。
なぜなら、コミュニケーション、抽象的思考、感情や思考の成果の共有、おおよそ大半の知的活動には思考を言語化する事が必要だからです。
実際、あなたの周りにいる「頭の良さそうな人」を思い浮かべてみてください。その人は、おそらく物事を面白おかしく話したり、あるいは文字にして説明したりするのが上手ではないでしょうか。
それも当然で、いくら素晴らしい思索や理論を頭の中に描いていても、面白い小話を知っていても、それが「外」にアウトプットされない限り、それは無いも同じなのです。
たとえかのアインシュタインでも、その思考を論文としてアウトプットできなければ、ノーベル賞を取ることは不可能だったでしょう。言語化とはそういう類のものなのです。
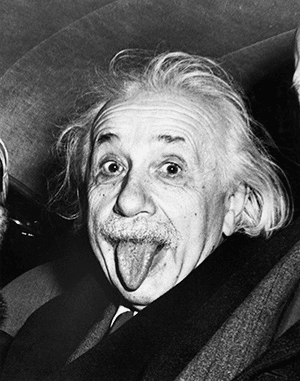
しかし、こんな重要なことなのに、学校では数学や英語のように「言語化」を教えてはくれません。それは先程も述べたように、言語化が極めて抽象的で説明の難しいスキルだからです。
しかしだからと言って、私の回りくどい文章に付き合ってくださる皆さんに、いまさら「じゃ、やり方は分からないけど頑張って言語化スキルを身に着けてね!」と言うのも不実が過ぎるというものでしょう。
ここは一つ、私なりに「言語化する」という行いを言語化してみましょう。
そうすることで、一体どうすれば言語化スキルというものが身につけられるのか、何を意識すればよいのかというポイントが見えてくるはずです。
◆「言語化」とは翻訳である
さて、私たちは言葉に先んじて、ぼんやりした「イメージ」を持っています。赤くて、丸くて、触るとしっとりしていて少し重い。齧るとシャクシャクして甘い。このイメージは一般に「リンゴ」と名付けられています。
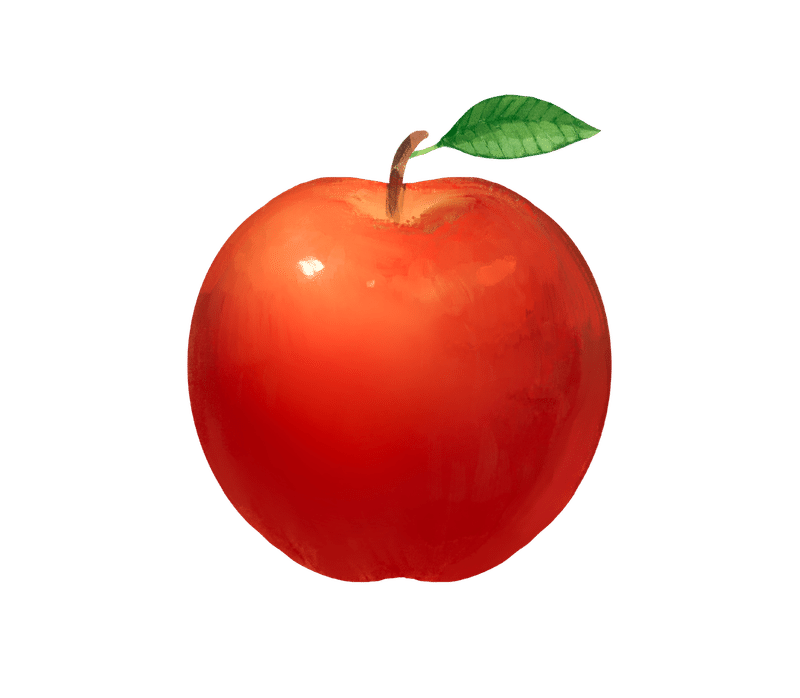
あるいは、なんだか不快で、頭の中や胸が重くなって、涙が出てくるような感じ…このイメージは通常「悲しい」と呼ばれます。
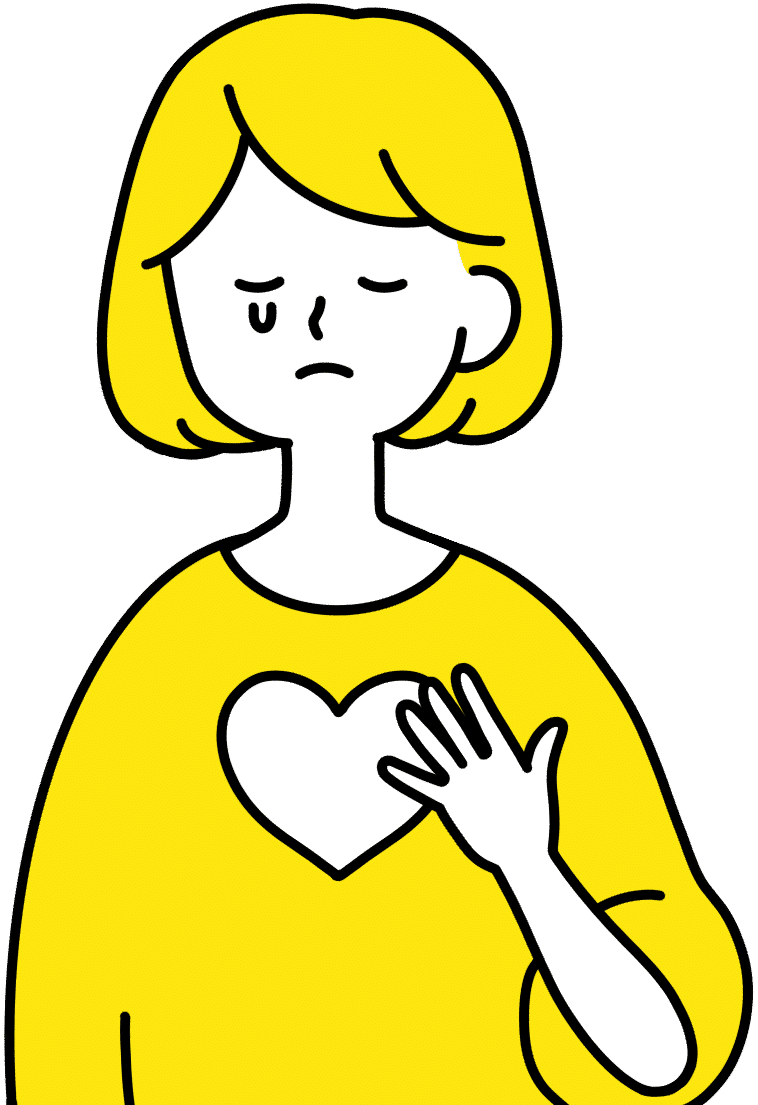
私たちはこのように、頭の中にある「イメージ」(記憶、思考、あるいは見聞きし感じたもの)を識別し、これを「言葉」として出力します。言い換えれば、言語化=言葉にするとは、あなたの頭の中にあるイメージを翻訳し、皆が知っている共通語に変換する営みなのです。
であるならば、何が重要かはいうまでもないでしょう。
そう、翻訳には「辞書」が必要です。
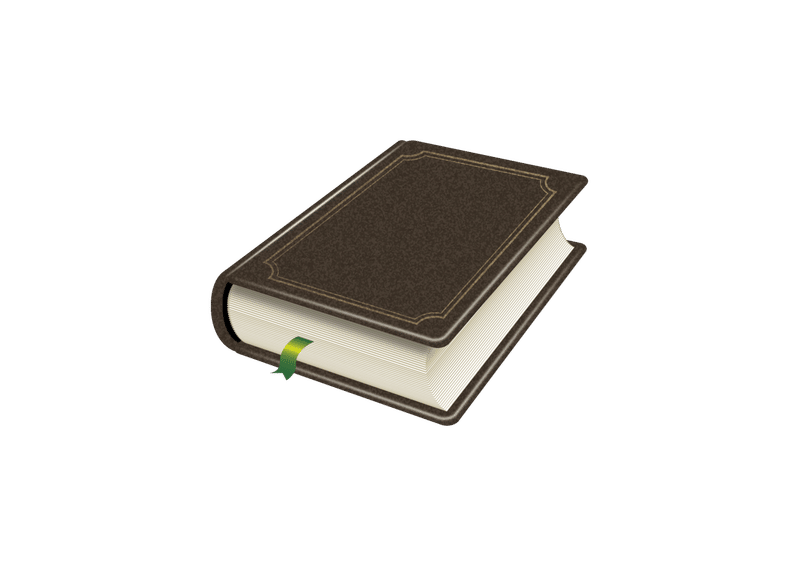
辞書の語数が多ければ、より豊かな表現が可能できます。また辞書をひくのが早ければ、よりスムーズに表現ができるできます。つまり、あなたの頭の中の「イメージ」と「言葉」が、いかにたくさん、スムーズに対応しているか。これが言語化スキルを左右する大きな要素です。
またこうしたイメージと言葉の結びつきは一対一ではなく、「連想」あるいは「関連」を通して網目のように広がりを持ちます。こうしたつながりの広さもまた、豊かでスムーズな表現、そして思考力・洞察力につながってきます。
頭の良い人と悪い人の物の見方の違い pic.twitter.com/veezNfo7HO
— ながりょー🎻(micorun) (@micorun) May 27, 2017
— ニーワルス(雑多) (@niewals) May 30, 2017
ということは、当然「言語化」スキルを高めるには辞書を充実させることが最も早道ということになるでしょう。
もっとも、早道といってもその道程はひたすら地道です。ひたすら素振りをしてフォームを覚えるように、言葉を「イメージ」に、「イメージ」を言葉に変換する経験を積まねばなりません。
こう聞くといかにも難しそうに聞こえますが、例えば今あなたがこの文章を読んでいるということもまた、私の言葉をあなたの「イメージ」に変換する行為そのものです。
またあるいは、あなたが身の回りで起きたことをTwitterでツイートするのも、あなたの「イメージ」を言葉に変換する行為です。要はたくさん読み、たくさん書けば良い。そう肩肘を張る必要はありません。
ただし、同じ「読む」「書く」でも学びの程度は人によって違うことは知っておいて損はありません。例えば、
青々と茂る草原の中に、所々白色の花弁が楚々と揺れている。吹き渡る風に乗って渡る草葉を追いかけて見れば、そこには澄み渡るような青空があった。
こんな小説の一節を読んだとしましょう。さて、あなたの頭の中にはどれほどのイメージが浮かびましたか?
これをただ文字としてうわべだけ読み流すか、脳裏にその風景を精彩に描きながら読むかでは、「経験値」の度合いはまるで違います。
「書く」時もまた同じです。ただ「つかれた~」と書くのと「今日は昼間の暑さがすごくて、ただ立っていただけなのに本当に疲れた。でも家に帰ってくるとホッとする」と書くのでは、どちらが頭の中のイメージを上手く、精度良く出力できているかは一目瞭然です。
言語・イメージの変換辞書は一朝一夕で充実するものではありません。しかし、言葉をより明確なイメージに変換し、自分のイメージをより正しく言葉に出力しようとする努力なくしては、上達することもまたありません。
千里の道も一歩から。今日読むネット記事の一つ、あるいは今夜するツイートの一つを、少しだけ集中して読んでイメージを膨らませ、あるいは多くのイメージを言葉にしてみる。
まずはそんな所から初めてみてはいかがでしょうか。
◆もう一つの「言語化」スキル
と、いかにも啓発っぽく締めた後なのですが、実は「言語化」の能力にはもう一つ重要な要素があると私は思います。ある程度「辞書」が充実している人にとっては、実はこちらのほうが重要かもしれません。
それが「論理性」です。
例えば、ある人の「イメージ」を言語化してみましょう。
火、赤い、燃える、温かい、冷たい、濡れる、体、乾く、心地よい
確かに言語化はされています。しかし、これではその人の「イメージ」が十分に伝わってこないことは、皆さんもお分かりでしょう。
では、どうすればいいか?…こうするのです。
火が赤々と燃えているおかげで温かい。すると冷たかった体が乾いてきて、とても心地よい。
お分かりいただけたでしょうか。
つまり、ただ「単語」を辞書で引いただけでは不十分なのです。こうした単語の間の繋がり、因果関係、論理関係を明確に示すことはそれ以上に重要です。
こうした言語化における「繋がり」の欠如は、特に読書量や知識は多くてもアウトプットの経験が少ない人に顕著です。あるいはアウトプットはしていてもイマイチ何が言いたいのか理解しづらい人も、得てしてこの視点を欠いています。
逆にわかり易い文章を書く人は、必ずと言っていいほど言葉と言葉の繋がりを重んじています。
・〇〇だから××です
・○○なのに××だった
・〇〇もあれば、××もある
・○○のあと、××があった
因果関係、逆接、並列、順序…こうした単語と単語、文と文の繋がりを正しく表現しなければ、文章とは半身不随になってしまうのです。
では、どうすればそうした「つなぎ」の技術が身につくか?
今回は「ひたすら素振りをすればいい」なんてことは言いません。実は私自身、基礎練習が大の苦手なタイプだったりします。というわけで、2つのテクニックをご教授しましょう。
まず、なるべく接続詞を使う癖をつけましょう。
接続詞というのは、以下のような言葉のことです。
・だから、だとすると(順接)
・しかし、ものの(逆接)
・また、同じく(並列)
・さらに、ひいては(付加)
・一方、反面(対比)
・たとえば、いってみれば(換言)
・さて、それはさておき(転換)
これら接続詞は、単語と単語、文章と文章の関係を明らかにするキーワードです。ゆえにこれを使えば、自分の伝えたいイメージをより正確に伝えることができます。
これがどれほど重要かが分かる文章を見てみましょう。
昨日は家に帰るのが遅かった。お腹が空いた。たくさん食べた。よく眠れた。
まるで小学校低学年の日記です。しかしここで接続詞を使ってみると、
昨日は家に帰るのが遅かったので、お腹が空いた。おかげでたくさん食べてしまい、そのせいかよく眠れた。
となります。言葉と言葉の繋がりが明確になり、すっと頭の中に入ってきます。
また副次的に、そうした言葉の「繋がり」が頭の中で漠然としていても、このような接続詞を使おうとすることで「この文章とこの文章は順接?それとも逆接?言い換え?」と、互いの関係性を考え、整理するきっかけになります。
思考を言語化するには、まず誰よりもあなたがその思考を理解していなければなりません。それを整理する助けとなり、また分かりやすく表現する手段である接続詞は、二重の意味で「言語化」の強い味方なのです。
そしてもう一つのテクニックが「自分の文章を再翻訳してみる」ことです。
あなたがイメージを「翻訳」した言葉は、当然「原文」を持っているあなたには意味がわかります。しかし、他の人は「翻訳」の結果である文章だけしか見ることができません。はたして、あなたの「イメージ」は言葉を通して十分に人に伝わっているでしょうか?
というわけで「翻訳元のイメージ」は一度忘れて、何も知らない人のつもりになってあなたの文章を「再翻訳」してみましょう。すると、おそらく思った以上にあなたのイメージは伝わっていないことに気づくはずです。そしてその事に気づいていない人は想像以上に多いです。
実は私自身、このことを特に恐れていて、こうして文章を書く時も一文一文、伝えたいことと文章がズレていないかを「再翻訳」して確認しながら書いていたりします。
言葉不足、語順による誤解、代名詞の対象の分かりにくさ、言葉選びによるニュアンスの違い…再翻訳すると、そうした言語化のアラがに気づくことができるようになります。
このように自分の文章を「再翻訳」する癖がつくと、自分の言語化のどこがまずいのか、どうすれば伝わるのかが試行錯誤できるようになって、メキメキと言語化能力が上がります。
もっともこの再翻訳自体にある程度のスキルがいるので、不慣れな人だと最初は難しいでしょう。けれど自分の文章を客観的に見つめ直す経験は、うまい文章を読むのと同じくらい、あるいはそれ以上に確実にあなたの言語化スキルを高めます。
改まって文章を書く時でなくともよいです。SNSに投稿する時、メッセージアプリで返信をする時、友だちと話す時…日常の中で「これで伝わるかな?」と自分の言語化を振り返る視点をぜひ持ってください。
◆さいごに
というわけで、今回はすべての知的活動の土台とも言える「言語化」について言語化してみました。
言語化とは、頭の中のイメージを翻訳する。続いて翻訳した言葉同士に「繋がり」を持たせて発信するという二段階のプロセスからなっています。
ゆえに言語化能力を高めるには「脳内のイメージと言葉の辞書を充実させる」のがもっとも重要で、また読む時、書く時にはこの言葉とイメージの繋がりを意識すると効果的です。
そして後者の「言葉の繋がり」については、「接続詞を使う癖をつける」「自分の文章を他人の視点で読み返す」という2つのテクニックを駆使することで大きく上達するでしょう。
結局の所、この文章を読んだくらいでいきなり「言語化」が上手くなることはありません。重要なのは日々の中での積み重ねであり、たくさん本を読み、たくさん文章を書くことです。
けれども、今回解説した「コツ」を意識することで、その経験値は何倍にもなります。忘れないうちにぜひ実践してみることをおすすめします。
さしあたって、手始めにこの文章を読んだ感想をコメントや引用RTで書いてみてはいかがでしょうか。
…というのは冗談として。
自分の思考を思い通りに言語化できるのは、この上なく楽しいです。私がこうして時間を溶かしてnoteを書くのも、ひとえにそうした言語化の喜びがあってこそ。
同じ喜びを共有する方が増えることを、私は心から楽しみにしています。
皆さまと言語の間に良いご縁が結べることを祈って。
思惟かねでした。
--------------------------------------------------------
Twitterでのシェアはこちらから
「言語化する」を言語化する:あなたの頭の中を上手にアウトプットする方法https://t.co/od8tnHUavo
— 思惟かね(オモイカネ)📕🔔 (@omoi0kane) August 25, 2021
思考を言葉にするのはコミュニケーション、論理的思考、情報発信など全ての知的活動の根幹です。
しかしこの「言語化」はどうすれば上達するのか?そのポイントを言語化して説明してみましょう。
--------------------------------------------------------
今回もお付き合いいただきありがとうございました。
引用RT、リプライ等でのコメントも喜んでお待ちしています。
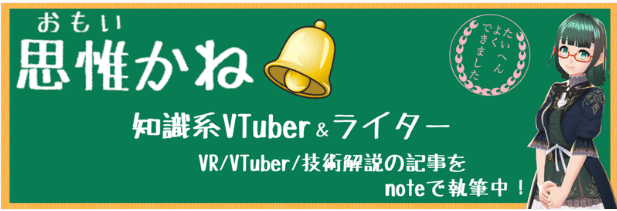
Twitter: https://twitter.com/omoi0kane
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpPeO0NenRLndISjkRgRXvA
Medium:https://omoi0kane.medium.com/
Instagram: https://www.instagram.com/omoi0kane/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100058134300434
マシュマロ: https://marshmallow-qa.com/omoi0kane
○引用RTでのコメント:コメント付のRTとしてご自由にどうぞ(基本的にはお返事しません)
○リプライでのコメント:遅くなるかもしれませんがなるべくお返事します
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
