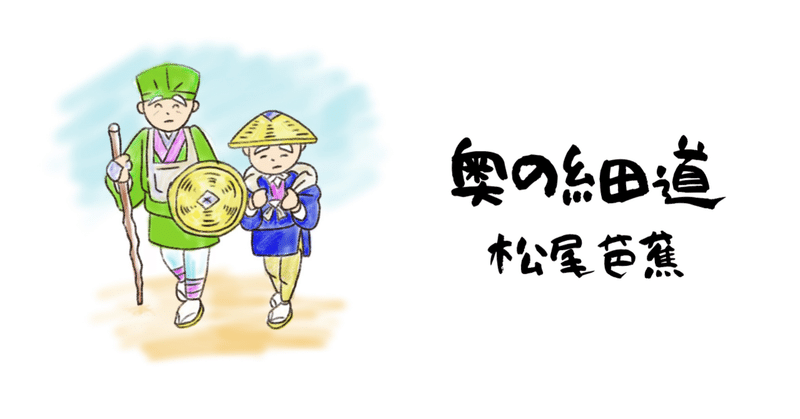
中野孝次『清貧の思想』から考える芭蕉「風雅の道に身を削る」
<一句として辞世ならざるはなし>
…風雅に身を削る松尾芭蕉
辞世(じせい)とはこの世に別れを告げることであり、そこから、この世を去る時(まもなく死のうとする時など)に詠む漢詩、和歌、発句などを指します。『芭蕉翁古文』と称する文書に、芭蕉の臨終の時のことが記してあるそうです。
「きのふの発句はけふの辞世、けふの発句はあすの辞世、わが生涯にいひ捨てし句々、一句として辞世ならざるはなし。もしわが辞世はいかにと問ふ人あらば、この年頃いひ捨ておきし句、いづれなりとも辞世なりと申し給はれかし」
と言ったそうです。つまり、芭蕉は全て辞世の句だと思って発句に取り組んでいたのです。
角川ソフィア文庫の『芭蕉全句集』(平成22年初版)によると、983句通し番号で掲載されています。983句、一句一句が辞世の句だと言うことになります。これが蕪村になると約2850句(『蕪村句集』角川ソフィア文庫)、一茶となると、確認できるだけで19800句あるそうです。(『一茶句集』角川ソフィア文庫)
角川ソフィア文庫には約千句ずつ収録されているので、芭蕉・蕪村・一茶の三人で、ほぼ三千句あることになります。
芭蕉は、風雅の道に身を削る、と『清貧の思想』著者の中野孝次さんは述べています。作る句すべてが身を削る辞世の句だったということです。風雅の道とは日常生活の当たり前の価値観とは違う世界です。日常生活の延長に風雅の道があるのではありません。風雅という芸術文化の道は衣食住の満足とは別次元の世界です。
しかし人として肉体をもって生きる以上、食べることをしないと死んでしまいます。雨風をしのぐ住居がないと苦しい人生で、病気になったり、事故にあったりするかもしれません。しかし、芭蕉は生活の安定を捨てて風雅の旅に出ているのです。蕪村はそれができませんでした。人は何のために生きるか。衣食住の安定にあるのではない事を、芭蕉の旅の人生が証明しています。
そのような人生で作り続けた983の句が、三百年たった現代でも人々の記憶に残るのです。その芭蕉は西行を深く尊敬していたようです。
「歌に実ありて、しかも悲しみそふる」
西行も妻子を捨てて旅に生きた人でした。「花を愛し孤独に耐えきる西行」としたのが中野考次さんです。(『清貧の思想』十八)西行も元は佐藤兵衛尉義清という名門の武士でした。武勇にすぐれ富も豊かな名門の出だったのです。しかし、世俗の生を捨てて出家し、風雅の道に生涯をささげたのです。
生とは何か。死とは何か。ほとんどの人が考えずに生きています。考えないようにしているのかもしれません。しかし残念ながら人間には寿命があります。50歳60歳になれば人は誰でも、あと何年生きられるだろうかと考えるようになります。良い人生を送りたいと痛切に思うでしょう。
芭蕉が傑出しているのは、死とは何かと問い続ける作句姿勢が983の句作のはしばしに垣間見られることです。一句として辞世ならざるなし、とは一句一句、死の覚悟が見え隠れするからです。しかしその句が人を生かすのです。救われる思いがするのです。風雅の道は三百年、人を救い続けているのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
