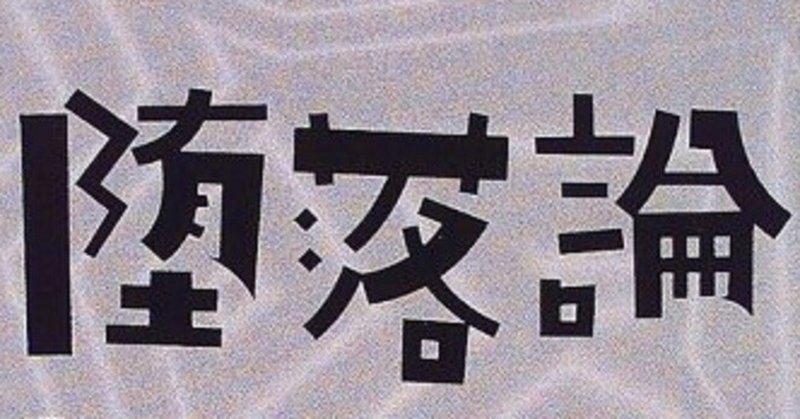
◆読書日記.《坂口安吾『堕落論』》
※本稿は某SNSに2021年7月2日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
坂口安吾の代表的随筆集『堕落論』読了。
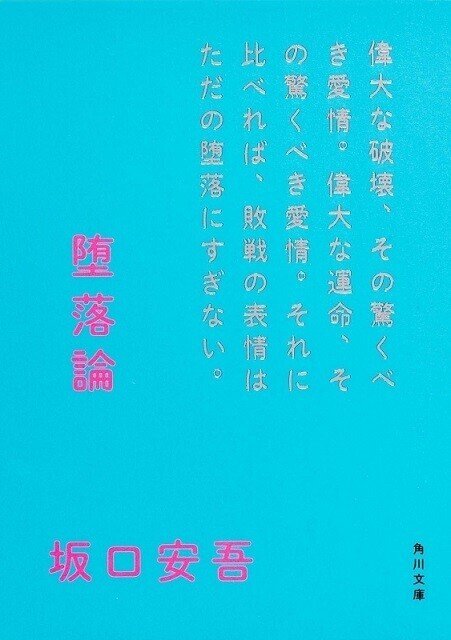
戦前の「日本文化私観」「青春論」と、戦直後の昭和21年から23年までに書かれた「堕落論」「続堕落論」「デカダン文学論」等、11編の随筆を集めた随筆集。
この本と小説集『白痴』の評判によって安吾は戦後一躍文壇の寵児となったと言われている代表作である。
本書は戦中~戦後の時期を通した著者の理論的な代表作であり、その実作が『白痴』と言う事となる。
つい先日「そう言えば安吾の『白痴』を読んでなかったな、読んでみよう」とふと思い立ったのだが、その前についでだから坂口安吾の理屈のほうも踏まえて「小安吾研究」的にやっつけてみようと思い付いたわけである。
◆◆◆
本書では、東洋大でインド哲学を学んだかの安吾が"論"という仰々しいタイトルを付けて文学や人間について語るという触れ込みだったので、ある種の哲学書に向かう気構えで臨んだのだが、やはり中身は「随筆」そのものだったという印象である。
この人の「論」には思想はあってもロジック的なものは疎かだ。
この人の文章を読んでいると、例えばカント的に緻密にして膨大なロジックの積上げ型の思想というものについては「シチメンドクセェ」という意識しかなかったのではないか、という気質を持った人だという印象を受けるのである。
というのもこの人の「論」というのはロジカルなものではなくアナロジカルなのである。
例えば「青春論」という題である程度の長さの文章を書いた場合、様々な論証を上げて行って最後に総括的な結論が待っている……といった書き方はしていないのである。
「青春」に関わる自分の普段からの考えや自分に関わった様々なエピソードやそれに関わる感想等といったように、話題が次々に横にスライドしていく。
それらが魔法に様に最後きれいに収まるものかと思いきや、どうもそうではない。
これは収束される事を想定して書いている書き方ではないのである。というより、興味があちこちに飛んでいるという感じだ。
ドイツ観念論のお歴々のように1テーマにつき粘り強く思考しぬくという徹底的な態度も見られない。
どうにもこの人の「思想」は本能と思い付きの連鎖反応で出来ているように思われる。
安吾も例えば本書収録の「戯作者文学論」で自分の作品の傾向を「そんなもの(※全部の見通しや計算や伏線のようなもの)の全然必要でないもの、ただ書くことによって発展していく場合が多く、私は元来そういう主義でそういう作品が主なのだけれども」と表現している。
続けて同文章に「考えている時間のほうが、書くよりも長い。尤も、書きだすと、考えていたこととなるで違ったものに自然になってしまうのが普通なのである」といった自分の性質についても言及している。
考えながら書き、書きながら考え、一つのテーマについて徹底的に思考し尽くすタイプではないようだ。
だから、この人の「思想」についての随筆は、短いもののほうが切れ味が鋭く、長くなると何だか方々に話題が散らかってしまうという印象があった。
ただ、それは「徹底的な思想を持っていなかった」といったグウタラな感じではなく、「思想のみ先行してしまう、頭の中だけで完結してしまう=頭でっかち性」を厭ったのだろう。
だから、彼の文学には「生活」が重要であり、「肉体」を無視して文学は成り立たない、人間を書く事はできないと考えたのだろう。
こういった所は確かに安吾の東洋哲学的な素養が関係していると感じる。
「生き方」そのものが「思想」であって、その思想があってこそ人間が書けるという考えに繋がっているのだろう。ライフスタイルそのものが修行であり、悟りという思想に至る道だという仏教的思想に類似している。
だから、しばしば安吾の文学論には「どう生きるか?」という話が出て来る。
そして、「青春」を語る事がそのまま自らの文学観に繋がっている事を語るし、「堕落」について語る時にそれがそのまま自らの「美学」に接続している事を語っている。
また、人生論の中で文学に触れ、文学論の中で人生論を語るのである。
自らが文士だから、何を語るにも小説の話が出て来るのではなくて、何を語るにしても自分の文学観が全て絡んでくる。というのが、安吾の文学だったのであろう。
「文学も思想も宗教も文化一般、根はそれ(※よく生きる)だけのものであり、人生の主題眼目は常にただ自分が生きるということだけだ(「教祖の文学」より)」
それが安吾の人生観であり、同時に文学観でもあった。
安吾はわりと実存主義的な考え方を持っていたようなのである。
してみると、文学観が独善的であり、他者の文学観を批判するスタンスも割合独善的であったのも、安吾の実存主義的なスタンスが関係していたのではないだろうか、とも思ってしまう。
つまりこの人にとって「人間にとっての文学一般」の本質論などは重要ではなくて、「オレの文学の本質」を追求するのが、安吾には重要だと考えていたのではないかとも思えるのだ。
だから、青春を論じるにも欲望を論じるにも、人間存在の一般がどう生きてどう死ぬかと言う事の指標を提示するのでなく「オレがどう生きるか」を示したのではないか。
だから、安吾の文学論は「文学のあるべき姿」の話にもならないし、「文学一般の本質論」にもなりはしないのである。
では、安吾の実存的な立場というのはどういうものだったのだろうか。それが安吾的「堕落」だったのではないかと思うのである。
◆◆◆
本書を読んで感じるのは、安吾の言う「堕落」というのは決してマイナスイメージの言葉ではなかったという事である。
そうでなければ「日本及び日本人は堕落しなければならぬ」等とは言わない。
安吾の「堕落論」はどことなくニーチェの道徳批判に雰囲気が似ているのである。
ニーチェは「一般的・普遍的道徳」の事を批判しているのではなかった。ニーチェの批判の矛先は、あくまで「西洋の伝統的なキリスト教道徳」にあった。
それに対して安吾の「堕落せよ」の矛先がどこに向いているのかと言えば、例えばそれが戦前の日本の道徳的なものとなった「武士道道徳」的なものにあったのではないかと思うのだ。
安吾は「堕落論」にて「武士道は人性や本能に対する禁止条項である為に非人間的、反人性的なものであるが、その人性や本能に対する洞察の結果である点に於いては全く人間的なものである」と書いている。
安吾は、女性というものは本来移り気であり人間であるからには不倫も浮気もするものだと考えた。
だから、武士道道徳的な「節婦は二夫に見えず」という考えは「非人間的」だというのだが、それは「女性(及び人間一般)は移り気で不倫も浮気もするものだ」と良く分かっていたからこそ、その防衛手段として女子の貞操などという「非人間的」なルールを作ったのだ、と主張しているのである。
「人間が正しいもの、正義を愛す、ということは、同時にそれが美しいもの楽しいものゼイタクを愛し、男が美女を愛し、女が美男を愛することなどと並立して存するが故に意味があるので、悪いことをも欲する心と並び存する故に意味があるので、人間の倫理の根元はここにあるのだ、と私は思う。
人間が好むものを欲しもとめ、男が好きな女を口説くことは自然であり、当然ではないか。それに対してイエスとノーのハッキリした自覚があればそれで良い。この自覚が確立せられず、自分の好悪、イエスとノーもハッキリ言えないような子供の育て方の不健全さと言うものは言語道断だ」
――坂口安吾『堕落論』収録「デカダン文学論」より
……と言っているように、安吾は人間的な欲望を肯定するのである。
だから、それを阻害する道徳は「贋道徳」だと言うのだ。
清純に生きよ、清らかな精神でいなさい、貞節を弁えなさい……といった、人間本来の欲望を無理に規制する「非人間的」な道徳に対して、安吾の「堕落せよ」の矛先は向かっているのである。
心のままに恋愛を謳歌し、気にくわない事があれば遠慮なく批判し、酒を呑んで、遊ぶ。
そういうグウタラな人生も「良い生き方」で、「勤労の美徳」とか「貞操観念」などクソクラエ、というのが安吾の言うような「自我自らを欺くことなく生きたい」という事だったのかもしれない。
女性と大いに恋愛をし、グデングデンになるまで酒に酔って、不安を打ち消すためにヒロポンに手を出し、作家仲間に悪口を言っては相手に言い返される人生。
それが生まれながらに自由奔放な気質を持っていたと言われる坂口安吾の「文学」だったのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
